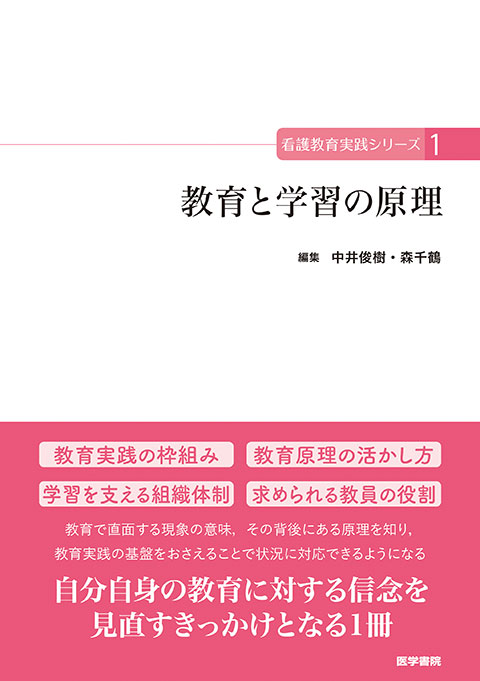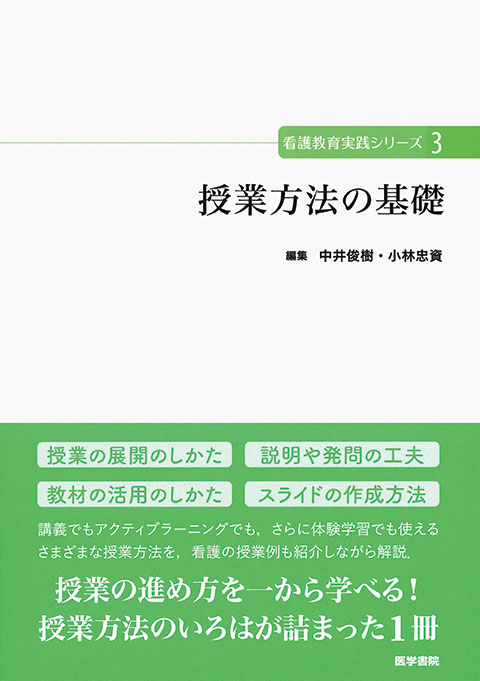教えるを学ぶエッセンス
[第5回] 初年次教育を成功させる工夫とは?
連載 杉森公一
2022.08.29 週刊医学界新聞(看護号):第3483号より
今回のポイント
✓ ゼミナール科目を充実させるために,担当教員のファシリテーション・スキル向上や授業設計の共有を目的とした研修を行う。
✓ 学習活動の配置を検討する際は,個人活動とグループ活動を交互にして協働力が次第に育成されるようにする。
学びの転機を感じた瞬間を覚えているだろうか。春,初めて足を踏み入れた校舎や教室,まだ折り目のない教科書のページを開いたときのインクの香り――。学習や経験を重ねているただ中ではなく,季節の変わり目が思い出されるかもしれない。これまで見てきた風景が一変する「節目」は,異なる教育段階をつなぎ合わせる「アーティキュレーション(接続)」と呼ばれる1)。高校3年生から大学1年生への変容を意識づけるために,まさに節目にある新入生に対して,教員は授業やカリキュラムをどう工夫すればよいだろうか。
“高校4年生”ではなく,大学1年生に移行を
18歳人口の減少や学生の多様な進学を背景に,「高大接続」の在り方が問われている。近年,中学・高校での学びを大学等の専門教育へ接続することを目的に,教育プログラムとしての「初年次教育(First Year Experience)」が大学で広がっている2)。初年次教育とは,「大学教育,大学生活への円滑な移行を目的とし,学習技能,学習意欲,さらには大学生としての自覚の涵養まで含む,正課・正課外にわたる総合的教育プログラム」とされ,ゼミナール科目を中心に構成される2)。専門教育への導入の側面があることから,看護教育における初年次教育では,学習技能のみにとどまらず,キャリア形成とプロフェッショナル・スキルも科目内で学ぶべき内容として強調される3)。
これまで初年次教育は多岐にわたった教育接続を引き受け,正課の必修単位として算定される過程で,多様な学習活動を内包してきた。しかし,独立したゼミナール科目で多様な学習活動の全てを抱えるのは困難であり,科目の枠組みは限界に差し掛かろうとしている。中学・高校教育の変化により,専門教育と卒後のキャリアの間に求められる適切なアーティキュレーションの在り方が改めて問われている。
学生の深い学び・協働を誘う授業を計画する
筆者が勤務する北陸大学では,臨床検査学と臨床工学の知識と技術を学ぶことを目的として,2017年に医療保健学部が新設された。本学部の「基礎ゼミナールI・II」の設計は,16年に行われた設置準備室教員・関係職員対象の研修と,就任予定の全教員へのFD研修を通じて行われた4)。研修講師は筆者が担当し,研修参加者に授業設計や学習...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。