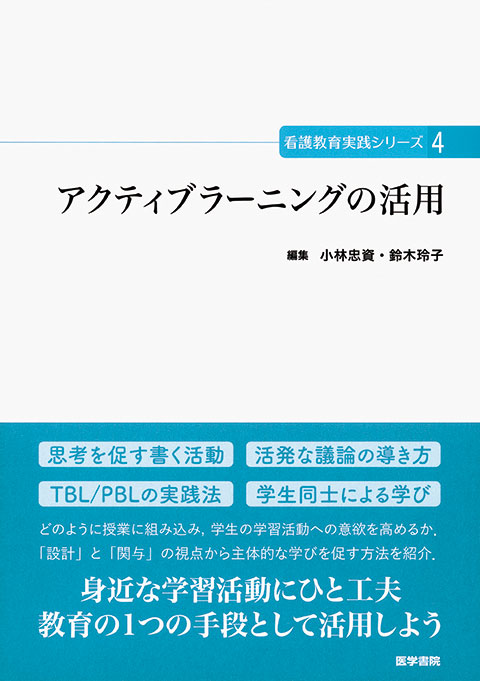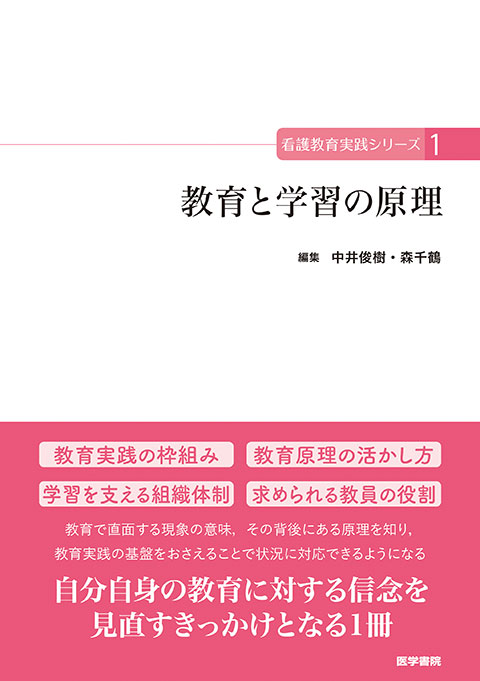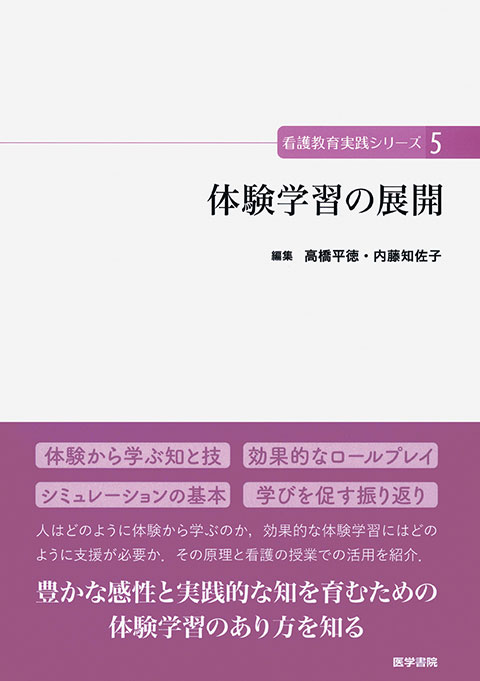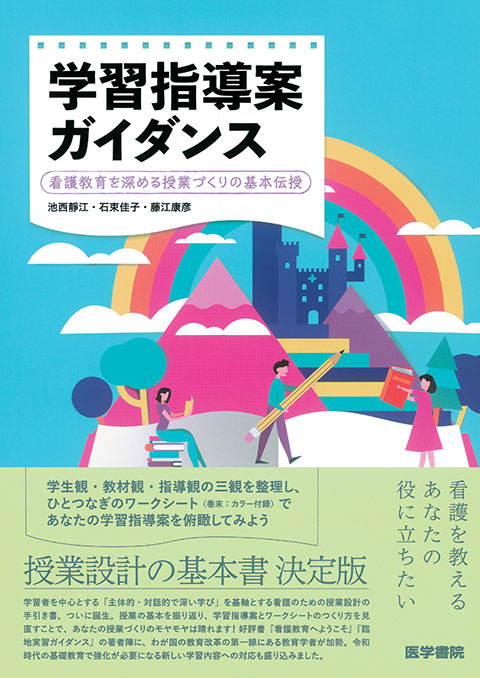教えるを学ぶエッセンス
[第3回]学習目標を明確にし,逆向きの授業設計を行う
連載 杉森 公一
2022.06.27 週刊医学界新聞(看護号):第3475号より
今回のポイント
✓ 逆向き設計では,目標に沿った学習評価の方法を先に定めてから,学習内容の配置を検討する。
✓ 授業設計の三角形を達成するために,「意義ある学習」の6つの特質を理解しておく。
学習者は授業で何を学ぶのか? 教師として学校や研修で計画的に何かを教えたことのある,誰しもがこの問いに直面するだろう。学習目標はどこにあり,そこに至る手段は何か,結果として学習者が何を身に付けるのか? 授業設計や研修設計を考える際はこの問いに基づき,授業や研修の目標・学習内容と学習活動・学習評価の整合性が取れているかを考える必要がある。
教育学のウィギンズらは,目標に準じて学習内容を定め,最後にテストなどの学習評価を行うという順序(順向き設計,forward design)が,知識の詰め込みを誘うと指摘している1, 2)。教師は,自身が専門家であればあるほど,知っていることを教えたいという「網羅の罠」に陥りがちであるからだ。
それに対し,目標に沿った学習評価の方法を先に定め,学習内容の配置を検討することを「逆向き設計(backward design)」という。基礎知識の定着を目標とするならば,最終的な学習成果を測るために,何らかの客観的テストやクイズを課すことが多い。逆向き設計では,その作問を先に行う。その問題を解くために必要な学習内容をあらかじめ厳選し,授業内外の学習活動の種類や時間配分を設計するのだ。目標に達するかどうかを授業の前に見通して考えておくこと,それに基づいて学習内容・活動の配分を行うことは,結果として学習者を主語とした授業設計につながる。
連載第2回で取り上げたアクティブラーニングの効果を高めるには,逆向き設計での目標や評価に照らして適切な学習活動をデザインする必要がある。ただし,活動すること自体が目的化してしまった場合には,「経験あって学びなし」となるだろう。教師は「印象に残るように豊富な事例をうまく与えられた」となり,学習者は「今日のグループワークはお互いをよく知ることができて楽しかった」となる。ところが,振り返っても内容を一向に思い出せない。これは活動を過度に重視する「活動の罠」となり,「網羅の罠」と合わせて「双子の過ち(twins of sin)」と呼ばれる。
授業設計の三角形を描くには
この過ちを乗り越えるには学習者の特徴やカリキュラム上の位置付け,環境・資源といった状況的要素の上に,あらかじめ授業設計の三角形を描く必要がある(図1)。教育学のフィンクは,授業設計の三角形を達成するために,「意義ある学習」の相互作用の特質を提唱している3)(図2)。バークレイらによれば,6つの特質を基に学習目標を明確にすることが可能になる4)。①基礎知識(重要な事実,原則,アイデア,および概念を理解し,想起できること),②応用(問題解決,スキル習得,批判的思考,創造的思考,または実践的思考などのために基礎知識を理解すること),③統合(授業内あるいは授業間の異なるアイデアを結びつけ,授業を越えて学生の日常生活に広げること)の3つは,学習者の認知的側面に焦点を当てる。学習者には授業を通して,主に知識や概念をどこまで理解し身に付けてほしいのかが...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.03
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。