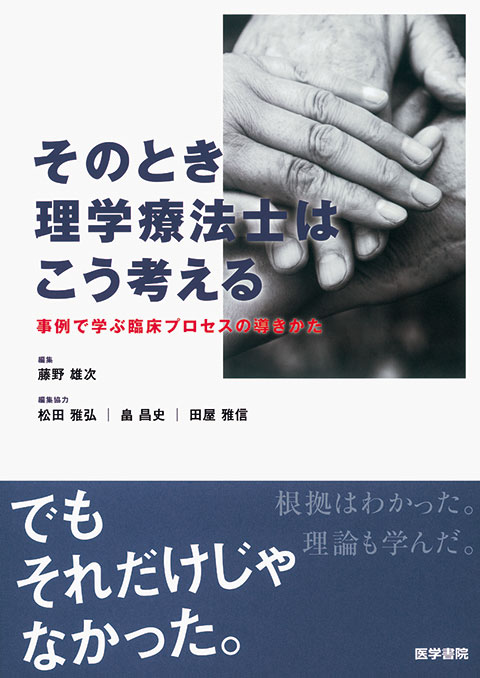米国の制度事情から考える,望ましい理学療法士教育の在り方
対談・座談会 Barbara Connolly,横山 美佐子
2025.08.12 医学界新聞:第3576号より

理学療法士の教育は,その国の医療制度や文化を反映しながら常に変化しています。日本と米国では,その教育システムにどのような違いがあり,また共通の課題は存在するのでしょうか。本年5月に日本で開催されたWorld Physiotherapy Congress(世界理学療法連盟学会)にてプログラム委員を務めた横山氏と,長年にわたり米国の理学療法士教育を牽引し,国際小児理学療法士機構(IOPTP)の会長も務めたConnolly氏が,それぞれの国の教育事情と課題を共有しました。
Connolly 私は40年近くにわたり教員を務めた理学療法士(以下,PT)です。長年教育に携わる中で,アメリカのPT養成は学士課程,修士課程,そして理学療法博士(Doctor of Physical Therapy:DPT)課程へと移行してきました。つまり,カリキュラムをはじめとする教育システムの変遷と,それに伴う卒業後のPTの働き方の目まぐるしい変化を目の当たりにしてきたことになります。現在は大学教育の現場から離れ,以前会長を務めていた国際小児理学療法士機構(IOPTP)で小児理学療法の発展に向けた国際的な活動に従事しています。本日は横山先生とお話しすることを楽しみにしてきました。
横山 思い返せば私たちの関係は,2014年,当時IOPTPの会長だったConnolly先生が私に突然,Facebookのフレンド申請を送ってきてくださったことから始まりましたね。私も小児理学療法を専門として活動・発信をしていたので,先生のプロフィール欄を見て驚いたことを今でも覚えています。その後,私たちのFacebook上での関係がきっかけで日本理学療法士協会(JPTA)がIOPTPともつながりを持つことになったので,このご縁に今も感謝しています。
米国では博士課程(DPT)修了が資格取得の必須要件
横山 同じPTとは言え,アメリカと日本では,資格取得までの過程が全く異なると認識しています。先ほど触れられていたように,現在アメリカでPTになるには,博士課程の修了が必須となっていますよね。
Connolly ええ。PTに求められる専門性が高度化する流れを受けて必須学位がDPTに移行したことは,アメリカのPT教育における近年で最も重要な変化と言えるでしょう。DPTは修士課程を経ずに進学できる,資格取得要件認定のための博士課程です。一般的に知られている,博士後期課程で学術を修めた人に授与される博士(PhD)とは全く異なります。
横山 DPTはアメリカ独自の制度ですが,諸外国では学士以上の学位を取得してからPTになる仕組みが一般的になっています1)。
Connolly そうですね。DPT課程への移行は1993年に始まり,2015年には全ての養成課程がDPTになりました。
横山 日本では大学での養成課程が拡大しつつも,現在も専門学校から資格を取得される方が多数を占めており,教育の多様性が保たれている現状があります。しかし今後,PTに求められる専門性や社会的責任の増大に対応するためには,教育水準のさらなる高度化と,大学教育の一層の充実を図る必要があると考えています。
Connolly 確かに,DPTの推進はカリキュラムの高度化と学生の能力向上にとってプラスに作用しました。一方で相応の課題も生じさせています。他国の取り組みから日本に適した要素を学び取り,柔軟に取り入れていくことが求められるでしょう。
横山 ちなみに,DPTへの移行によってどんな課題が生じたのですか。
Connolly 大きなところでは,DPT修了後のPhDを取得するPTが少なくなっていることが挙げられます。DPTを最終学位だと考えてしまい,それ以上にアカデミアで学ぼうとする人が減ってしまったのです。アメリカの教育システムでは,全ての養成プログラムに中核職員と呼ばれる教員を配置するよう定められています。当初,中核職員の要件にはPhD取得が明記されていたものの,結果的に中核職員をはじめとする現場の教員不足を引き起こしました。現在はその対策として中核職員の要件を変更し,特定の条件を満たしたスペシャリストのPTも同じ役割を担えるように制度が変更されましたが,依然として教員不足は大きな課題です。DPTを推進した結果,PhD取得者がこれほどまでに減少するとは予想していませんでした。これからアメリカでPTをめざす人々には,DPTはあくまで入門レベルの学位であることを一層強調していかなくてはなりません。
また大学院進学を前提とした制度設計による学生の経済的負担増加も見過ごせない課題です。資格取得までの専門性涵養を重視しつつ,経済的理由でPTをめざすことをやめてしまう学生が出てくることを防ぐような仕組みづくりが今後さらに必要になるでしょう。
時代の変化と役割の多様化に即した教育システムの構築を
横山 医療の高度化や地域移行,それに伴う多職種連携の広がりなどを背景に,日本におけるPTの役割もますます多様化し,需要も増加しています。しかしこうした変化に各施設のカリキュラムや教育システムは対応しきれておらず,大学化推進の遅れとは別に,日本の卒前教育が抱える課題であると考えています。指定規則やガイドラインで大まかな指針は示されているものの,実際の指導内容は現場の教員に委ねられているのが実情です。
Connolly 難しい問題ですね。現場の主体性は大切ですが,それが発揮できるのは前提となる枠組みがしっかりしているからこそとも言えます。
横山 まさにそうです。結果として教育者や施設ごとの強みの多様化にはつながっておらず,無難な方向への均質化が進んでいるように感じています。例としては国家試験対策ばかりを意識した知識偏重の教育スタイルです。また,教育モデルの開発が進んでいる医学教育の型に理学療法の学習を適用しようとするあまり,疾患ベースでの学習ばかり実施してしまうケースも散見されます。例えば小児,成人,老年といった区切り方でアプローチを考えることは臨床では当然重要ですが,そうした切り口での考え方がなかなか身につきにくい環境ができ上がっているのです。この点,アメリカのカリキュラム設計はどのような工夫がなされているのでしょう。
Connolly アメリカの場合,理学療法教育認定委員会(Commission on Accreditation in Physical Therapy Education:CAPTE)の基準により,各養成機関での教育内容は,現代の理学療法実践,実践基準,最新の文献,そして教育理論に基づいていることが求められます。最新の基準は2023年に採択されました2)。
教育カリキュラムの設計と実行に当たっては,解剖学,生理学など個別の科目ごとに系統立てて学習する「システム型」,疾患や特定の科目に関する学習を小児や成人,老年などの切り口で考える「ライフスパン型」,症例を提示し,「この患者にどのようにアプローチするか」を学生に考えさせる「問題解決型」などのアプローチが,養成機関や科目に応じて採用されています。CAPTEの指針は具体的かつ複数の教育的アプローチを示しているので,多様な教育の需要に応えつつも,全体の質を担保することにもつながっています。一方で柔軟性,多様性を考慮するあまり施設や地域によって教育スタイルが大きく異なり,全体で見れば結果的に複雑な教育体系を構築していることも事実です。
横山 とても参考になります。多様な教育の在り方という観点でさらに質問させてください。近年,オンラインツールを取り入れた教育が領域を問わず世界的に盛んになっています。アメリカのPT教育では,どのような活用・実践が行われているのでしょうか。
Connolly オンライン教育の活用で特筆すべきトピックとして,過去10年間で開発されたハイブリッドプログラムがあります。これは,学生がウェブセミナーや遠隔学習で多くの授業を受講し,臨床実習や実践的な学習のみを目的に短期集中的に数週間だけキャンパスを訪れる形式です。これにより,遠方の学生や個人的な事情でキャンパスに恒常的に通えない学生を拾い上げることも実現しています。当初はオンライン教育の学習効果に懸念もありましたが,国家試験の合格率は通常のプログラムと遜色ありません。この柔軟な学習形態は,世界的に新たな潮流になる可能性を秘めていると感じます。
PTによる早期介入の重要性
横山 私たちは小児理学療法の専門家でもあるので,本分野にフォーカスした話もしたいと思います。日本では,小児を対象とした実践教育に関してはまだまだ不足しているのが現状です。運動発達学の授業ですら,小児の発達への理解に重点を置いていないケースがあります。
Connolly なぜそのような状況が発生しているのでしょうか。
横山 実践的に理解するためのカリキュラムがそもそも整備されていないことが原因でしょう。また,「成人の運動学習を学んでいれば,小児にも応用できる」といった考え方が,教育現場に根付いていることも背景にあるのかもしれません。臨床現場においても小児領域の課題は多く,例えば子どもの発達が遅れている場合,基本的には疾患ベースで考えるため,診断がつかなければ経過観察になりがちです。こうしたケースではPTが早期介入することで環境要因を特定し改善につながることは少なくないので,もどかしい気持ちもあります。
Connolly 早期介入は,アメリカでは法的基盤が定められているほど重要視されています。障害者教育法(Individuals with Disabilities Education Act:IDEA)は早期介入の対象や目的を規定するだけではなく,早期介入サービスを受けることは発達の遅れや障害を持つ子どもの権利であると保障し,各州に早期介入プログラムの整備を義務付けています。
横山 素晴らしいです。もちろん日本でも発達の遅れや障害を持つ子どもを支援する法律や福祉は整備されていますが,PTの早期介入について法的根拠はありません。また各サービス・制度はどうしても縦割りになりがちで,医学的診断がついた後はスムーズなケアにつながることが多い反面,診断がつく前のサポートは地域や専門機関ごとにかなり差があります。この点はアメリカのように「子どもの権利」を法的にも整備し,PTによる早期介入に限らず,各種サポートへのアクセスを改善していく必要があると考えます。
実践を重視する米国の教育スタイル
横山 PTによる早期介入の社会基盤が整っているということは,卒前教育における実習が非常に重要になりますよね。Connolly先生が大学で指導していたころはどのような実習を行っていたのですか。
Connolly 具体的な実習の内容は施設ごとに異なる部分も多く一概には言えませんが,前提としてアメリカではPT教育全般において,学生が早い段階から実践的な経験を積むことが重視されています。
私が担当していた授業では,本格的な臨床実習が始まる前の段階で,学生を児童リハビリテーションセンターや学校,あるいは特別な支援を必要とする子どもたちと健常な子どもたちが一緒に過ごす地域のプログラムに参加させていました。まず学生は授業で学んだ評価ツールを使って子どもたちを評価し,治療計画を立てる練習をします。次の週には,教員の監督のもと,実際に治療を試す機会を与えていました。これは,学生がフルタイムの臨床実習に行く前の貴重な「手を動かす」経験となっていました。フルタイムの臨床実習については,私の授業では8週間の実習を2回,別々の施設で行っていました。
横山 それだけ実践を重視して実習の量を増やしている状況では,指導・評価する教員にもハイレベルな臨床能力が求められますよね。
Connolly その通りです。教員自身の臨床能力向上のために,在籍していた大学では研究を主に行う教員を除き,全員が週に最低1日は臨床に出ていました。その大学はキャンパス内でクリニックを運営していたので,教員がそこで患者を診る際に学生を連れて行き,治療中の様子を見学させることも可能でした。
横山 自身の臨床を実際に見せることができるのは良いですね。実習とはまた違った学びが得られそうです。
Connolly 加えて小児理学療法の教員は,実際の早期介入プログラムに参加し,週に1日子どもの自宅を訪問する際に学生を同行させていました。こうした経験は学生にとって,臨床実習とは別に現実の世界で臨床を学ぶ重要な経験になり,診療報酬や保険償還といった実務的な側面を学ぶ機会にもなります。
横山 お話を伺っていると,教員に求められるタスクの幅が想像以上に広く,負担がかなり大きいようにも感じられますね……。
Connolly 実際に現行制度下での教員の負担の重さは問題視されていますので,今後改善していくべき課題と言えるでしょう。昨今では,実際の現場に行かずとも精巧なモデルを用いて臨床スキルを学べるシミュレーションラボの導入が進んでおり,以前は初期の臨床現場で期待されていたような患者対応の経験を,キャンパス内で積むことができるようになってきています。今後はこうした技術の活用もますます広がっていくでしょう。
資格取得は生涯にわたる学びの始まりにすぎない
横山 本日お話しして,アメリカの教育システムから学ぶべき点が本当に多いと改めて実感しました。欧米は日本と比べてPTの社会的認知度が高く,専門職として任せられている役割の範囲も広い傾向があります。日本も追随するには,医療や社会に貢献するための専門性と実践力をこれまで以上に培うための教育づくりが不可欠です。海外の教育制度から多くを学び,日本に適した形で取り入れていけるよう頑張りたいと思います。最後にConnolly先生から,PTをめざす日本の学生にメッセージをいただけますか。
Connolly 国家試験に合格し,PTの資格を得ることは始まりにすぎません。大切なのはキャリアを通じて学び続けること,つまり生涯学習に対する意識を忘れないことです。なぜなら,養成課程で学んだことは,5年から10年以内に新しいものに取って代わられるからです。私は54年間,PTとしてこの領域に携わっていますが,理学療法,そして医療は常に変化しており,どれだけ長く専門職として働いていても,常に新しい学びがあります。
そして小児理学療法士を志す方にもう一つ伝えたいことがあります。小児理学療法士は,自分の手で子どもを変えていると信じがちです。しかし,実際はあなたの手ではなく,あなたが子どもを見て,何が必要かを判断する能力こそが違いを生むということを覚えていてほしいです。
横山 今日はありがとうございました。
(了)
参考文献・URL
1)日本理学療法士協会・日本理学療法教育学会.理学療法教育モデルの検討報告書.2019.
2)CAPTE. STANDARDS AND REQUIRED ELEMENTS FOR ACCREDITATION OF PHYSICAL THERAPIST EDUCATION PROGRAMS. 2023.

Barbara Connolly(バーバラ・コノリー)氏 テネシー大学ヘルスサイエンスセンター 名誉教授 / 前・国際小児理学療法士機構 会長
1970年に米フロリダ大を卒業し理学療法の学士号を取得。80年メンフィス大教育学博士課程修了。2007年テネシー大理学療法博士課程修了。世界理学療法連盟の下部組織である国際小児理学療法士機構の会長を07年の設立時から15年まで務める。1986~2010年までテネシー大ヘルスサイエンスセンター理学療法学科学科長,以降同センター名誉教授。理学療法の研究資金提供を専門とする財団である理学療法財団の評議員を務め,15~16年まで同財団理事長。『Therapeutic Exercises in the Developmental Disabilities』(SLACK Incorporated)ほか著書多数。

横山 美佐子(よこやま・みさこ)氏 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 講師
1986年東京衛生学園専門学校リハビリテーション科卒。同年より北里大病院リハビリテーションセンター部,91年より医療法人社団健省会中村整形外科での勤務を経て,2001年北里大病院リハビリテーションセンター部に復職。06年より現職。01年放送大発達と教育専攻卒業。08年国際医療福祉大大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻修了。13年北里大大学院医療系研究科医学専攻修了。博士(医学)。発達期の運動療法,小児呼吸理学療法などを専門とする。一般社団法人日本小児理学療法学会副理事長。2025年の世界理学療法連盟学会では日本人で唯一のプログラム委員を務めた。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。