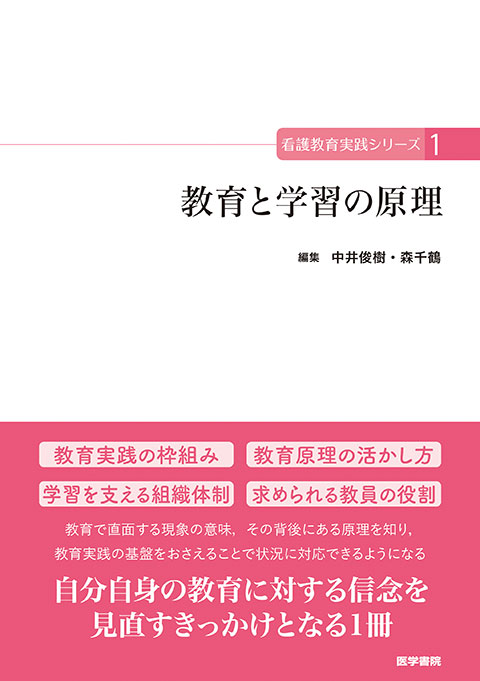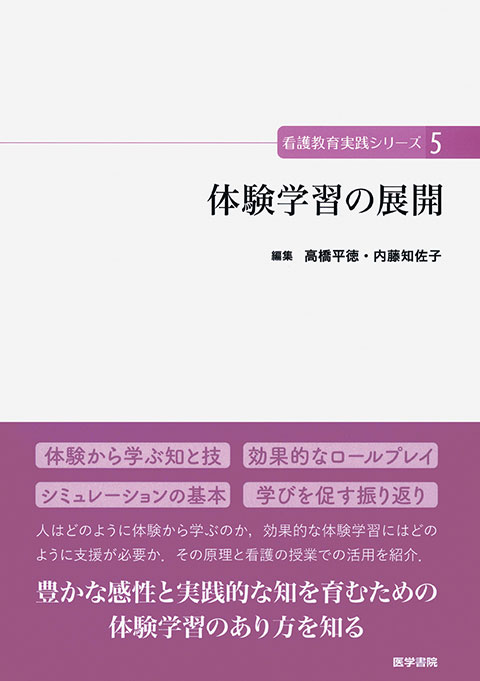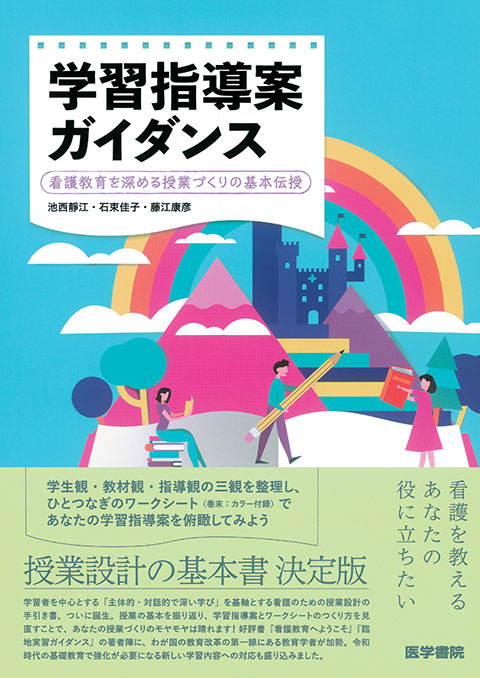教えるを学ぶエッセンス
[第1回]教えるということ,学ぶということ
連載 杉森 公一
2022.04.25 週刊医学界新聞(看護号):第3467号より
今回のポイント
✓ 学習者が,身についた・学んだとの実感を持って初めて「教えた」が成り立つ。
✓ Learn(学び)→unlearn(学びほぐし)→relearn(学びなおし)の学習サイクルが,受動態としての「教わった」から,能動態としての「学んだ」へ転換する。
本連載のテーマは「教え方」である。看護職を主な読者対象に,「教え方」について共に理解を深めていきたいと考えている。読者の中には,看護師養成校や看護系大学で教員をされている方,臨床で管理職や先輩看護師として人材育成や後輩指導を担われている方,あるいはこれから教える立場になる方も多いのではないか。また,患者やご家族に健康指導や助言をする方の中にも,「教え方」に関心をお持ちの方がいるかもしれない。
ここでのポイントは,どのような立場であれ,教える側は相手があって初めて教え手になるということだ。「教える」という行為が成り立つ(=「教えた」)のは,相手が「身についた・学んだ」と実感を持った時である。相手の実感がなければ,教えたのではなく伝えたにすぎない。
生涯にわたる学びと「教え方」
私たちは生まれた瞬間から,泣き,笑い,食べ,動き,感情や行為,言葉を見習い,真似て育ってきた。学ぶは「真似ぶ」に由来するとよく言われるように,人は生来学ぶことに長けた生き物であり,私たちは皆,学びの専門家とも言えるかもしれない。
いまや18歳人口の80%以上が高等教育機関(専門学校,短大・大学,大学院)へ進学し,社会人になってからも生涯学習やリカレント(学び直し),リスキリング(再スキル習得)といったキャリア形成が続く。長期化する学習の過程で,ともすると知識とスキルは「効率よく」「大量に」「高度に」摂取させられているようにも見える。工業社会から知識社会への転換点である「情報化の時代」に生きる現代人は,急速な社会変化と氾濫する情報に影響されて,ゆっくりじっくりと学ぶ余裕がなくなっているようにも感じられる。
「教育」を意味するeducationは,ラテン語の「引き出す(educere)」,あるいは「養育する(educare)」が語源とも言われる。学校において教師が教えることで子どもが育つ,との意味は元来持っていなかったようだ。福沢諭吉はeducationに「発育」の訳語を当てたが,現代の長い学習歴においてはdevelopment=発達のほうが合致しているかもしれない。
筆者は非医療職で,実は教育学者でもない。専門分野は化学を出自とし,現在は大学にて理学療法士,臨床検査技師,臨床工学技士を志す大学生への生物や化学の指導を担当する傍ら,「教育開発者(educational developer)」と呼ばれる職に就いている。大学で教える研究者(教員)に授業設計や教育技法を研修する専門職であり,北米では大学教員200人に対して1人程度必要と言われているものだ。
本連載では,そのような筆者の立ち位置から「教え方」について,特に生涯にわたる学びの中にある読者に,教え方にまつわる理論から実践までの広範なトピックスを紹介できればと思っている。それは翻って,学びのただ中にいる筆者自身にとっても新たな学びの理解となるであろう。
なぜ学ぶかの前提を問い直す
「私は大学でたくさんのことを学んだが,そのあとたくさん,学びほぐさなければならなかった」。これは哲学者の鶴見俊輔が大学生の時に,ヘレン・ケラーから掛けられた言葉だ。近年,「学びほぐし(unlearn)」という言葉がよく聞かれるようになったが,この鶴見とヘレン・...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
杉森 公一(すぎもり・きみかず)氏 北陸大学高等教育推進センター長・教授
2002年筑波大第一学群自然学類卒。04年同大大学院教育研究科修士課程,07年金沢大大学院自然科学研究科博士後期課程修了。同大教育開発・支援センター准教授などを経て21年より現職。修士(教育学),博士(理学)。専門は計算量子化学,理科教育および大学教育開発。
いま話題の記事
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。