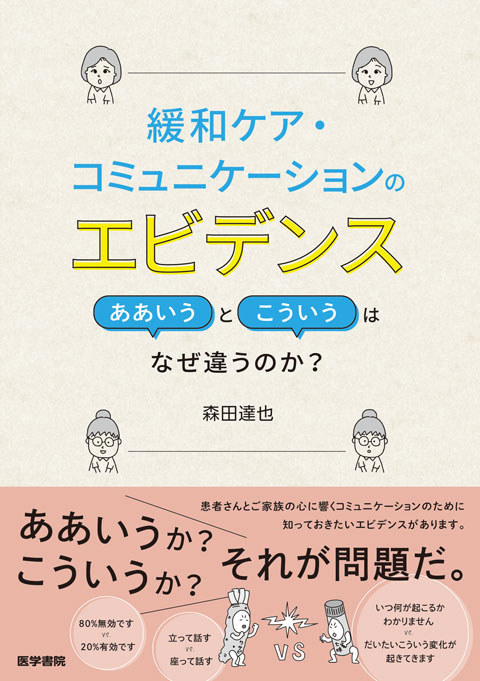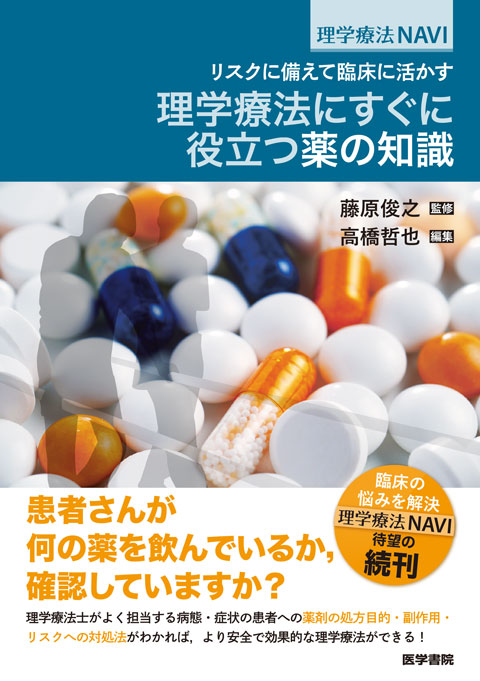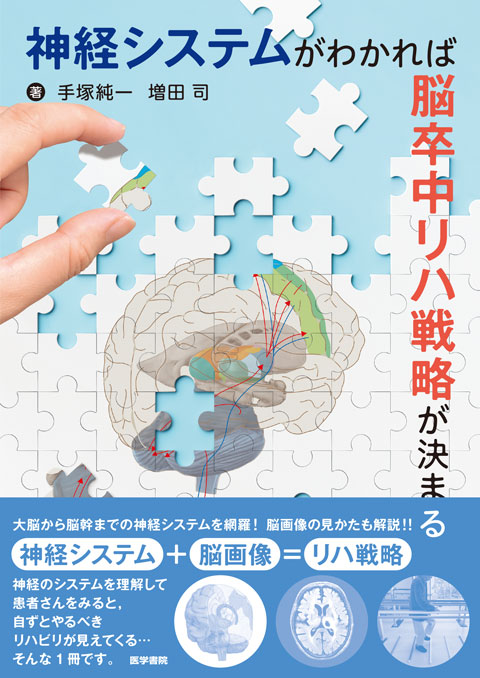MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.10.04 週刊医学界新聞(通常号):第3439号より
《評者》 頭木 弘樹 文学紹介者
患者目線で読んでみた――全医療者に読んでほしい本!
病院に行くとき,録音機を持って行こうかと迷う。説明を覚えきれないからだ。いい加減に聞いているわけではない。その逆で,一つひとつの医師の発言に集中し,ちゃんと理解しようとしている。それだけにそしゃくに時間がかかり,次々に繰り出される言葉を飲み込みきれなくなる。
しかし,いまだに持って行ったことはない。医師のショッキングな発言が録音されるといやだからだ。消せばいいだけなのだが,録音されたらと思うだけで,もう胸が苦しくなり,やめてしまう。
それくらい,医師や看護師の言葉は患者に突き刺さる。医療者が一度発しただけの言葉を,患者は何百回も反すうすることがある。病院の待合室で話していると,「20年前のあの医師の言葉がいまだに忘れられない」などという人がたくさんいる。
もちろん,患者側が過敏すぎる面もある。医療者は大勢の患者を相手にしているわけで,全員に気を遣ってはいられない。治療さえちゃんとやってくれれば,言葉とがめはなるべくしたくないと思っていた。
だからこの本も,読む前は,「患者の気持ちをわかってあげましょうと書いたところで,現実には難しいのでは?」と思っていた。ところが,そういう本ではなかった。「相手をわかろうとすることがどういうことか生まれついて『わからない』人に自然なコミュニケーションを求めるのは酷」とまで著者は断じている。医療者にだって,当然そういう人はいる。「人は共感性も態度もなかなか変えられない。それならば,せめて,ああいう・こういうを工夫する」という,じつに現実的な本で,目からウロコだった。
実際,この本に書かれている工夫は,患者の側から見て,「ぜひそうしてほしい!」と思うことばかりだ。例えば副作用の説明で「5パーセントに吐き気が起こる」と「95パーセントで吐き気は起こらない」では,たしかに言われる側としては大違いだ。しかも,そのような言い方をすることで,「副作用の発生率を減らすことができる」ということに驚いた。
客に愛想がよくてまずい鮨屋より,無愛想でもうまい鮨屋のほうがいい。医療者に関しても,そういうふうに思ってしまうところがある。しかし,この本を読むと,患者への言い方を気をつけることは,治療ともなり得るのだ。これも目からウロコだった。
患者の「言葉と意図は違うことがある」と著者が認識していることにも深く感動した。それが原因の医師と患者の行き違いは,入院中に6人部屋でたくさん目にした。それがどういうことかは,この本に出てくる事例を読んでみてほしい。事例が豊富なのも,この本のありがたいところだ。
というわけで,読む前とは完全に考えが変わり,今は全ての医療者にこの本を読んでほしいと思っている。自分の主治医にも。
また,ここに書いてあることは,医療者と患者だけでなく,さまざまなところに応用できると思った。私自身,仕事やプライベートでも,ああいう・こういうを工夫してみるつもりだ。
《評者》 森 明子 兵庫医療大准教授・理学療法学
理学療法士のリスク管理能力を進化させる一冊
「理学療法」と「薬」,どちらも医師の処方という共通点がある治療法です。その両者の視点を踏まえた,すぐに役立つリスク管理本がこれまであったでしょうか。本書には読者を引き込み,理学療法士の頭脳に響く仕掛けがちりばめられており,まさにリスク管理能力を進化させる書籍です。
2020年4月以降の理学療法士養成校への入学生は,改正された「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」が適用となり,専門基礎分野として「臨床薬理の基礎」を学ぶことが必修化されました。その背景には医療の高度化やさまざまな医療ニーズに対応していくため,理学療法士も薬の知識が必要不可欠とされたことがあります。
チーム医療の概念が広まり,医療現場において医師,薬剤師,看護師,理学療法士,作業療法士などは,お互いに連携して患者の治療に当たり,患者中心の医療を展開することが定着してきました。そこではさまざまな情報交換や共有がなされますが,これまで理学療法士は薬の知識を学ぶ機会が少なかったため,患者に処方されている薬の情報を得ても,それを踏まえたリスク管理下での理学療法につなげる難しさがありました。
本書には,理学療法士が担当することの多い疾患の病態や症状の特徴が簡潔に書かれています。各疾患における「その薬が処方されている目的と効果」,「薬剤はいつまで使われるか?」など,投薬治療の一般的な見通しについての解説があります。日ごろ,臨床で経験する場面が会話形式で書かれており,理学療法上,特に留意すべき薬剤について触れられています。さらには「理学療法上のPOINT!」として「理学療法中の事故を防ぐための中止基準」や「リスクマネジメントの具体策」も提示されています。常に日々の臨床場面に当てはめて読み進めることができる構成なので,まるで本書に登場する理学療法士が自身であるかのような感覚になります。書かれている内容の一つひとつがふに落ち,多くの気付きが得られ,深い学びにつながる流れになっています。
重複疾患を有する患者の場合,処方される薬は複数に及ぶため,薬の全てを把握することに困難さを感じることもあります。しかし,本書にもある「クスリはリスク」という言葉を踏まえると,薬の数だけリスクがあると読むことができます。そのため,理学療法を実施する上で,なぜ薬の知識を知っておく必要があるのか,本質的に理解しておくべきことは何なのかを端的にまとめてあり,具体例も示されています。
本書は初学者にも読みやすい内容になっています。理学療法士だけではなく,臨床実習に臨む実習生や,リハビリテーション医療に携わる多くの関連職種の方にお薦めします。急性期・回復期・生活期などさまざまな臨床場面でより適切なリスク管理を行うためにもぜひ,お手元に置いていただきたい一冊です。
《評者》 諸橋 勇 青森県立保健大教授・理学療法学
臨床と脳画像の橋渡しとなる一冊
◆難しいことをやさしく,やさしいことを深く
「難しいことをやさしく,やさしいことを深く,深いことを面白く」。
本書を手に取った瞬間,故人である作家の井上ひさし氏の言葉が頭に浮かびました。これは教育や学びの極意であり,本書はこれを満たすとともに,「こんな本が欲しかった」という私の希望をかなえる一冊です。CT,MRIやPETなど機器の発展に伴い,長らくBlack Boxといわれてきた脳の機能が次々に解明されてきました。脳画像診断や脳機能に関する本が多数出版され,多くのリハビリテーション専門職が学びを得ることができました。ただし,その執筆者の多くが脳を専門とする医師や研究者であったことも事実です...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。