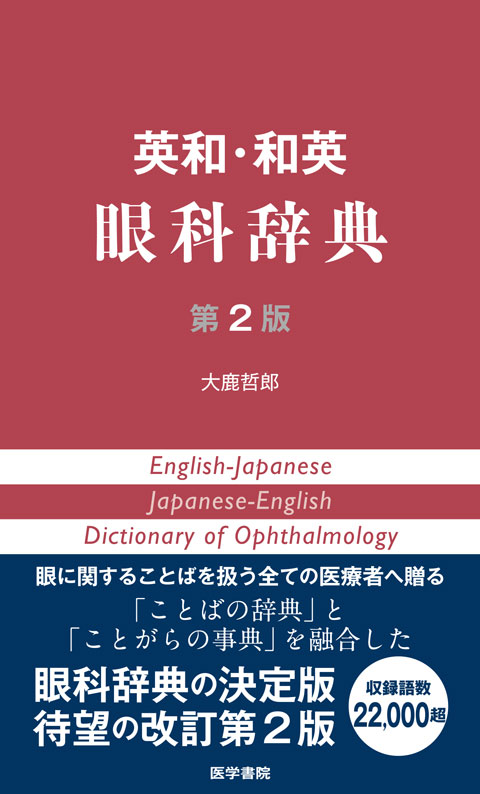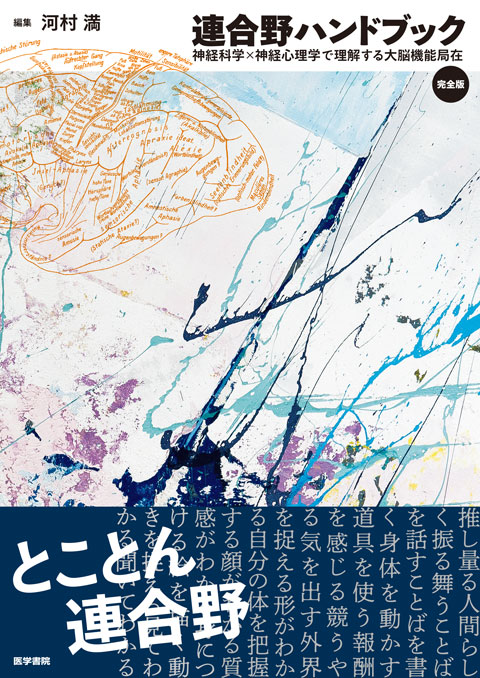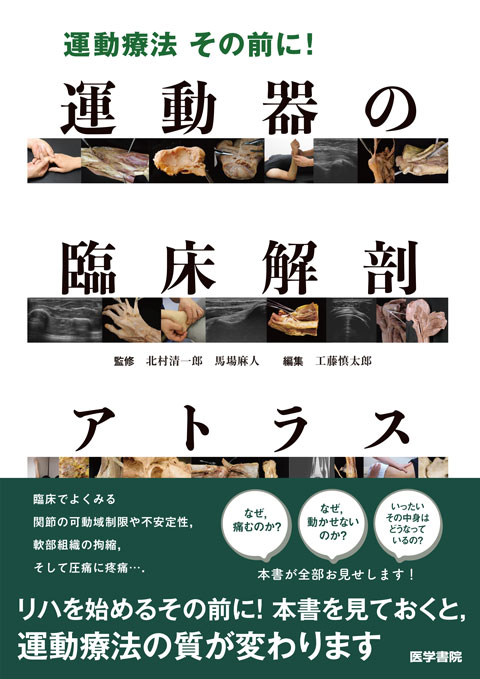MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.08.02 週刊医学界新聞(通常号):第3431号より
《評者》 辻川 明孝 京大大学院教授・眼科学
眼科とその関連分野の用語・知識を集約した一冊
人は外界からの80%以上の情報を視覚から得ているといわれており,視覚は眼球という器官で受容されます。眼球は直径24 mmの小さな器官ですが,結膜,角膜,水晶体,ぶどう膜,硝子体,網膜,視神経などの多くの組織から構成され,独自の役割を持ち,協働しながら視覚情報を得るために機能しています。各組織にさまざまな臨床所見があり,病態があり,病気が生じ得ます。視覚情報に対して人は非常に敏感ですので,わずかな視力の低下,少しの像のゆがみ,色の違い,大きさの違い,目のかすみなどに,すぐに気が付きます。また,小さな異物が入っただけでも角膜の表面に傷がつき異物感を感じるなど,痛み,痒みなどの刺激にも敏感です。そのため,眼球には非常に多くの病気が存在し,詳細に分類されています。先人のたゆまぬ観察・研究の蓄積により多くの病気が発見され,病態が解明されてきたのです。
また,眼科診療はものすごいスピードで進化しています。眼科は眼底写真,光干渉断層計,造影検査などの画像検査を多用するため,検査機器の進歩とともに新たな病態・所見が明らかになり,診療に生かされてきました。現在の診療レベルと20年前の診療とでは全く異なったモノになり,眼科の種々の分野別の専門化が進んでいます。そのため,恥ずかしながら,私も自分の専門分野以外のことはあまりわかりませんし,専門分野でも最新のことを全て網羅できているとはいい難いです。
初版から23年の歳月を経て,今回改訂された『英和・和英 眼科辞典 第2版』では,この期間の新しい内容が完全にアップデートされました。眼科からその周辺の関連分野にかけて2万2000の用語が収録され,英語・日本語の用語の翻訳に加えて,用語の解説が添えられています。眼科関連の用語が網羅されているだけでなく,先人の偉業から最新の情報まで眼科の知識が集約されています。英語の文献を読む時,眼科に関する用語を調べたい時には何でも用が足りるベストの一冊といえるでしょう。
《評者》 花田 恵介 医療法人錦秀会阪和記念病院 リハビリテーション部
“不思議な”症状に遭遇するセラピストに薦めたい
神経科学は,PT,OT,ST(セラピスト)が脳機能を理解し,リハビリテーション介入を計画する上で欠かせない。脳損傷後のリハビリテーションにおける革新的な治療機器開発においても,その理論的根拠は神経科学の知見によるところが大きい。しかし,一人ひとりの患者が見せる症状は,統制された実験環境における反応よりもはるかに複雑で,一見では整理し難いように思う。また,われわれは,「目の前の患者がなぜそのような症状を見せるのか?」を説明したいとき,神経科学の表面的な示唆だけをすくい取って曲解しがちである。本来であれば,患者の症状が真にその知見と合うかどうか,細かく症候を鑑別すべきである。
他方の神経心理学は,脳損傷患者の神経症状をどう鑑別し,患者の理解につなげるかを教えてくれる,臨床現場に密着した知見である。しかし,神経心理学的な知見のみでは,リハビリテーションを系統的に計画するための材料が不足しているように思う。われわれには,急速に進歩する基礎研究の知見を取り入れ,脳損傷ではそれがどう症状として反映されるかを注意深く観察,記述していくことで,隔たりを埋めていく作業が求められている。
本書は,その相補関係をまさに表現している。そして,大脳連合野の神経学における過去(歴史),現在,そして未来(課題)が示されている。この2点が,本書の大きな魅力である。まず,本書の編者である河村満先生が,連合野研究の歴史を解説なさっている。私が学生時代,当然のごとく学んだ用語や概念がどういった変遷を経て成立したかを知ることができる。当時ブラックボックスとされていた脳機能が,現代の技術でより詳しく説明できるようになったが,だからと言って,人間の脳が昔と現代で大きく変わったわけではない。過去の神経学者は,特殊な機器がなかった代わりに,現象をきめ細やかに記しているし,それは現代にも十分通用する考え方である。「古を以て鏡と為せば,以て興替を知る可し」である。
本書のメインテーマである「連合野」については,前頭・頭頂・側頭に分けられ,各連合野の解剖と神経科学,神経心理学の現在がセットで論じられている。他の書籍の中には,神経科学と神経心理学の双方の視点が整理されずに書かれているものもあるが,本書は「基礎編」と「症候編」でそれぞれの立ち位置が明確である。基礎編では各領野における研究の変遷から最近の知見が示されている。また症候編では,諸先生方の豊富な自験例が提示されており,読者はそれを読めば,患者の症候をどのように鑑別すれば良いかがわかる。
終章である「連合野私論」は,福武敏夫先生が執筆されている。長きにわたり臨床神経学を体現してこられた先生の自験例から,まだ明らかにされていない神経心理症候の可能性が示されている。福武先生がお示しになっている「今後の課題」は,私たちが未来の臨床で明らかにすべき命題だと思う。
セラピストは,他の医療職よりも同じ患者に長く接する機会が多く,それゆえ患者が見せる“不思議な”症状に遭遇する頻度も高いはずである。この分野に携わるセラピストであれば,ぜひ長く手元に置いておき,折に触れて参照したい。
《評者》 小林 匠 北海道千歳リハビリテーション大教授・理学療法学
解剖・運動器エコー・運動療法
3テーマの要点が一冊に
真っ先に感じたのは,「自分が若手の頃にこの本に出合えていたら,ものすごく助かっていただろうな」ということである。
本書は,運動器リハビリテーションの臨床場面において遭遇することの多い疼痛や機能障害に焦点を当て,それら...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。