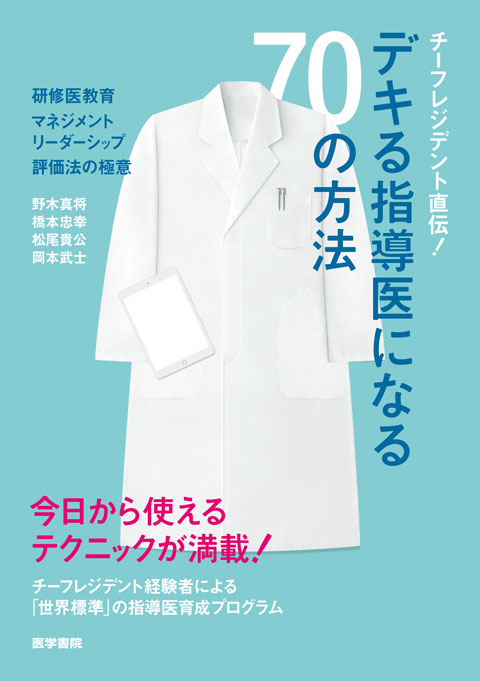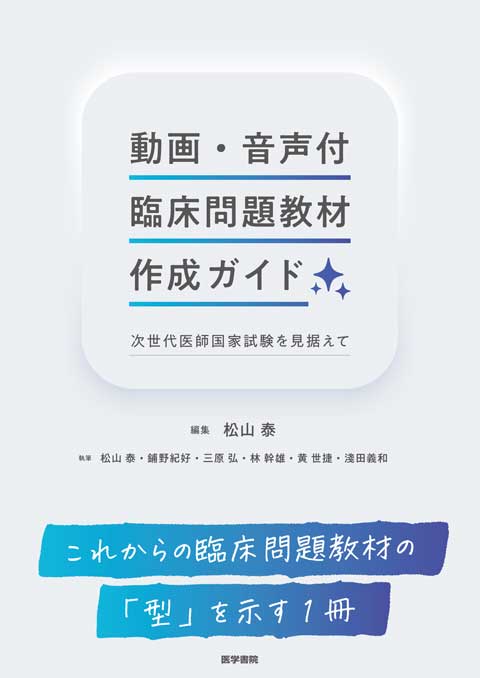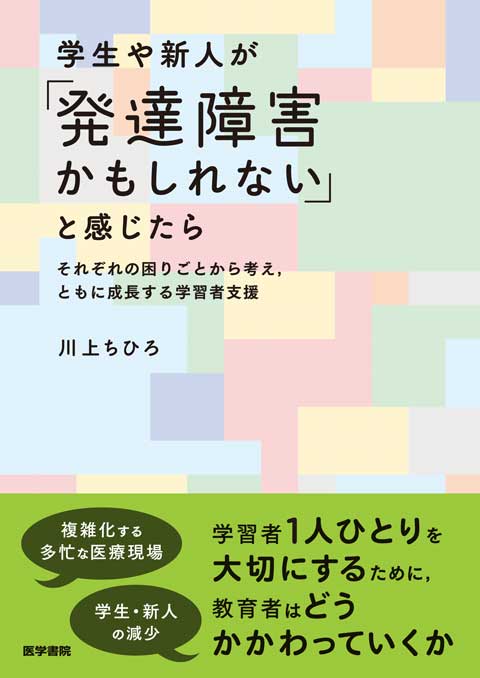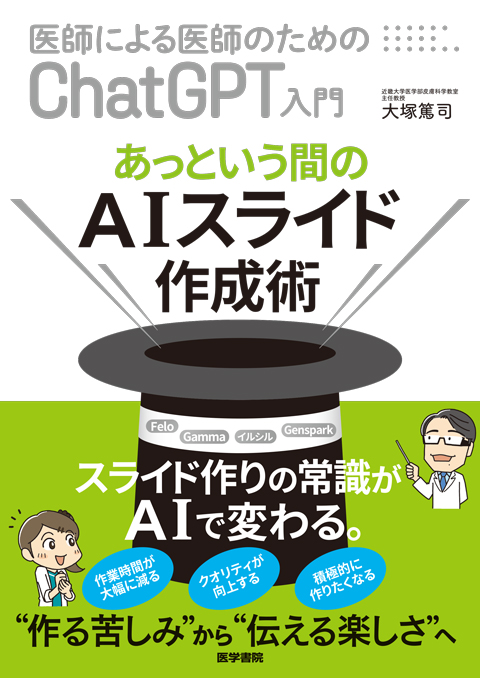- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2025年
- 医学界新聞プラス 第57回日本医学教育学会大会開催
医学界新聞プラス
第57回日本医学教育学会大会開催
取材記事
2025.09.09

第57回日本医学教育学会大会(大会長=秋田大学・羽渕友則氏:写真 )が7月25~27日,「次世代の医学・医療を拓くデジタル教育の新たなステージへ――All For Patients, All Together! 理想的なチームビルディングを目指して」をテーマに,あきた芸術劇場ミルハス(秋田市),他で開催された。
『医学界新聞プラス』では,シンポジウム「臨床研修指導医講習会の創意と工夫 」(座長=藤田医科大学・石原慎氏,日本赤十字社・横江正道氏)の模様を報告する。
◆議論の活性化や指導力の向上をめざした新たな試み
初めに登壇した 筑波大学附属病院の瀬尾恵美子氏は,受講者全員が能動的に学ぶために,講習会から全体発表をなくす試みについて紹介した。指導医講習会では一般に,プレナリーセッションと,その後の小グループ討論を繰り返すワークショップ形式で運営されることが多いと説明。この形式の場合,最終的にグループ討論の成果が全体発表で共有されるが,大人数の会場で一方向性の発表が行われるため,多くの受講者にとって能動的な学びにつながっていないと指摘した。その解決策として,筑波大学・茨城県・茨城県医師会が共同開催する茨城県指導医養成講習会で採用している「ワールドカフェ方式」(註)を紹介。積極な意見交換のために全体発表をなくし,少人数グループ同士での発表と意見交換を促すことで,大幅な時間短縮につながる上,活発な議論と他グループの成果共有を両立できると解説した。一方で,この方式にも注意点がある。同氏は懸念点として,最終的な成果物を全員に共有できない点を挙げ,全体に向けて掲示する工夫が必要であると述べた。
指導医講習会は,オンライン方式での実施も可能であることが2023年に公表された厚労省通知「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針について 」1)で明記され,オンライン会議システムを利用した講習会の開催が進んでいる。望月篤氏(聖マリアンナ医科大学)は,従来の1泊2日の対面講習から,オンデマンドによる事前学習と対面講習を組み合わせたハイブリッド型講習会へ移行した事例を共有し,時間的・費用的制約の解消に加えて,受講者の能動的な学習を促されたと述べた。同氏は理由として,受講者が自身のペースで学習し必要に応じて繰り返し視聴できる点や,基礎知識を持った状態で対面講習に臨めるため講義時間を短縮し,グループワークやディベートセッションに時間を割ける点を挙げる。オンラインのみの開催では討論が活発化しにくい傾向があることから対面講習も行う重要性も指摘した上で,今後は事前学習と対面講習のバランスをより精査し,プライマリーセッションをさらに事前学習へ移行し,対面ならではのプログラムを構築する必要性があると発表を締めくくった。
次に小松弘幸氏(宮崎大学)は,指導医講習会における「研修プログラム立案」のセッションに,受講者自身が担当する診療科をテーマとした「Myミニカリキュラム」の作成を追加した事例を報告した。従来の小グループ討議では,立案したカリキュラムを自身の指導にどう生かすべきか戸惑う受講者の声があったと述べる。これに対し氏が考案した個別作業のプログラムは,受講者が自分の診療科で研修医に実施することを目的とした現実的なテーマでカリキュラムを作成するものであり,氏はカリキュラム立案に対する受講者の当事者意識とモチベーションの向上が期待できると説明した 。
新たなプログラムの利点を述べる一方で,「Myミニカリキュラム」における個別目標の設定は,従来のプロセス基盤型教育に当てはまり,アウトカム基盤型教育へシフトする近年の潮流と齟齬が生じるという懸念を同氏は示す。医学教育理論や研修環境の変化を踏まえ,多忙な現場の指導医のニーズにマッチした講習会を構築するため,全国での好事例の共有や実態調査の必要があると呼びかけた。
長崎大学病院群が開催する指導医講習会における「OSTE(客観的臨床教育能力評価)」について述べたのは松島加代子氏(長崎大学病院)だ。OSTEは,OSCEの指導医版であり,臨床現場を模した小部屋にシナリオに沿って演技をする標準化研修医 を配置し,指導医として模擬的に研修医への教育を実演することで,その指導の仕方を評価するもの。評価によって研修医や学生に対する指導方法の振り返りを促すことが狙いだ。松島氏は,一年以内に講習会を受けた指導医のOSTEの成績と日頃の研修医からの評価には正の相関が見られることから,講習会で学んだスキルが実際の指導力向上につながると報告した 。
4人のシンポジストによる発表後,厚生労働省医師臨床研修推進室の野口宏志氏が登壇し,臨床研修指導医講習会の開催指針について近年の改正内容も踏まえて概説した。
講演後のディスカッションでは,受講者が当事者意識を持つための工夫や,開催指針の中で特に重点を置いている指導医講習会のテーマついて活発な意見交換がなされた。
註:少人数のグループで対話を行い,メンバーを入れ替えながら議論を深めていく手法。リラックスした雰囲気で,参加者全員が主体的に意見交換することを目的とする。茨城県指導医養成講習会では,10人1グループでの討論の後,自分のグループに発表担当の2名が残り,他のメンバーはそれぞれ別グループの部屋へ移動し意見交換を行う。その後,全員が自分のグループに戻り,互いに他グループの意見を報告するという流れで進行している。
参考文献
1)厚生省.医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針について.2024
『医学界新聞』では過去に,「指導医の育成を考える」をテーマとした座談会を掲載しています。シンポジウムに登壇された瀬尾氏,松島氏にもご参加いただいており,今回のご発表とも通じる内容となっています。ぜひ併せてご覧ください。
タグキーワード
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。