動画・音声付臨床問題教材作成ガイド
次世代医師国家試験を見据えて
次世代医師国家試験を見据えた臨床問題教材作成のためのガイドブック
もっと見る
厚生労働省による医師国家試験改善検討部会の報告書によれば、医師国家試験のコンピュータ試験化(CBT化)に伴い、動画や音声などのマルチメディア素材を活用した臨床問題の出題が推奨されている。本書ではCBT形式に対応可能な動画・音声付臨床問題の作成方法と、その教材化の実践的ノウハウを紹介。医療系教育関係者必読の1冊。
| 編集 | 松山 泰 |
|---|---|
| 発行 | 2025年07月判型:B5頁:184 |
| ISBN | 978-4-260-05981-7 |
| 定価 | 8,800円 (本体8,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
- 付録・特典
序文
開く
序
「医学教材を作成するガイドブック」という,これまでにないタイプの書籍をここに上梓する。しかも,写真や図,表,文章といった静的な素材で構成された従来の教材とは異なり,動画や音声などのマルチメディア素材を活用したDX対応の教材作成ガイドである。そのうえ,「臨床問題教材=臨床問題+(正解と解説による)教材」という構成を採用しているため,臨床問題自身を作成するマニュアルともなっている。極めつけは,「次世代医師国家試験を見据えた」教材という点である。
厚生労働省の医師国家試験改善検討部会の報告書によれば,医師国家試験のコンピュータ試験化(CBT化)が検討されており,CBT形式では静止画像に加え,動画や音声などのマルチメディア素材を活用した臨床問題の出題が推奨されている。本書では,CBT形式に対応可能な動画・音声付臨床問題の作成方法と,その教材化の実践的ノウハウを紹介している。
さらに,本書では最新の電子端末や生成AIといった先進技術を積極的に取り入れ,効率的かつ効果的な教材作成の方法にも踏み込んでいる。今後,教育現場において「何を教えるか」だけでなく,「どのように教えるか」がますます重要になる中で,科学技術を活用した教育コンテンツの未来像を示す一冊となることを目指した。
本書の主たる読者として想定しているのは,動画や音声といった臨床素材を活用して教材を作成したい医療系教育者,臨床問題の作成に悩む医療系学部の教員,そして次世代国家試験に向けた準備を始めたい学生の方々である。しかし,こうした新しい教育アプローチに関心をもつ他分野の教育関係者にとっても,多くのヒントが得られる内容となっているはずである。
本書が,それぞれの現場で未来の学びを切り拓く一助となることを願ってやまない。
2025年5月
松山 泰
目次
開く
第1章 医師国家試験のコンピュータ試験化
I 医師国家試験は進化する──「次世代医師国家試験」とは
II 医師国家試験のコンピュータ試験化の動向
III なぜ今,医師国家試験のCBT化が必要なのか
IV 医師国家試験CBT化に立ちはだかる課題と対策
V 医師国家試験CBT対応の動画・音声付臨床問題教材
第2章 臨床問題教材の作り方
I なぜ臨床問題教材か?
II 臨床問題の作成ルール
III 「臨床問題」を「臨床問題教材」にするためには
IV 臨床推論のプロセスを見直す
V 臨床問題の作成手順
VI 臨床問題における動画・音声素材の活用
VII 臨床問題におけるテーマの範囲
第3章 動画・音声付臨床教材の作成手順
I これまでの取り組みとその変遷
II ICT臨床教材の基本形式
III コンテンツ作成の具体的手順
IV 推奨される教材作成手順を用いた具体例の提示
V 医師国家試験のCBT化を見据えた1題ごとの臨床問題作成手順
第4章 動画・音声付臨床問題と教材との関連性
I 臨床問題から学習意欲を高める教材へ
II 動画・音声と教材の関連
III 動画・音声を用いた教材作成の注意点
第5章 動画・音声素材の収集・編集のポイント
I はじめに
II 機材およびソフトウェア
III 撮影・収録の仕方
IV 動画・音声素材の編集
V おわりに
第6章 CBT革命:動画・音声を活用した効率的作成ガイド(応用編)
I なぜ,動画・音声素材の作成手順の整理・出版・議論が必要か
II 通信技術を利用したコミュニケーション動画素材作成の実践的な手順
III 診察と基本的医行為の動画・音声作成
IV 検査結果のマルチメディア化
V チームダイナミクス動画の作成と応用
VI 生成AIを用いた動画・音声素材の生成
[TOPICS1] 生成AIに作問をさせることはできるか?
[TOPICS2] 生成AIは学習者にフィードバックできるか?
第7章 主体的な学習を促すためのICT活用
I 主体的な学習を促すためのICT活用
II 動画・音声付臨床問題教材の運用方法
III 動画・音声付臨床問題教材と評価
索引
書評
開く
教育効果の向上をめざす教育者に
書評者:新納 宏昭(九大大学院教授・医学教育学)
本書は,次世代医師国家試験のコンピュータ試験(Computer-Based Testing;CBT)化を見据え,動画・音声を用いた臨床問題教材の作成方法とその教育的意義を解説した類まれな一冊である。その内容は,単なる作成マニュアルにとどまらず,医学教育の変革,DX時代に求められる医師の資質・能力,そしてAI技術の活用に至るまで,時流に沿った興味深いものである。
医師国家試験のCBT化が,現行の診療参加型臨床実習をさらに活性化し,同時に実践力を総合的に評価するツールとなることには全く同感である。従来の筆記試験では評価が困難とされた「医師の知覚情報の認知と言語化能力」や「情報識別力と応用力」に着目し,これらの能力評価には動画・音声素材が不可欠であるという点は論をまたない。
「臨床問題教材の作り方」の章では,単なる知識の羅列ではなく臨床実践に即した問題作成のルールが具体的に示されている点は本当にありがたい。「河北班」臨床推論モデルに基づいた問題作成手順は,思考プロセスを可視化し,同時にEBMの適応を促す点で高い教育効果を期待させる。
本書の大きな魅力は,生成AIの活用にも積極的に言及している点である。模擬患者や模擬医療者の生成,医療画像の生成,さらにはチームダイナミクス動画の作成まで,最新のAI技術が医学教育コンテンツ作成に与える可能性が具体例と共に提示されており,今後を見据えた観点には目を見張るものがある。ただその一方で,AIのハルシネーションといった課題にもきちんと触れつつ,DX時代における教育ではAIの適切な活用について継続的な議論がまだまだ必要であろう。
本書の魅力のもう一つは,作成した教材の活用方法といった運用面まで触れている点である。PICRATモデルを用いた教育の俯瞰,LMSの活用,H5PやSCORMといった紹介など,教材をより多くの学習者に届けるための具体的な方法が示されている。学習履歴に基づく学習者の評価や教材の評価に関する考察は,より深い学習成果の測定につながる可能性があり,教育効果の向上をめざす教育者にとって役に立つに違いない。
本書は,医師国家試験のCBT化という変革期を好機ととらえ,動画・音声,そしてAIといった最新技術を医学教育に統合するための手引書となるタイムリーな一冊である。医学部の教員,医療コンテンツ開発者,そして次世代の医療を担う医学生の全てにとって,手放せない書となることを信じてやまない。
次世代の医学・医療を拓くデジタル教育の新たなステージへ導く革新のテキスト
書評者:長谷川 仁志(秋田大大学院教授・医学教育学)
◆ 動画・CBT・生成AIによる実践力評価・教育の質保証をあらゆる現場教育・研修に!
医療の高度化・高齢化・多様化が進む中,医師に求められる10の資質(医学教育モデル・コア・カリキュラム〈令和4年度版〉)では,知識・技術・態度を包括した総合的な実践力(コンピテンス)を修得し,それを生涯にわたって向上させることにより,理想的かつ教育的な医療現場の構築をめざすことが求められています。
医療情報が爆発的に増え続ける現在,社会の期待に応える次世代の理想的医療を拓くには,デジタル教育技術の大胆な活用が不可欠です。それにより,臨床現場に即した症例ベースの基礎・臨床・社会・医療行動科学の統合教育に加え,実践力の評価とフィードバックの反復的な実施を充実させることが可能となります。
とりわけ,(1)コミュニケーション能力(チームビルディング力・教育力・マネジメント力等),(2)情報収集力(医療面接,身体診察,検査,EBM),(3)総合的判断力(臨床推論,心理,倫理)といった,医療の根幹をなす力の実践力評価が重要視されており,現場評価だけでは限界がある中で,デジタル技術の導入が鍵を握っています。
こうした教育・評価の改革をリードしているのが,本書の著者らで構成された厚生労働科学研究事業班,いわゆる「河北班」です。医師国家試験のCBT(Computer-Based Testing)化,動画や音声を取り入れたマルチメディア型評価,さらに生成AIの活用による革新的な手法の導入を進め,実践的能力を的確に可視化する次世代型の取り組みを加速させています。
本書は,このような動向を的確に捉え,「評価のアップデート」に真正面から取り組んだ実践的なガイドです。動画や音声を活用した臨床問題の具体例に加え,客観試験形式にとどまらず,生成AIを活用することで従来は困難とされてきた記述式・論述式問題や,カルテ記載・各種総括記載の表現といった評価の最新かつ実用的な運用手法も紹介されています。現場で求められる「納得感ある評価」の実現に向けた,具体的かつ多様な工夫が豊富に盛り込まれています。
「卒前教育」にとどまらず,「臨床研修」「専門医制度」「多職種連携教育」「生涯教育」といった各段階においても広く活用できる本書は,次世代の医学・医療教育,チーム医療教育を担う全ての関係者にとって,教育の質と実践力を高めるための貴重な一冊です。次世代の教育と評価のあり方を真剣に考える全ての方に,ぜひ手に取っていただきたい実践的テキストです。
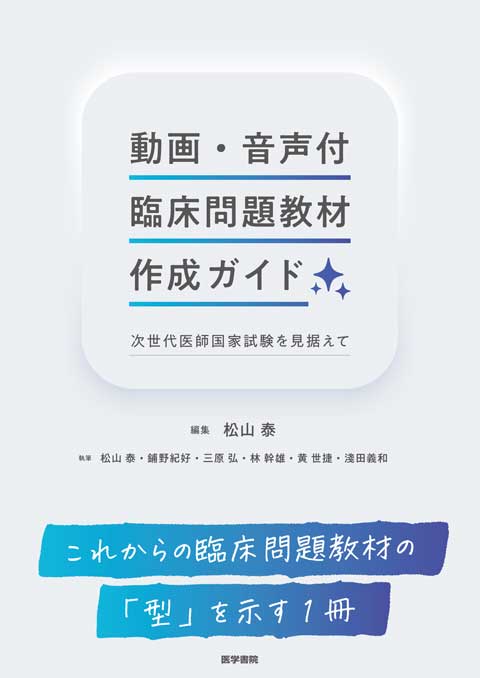
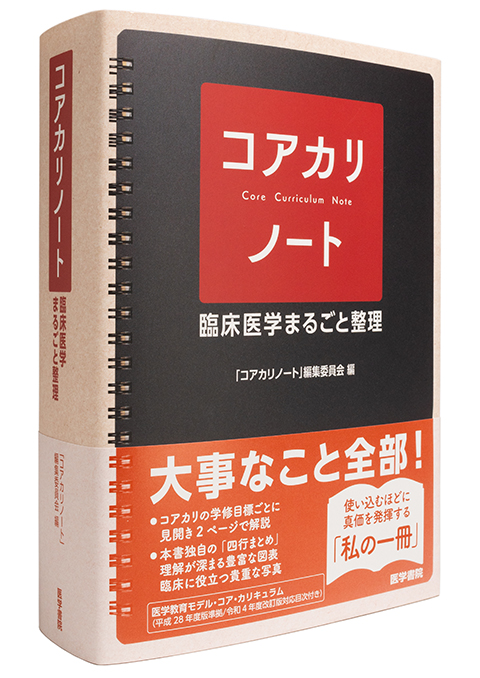
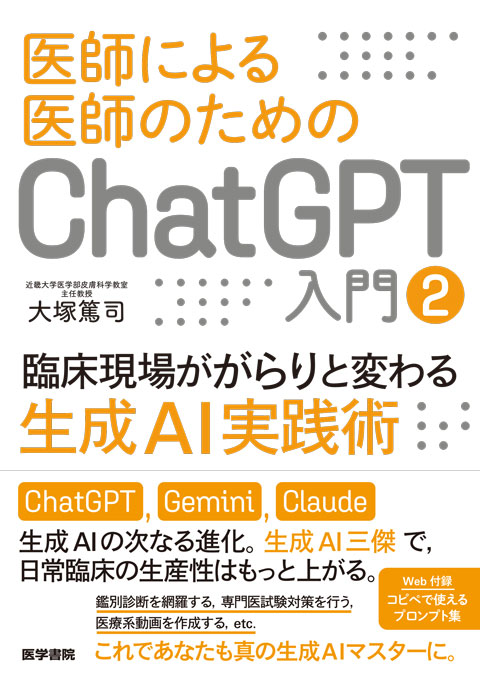
![新臨床内科学 [ポケット判] 第10版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/1316/0458/6749/93095.jpg)
