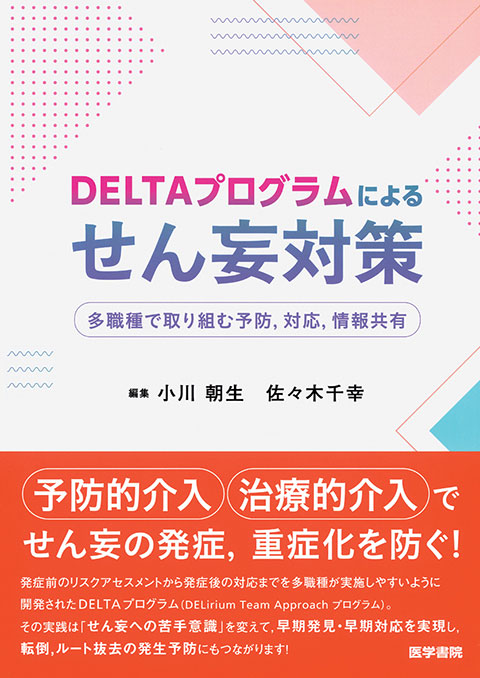がん患者のせん妄を看護する エビデンスと臨床の間で
[第1回] がん医療におけるせん妄――せん妄のもたらす影響とケアの重要性
連載 角甲 純
2025.09.09 医学界新聞:第3577号より
本連載では,2025年に改訂予定の『がん患者のせん妄に関するガイドライン 第3版』を踏まえ,せん妄の予防・アセスメント・対応について,最新の知見と実践的な支援の在り方を全12回にわたり紹介します。せん妄は現場での判断やケアの難しさがつきまとう症状ではありますが,本連載ではその“エビデンスと臨床の間”に橋をかける視点を大切にしながら解説をしていく予定です。
初回となる今回は,がん医療におけるせん妄の頻度や影響,そしてこのテーマにおける看護師の役割について考えます。
がん患者にとっての「せん妄」――発生頻度と影響
せん妄(delirium)とは,身体的異常や薬物の影響によって急性に発症する意識障害を主とする病態です1)。認知機能の障害に加えて,幻覚・妄想・錯覚などの知覚異常,不穏・無気力といった行動変化,気分の変動など多様な精神症状を呈し,日内での症状の変動もよく見られます。一過性で回復可能なこともありますが,時に深刻な経過をたどることもあります。
がん患者におけるせん妄は,決してまれな症状ではありません。発症頻度をみると,一般病院の入院患者では約10~30%,高齢の進行肺がん患者では約40%と報告されています。さらに,緩和ケア病棟では入院時に約42%の患者がせん妄を呈し,死亡直前には約88%と,ほとんどの患者が最終的にせん妄を経験するというデータもあります。このように高頻度に発生するせん妄は,患者・家族・医療者に多大な影響を及ぼします2~4)。
多面的で深刻な影響を及ぼす
せん妄中の体験を患者は想起できないと考えられがちですが,多くの患者がその体験を恐怖や不快感として記憶していることが報告されています5,6)。また,全身状態の悪化により,転倒・転落などの事故や二次合併症が生じ,入院の長期化,認知機能の低下,死亡率の増加につながることもあります7,8)。さらに,家族も患者の急激な変化に動揺し,強い精神的苦痛を経験します5,6)。特に終末期に見られる過活動型せん妄は,死別後の抑うつ症状とも関連しており,遺族の悲嘆を複雑にする要因となることがあります9)。医療者にとっても,特に夜間に生じる過活動型せん妄への対応は,心身の大きな負担となり,症状が遷延する場合にはバーンアウトの一因ともなります。さらに,入院の長期化は医療資源の消耗やコストの増大にもつながり,現実的な課題となっています2,10)。
このように,せん妄は患者への影響,家族の苦悩,医療安全や医療体制への影響など,多面的で深刻な影響を及ぼす症状です。対応は「発症後の対処」にとどまらず,「予防」や「早期発見」を含めた包括的な視点が不可欠であり,その実現には,日常的に患者とかかわる看護師の役割が極めて重要です。
がん医療におけるせん妄の複雑性と看護の要点
原因が多様・複雑ながん患者のせん妄
がん患者におけるせん妄は,他の臨床状況に比べて原因が多様かつ複雑であり,看護においても高度な対応が求められます。身体的苦痛,疾患進行による臓器不全,高カルシウム血症や脳転移といったがん特有の要因,さらにはオピオイドやステロイドを含む多剤併用など,複数の身体的・薬剤的因子が重なりやすく,発症リスクが高まります。また,実際には複数の要因が同時に関与することも少なくありません。
がん医療では,低活動型や終末期のせん妄に遭遇する機会も多く,特に低活動型せん妄は抑うつとの鑑別が難しいため,気づかれにくい点に注意が必要です。終末期のせん妄では,原因によって回復可能性が異なり,電解質異...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
角甲 純(かこう・じゅん)氏 三重大学大学院医学系研究科看護学専攻生涯発達看護学講座 教授
2006年広島大医学部保健学科看護学専攻卒。20年東京医歯大(当時)大学院医歯学総合研究科博士課程修了。兵庫県立大看護学部准教授などを経て,22年より現職。がん看護専門看護師。日本サイコオンコロジー学会ガイドライン策定委員会せん妄小委員会副委員長。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。