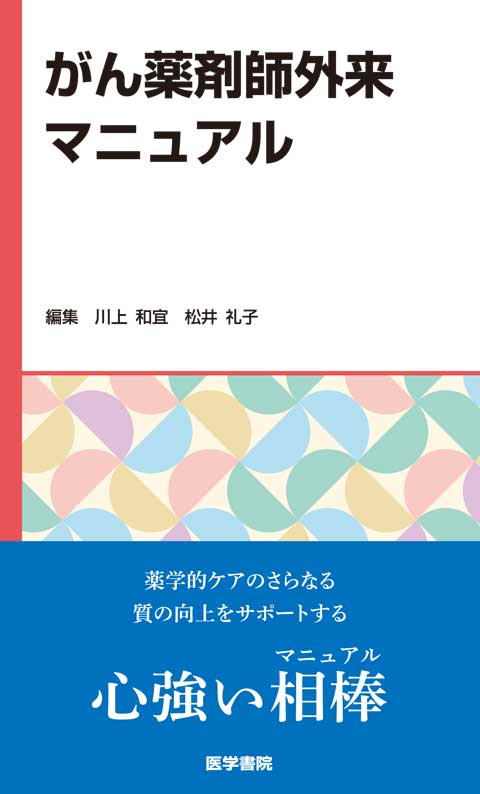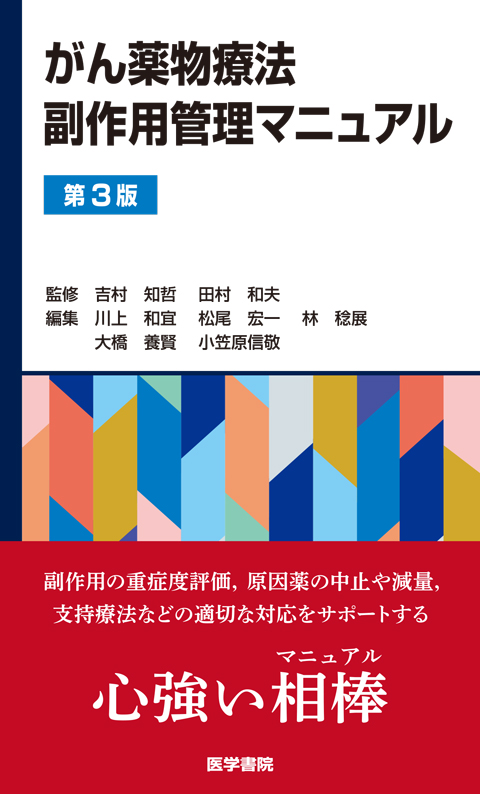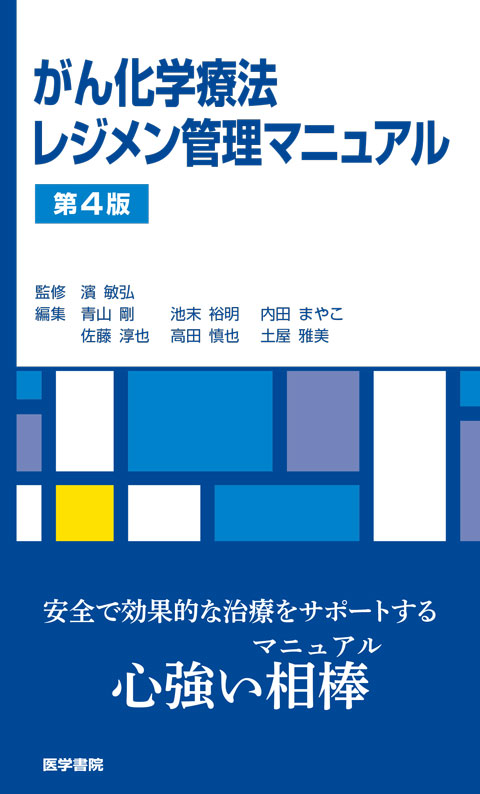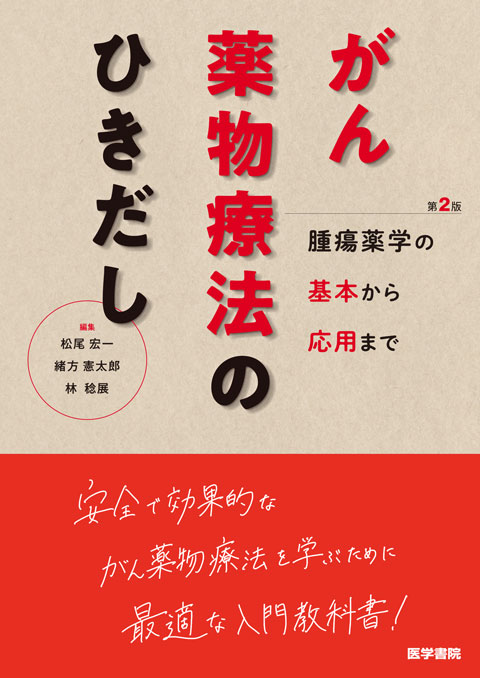がん薬剤師外来で実現する,薬剤師だからこそ担える役割
対談・座談会 川上 和宜,坂田 幸雄,小澤 有輝,葉山 達也
2025.03.11 医学界新聞:第3571号より

2024年6月に新設されたがん薬物療法体制充実加算(100点)は,医師の診察前に薬剤師が患者と面談する「がん薬剤師外来」の実施が算定条件とされています。しかし,副作用の評価や処方提案といった外来業務になじみのある薬剤師はまだ少数でしょう。本座談会では,がん薬剤師外来の立ち上げを経験し,現在も日々外来業務に従事する4氏に,各施設での経験や,外来を軌道に乗せるための工夫についてお話しいただきました。
川上 このほど『がん薬剤師外来マニュアル』1)(医学書院)を上梓しました。2024年度の診療報酬改定で,薬剤師による医師の診察前面談,いわゆる「がん薬剤師外来」に保険点数が付くようになったことを受け,これから「がん薬剤師外来」を始めようとする方たちに向けて,その具体的な業務内容を中心に実践的な情報をふんだんに盛り込んで書籍とした次第です。
本日の座談会では,書籍の中では語り尽くせなかった点,特にがん薬剤師外来を立ち上げた当初のお話を中心に伺えればと思っています。よろしくお願いします。
診察の“前”に薬剤師が介入する
川上 初めに,皆さんががん薬剤師外来を始めたきっかけを伺えますか。
小澤 もともと当院では100%院内処方を行っており,受け渡し窓口にて経口抗がん薬に関する診察後面談を実施していました。ところが2019年に院内処方から院外処方への全面切り替えという方針変更がなされ,病院薬剤師による介入を継続するために診察前面談の導入を検討するようになったのです。
川上 診察“後”ではなく診察“前”とした理由はあるのですか。
小澤 診察後面談を行っていた時の課題として,会計等の院内での処理が全て終わってから患者さんと面談する形をとっていたことから,薬剤師による処方提案を行うことの難しさがありました。アドヒアランスに関する助言や服薬指導を手厚く行うことは可能なのですが,処方提案となると一旦外来に戻ってもらう必要がありますし,会計がやり直しになるなど手続き上のロスが大きいです。
川上 医師による診察前・後のどちらで薬剤師が介入するのかは,一つ大きなポイントですね。薬剤師が職能を発揮するには,診察前に介入できるスキームを作ることが必要なのだと考えます。
葉山 同感です。当院はほぼ100%院外処方であるため,どこかのタイミングで経口抗がん薬のマネジメントに病院薬剤師がかかわりたいと考えていて,「がん患者指導管理料3」(当時)が新設された2014年にがん薬剤師外来を開始しました。立ち上げ当初から経口抗がん薬では診察前面談を行い,処方提案,用量調節などの面で薬剤師の職能を発揮することを重視しながら方向性を模索しています。
川上 坂田先生の施設はいかがでしょうか。
坂田 当院は,切除不能な肝がんに対して分子標的薬であるソラフェニブが保険適用となった2009年をきっかけに,肝臓専門医から副作用に関してのサポートを薬剤師に行ってほしいとの依頼があったことが始まりです。2010年から薬剤師による診察前面談を行うようになり,電話による患者サポートも行っています。いずれのサポートも,行うのは患者さんが希望する場合に限ります。
川上 医師や看護師からの反応はどうでしたか。
坂田 とても良好でした。当院の場合はもともと医師側からの要請があって始めたこともあるとは思いますが。
小澤 当院でも他職種からの反応は総じて良く,手応えを感じています。
葉山 投与基準や減量・休薬の有無があらかじめ提示されていることでスムーズな診察につながるとのフィードバックがありました。
川上 処方提案というと,多くの薬剤師はハードルが高いと感じてしまうかもしれません。また,診察時間よりも前に薬剤師が介入を行うことで診察を遅らせてしまったらどうしよう……といった不安を抱く方もいることでしょう。しかし,薬剤師による介入は他職種の負担軽減に直結しますから,まずは導入してみて,薬剤師外来がどのようなものかがわかってもらえれば,周囲からはポジティブな反応が返ってくるはずだと確信しています。
自身の提案に責任を持つマインド
小澤 診察前と後のどちらで介入するかが重要だと川上先生がおっしゃいましたが,診察前に面談を行うようになって感じる一番のメリットは,抗がん薬の中止・減量の提案が行いやすくなったことです。診察後の提案により医師の見立てを否定しているように受け取られる可能性がなくなるだけでも,薬剤師側の精神的負担が軽くなります。
坂田 初めは緊張しますよね。医師に対して中止や減量の提案をするのって。
小澤 はい。ですから私は,初めの頃は医師のところへ伺って,顔を合わせて直接提案していました。電話ではなく,直接。そうすると,案外温かく迎えてくださって,「わざわざ伝えに来てくれてありがとうございます」といったリアクションをもらうことが多くて驚きました。
葉山 単純なことに思われるかもしれませんが,電話ではなく直接伝えるというのは重要なポイントだと思います。私も電話で提案しないよう後輩に指導しています。診察を中断させてしまうことも多いですから。
川上 そうやって信頼関係を積み重ねていくと,その後の仕事もやりやすくなりますね。
加えて,減量・中止を提案する際には,「中止を検討いただけないでしょうか」ではなく,「中止を推奨する」のような表現をすべきだと考えています。中止が適当だと自身が考えたのなら,言い切るくらいの書き方をしなければならないと。
坂田 薬剤師として責任を持つマインドでもって判断を下すということですね。
川上 根拠を持って判断を下すことが習慣になってくると,患者さんへの説明もスムーズに行えるようになります。「こういう理由で減量をしなければこういう状態になる可能性が高いから減量しましょう。減量しても効果自体は継続します」と詳細に説明することは,患者さんのためにもなります。
医師と判断が違ったとき,どうする?
葉山 薬剤師として責任を持つマインドの話は,「評価」にも通ずるところかと思います。皆さんは有害事象等の評価をどう下していますか。
川上 提案を行うに当たって,Gradeがいくつといった具体的な記載をすべきという話ですね。そうした評価をカルテに書くことに,抵抗を覚える薬剤師も少なくないでしょう。
坂田 若い薬剤師に聞くと,「評価をするのが怖い」と言われることがありますね。
小澤 私も初めは抵抗がありました。怖いのもありますし,恥ずかしい気持ちもあるのだと思います。自分の考えた評価を書き込んで,それを後で他職種に読まれた際にズレたことを書いてしまっていたらどうしよう……という気持ちです。
葉山 例えば,実際に自身が記載したCTCAE(Common Terminology Criteria for Adv...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

川上 和宜(かわかみ・かずよし)氏 がん研究会有明病院薬剤部・調剤室 室長
2000年昭和薬科大大学院医療薬学専攻修了。博士(薬学)。同年癌研究会附属病院(当時)に入職。その後同院医療安全管理部を経て,24年より現職。日本医療薬学会がん専門薬剤師,がん指導薬剤師。編著に『がん薬剤師外来マニュアル』『がん薬物療法副作用マニュアル 第3版』(ともに医学書院)。

小澤 有輝(おざわ・ゆうき)氏 けいゆう病院薬剤部 副主任
2012年昭和薬科大薬学部卒。同年川崎幸病院に入職。その後,14年けいゆう病院に入職。23年より現職。日本病院薬剤師会がん薬物療法専門薬剤師,日本緩和医療薬学会緩和医療暫定指導薬剤師。

坂田 幸雄(さかた・ゆきお)氏 市立函館病院薬剤部薬物療法科長
1989年北海道医療大薬学部卒業後,株式会社ツルハホールディングス勤務を経て,90年市立函館病院薬局に入局。2020年より現職。日本病院薬剤師会がん薬物療法認定薬剤師。青森大客員教授を兼務。

葉山 達也(はやま・たつや)氏 日本大学医学部附属板橋病院 薬剤部 技術長補佐
2011年日大大学院薬学研究科博士後期課程修了。博士(薬学)。03年に日大板橋病院に入職後,同院薬剤部主任を経て,21年より現職。日本医療薬学会がん専門薬剤師,がん指導薬剤師。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
寄稿 2024.10.08
-
対談・座談会 2025.12.09
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。