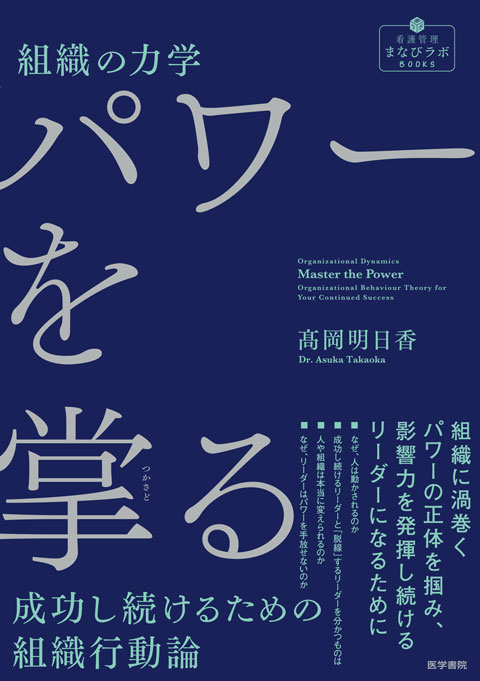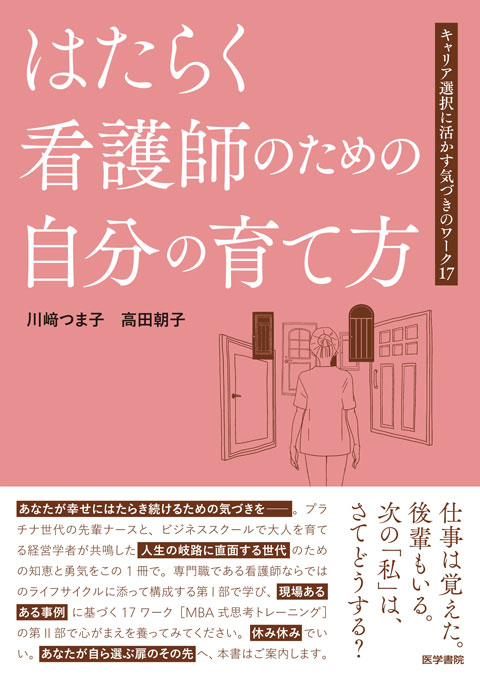組織の対人関係に渦巻くパワーを掌る
対談・座談会 川﨑つま子,髙岡明日香,田中いずみ
2024.11.12 医学界新聞(通常号):第3567号より

看護管理者をはじめ医療機関のリーダー職の中には,自身のどのような行動が適切な影響力の発揮,ひいては組織のパフォーマンスの最大化につながるのか,具体的なイメージを持てていない方も多いのではないでしょうか。本紙では『看護管理』誌での1年間にわたる連載をもとに『組織の力学 パワーを掌る――成功し続けるための組織行動論』(医学書院)を上梓したグロービス経営大学院教授の髙岡氏と,看護管理者の立場で多くの課題に向き合ってきた川﨑氏,田中氏との座談会を企画しました。組織の中に渦巻くさまざまな「パワー」とその向き合い方について模索します。
川﨑 私はいくつかの中小規模病院を運営する法人の統括看護部長という職に就いています。各病院の看護部長と協力して,看護部をどうまとめ上げていくかが現在の課題なので,今日は髙岡先生にお話を伺うのを楽しみにしてきました。
田中 現在の病院で看護部長に就任してから今年で10年目になります。2019年からは副院長を兼任しており,看護部のマネジメント業務に加え病院の課題を経営的観点から解決すべく日々奮闘しています。
髙岡 私はコンサルティングの領域に長年従事し,経営層の評価・選抜・育成などを専門にしてきました。現在は経営学者として米国でコーポレート・ガバナンスや企業倫理に関する研究を続けながら,パワーと影響力,リーダーシップなどに関する授業を日本のビジネススクールで担当しています。自分自身,管理職として仕事自体よりも対人関係で悩んできた経験があり,それが今回上梓した『パワーを掌る』のテーマであるパワーの研究を始めるきっかけになりました。
パワーとは人や組織の行動に影響を与える力
川﨑 まずは髙岡先生の書籍のタイトルにもある「パワー」について教えてください。
髙岡 数多くの定義がありますが,特に用いられるのはドイツの社会学者マックス・ウェーバーが提唱した「パワーとは,相手側の抵抗にもかかわらず自分の望むもの(利益)を実現する能力」です1)。強制的な意味合いを強く感じさせる定義であるものの,現代の組織の人間関係におけるパワーは,さまざまな種類・次元・強度で生じるため,「人や組織の行動に影響を与える力」と単純化してとらえていただいて構いません。
川﨑 そう考えると,どんな人間関係にも多かれ少なかれパワーが生じているということですね。
髙岡 その通りです。併せて重要なのは,パワーにはポジティブ/ネガティブの両面が存在することです。人が動かされるときを考えてみましょう。多くの場合,パワーを持つ者が他者に刺激を与え,パワーの受け手はそれに応じた行動をとる構図になりますが,上司でなくとも尊敬する人からアドバイスをもらい努力した結果,実績や昇進につながったというようなケースはポジティブなパワーが働いたと言えます。反対に,役職の力を背景に強権を発動し否応なく部下を従わせる場合はネガティブなパワーが働いたと表現できます。個人あるいは組織が成功を収めるには,こうしたパワーの概念を正しく理解し,対人関係において適切に行使することが重要です。
田中 これまではパワーと言われると,どちらかと言えば立場が上の者から下の者に対して行使される権力のようなネガティブなイメージが強かったです。しかし実際にはポジティブな側面もあり,必ずしも上司だけがパワーを有するとも限らないのですね。
髙岡 ええ。私たちはパワーの適切な行使により,相手を自発的に動かすことで仕事のパフォーマンスを向上させ,結果的にチーム全体の働きやすさを改善することができます。適切なパワーの行使には,組織に存在するパワーとパワーが発揮されるメカニズムへの理解が重要であり,それこそがパワーについて学ぶ意義だと言えます。
部下マネジメントにおいて公式のパワーが持つリスク
髙岡 川﨑先生,田中先生は多くの部下を抱える立場だと思います。マネジメントでは日ごろどのような難しさを感じていますか。
田中 師長にうまくパワーを使いこなしてもらうにはどうすれば良いかと悩むことが多々あります。師長たちは各現場のリーダーでもあるので,自発的に判断し動いてくれることを期待していますが,問題意識や方向性の共有はできていても,実際に行動する前には「看護部長や病院長から指示してほしい」と言われてしまうことがあります。
川﨑 難しい問題に直面したとき,より上の立場にいる人に解決してもらおうとするケースは多いですよね。ある意味,そうした方はパワーの権力的側面をよく理解しているとも言えるのでしょうが……。
髙岡 パワーにはさまざまな種類があるのですが,組織のヒエラルキーを背景に行使されるものは,「公式のパワー」という概念に当たります。現実には公式のパワーでしか対応できないケースはあるのでその行使は必要です。ただ行使に当たっては2つの点に注意しなくてはなりません。1つは強制力の大きさです。強制的に何かをさせられることで,公式のパワーの受け手は強い不満を持つ可能性があり,極端な例では組織にとっての大きな抵抗勢力の形成につながるリスクもあります。
もう1つは役職より全人格を重視する近年の傾向です。特に若い世代では「上司からの指示だから」という理由だけでは必ずしも動かないこともあり,「尊敬する○○さんのお願いだから」「△△さんとは仲がいいから」といった事情が行動の契機になることが少なくないです。公式のパワーが昔よりも効きにくくなってきている点に注意すべきだと思います。
川﨑 確かにその通りかもしれません。看護の現場で例えれば,自分の考えをはっきり示さないままに「看護部長からの指示だから」というスタンスを師長が安易に取ってしまうと,その師長は組織の言いなりで,自分たちのことを守ってくれる・率いてくれる存在ではないのだと部下からはとらえられてしまいます。師長が公式のパワーに頼っていることを,部下たちは意外とシビアに評価している印象です。
田中 同感です。師長をはじめとするミドルマネジャーの難しさでもありますが,上司からの指示を伝達するだけのメッセンジャーのような存在にはなるべきではないでしょう。組織の決定や方針に対して自分自身はどう感じているのか,それを...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

川﨑 つま子(かわさき・つまこ)氏 大坪会グループ(OZAK会) 看護局長
1978年国立埼玉病院附属看護学校卒。88年日本赤十字社幹部看護師研修所卒。2010年東京医療保健大修士課程修了。同年認定看護管理者(日看協)。大宮赤十字病院(現・さいたま赤十字病院)附属専門学校専任教員,同院看護師長などを経て,小川赤十字病院,足利赤十字病院,東京医歯大病院(現・東京科学大病院)で看護部長を歴任。22年より現職。共著に『はたらく看護師のための自分の育て方』(医学書院)。

髙岡 明日香(たかおか・あすか)氏 グロービス経営大学院 教授 / ジョージ・ワシントン大学 客員研究員
博士(経営)。一橋大大学院国際企業戦略研究科博士後期課程修了(DBA)。一橋大大学院国際企業戦略研究科修了(MBA)。MBA取得後,マッキンゼー・アンド・カンパニーにて戦略案件を担当した後に,人事コンサルティング,特に社長指名に従事。タワーズワトソン株式会社アセスメント事業のアジア責任者を務める。現在は,米ジョージ・ワシントン大にてコーポレート・ガバナンス,企業不祥事,企業倫理について研究を行う。Bancho Board Advisory株式会社代表取締役。著書に『パワーを掌る』(医学書院)。

田中 いずみ(たなか・いずみ)氏 手稲渓仁会病院 副院長 / 看護部長
1988年帯広高等看護学院卒。95年に手稲渓仁会病院に入職。2010年に北海道医療大大学院修士課程を修了し,同年がん看護専門看護師に認定。14年には認定看護管理者となり,15年4月より手稲渓仁会病院看護部長に就任。19年より副院長を兼務する。著書に『看護管理者が進める地域療養支援ガイドBOOK』(メディカ出版)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。