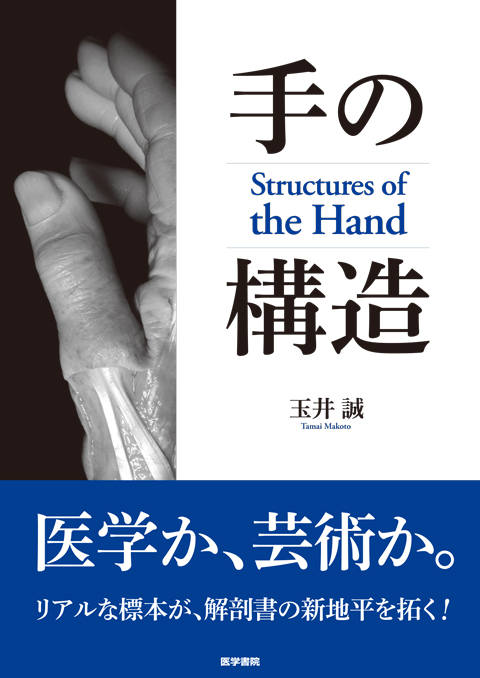MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2024.10.08 医学界新聞(通常号):第3566号より
《評者》 岡田 佳詠 国際医療福祉大教授・看護学
百聞は一見に如かず。対話のコツとその効果をWeb動画で
本書は,2016年の初版から,8年を経て改訂された秀作である。
国内で精神障がい者の地域移行支援が推進される中,著者である萱間真美氏には,今回の改訂に当たり「これからの地域支援に当たる看護師や多職種スタッフが,当事者とストレングス・マッピングシートを用いた対話を通して,当事者の夢の実現に向けて伴走者の役割を果たしてほしい」との強い思いがあったと思われる。それが本書全体を通して,随所に表れている。
まず読者に語りかけるように,そしてどの職種にもわかるように,平易な言葉で,ストレングスモデルとは何か,その役割,基本理念,原則,そして当事者との関係性と対話の大切さやコツ,ストレングス・マッピングシートの用い方などを伝えている。
また看護師をはじめ医療従事者が陥りやすい問題解決モデルへのこだわりを取り上げ,そこからどうストレングスモデルに転換するのかという難しい局面を,違いを明確に表示しつつ,事例も使い,丁寧にわかりやすく説明している。問題解決モデルは医療現場では必要である一方,当事者の変化や状況に応じてストレングスモデルを取り入れることの重要性も伝わってくる。
本書のユニークなところは,ストレングス・マッピングシートを用いた当事者と萱間氏の対話を,Web動画で見られることである。対話で用いた,当事者が事前に作成したストレングス・マッピングシートと,萱間氏との対話で補足・追加されたストレングス・マッピングシートを対比して見ることができるため,対話を経てシートが豊かになっていく様子がよくわかる。またこの動画の優れたところは,対話のポイントとスキルがわかるように編集されたバージョンもあることで,本書のページを参照しながらスキルを確認し,どう話を展開すると良いかが理解しやすくなっている。具体的にスキルを学び,臨床で生かしたい読者にとっては,とてもうれしいことだろう。中でも印象的だったのは,対話に登場している当事者の表情の変化である。萱間氏からの夢に焦点を当てた問いかけやフィードバックにより,当事者の表情が楽しそうに生き生きとし始め,そして輝いてくるのである。これがまさにストレングス・マッピングシートを用いた対話の効果であり,夢の実現に向けて当事者とともに考え,行動することの大切さを物語っていると感じた。
最後にストレングスモデルへの転換は,当事者のみならず,私たち看護師や他の医療従事者の夢や希望にもつながることを改めて実感した。当事者を問題解決モデルで見ると,ネガティブなところがどうしても目につき,「できない」「やれない」と思い込むと,明るい未来が見えず,ケアの意欲も湧かなくなる。そこから悪循環に陥り,当事者の退院や地域移行は行き詰まる。しかしストレングスモデルで当事者と対話ができると,当事者から逆にエンパワーされ,元気をもらう。まずは私たちが見方を変え,ストレングスモデルで当事者と対話を持つ努力を始めれば,好循環へと舵を切ることができると,本書から教えてもらったように思う。
《評者》 越後 歩 札幌徳洲会病院整形外科外傷センター・手外科専門作業療法士
未体験の美麗な標本。これは驚異的な解剖学書である。
『手の構造 Structures of the Hand』は驚異的な解剖学書である。
著者の玉井誠先生は手外科の臨床家,解剖学者であり,写真家でもある。
手外科医としての冷静で的確な医学的解説と,艶やかで芸術的な手の解剖写真とのインテグレーションに魅了される。
玉井先生は2000~2003年にかけ,米国のケンタッキー州ルイビルにご留学された。手外科医としての臨床業務に並行して,手の解剖に心血を注がれ,自ら撮影された写真は1.5万枚以上にも及ぶという。
姉妹書である『The Grasping Hand――Structural and Functional Anatomy of the Hand and Upper Extremity』(Thieme)は,Dr.Guptaと玉井先生の共同編集で2020年に出版され,2023年には玉井先生,村田景一先生監訳で『The Grasping Hand 日本語版――手・上肢の構造と機能』(医学書院)が出版されている。こちらの書籍でも玉井先生が撮影した写真を基に,手外科のエキスパートたちによる手の解剖に関する詳細な情報や臨床との関連が記されている。この『The Grasping Hand』とは異なる角度から,臨床家の目線で,手の構造について簡潔に解説したのが,本書『手の構造 Structures of the Hand』であり,美しい解剖と撮影技術で,厳選された標本の一枚一枚が収められている。
他の解剖書と大きく異なるのは,標本の質感である。標本は新鮮屍体を用い,組織の変性が抑えられ,組織の硬さ,柔らかさは生体に近いものである。また,組織の乾燥を防ぐために,撮影中の標本の質の維持にも配慮されている。
変性・変色した標本に慣れている私たちにとって,筋肉の張りや質感,神経と腱の微妙な色の違い,腱膜や靱帯の線維の方向など,これまで得られなかったさまざまな情報を知ることができる。
また,工夫を凝らした解剖や撮影のアイデアが素晴らしい。読者の左手と見比べるため,標本は左ページに印刷されている。写真...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

![対話でリカバリーを支える ストレングスモデル実践活用術[Web動画付] 第2版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/3417/1575/7176/115139.jpg)