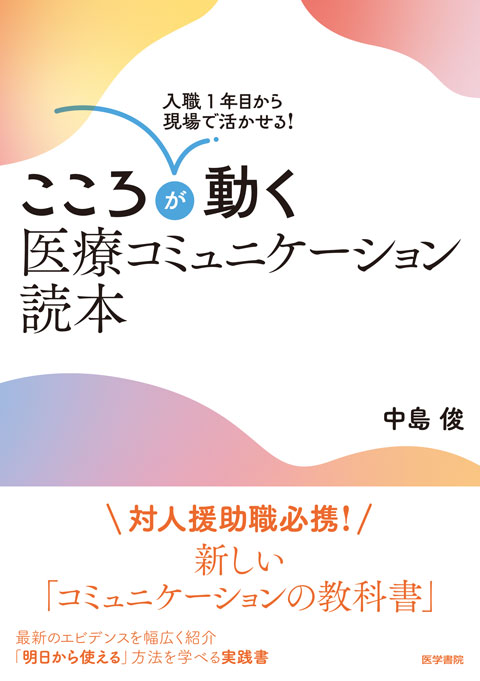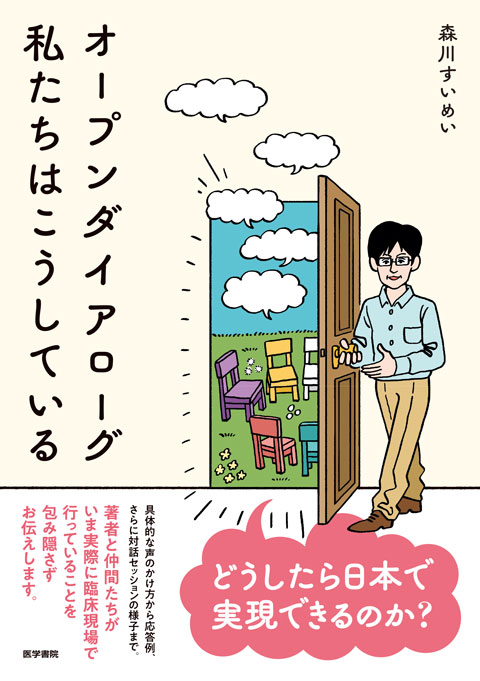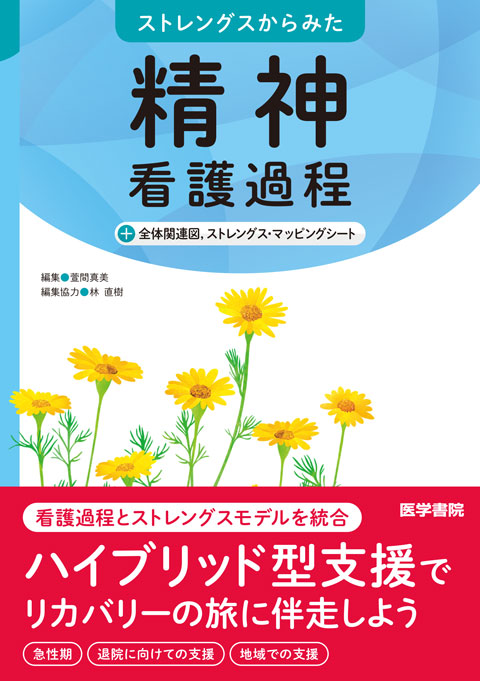対話でリカバリーを支える
ストレングスモデル実践活用術[Web動画付] 第2版
対話を通じて、リカバリーに向かうストレングスをともに見出すための1冊
もっと見る
ストレングスモデルは個人がもつ強み・希望や、その人を取り巻く環境の強みに着目し、ケアの資源として活かす支援方法。当事者中心のこのモデルを真に実践し活用するためには、わかりやすい強みに着目して弱点から目をそらすのではなく、当事者と対話するなかで、本人の言葉を通じてストレングスを理解する必要がある。著者オリジナルのストレングス・マッピングシートを使った対話の様子を、付録動画として収載した。
| 著 | 萱間 真美 |
|---|---|
| 発行 | 2024年05月判型:B5頁:144 |
| ISBN | 978-4-260-05619-9 |
| 定価 | 2,420円 (本体2,200円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
- 付録・特典
序文
開く
ストレングス・マッピングシートその後:第2版まえがき
2016年の本書(初版)出版から8年。精神障がい者の地域移行支援は、精神障がいにも対応した地域包括ケアの推進とともに進展しつつあります。精神障がいを持つ人を地域で支えるために2012年に新設された訪問看護ステーションからの精神科訪問看護を対象とする診療報酬、精神科訪問看護基本療養費は、利用者の大幅な増加をみています。
本書は、当時は精神科医療施設から地域に移行しようとする精神障がい者と、その支援にあたる病棟看護師をイメージして書いた本でした。しかし、現在では地域で支援にあたる訪問看護スタッフや、医療につながる前に行政が提供するアウトリーチケアに従事する様々な職種のスタッフにも活用いただいています。著者にとって、それは望外の喜びです。
初版の発行当初、ストレングス・マッピングシートが使われる自信は持てずにいました。なぜ活用が進んだのでしょう。
今、当事者と支援者の間で日々紡がれていく対話がとても大切だからだと思います。もちろん精神科看護の場では、体のケアをしながら、毎日生きていくことへの共感やいたわりの気持ちを伝えることもあります。でもそのような関係に至る前、また、信頼を得るためには、支援者が当事者を脅かす存在ではないことや、当事者の気持ちや考えを伺って、それを大切にしたいと思っていることを伝えるための対話、言葉を用いたやりとりの時間が必要です。
ストレングス・マッピングシートは、その対話の話題として使えます。記入項目のならびが、対話の方向を提案しており、こんな単語、言い回しを使うと当事者のストレングスを探せることを示すものでもあります。
今回の改訂では、地域で暮らす精神障がい者や家族、関係者との対話にも焦点を当て、対話についての内容を追加することにしました。また、スタッフ教育や基礎教育でストレングスモデルを活用する動きの進展をふまえて、病棟での地域移行に向けた対話やアセスメントに活用していただくための記録様式、電子カルテを用いた活用方法についても触れました。
あなたが何をしたいのか、私でよかったら聞きますよ、と言えたらいいなと思うのです。うまく聞けるかとか、妄想の話にどう対応したらいいかとか、せっかく話してくれた気持ちに応えられるだろうかとか、様々な恐れや緊張を持ちながら言葉をかける支援者の背中を、お話を聞いてみようよと、そっと支えられる本として使っていただけることを、願っています。
2024年3月
萱間真美
目次
開く
ストレングス・マッピングシートその後:第2版まえがき
初版まえがき
第1章 対話でリカバリーを支えるストレングスモデルとは
ストレングスモデルの必要性
看護師自身へのメリット
ストレングスモデルの役割
第2章 臨床看護における実践活用法
1.アセスメントの基本──その人の“ストレングス”とは
ストレングスモデルの価値観
ストレングスモデルの基本理念
ストレングスモデル6つの原則
2.対話をする──リカバリーの旅のパートナーになる
ストレングスモデルで変わる関係性
関係性を構築する対話のコツ
コラム①:ジョイニング
3.したいこと、夢を文字にする──その人だけのリカバリーの旅の地図を作る
ストレングス・マッピングシートのコンセプト
コラム②:マッピング
ストレングス・マッピングシートを用いて対話するときの看護師のスタンス
ストレングス・マッピングシートの書き方と問いかけのコツ
ストレングス・マッピングシートと対話の基本9箇条
動画でみる対話の技術とアセスメント・フィードバックのポイント
コラム③:グループでのストレングス・マッピングシート利用
4.行動計画・看護計画を立てる──夢への道程を分割し、役割を分担する
夢を短期目標に分割する方法
看護計画への活用
5.看護記録に活用する──ストレングスを記録・共有しよう
コラム④:ストレングスモデル仕様の電子カルテとは
6.退院調整・地域連携に活用する──どんな場所でも「その人らしさ」を支える
ストレングス・マッピングシートを使った情報共有
7.事例で読み解く実践のコツ──アプローチの方法と看護の経過
ストレングスモデルでその人を描く
《事例1》 「自分は悪くない」とくり返す修司さん
《事例2》 周囲に怖がられていた翔さん
《事例3》 衝動のコントロールが苦手な千夏さん
《事例4》 認知機能の低下で食事に集中できない静子さん
第3章 教育の場での実践活用法
1.基礎教育の場で実践する
看護学生に、どう教えるか
2.臨床教育の場で実践する
仲間を増やそう
謝辞
第2版の謝辞
付録〈ストレングス・マッピングシート〉
索引
困ったときのINDEX
書評
開く
百聞は一見に如かず。対話のコツとその効果をWeb動画で
書評者:岡田 佳詠(国際医療福祉大教授・看護学)
本書は,2016年の初版から,8年を経て改訂された秀作である。
国内で精神障がい者の地域移行支援が推進される中,著者である萱間真美氏には,今回の改訂に当たり「これからの地域支援に当たる看護師や多職種スタッフが,当事者とストレングス・マッピングシートを用いた対話を通して,当事者の夢の実現に向けて伴走者の役割を果たしてほしい」との強い思いがあったと思われる。それが本書全体を通して,随所に表れている。
まず読者に語りかけるように,そしてどの職種にもわかるように,平易な言葉で,ストレングスモデルとは何か,その役割,基本理念,原則,そして当事者との関係性と対話の大切さやコツ,ストレングス・マッピングシートの用い方などを伝えている。
また看護師をはじめ医療従事者が陥りやすい問題解決モデルへのこだわりを取り上げ,そこからどうストレングスモデルに転換するのかという難しい局面を,違いを明確に表示しつつ,事例も使い,丁寧にわかりやすく説明している。問題解決モデルは医療現場では必要である一方,当事者の変化や状況に応じてストレングスモデルを取り入れることの重要性も伝わってくる。
本書のユニークなところは,ストレングス・マッピングシートを用いた当事者と萱間氏の対話を,Web動画で見られることである。対話で用いた,当事者が事前に作成したストレングス・マッピングシートと,萱間氏との対話で補足・追加されたストレングス・マッピングシートを対比して見ることができるため,対話を経てシートが豊かになっていく様子がよくわかる。またこの動画の優れたところは,対話のポイントとスキルがわかるように編集されたバージョンもあることで,本書のページを参照しながらスキルを確認し,どう話を展開するとよいかが理解しやすくなっている。具体的にスキルを学び,臨床で生かしたい読者にとっては,とてもうれしいことだろう。中でも印象的だったのは,対話に登場している当事者の表情の変化である。萱間氏からの夢に焦点を当てた問いかけやフィードバックにより,当事者の表情が楽しそうに生き生きとしはじめ,そして輝いてくるのである。これがまさにストレングス・マッピングシートを用いた対話の効果であり,夢の実現に向けて当事者とともに考え,行動することの大切さを物語っていると感じた。
最後にストレングスモデルへの転換は,当事者のみならず,私たち看護師や他の医療従事者の夢や希望にもつながることを改めて実感した。当事者を問題解決モデルで見ると,ネガティブなところがどうしても目につき,「できない」「やれない」と思い込むと,明るい未来が見えず,ケアの意欲も湧かなくなる。そこから悪循環に陥り,当事者の退院や地域移行は行き詰まる。しかしストレングスモデルで当事者と対話ができると,当事者から逆にエンパワーされ,元気をもらう。まずは私たちが見方を変え,ストレングスモデルで当事者と対話を持つ努力を始めれば,好循環へと舵を切ることができると,本書から教えてもらったように思う。
![ストレングスモデル実践活用術[Web動画付] 第2版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/3417/1575/7176/115139.jpg)