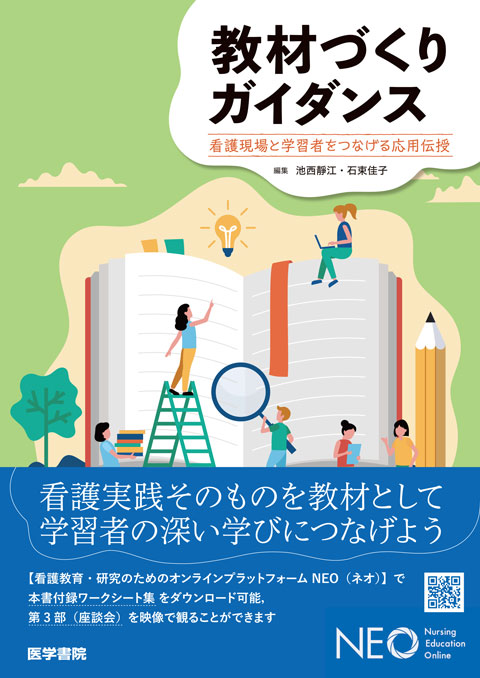MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2024.07.09 医学界新聞(通常号):第3563号より
《評者》 中山 健夫 京大大学院教授・公衆衛生学・疫学 / 同大病院倫理支援部部長
奥深く,魅力ある因果推論の世界へと誘う
本書の執筆者である井上浩輔先生,杉山雄大先生,後藤温先生の3先生は,人間・人間集団・社会を対象とするパブリックヘルス,ヘルスサービス,疫学の分野において,最も目覚ましい活躍をされている気鋭の医学研究者です。本書は,先生方自身の高いレベルでの研究成果に基づき,近年世界的に関心が高まっている因果推論の最前線の知見を入門から専門レベルまで解説された充実の一冊です。
医学における因果推論は,古典的には単一病因説に始まり,多要因病因論から,1964年に米国公衆衛生総監(Surgeon General)によって取りまとめられた「喫煙と健康」報告書の5基準(一致性,強固性,特異性,時間性,整合性),1965年に英国の統計学者Bradford Hillsによる9視点(関連の強さ,一貫性,特異性,時間的先行性,生物学的勾配,可能性,合理性,実験験的証拠,類推)が示され,その後,米国の疫学者Kenneth J. Rothmanがパイモデルを提案しました。近年では,利用可能な大規模データベースの充実と,ランダム化比較試験が困難な状況での観察研究の意義が見直される流れの中で,解析手法の高度化とともに,因果推論の方法論が大きく発展しました。
本書は総論・各論・まとめの全19章と,6つの魅力的なコラムからなります。第1章「因果推論で医学研究を身近で素敵なものに!」では次のように述べられ,読者は奥深く,魅力ある因果推論の世界に誘われます。
「因果推論を学ぶことで,科学的な良い研究デザインの想起が可能になり,結果的に研究が『身近』になるのです。さらには,行う研究の質が高く,臨床的な示唆に富み,興味深い『素敵』なものになると期待できます」と記され,次のように締めくくられます。「観察研究のエビデンスを適切に咀嚼する穏健な姿勢」を会得し,「科学的で節度のある『ふむふむの境地』をめざして,私たちと一緒に因果推論を学んでいきましょう」。
総論におけるDAG(非巡回有向グラフ)の活用と反事実的思考による潜在アウトカムを起点とし,各論では層別解析から多変量回帰モデル,傾向スコア分析,逆確率重み付け,G-computation,効果修飾,異質性,因果媒介分析,バイアス分析,操作変数法,メンデルランダム化,差分の差分法,分割時系列分析,回帰不連続デザイン,中間因子にかかわる一般化フロントドア基準,機械学習の応用など,意欲ある研究者が待ち望んでいた内容が網羅されています。
まとめの第19章「因果推論の理解を深め,人と社会が健康な未来の実現を」では,因果推論がどのように医学研究に貢献し,人々の健康の向上に寄与できるかが語られています。これは,本書が単に理論の紹介だけでなく,どのように社会的課題の解決に役立てていくかを考えて続けたいとする3先生の熱意と真摯さが伝わる内容で,大いに感銘を受けました。
1990年代の終わりに,先生方と同じ米国カリフォルニア大ロサンゼルス校(UCLA)に留学中だった評者は,刊行されたばかりのRothmanの“Modern Epidemiology”第2版(DAGはまだ記述がありませんでした)に,同書の共編者で『因果推論レクチャー』にも登場するSander Greenland教授からサインと激励のお言葉をいただいたことを懐かしく,うれしく思い出しました。
本書は今日の医学研究者の期待に応え,さらなる高みに導く素晴らしい書籍です。多くの方々が手にされることを願い,推薦いたします。
《評者》 佐藤 浩章 大阪大学学際大学院機構教授
新任からベテランまで世代を超えて役立つガイドブック
本書は,看護教員が授業を実施するためのガイドブックである。評者は長らく大学教員の能力開発業務を担当しているが,看護教育分野の実践と研究の豊かさには感嘆する。看護教員のための授業づくりに関する類書は他にもあるが,本書はその中でもユニークな特徴を持っている。
新任看護教員が思いつく,授業にかかわる素朴な30の問いにベテラン教員が直接丁寧に答えるような,Q&A形式で構成されている。その問いは,「アクティブ・ラーニングってなんですか?」「筆記試験ってどうやってつくればいいのでしょうか?」というような分野を越えて新任教員が抱きそうなものもあれば,「学生同士で演習すると真剣味に欠けるのですが,何かいい方法はありませんか?」「演習の振り返りってどうすればいいのでしょうか?」というような,看護教員がよく遭遇する場面に対応したものもある。
それらの問いに対応する答えは,教育学や心理学の理論やツールに基づくものが多く,その信頼度も高い。ケラーのARCSモデル,ダニング・クルーガー効果などの専門用語や,ルーブリック,リフレクティブサイクルなどのツールも平易に学ぶことができる。一方,本書の随所には著者らの長年の教育実践に裏付けられた記述もあり,有用度も高い。さらにWeb付録(閲覧するには書籍ごとに発行されているシリアル番号が必要)には,シラバスやコマシラバス(授業計画),ルーブリックなどの資料の他,紙面では伝わりにくい,オンライン授業の方法に関する動画資料などが収載されている。
本書の冒頭には,本書が「教員になったばかりのときを振り返り,こんなことが知りたかったな,こんなことを知っているとよかったなと思ったことを詰め込んだ」ものであると書かれている。この裏には「最低限このくらいのことは知っておいてね」「知らないと苦労するよ」という先輩看護教員からの愛に溢れたメッセージがある。
もちろん新任看護教員が手元に置いておくには最適な書籍ではあるが,中堅・シニア教員が自らの教育実践を振り返るためのチェックリストとして,あるいは新任教員のメンターをする際のガイドとしても活用できる。世代を超えた多くの看護教員に手にとっていただきたい書籍である。
《評者》 新井 英靖 茨城大教育学部教授
事例を通して理論と実践の両方を学ぶ看護教育の好著
近年,看護教育においても,「アクティブ・ラーニングが大切だ」と叫ばれる時代になりました。これは,単に話し合えばよいというのでもなく,実技を含めて教えればよいという意味でもありません。看護の理論と現場での実践・経験が1つになって,学生の深い学びを実現することが,アクティブ・ラーニングでは重要です。
看護教育を担う教員の多くは,看護師として医療現場で多くの経験を積んできた人であると思います。そして,看護教員になろうと一念発起して,看護学校で勤め始めた人は,「これまでの自分の経験を,次の世代を担う若い人に伝えていくことができればよい」という思いを抱いて,医療の現場からいったん離れ,教育の現場に足を踏み入...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

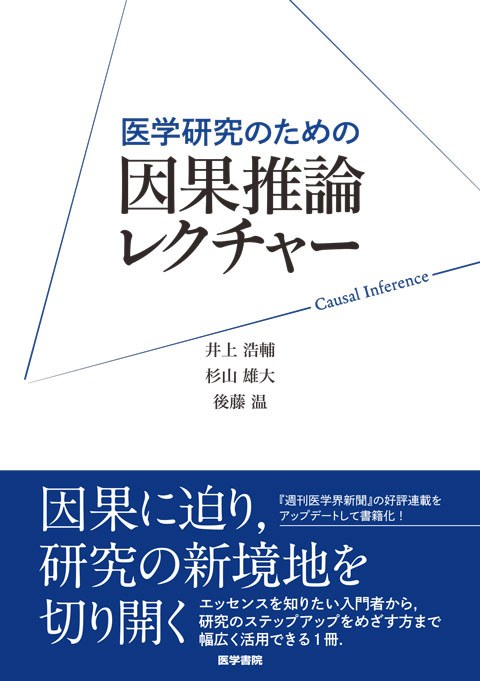
![看護のための授業づくりガイド[Web付録付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/8417/1332/1896/112193.jpg)