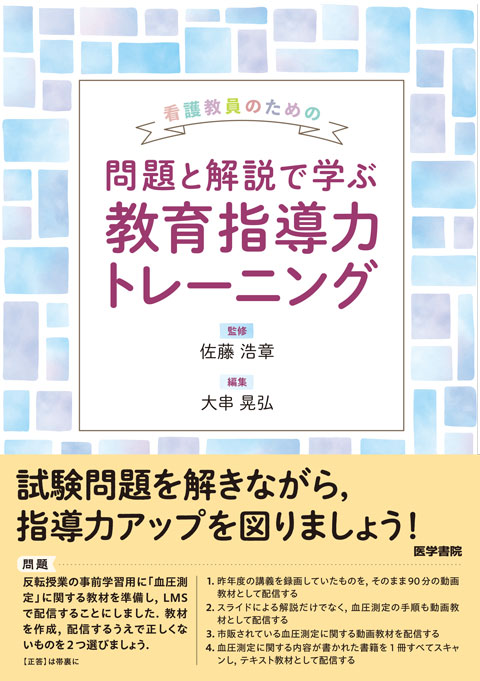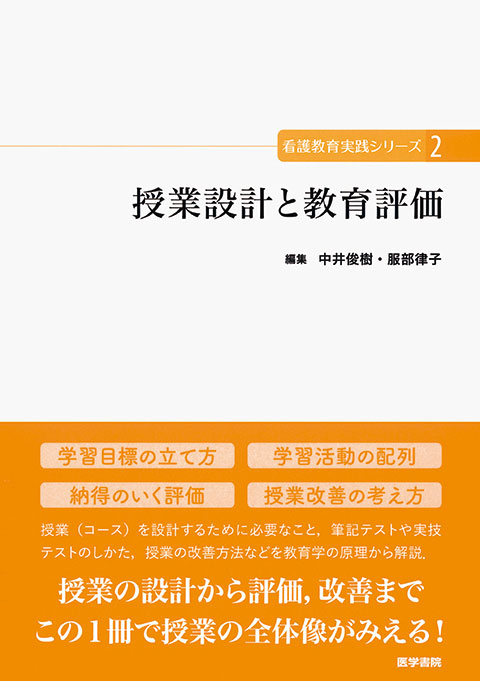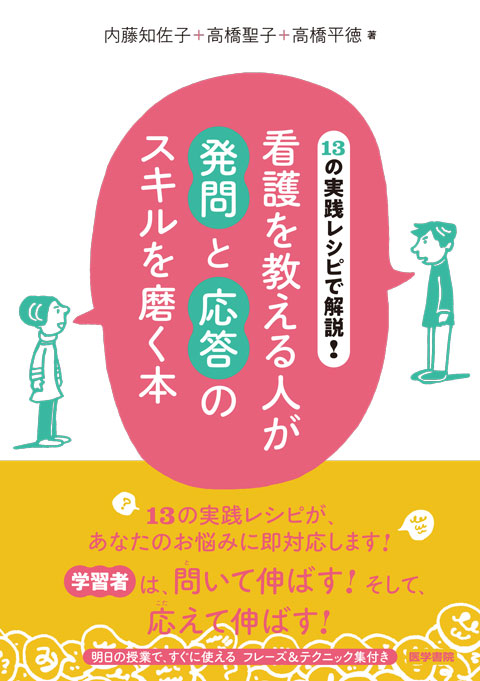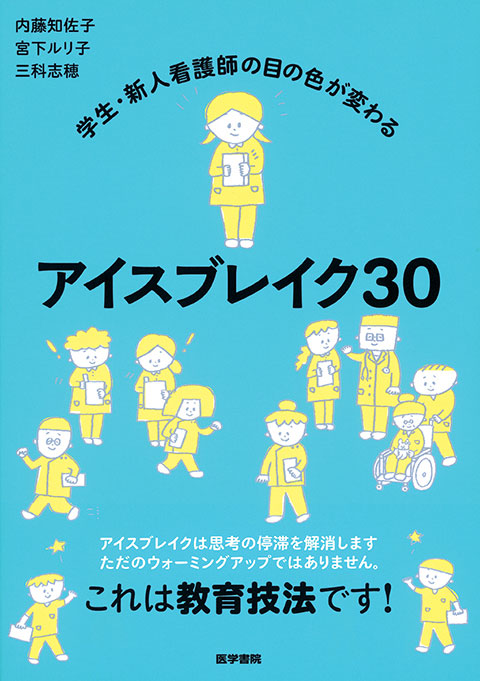看護のための授業づくりガイド[Web付録付]
30のQuestionとその答え・解説で、授業づくりの悩みを一発解決!
もっと見る
本書は、初めて授業をすることになった看護教員が「知りたい」と思う内容を、30のQuestionとそれに対する答え・解説で構成しました。著者らが自分たち自身が教員になったばかりの時を振り返り、「こんなことが知りたかったな」「こんなことを知っているとよかったな」と思った内容を詰め込んでいます。Web付録の動画と資料も活用しながら、授業づくりを見直しブラッシュアップしてみてください。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 著者による本書の紹介
- 序文
- 目次
- 書評
- 付録・特典
著者による本書の紹介
開く
序文
開く
はじめに
この本は,私たちが教員になったばかりのときを振り返り,こんなことが知りたかったな,こんなことを知っているとよかったなと思ったことを詰め込んだものです.
取り上げている項目は奥が深く,とてもこの1冊で説明しきれるような内容ではありません.しかし,教員になって間もない頃は,その1つひとつを深く学んでいるゆとりはなく,ちゃんと学びたいなと思いつつも日々の業務に追われ,先輩や同僚に聞いたり相談したりしながら,なんとか“自分なり”にやっているというのが実情ではないでしょうか.また,困っていることや改善したいことはあっても,そのために何を学べばよいか,どんな本を読めばよいのかわからないということもあります.
臨床などで実践を積んできて,さまざまな場面に応じて看護することの醍醐味を感じるようになると,そのことを学生たちに伝えたいと思う一方,教員になって授業をしてみると,初めて看護を学ぶ学生にわかるように教えることの難しさを痛感します.自分が学生のときに教わってきたことを思い出しながら授業してみてもうまくいかないことも多々あり,教員には,優れた看護の実践者であることに加え,教育に関する知識が不可欠であることを実感します.
そんなときに活用していただけるよう,看護を教育するうえで必要となる知識を,「まず,こんなことがわかっているといいな」と思う内容に絞り込み,「忙しいなかでも,必要な項目をさっと読める」ことを目指してこの本をつくりました.そして,初めてのときには「これってどうつくればいいの」と思うような教育の場面で使う様式の例や「百聞は一見に如かず」と思われる場面を動画で見ていただけるよう,Web付録として資料を提供しました.さらに詳しく知りたいという場合には参考文献を活用して知見を広めていただければと思います.
専門分野に関する知識や技術を,学習者が効果的,効率的に学べるよう,教育の質を向上させることが求められている今,さまざまな教育方法を活用し,学生の皆さんが関心をもって主体的に学べるよう工夫することは容易ではありません.それでも,専門職を育てるやりがいも大きいのが看護教育です.
「こんなときどうすればいいんだろう」「何かいい方法はないかな」と思ったときに参考にしていただける,そんな1冊としてお役立ていただければ幸いです.
2024年4月
著者を代表して 服部律子
目次
開く
1 授業設計──授業計画はこう立てる
Q01 授業はまず何から準備すればいいのでしょうか?
Q02 授業はどう組み立てればいいのでしょうか?
Q03 学習目標ってどうやって決めればいいのでしょうか?
Q04 どうしてシラバスが必要なのですか?
Q05 1回分ずつ授業のシラバスをつくったほうがいいのでしょうか?
Q06 学生の学習意欲を高めるにはどうすればいいのでしょうか?
Q07 課題をする時間が足りないと学生が言いますが,どうすればいいのでしょうか?
Q08 授業評価アンケートって必要なのでしょうか?
2 授業方法──さまざまな方法を活用して授業する
Q09 どうしたら上手に講義ができるでしょうか?
Q10 どうすれば授業中に学生の思考を促せるでしょうか?
Q11 学生を惹きつける授業にするためにはどうすればいいのでしょうか?
Q12 オンライン授業にはどのような方法がありますか?
Q13 アクティブ・ラーニングってなんですか?
Q14 教員が説明する以外の授業方法って何かありますか?
Q15 グループワークをうまく実施するコツってありますか?
Q16 ディスカッションや実践の時間を授業中にとれるようにする方法はありませんか?
Q17 シミュレーション学習ってどうすればいいのですか?
Q18 高機能なシミュレータがないのですが,シミュレーション学習はできますか?
Q19 学生同士で演習すると真剣味に欠けるのですが,何かいい方法はありませんか?
Q20 演習の振り返りってどうすればいいのでしょうか?
3 評価方法──講義・演習・実習はこう評価する
Q21 学修成果はどのように評価すればいいのでしょうか?
Q22 どうすれば学生のがんばりを評価できますか?
Q23 筆記試験ってどうやってつくればいいのでしょうか?
Q24 実技テストの評価ってどうすればいいのでしょうか?
Q25 グループ課題の場合,学生1人ひとりを評価することってできますか?
Q26 実習の評価はどうすればいいのでしょうか?
4 改善方法──それぞれの段階で改善する
Q27 授業を改善したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
Q28 コースの途中で学生の理解度を確認したほうがいいのでしょうか?
Q29 授業の途中で学生の理解度を確認したほうがいいのでしょうか?
Q30 カリキュラムが適切かを評価するにはどうすればいいのでしょうか?
Column
1 指定規則って何?
2 モデル・コア・カリキュラムって何?
3 学習の動機づけ
4 教育制度の基本
5 成人学習
6 短時間でできるアイスブレイク
7 看護過程の学習にシミュレーションを組み込むことも効果的
8 実習の単位を認定できるかを評価するって難しい
9 Carrollの時間モデル
10 3つのポリシーって何?
参考文献
おわりに
索引
資料・動画一覧
資料1-1 配付シラバスの例:母性看護学概論
資料1-2 同:成人・老年看護学概論
資料2-1 コマシラバス(指導案)の例:母性看護学概論 第〇回
資料2-2 同:成人・老年看護学概論 第○回
資料3 反転授業で実施した演習の例:母性看護援助論演習 第〇回
資料4 チェックリストの例:分娩介助技術
資料5 ルーブリックの例:母性看護学実習評価
動画1 母性看護学を例にしたGoogle Classroomを用いたオンライン教材作成法:Classroomの作成
動画2 同:資料と動画のアップ方法
動画3 同:課題のアップ方法
動画4 同:Formでの小テストの作成
動画5 協同学習の方法:シンク・ペア・シェア
動画6 同:ジグソー法
動画7 同:ワールドカフェ
動画8 教員や臨床看護師が演ずる模擬患者活用のポイント
動画9 学生同士でのロールプレイの注意点
書評
開く
新人教員にはバイブルとして、ベテラン教員には振り返りに役立つ必見の書
書評者:前田 ひとみ(熊本大学名誉教授・特命担当教授)
本書に最初に目を通した時に、ヴァージニア・ヘンダーソンの著書『看護の基本となるもの』の【はじめに】の言葉が頭に浮かびました。「この本には、基本的看護を構成している諸活動の大要を述べてある。(中略)この小冊子は看護を一般的に論じ、どのような患者のケアにも応用可能としているところから、基本的な看護活動を述べることしかできない。つまり方法を記述することはできない。これは決してマニュアルではない。方法については読者はそれぞれの国の教科書類を参照してほしい」1)というくだりです。そして、大学の教員となって2か月目の新人看護教員が本書を読んでうれしそうに、「こんな本が欲しかったんです! 新人看護教員のバイブルです!!」と言うのを聞いて、それが確信に変わりました。
大学教員は学術論文が評価の対象となることから研究手法の訓練は積んでいても、教育方法についてはよく理解できないまま、これでいいのかと常に葛藤しながら、自分ができるもので日々の授業をこなしていることが少なくないと思います。学生の学力低下が問題視されていますが、その原因に、このような教員側の状況は関係ないでしょうか。研究を進めるにあたって研究計画書は欠かせませんし、研究計画書を書くためには研究に対する知識が必要です。同様に、授業をするためには授業計画作成に必要な教育の知識が必要です。しかし、たくさんの教育理論や教育方法論から、どれが看護教育に生かせるのかを見いだすことは容易ではありません。本書では、授業計画、授業方法、評価方法、そして改善方法についての基本が『看護の基本となるもの』と同様に簡潔にまとめられています。各項目についてもっと具体的に知りたい、学びたいと思う人はまずは示されている文献を読んでみるといいと思います。
また、Web付録は、ちょっとした隙間時間で見られる長さでポイントが押さえてあり、自分の授業でも使えそうなものです。中でも、グループワークやロールプレイを効果的に進めるために大事な雰囲気づくりについても、その方法を見ることができます。もっとも、実際にやってみるとそう簡単にはいかないでしょうから、何度も視聴し確認しながら進めたいところです。
新人看護教員においては、本書はバイブルとなり得、ベテラン教員においては自分の授業を振り返る方法を確認でき、自己啓発や授業改善につながると思います。良い授業を行いたい人必見の本です。
[文献]
1)ヴァージニア・ヘンダーソン(著)/湯槙ます,小玉香津子(訳):看護の基本となるもの. p.8, 日本看護協会出版会, 2018.
(「看護教育」 Vol.65 No.4 掲載)
新任からベテランまで世代を超えて役立つガイドブック
書評者:佐藤 浩章(大阪大学学際大学院機構教授)
本書は,看護教員が授業を実施するためのガイドブックである。評者は長らく大学教員の能力開発業務を担当しているが,看護教育分野の実践と研究の豊かさには感嘆する。看護教員のための授業づくりに関する類書は他にもあるが,本書はその中でもユニークな特徴を持っている。
新任看護教員が思いつく,授業にかかわる素朴な30の問いにベテラン教員が直接丁寧に答えるような,Q&A形式で構成されている。その問いは,「アクティブ・ラーニングってなんですか?」「筆記試験ってどうやってつくればいいのでしょうか?」というような分野を越えて新任教員が抱きそうなものもあれば,「学生同士で演習すると真剣味に欠けるのですが,何かいい方法はありませんか?」「演習の振り返りってどうすればいいのでしょうか?」というような,看護教員がよく遭遇する場面に対応したものもある。
それらの問いに対応する答えは,教育学や心理学の理論やツールに基づくものが多く,その信頼度も高い。ケラーのARCSモデル,ダニング・クルーガー効果などの専門用語や,ルーブリック,リフレクティブサイクルなどのツールも平易に学ぶことができる。一方,本書の随所には著者らの長年の教育実践に裏付けられた記述もあり,有用度も高い。さらにWeb付録(閲覧するには書籍ごとに発行されているシリアル番号が必要)には,シラバスやコマシラバス(授業計画),ルーブリックなどの資料の他,紙面では伝わりにくい,オンライン授業の方法に関する動画資料などが収載されている。
本書の冒頭には,本書が「教員になったばかりのときを振り返り,こんなことが知りたかったな,こんなことを知っているとよかったなと思ったことを詰め込んだ」ものであると書かれている。この裏には「最低限このくらいのことは知っておいてね」「知らないと苦労するよ」という先輩看護教員からの愛に溢れたメッセージがある。
もちろん新任看護教員が手元に置いておくには最適な書籍ではあるが,中堅・シニア教員が自らの教育実践を振り返るためのチェックリストとして,あるいは新任教員のメンターをする際のガイドとしても活用できる。世代を超えた多くの看護教員に手にとっていただきたい書籍である。
![看護のための授業づくりガイド[Web付録付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/8417/1332/1896/112193.jpg)