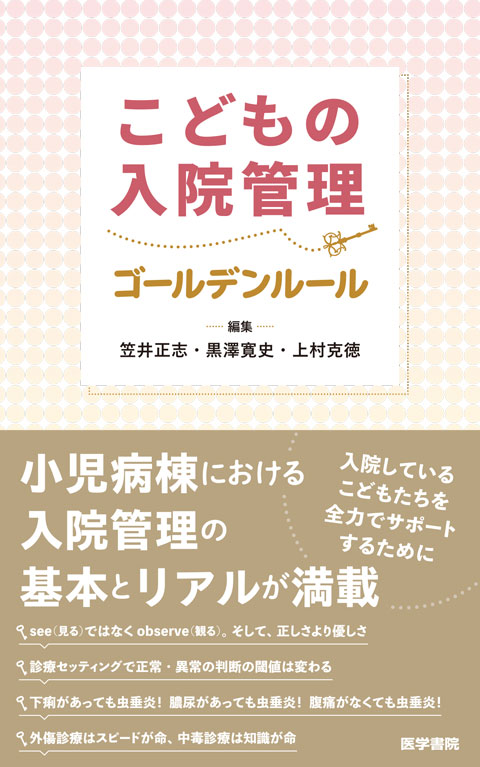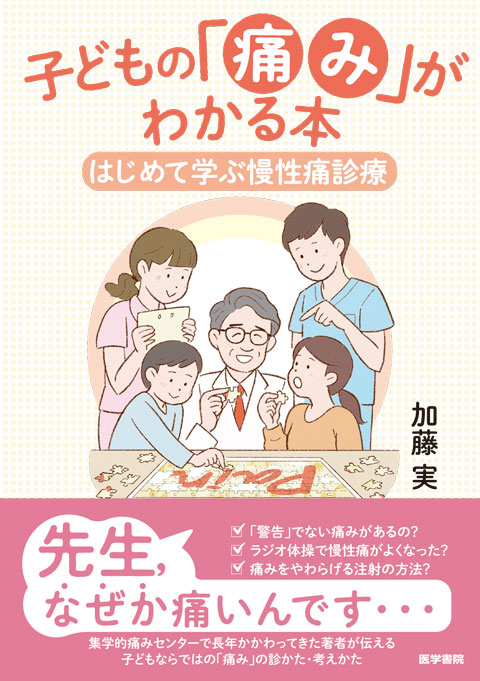小児医療の明るい未来を切りひらく
対談・座談会 笠井正志,黒澤寛史,上村克徳
2024.01.29 週刊医学界新聞(通常号):第3551号より

Hibワクチンや小児用肺炎球菌ワクチンなどの予防医学の発展によって,重症の小児入院患者は減少している。そのため子どもの入院管理では,軽症例に潜む重篤な疾患をいかに見逃さないかが重要となる。少子化が進み小児科医一人当たりが経験できる症例数が少なくなる中で,重症例の見極めをどう体得すればよいか。
本紙では小児患者の入院管理に必要な知識をまとめた新刊『こどもの入院管理ゴールデンルール』(医学書院)の編者である笠井氏,黒澤氏,上村氏による座談会を企画。小児科医として臨床現場の最前線で長年活躍し,指導医として後輩の教育にも尽力する3氏の議論から,小児医療の今後の展開を考えたい。
笠井 少子化に伴い,日本の小児医療はこの数十年で目まぐるしく変化してきました。急速な変化に伴い表出した課題に対し,われわれ指導医世代が試行錯誤することは,次世代への良いバトンになるはずです。
このたび小児入院患者への診療の要点をまとめた『こどもの入院管理ゴールデンルール』が発行されました。本日は共に編者を務め,後進の育成も行う黒澤先生と上村先生にお集まりいただき,小児医療が抱える課題や小児科医が伸びやかに成長していくための方策などをお話しできればと思います。
重症例が減る中で経験値をどう高める?
笠井 本日のメンバーは全員卒後20年以上が経過し,長きにわたり小児医療に従事してきたと言えます。これまでの臨床経験から,日本の小児医療にどのような変化を感じていますか。
上村 ワクチンなど予防医学の発展によって軽症例の割合が増え,われわれが若手であった頃よりも急性疾患による入院患者が減少したことです。もちろん,それは喜ばしいことですが,研修や教育の観点からは重篤な疾患に対する経験値が不足しやすくなっている現状があります。
黒澤 同感です。われわれが若手の頃は,はしかや髄膜炎を発症する子どもが少なからずいました。一方で,現在の小児科専攻医でそうした疾患を診たことのある人は少ないのではないでしょうか。
笠井 小児医療において見逃してはならない重篤な疾患の一つが髄膜炎であり,Hibワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの定期接種が2011年に開始されるまでは月に1~2例経験するほどの疾患でした。かつては同疾患に対して正しく対応できて初めて一人前と考えられていたものです。一方でワクチンが普及した現在では当施設でも年5~6例を扱うにとどまります。髄膜炎が重篤な疾患であることは今なお変わらないものの,若手の医師で同疾患を診たことのある人はあまり多くないはずです。
また,小児医療の臨床経験を積める場所も減っています。小児科の専門機関でなければ,他科との混合病棟しかない施設も増えているのが実情です。
上村 小児病棟を設置している施設のほうが少ないですよね。子どもの人数が減っているから当然なのですが,今の体制をこのまま続けていくと小児医療がいずれ先細りになるのは明白です。
黒澤 集中治療の領域でも経験値をどのように高めるかは課題となっています。重篤な疾患は対応が遅れると後遺症をもたらす可能性があるので,容態が急変した場合に小児病棟の入院患者をいつICUに転送するかを見極めるのはとても重要です。従来はICUに転送される小児患者が一定数存在し,転送の見極めのノウハウが個々人に蓄積されていったものの,現在ではそうしたスキルアップが難しくなっています。
笠井 現在,小児科を抱える病院は小児医療から撤退するか,他施設の症例も集約できるほど規模を大きくするかのどちらかを迫られています。個人的には後者であってほしいですし,だからこそハイボリュームな専門機関は多数の症例を診るだけでなく,人材を教育する観点も持ち合わせる必要があるでしょう。兵庫県では当施設と上村先生の所属する兵庫県立尼崎総合医療センターがタッグを組んで小児科研修を行っているので,ぜひこうした事例が全国的に普及していくことを願っています。
時代や環境の変化に応じた指導法の選択
笠井 皆さんは普段,後輩を教育する機会が多いと思います。指導する中で意識していることがあれば教えてください。
上村 自らを成長させるには①話すこと,②考えること,③書くことが重要だと若手に伝えています。現代は検査の手法や機器が発達したために,鑑別疾患を突き詰めて考えなくても結論が出るでしょう。また,生成系AIの台頭により推論しなくても診断できてしまう未来もあり得ます。しかし,それだけでは事前の想定とは異なった場合に応用が利きません。だからこそ①~③を行うことで医師に必要な思考パターンの基本を身につけておく必要があるのです。
笠井 ただし,①~③を行うように伝えてもなかなかすぐに実践されないのが現実です。例えば②考えることを実践させたいのであれば,考えなければいけない状況を指導医側がつくりだすか,考えることが普通であるとの空気を組織内に醸成するかのどちらかを整備しなければならないでしょう。
黒澤 われわれが若手の頃は前者でした。卒後1~2年目から一人きりで当直を担当し,指導医に気軽に相談できない状況がよくありましたから。
笠井 従来は何人もの患者を主治医として担当していましたが,現代では子どもの数が減り,重症例も減っている。そうした中で同じ学びのスタイルを採り続けるのは効率的とは言えません。
上村 同感です。ですので,若手を指導する際は個人がひたすらスキルや知識を吸収していく方法から,事例や学びをシェアするスタイルに変えることを意識しています。
黒澤 全体の底上げという点で効率的な手法だと思います。効率的に学習するには専門機関に学びに行く「...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

笠井 正志(かさい・まさし)氏 兵庫県立こども病院 感染症内科 部長
1998年富山医薬大(当時)を卒業後,淀川キリスト教病院に勤務。千葉県こども病院,長野県立こども病院,丸の内病院などを経て,16年より兵庫県立こども病院感染症科の立ち上げにかかわり現在に至る。小児科専門医。一般社団法人こどものみかた副理事長。編著に『こどもの入院管理ゴールデンルール』(医学書院),『HAPPY! こどものみかた第2版』(日本医事新報社)など。「自分に適した環境かを見極めるには,さまざまな人と会い,本を読んで感性を磨くことが重要です」。

黒澤 寛史(くろさわ・ひろし)氏 兵庫県立こども病院 小児集中治療科 部長
2000年東北大を卒業後,仙台市立病院に勤務。国立成育医療研究センター,神戸市立医療センター中央市民病院,静岡県立こども病院にて研さんを積んだ後に米フィラデルフィア小児病院,豪メルボルン王立小児病院に留学。15年兵庫県立こども病院に赴任。16年同院に小児集中治療科を開設し現在に至る。集中治療専門医,救急科専門医,小児科専門医。編著に『こどもの入院管理ゴールデンルール』(医学書院),訳書に『PICUハンドブック』(テコム)。「小児集中治療は『子どもが好き』なだけでは務まりません。タフな精神力を持った若手をお待ちしています」。

上村 克徳(かみむら・かつのり)氏 兵庫県立尼崎総合医療センター 小児科 部長
1992年愛媛大卒。国立成育医療研究センター,兵庫県立こども病院救急総合診療科などを経て,20年より現職。小児科専門医。『こどもの入院管理ゴールデンルール』(医学書院),『HAPPY! こどものみかた第2版』(日本医事新報社),『小児科研修の素朴な疑問に答えます』(メディカル・サイエンス・インターナショナル)など編著書多数。「伸びやかな成長のためには良い指導医について,その指導医を超えるためにどう学ぶかを考えてみましょう」。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。