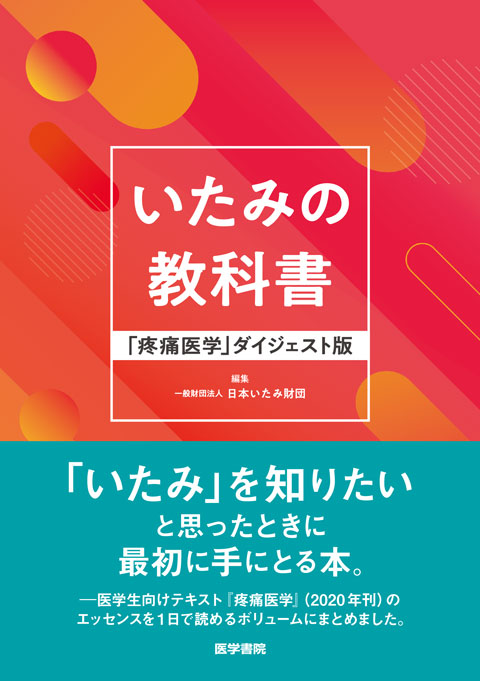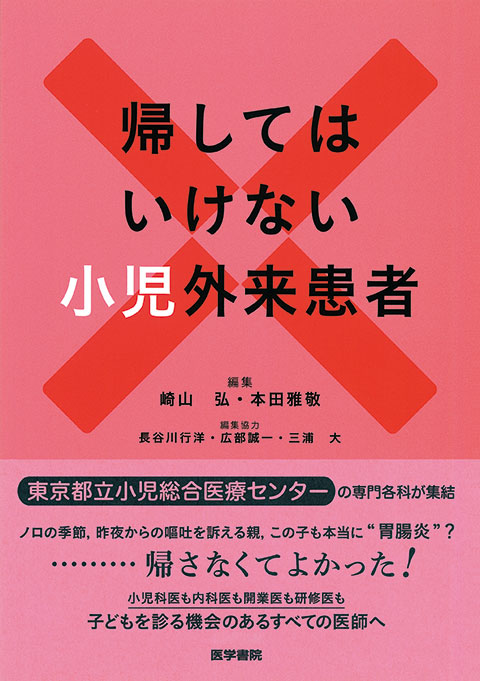子どもの「痛み」がわかる本
はじめて学ぶ慢性痛診療
誰も教えてくれなかった、子どもならではの「痛み」の診かた・考えかた
もっと見る
子どもは大人より痛みを感じやすい? 子どもの頃の痛みの体験がその後も影響する? 予防接種の時に痛みを減らす方法があるの? 集学的痛みセンターで長いあいだ慢性痛診療に取り組んできた著者が伝える、子どもならではの「痛み」の診かた・考えかた。同じ「痛み」でも急性痛と慢性痛のメカニズムのちがいを、診療のコツや豊富な症例を交えながら、わかりやすく解説している。巻末付録には日常臨床の疑問に答えるQ&Aもあり。
| 著 | 加藤 実 |
|---|---|
| 発行 | 2023年01月判型:A5頁:160 |
| ISBN | 978-4-260-05008-1 |
| 定価 | 3,850円 (本体3,500円+税) |
更新情報
-
正誤表を追加しました。
2022.12.20
- 序文
- 目次
- 書評
- 正誤表
序文
開く
はじめに──子どもの「痛み」を「そうだったのか」と理解することから始めてみませんか
子どもの痛みは,世界的に過小評価されやすい傾向にあります.「注射の痛みはちょっとチクンだけだから」「そのうち治るから大丈夫」「がまんして当たり前」などとあまり問題視されないため,適切な痛み対応を受けられない子どもは珍しくありません.しかし近年,子どもの時の痛みの体験が,その後の痛みの感じ方や大人になってからの慢性痛など将来的に影響を及ぼす事実が明らかになってきました.現在,国際的にも,子どもを含めた弱者への痛み対応が最重要課題として掲げられています.
ふり返ると,私自身の子どもの痛みとの関わりは,1983年に駿河台日本大学病院麻酔科(当時)へ入局し,子どもの術後痛管理に携わった時から始まりました.そこでは手術後の傷の辛さを減らす工夫をしていました.また1990年代にはペインクリニックの業務で,がんの痛みで苦しむ子どもにモルヒネやケタミンなどを持続静脈内投与しながら,小児科医や精神科医と一緒に痛み対応に携わってきました.
その後,1996年から留学したトロント大学では,Acute Pain Research Teamのスタッフの一員として,手術侵襲の前から侵害刺激(メスや注射など身体に痛みを誘発する刺激)の積極的な予防に携わり,中枢性感作(中枢神経の過敏化)の誘発予防との相関を調べる臨床研究にも従事していました.加えて,難治性慢性痛患者に対し多職種で集学的に診察結果を討論するPain Roundというカンファレンスに参加する機会があり,そこで子どもの慢性痛と出合うことになります.カンファレンスでは「とれない痛みで困っている子ども」に対して,多職種による集学的アプローチを介して生物心理社会的(biopsychosocial)評価から痛みの原因を明らかにし,原因に応じた対応法や治療先を選択していました.子どもの慢性痛の原因には身体的要因だけではなく,心理・社会的要因の複雑さが隠れており,その情報を見出すために多職種が連携する必要性を強く感じました.
この体験から約10年後の2007年に,国内で慢性的な痛みで苦しむ子どもに対し,小児科あるいはペインクリニック科単体では適切な痛み対応ができない場面に遭遇しました.必要に迫られた形で小児科,ペインクリニック科,整形外科,心療内科,精神科,そして臨床心理士や理学療法士,作業療法士と連携しながら診療を行ったところ,患児の痛みの軽減と日常生活の改善に辿りつけました.この経験が日本大学医学部附属板橋病院の集学的痛みセンターの多職種医療につながったことは間違いありません.
これまで子どもの痛みに焦点を当てて,生物心理社会的な視点から系統的に書かれた書籍はありませんでした.そこで今回,子どもの痛みの理解をより深めていただくために,必要な痛みの基礎知識,加えて臨床現場での痛みの予防や痛みで困っている子どもと保護者の対応に役立つ書籍を執筆することにしました.
本書が皆様の日常診療の一助となり,子どもたちの笑顔につながることを願っています.
最後に,子どもの痛み治療に一緒に携わってきた日本大学医学部附属板橋病院の皆様,麻酔科 松井美貴先生,荒井 梓先生,小児科 川口忠恭先生,公認心理師 高橋桃子先生,精神科 久保英之先生,横瀬宏美先生,看護師 佐藤今子さん,牛山実保子さん,塚原美保さん,薬剤師 上島健太郎さん,坂田和佳子さん,作業療法士 鳥沢伸太さん,事務担当の中山 満さん,高石智恵さん,そして,麻酔科OBの後閑 大先生,上田 要先生,山本悠介先生に心より感謝申し上げます.また「子どもの痛み」をテーマにした書籍を世に出すことに多大なお力添えいただきました医学書院編集部の塩田高明氏,制作部の日高汐海氏に深甚の謝意を表します.
2022年10月
加藤 実
目次
開く
はじめに──子どもの「痛み」を「そうだったのか」と理解することから始めてみませんか
I.子どもの「痛み」を理解する
① なぜ「痛み」を感じるのか?
「痛み=警告」とは限らない
脳で痛みが作られるまでの仕組みと,伝わりにくくさせる仕組み
急性痛と慢性痛の違い
機序からみた痛みの分類
痛みの定義と子どもの特性
② 子どもは大人より「痛み」を感じやすい?
③ 強い「痛み」の体験はその時だけでは終わらない?──痛み予防の意義
④ ワクチン注射時の痛みの軽減法──笑顔につながる子どもの痛み予防
5Pアプローチによる痛みの軽減法
新型コロナワクチンの接種研修でのポイント
II.子どもの「痛み」を診る
① 痛みを尋ねる際に知っておきたい5つのポイント
② 急性痛と慢性痛の見きわめ方──その原因,随伴症状と特徴
③ 慢性痛を評価する
痛みの基本情報と時系列変化の情報収集
身体診察
子どもの慢性痛の診断と病態の総合評価
④ 慢性痛に対するアプローチ
治療の目標設定
痛み基本対応の3Pアプローチ
小児慢性痛対応のWHOガイドラインの誕生
⑤ 代表的な痛みの部位と慢性痛をきたす疾患
頭・口腔・顔面の痛み
四肢の痛み
複数の部位にわたる痛み
腹部の痛み
背部・腰部・肩部などの体幹の痛み
⑥ 症例紹介
症例1 スマホゲームが原因で不登校になった,難治性頭痛を抱える中学生
症例2 骨折後ギプスを外した後に新たに手の痛みが生じた子ども
症例3 腰痛と子宮頸がん予防ワクチン接種との関連に不安を抱いて来院した子ども
症例4 痛み治療に難渋し来院した多関節痛の子ども
症例5 保護者の行動変化を契機に腹痛が消失した幼児
症例6 薬物療法と運動療法で手術後の指の痛みが改善した子ども
症例7 小児科・整形外科疾患ではない腫れ,感覚・運動障害を伴う手の痛みを訴える子ども
症例8 ペインクリニック,作業療法士,臨床心理士の集学的アプローチがうまくいった慢性痛患児
症例9 集学的アプローチと神経ブロックにより改善に向かった全身の痛みを抱える子ども
症例10 集学的アプローチを通じて,学童期のトラウマ体験が痛みの増強要因とわかった成人の慢性痛患者
⑦ 集学的アプローチによる痛み治療
集学的痛みセンターのはじまり
痛みセンターにおける子どもの多面的評価
集学的アプローチに基づく痛みセンターの特徴と実際
日常診療における子どもへの問診テスト結果から具体的な集学的アプローチにつなげるアルゴリズム
付録 Q&A
索引
コラム
1 Nociplastic pain(痛覚変調性疼痛症)
2 痛みの定義が誕生した背景とその意義
3 慢性痛の現状──成人と子どもの比較
4 村上春樹さんの書籍から学ぶ痛みの奥深さ
5 TRPV1は「末梢侵害刺激受容体」
6 慢性痛が持続する機序
7 子どもの適切な痛み対応習得のための教材──痛みについて知り,理解を深めるために
8 臨床倫理の3原則──人間尊重,与益,社会的適切さ
9 子どもの慢性痛の管理・対応に関するガイドライン
10 ICD-11に新たに疾病登録された慢性痛
11 いたみマネージャー
12 慢性の痛み政策研究事業
書評
開く
子どもの痛みをとらえ,最小限にできる支援をめざして
書評者:河俣あゆみ(三重大病院副看護部長/小児・AYAがんトータルケアセンター副センター長/小児看護専門看護師)
「痛み」は主観的な症状であり,認知や言語的発達が途上である子どもの場合,痛みを他者に的確に伝えられないことから,その子どもを取り巻く第3者が痛みを客観的にとらえることが重要となります。痛みが軽減される,あるいは痛みから解放されることは,子どもにとって安楽や安寧が守られる権利であり,子どもを尊重したケアであることは言うまでもありません。しかしながら,子どもの年齢や発達,置かれている状況および特性などから,子ども自身が痛みを表現することや,医療者がその表現をとらえて評価し,痛み緩和ケアにつなげることは難しい場合があります。看護職に求められるのは,子どもの痛みを捉える感受性と判断,そして痛みを緩和できるケアを選択し,組み合わせて実践するといったスキルになります。発達段階によって,子どもの痛みの表現は異なり,「子どもの痛みをとらえてアセスメントする」ことが簡単ではないことも少なくありません。子どもの権利を尊重し,子ども自身が主体的に痛みを緩和することができるように,家族と協働することも重要になると考えます。
本書を手にしたとき,子どもの痛みに関する新しい知見が盛りだくさんに説明されており,メモや付箋を貼りながら一気に読み進めてしまいました。本書のコラムにも大変興味深い内容があります。コラム3「慢性痛の現状―成人と子どもの比較」にある,「国際的研究事業であるカナダのPain In Child Health(PICH)のデータによると,子どもの5人に1人が慢性痛を抱えており,さらに20人に1人が痛みを原因に不登校になっていると報告がされています」という記載には大変衝撃を受けました。さらに症例紹介では,診療時の子どもや家族と医師とのやり取りがリアルで,その場にいるかのように引き込まれます。
II章4「慢性痛に対するアプローチ」では,2021年2月にWHOが公開した子どもの慢性痛の管理に関するガイドラインによると,小児の慢性痛は3~4人に1人と高頻度にあることが紹介されています。現状,治療を受ける子どもの疼痛緩和については積極的に取り組まれていますが,慢性痛については本書から多くのヒントをいただけたと感じるとともに,看護職として取り組まないといけない課題があるのではないかと感じました。
本書を読むことは,外来診療や子どもの生活にかかわる看護職が子どもの慢性痛に対する理解や緩和ケアについて,今一度考える良い機会になると考えます。「いたみマネージャー」や「集学的痛みセンター」の活動も大変興味深いです。子どもの痛みが最小限になる,痛みから解放されることをめざして,子どもと家族を支援する多くの看護職の方々にもぜひ手に取って読んでいただきたいと思います。
「子どもを主語に」小児の慢性疾患にかかわる全ての人へ
書評者:余谷 暢之(国立成育医療研究センター総合診療部緩和ケア科診療部長)
子どもの痛みは歴史的に過小評価されてきました。その中で,多くの研究者たちが子どもの痛みについてのエビデンスを積み重ね,「子どもはむしろ痛みを感じやすい」ことが明らかになりました。その結果,諸外国では子どもへの痛みの対応が丁寧に実践されていますが,わが国においては十分に対処されているとはいえない状況があります。著者である加藤実先生は子どもの痛みに真摯に向き合い,丁寧に臨床を重ねられ,さまざまな学会でその重要性を訴えてこられました。その集大成が本書であると思います。
本書で紹介されている慢性痛は,急性痛とは異なるアプローチが必要となりますが,そもそも小児領域では急性痛,慢性痛という概念すら十分に浸透していない状況です。慢性痛は心理的苦痛や社会的影響を伴い,子どもたちの生活の質に深刻な影響を及ぼす可能性があり,生物心理社会的(biopsychosocial)アプローチが必要となります。3~4人に1人が経験するとされ決してまれでない慢性痛は,小児プライマリケア診療においても重要な領域ですが,体系立って学ぶ機会が少なく,本書の役割は大きいといえます。
本書では痛みを「感覚」「情動」「認知」の3つの成分に分けて,その要因の評価と対処法が記されています。通底するメッセージは「子どもを主語に」です。それは著者の「痛みを治すのは医師や薬ではなく,あなたです」という言葉に表れています。痛みの対応を自分ごととして取り組むために,多職種アプローチでその子の背景にある情報を丁寧に収拾し,アセスメントを行い,子ども本人が自身の痛みの原因と機序について理解できるように説明すること,これが子どもと家族にとって大きな支援になっているのではないでしょうか。自分の痛みがこのようにして起こっているのだと理解することで,痛みが理由もわからない怖いものから,理由があるコントロールできるものに変わるのだと思います。それが,痛みに対して自分で取り組もうというモチベーションにつながり,コントロールできるようになることで自己効力感が高まるという正の循環に入るのだと思います。
とはいえ,このアプローチは容易ではありません。本書では,慢性痛の理論的な背景が非常にわかりやすい言葉で説明されているだけでなく,具体的な症例へのアプローチの方法も「症例紹介」の中にたくさん紹介され,まるで加藤先生の臨床を傍らで眺めているような臨場感にあふれています。これを読めば,慢性痛を訴える子どもが自分の外来を受診した際に具体的にどうかかわるかのイメージが持てるでしょう。このコンセプトは痛み診療に携わる方だけでなく,小児の慢性疾患にかかわる全ての人にとって参考となる内容です。子どもにかかわる多くの方に手に取っていただきたいと思います。
児童・思春期の医療・教育に携わる人へ
書評者:倉澤 茂樹(福島医大教授・作業療法学)
感覚過敏や鈍麻など,臨床を通じ肌身でとらえた子どもの感覚世界を,子どもの代弁者となり保護者や多職種に伝えることの重要性を実感している。本書を読み終え,著者である加藤実先生に勝手ながら妙な親近感を覚えた。長年にわたり子どもたちの痛みと向き合ってきた臨床家としての経験知,そしてエビデンスを重視する研究者としての姿勢に共感したのである。
子どもの痛み体験は,身体的反応だけでなく,不安や恐怖など情動体験として認知形成され,長期的な影響も引き起こす。この事実はわが国の児童・思春期医療において十分に認識されていない。処置時の痛みは「一瞬だから」と軽視され,「そのうち慣れる」と放置されることも少なくない。リハビリテーションに携わるセラピストも例外ではない。新生児集中治療室ではカテーテルやモニター機器が装着され,臓器発達の未熟な新生児は動くことにさえ苦痛を伴うだろう。術後早期から開始されるリハビリテーションにおいて“機能回復”を優先するあまり,痛みを蔑ろにしていないだろうか? エビデンスとともに示される事実によって,われわれセラピストは内省する機会を得るだろう。
本書は,臨床現場における子どもの痛みの予防,痛みに苦しむ子どもと保護者への対応に寄与することを意図して構成されている。
第I章「子どもの『痛み』を理解する」では,痛みの定義,メカニズムそして痛みに伴うさまざまな影響について,専門的知識を有さない読者にも伝わりやすいようわかりやすく説明されている。慢性痛への対応には,保護者をはじめとして子どもの生活を支えている周囲の人々の協力が重要となる。支援者の正しい理解と適切な対処方法を引き出すために,家族・心理教育(あるいは疾病教育)が有効とされており,本章にはそのヒントが詰められている。
第II章「子どもの『痛み』を診る」では,見逃されやすく言語化されにくい子どもの慢性痛をどう評価するかについて,臨床実践と研究に裏付けられた5つのポイントが,具体例とともに示されている。そして,そのアプローチ方法についてWHOによるガイドラインを引用しながら,身体的要因への対応,心理・社会的要因への対応,薬物療法が解説されている。本章に登場する10の症例は,慢性痛を引き起こす各疾患の理解を促すだけでなく,診療を進めるための道筋を示している。症例ごとに記載されている“診察者の頭の中を覗く”では,いかに子どもの症状をとらえ,類推し,診断・治療へと導くか,が述べられ,読者は関心をもって読みすすめるに違いない。さらに症例報告にはさまざまなノウハウが凝縮されている。例えば,図を用いて子どもに痛みの原因を説明する方法は,子どもの不安を取り除くだけでなく,治療へのコンプライアンスを確保するために効果的な工夫と言えよう。
慢性痛は,国際疾病分類 第11版(ICD-11)において初めて疾病として位置付けられた。今後,診断・治療される子どもが増えることが予想される。著者が強調するように子どもの慢性痛の要因は複雑に絡み合っていることが多く,中・重度の場合は理学・作業療法士を含めた集学的アプローチが必要となる。本書はその先駆けであり,優れた入門書である。
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。