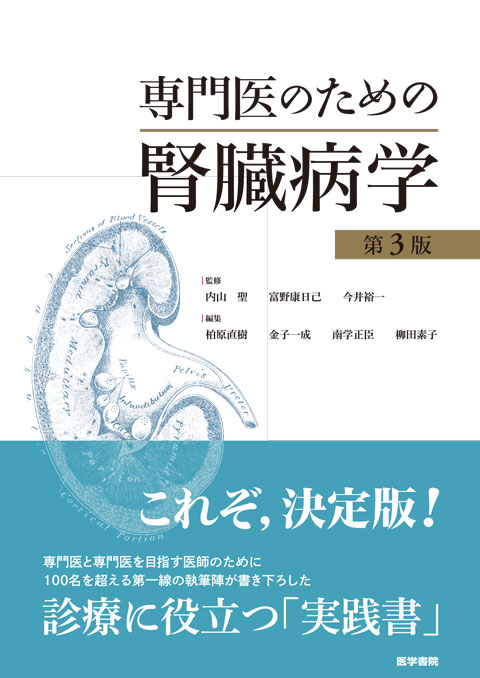MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2023.09.18 週刊医学界新聞(通常号):第3533号より
《評者》 山口 智志 千葉大大学院国際学術研究院准教授/千葉大大学院整形外科学
この本は今すぐ買うべし! その理由は?
一読した感想は,「今すぐ買うべし!」である。本書は,待望の足部・足関節骨折の手術治療に特化したテキストである。これから骨折治療を学ぶ後期研修医から指導医,足の外科の診療,研究に携わるエキスパートなど,経験によらずあらゆる整形外科医,外傷医にとって必携の書と断言できる。
足部・足関節骨折の手術は専門性が高く,治療法を学ぶ上でいくつかの問題がある。まず,足部・足関節は多くの関節から成る複合体である。例えば,足関節骨折とリスフラン関節骨折ではまったく異なる評価,治療戦略が必要である。しかし,ベテランの医師であっても全ての部位の骨折治療を経験することは容易ではない。経験がない骨折では,アプローチすらわからないことも少なくない。加えて,足部・足関節骨折の手術は決して簡単ではない。足関節果部骨折は,骨折手術の入門編として後期研修医が執刀することも多い。しかし,十分な整復が得られず短期間で変形性関節症に至る症例も少なからず存在する。
本書を手元に置いておくことで,われわれが臨床で抱えるこれらの問題は解決される。本書は,脛骨遠位部から趾骨骨折まで,比較的まれな骨折を含めて全範囲の骨折を網羅している。どのような骨折に遭遇したときも,必ず治療のヒントになる情報を提供してくれる。また,膨大な症例とイラスト,X線画像,手術写真を用いて術前計画から手術手技,術後管理まで一貫した形式で論じている。必要なときに素早く情報にアクセスすることができ,かつ理論と実践のギャップを埋める実用的なガイドとして非常に有用である。さらに本書は,現時点での治療のスタンダード,すなわち最良の治療を網羅している。例えば,踵骨骨折では拡大L字切開から足根洞アプローチ,経皮手術まで多様な術式を網羅しているため,足部・足関節を専門に治療する評者にとっても多くの学びがある。
術中に陥りやすいピットフォールとその回避方法,代替テクニックを詳細に解説しているのも,本書の特徴である。例えば,見落としがちな骨折面に嵌入した小骨片の対処法,整復困難例での次の一手などを具体的,明快に提示している。術後レントゲン写真を見て,「こうすれば良かった……」と後悔し,眠れぬ夜を過ごすことは誰しも経験することである。本書を熟読することにより,偉大な先人の経験を自分のものとして手術に臨むことができる。
本書は,足部・足関節骨折管理の技術をまったく新しいレベルに引き上げてくれる。患者を助けるとともに,日々の治療に悩む医師の安眠を助ける名著である。評者も,整形外科医としてのキャリアの中で,今後も何十,何百回と本書を開くであろう。
《評者》 松尾 清一 国立大学法人東海国立大学機構機構長
研究に裏打ちされた腎臓病診療のいまがわかる実践書。
現代日本においては少子高齢化がますます進み,2021年の段階で65歳以上人口が28.9%という超々高齢社会(評者の造語。ちなみに7%以上は高齢化社会,14%以上は高齢社会,21%以上は超高齢社会と定義されている)になっており,今後も一層高齢化が進むと予測されている。寿命の延長は世界的に進んでおり,人生百年時代の提唱者で,『ライフシフト――100年時代の人生戦略』(東洋経済新報社,2016年)の著者リンダ・グラットンさんらによると,若い世代ほど寿命は長く,2007年に日本で生まれた子供の半分は107歳まで生き,先進国では軒並み100歳を超えると予測されている。つまり,現代では人の寿命は100年が当たり前の時代になっている。
私たちが100年間,生命を保つだけでなく,人として社会とかかわりながら生きてゆくためにはあらゆる臓器がお互いに連関しながら,しっかりとその機能を保つことが重要であり,言うまでもなく,腎臓はその要となる臓器の一つである。また,腎臓は万一その機能を失ったときでもそれを代替する治療法が発達し,日常生活を継続できる数少ない臓器でもある。このような進歩は,極めて多くの研究者による病態の解明とそれに基づく治療への応用という気の遠くなるような努力の積み重ねがあってのことである。このような努力は今も日々続けられており,それらの新たな知見は順次,実臨床の場で応用されている。
本書はタイトルにあるとおり,腎臓専門医のために書かれたテキストブックであるとともに,実践に役立つ書となるよう編さんされている。これまで2002年に初版,2009年に第2版が発行されており,多くの腎臓専門医に活用されてきた定番の書でもある。しかし第2版発行から14年が経過し,この間,サイエンスの進歩は目覚ましく,腎臓病の研究は大きく進展し,臨床もその恩恵を受けている。このような中で待望されていた第3版は,これまでの長所は残しながらも,最先端の知...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

![AO法骨折治療 Foot and Ankle [英語版Web付録付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/5616/8248/3611/110660.jpg)