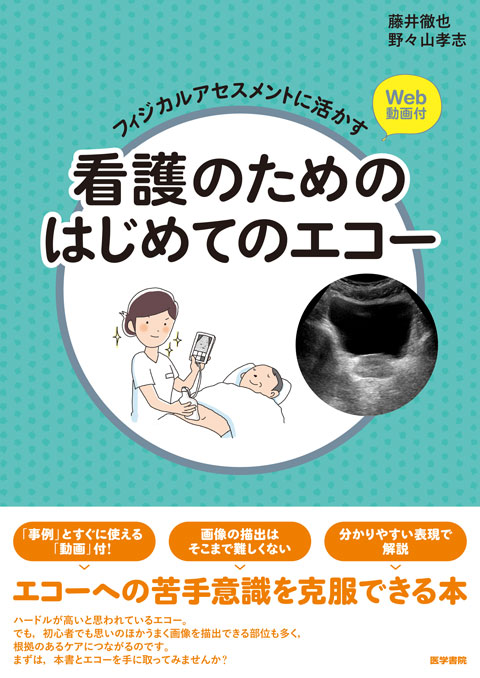排便トラブルの“なぜ!?”がわかる
[第2回] 救急外来でこんな相談を受けたら
連載 三原弘
2023.07.31 週刊医学界新聞(看護号):第3527号より
排便トラブルの判断で急を要するのは,電話対応や救急受診の可否,排便処置ではないでしょうか。排便トラブルに潜む病気を医師と力を合わせて拾い上げ,患者さんに安心してもらいたいところです。今回は,救急外来における排便トラブルにまつわる相談を中心に知識を整理しました。しばしば経験するシーンを1つずつ見ていきましょう。
〇×クイズ
本文を読む前の理解度チェック!
①排便困難感,残便感は改善しやすい
②急性に比べて慢性の便秘症状のほうが危険である
③救急に定期的に浣腸しに来る患者さんは常に希望通り対応すべきである
便秘で受診したい
昔から便秘で悩んでいます
患者さんから便秘の訴えがあった場合は「いつからか」と質問し,危険性の高い急性と比較的低い慢性に分けます。その上で下記のいずれのタイプかを確認しましょう。便形状については第1回(本紙3523号)で紹介したブリストル便形状スケールで表現すると関係者間でのやり取りがスムーズです。
・糞便の移動が遅いタイプ
質問例:週に3回未満か? 糞便が硬いか?
・排便が困難なタイプ
質問例:強くいきむ必要がある? 排便を困難と感じるか? 残便感は?
・便秘型過敏性腸症候群に近いタイプ
質問例:腹痛があるか? 腹部不快感はあるか?
慢性の便秘に昔から悩んでいるとの訴えがあれば,下記の通り場合分けして対応に当たるとよいでしょう。
①慢性のタイプ
排便習慣の急激な変化,予期せぬ体重減少,血便,腹部腫瘤,腹部波動(腹水),発熱ならびに関節痛などの警告症状と,50歳以上での発症および大腸器質的疾患の既往歴・家族歴等の危険因子を聴取します。全てない場合は,緊急性は乏しいと判断されます。
②糞便の移動が遅いタイプ
ほうれん草,ブロッコリーといった不溶性食物繊維(連載第5回で詳述予定)の摂取が少ない場合は摂取を勧めます。十分摂取している場合は市販の緩下剤の内服を勧めた上で,効果が乏しい場合には外来受診を勧めましょう。
③排便が困難なタイプ
難治性であることが多く,苦労を労うと共に,便秘を専門にする医師につなぐようお願いします(○×クイズ①)。
④便秘型過敏性腸症候群に近いタイプ
食事指導(連載第5回で詳述予定)を行います。効果的な薬剤もありますので,食事指導で改善を認めなければ,外来受診を勧めてください。
なお,妊娠中はプロゲステロンと消化管の圧迫により便秘や逆流性食道炎になりやすいとされます。また妊娠30週以降は体内への水分の吸収が増えることもあり,便秘や痔核が悪化しやすいです。妊婦から便秘の相談があれば,これらを説明した上で,体を冷やさず,適度な運動・リラックス,排便リズム,規則正しい食事と水分摂取を勧め,硬便にはマグネシウム剤が第一選択であることを情報提供しましょう。
急に便が出なくなった
急性の場合,嘔気・嘔吐,排ガスの消失,腹痛,発熱などがあれば器質性の便秘,特に大腸癌や腸閉塞による便秘が疑われるため受診が勧められます(○×クイズ②)。とりわけ血便や便が細いという症状を訴えて...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。