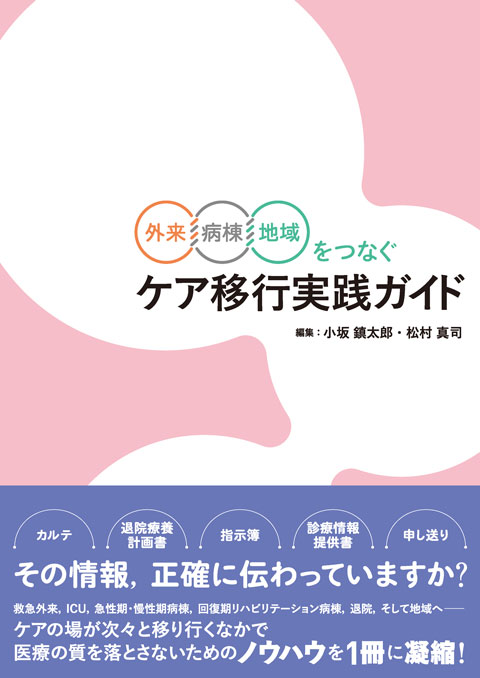レジデントのための心不全マネジメント
[第11回] 心不全緩和ケアを考える
連載 河野隆志
2023.05.15 週刊医学界新聞(レジデント号):第3517号より
“緩和ケア”という言葉に,どのようなイメージを皆さんはお持ちですか? がんを対象として発展してきたので,“心不全の緩和ケア”と聞いてもピンとこない方がまだいるかもしれません。実は,緩和ケアは心不全診療ガイドラインでclass Iとして推奨され1),一定の条件を満たす末期心不全では診療加算の算定が可能です。心不全マネジメントにおける緩和ケアは,通常診療からの撤退でもなければ,看取るためだけのものでもありません。緩和ケアは,患者さんの苦痛を和らげQOLの改善をめざす前向きなアプローチであり,心不全の通常診療・ケアと統合しながら提供されるべきものとされています。多岐にわたる心不全マネジメントを紹介してきた本連載ですが,最終回は緩和ケアを取り上げます。
いつ,誰が行う?
現場でしばしば遭遇するのが緩和ケアのタイミングに関する問題です。「緩和ケアチームに依頼しては?」「まだ緩和ケアを導入するタイミングではない」と議論になります。心不全は,長期にわたって入退院を繰り返しながら最期は比較的急速に増悪することが多く2),終末期の判断が難しいことが,この議論の根底にあります。一方で,心不全患者の身体的・精神的な苦痛症状,社会的問題,スピリチュアルな側面の問題は,終末期に限定して生じるわけではありません。そのため積極的な心不全治療と同時に緩和ケアを提供し,病状の進行に伴って緩和ケアの比重を増やしていくマインドスイッチが必要です(図1)3)。

ところで,心不全緩和ケアは誰が実践するのでしょう。実は,緩和ケアを専門としない医療者の役割がとても重要で,このかかわり方は基本的緩和ケアと呼ばれています。他方,非専門家には難しい症状管理や意思決定支援の問題など,複雑な問題に対処する必要がある段階では,緩和ケア専門家に主導していただく専門的緩和ケアが必要になります4)。ここでは,基本的緩和ケアの重要な構成要素であるアドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning:ACP)と基本的な症状緩和の方法を紹介します5)。
双方向性のコミュニケーションをバランス良く行う
ACPは“患者が自分で意思決定ができなくなった場合の将来的な医療について,医療・ケアチームと患者,家族または代理意思決定者間で継続的に話し合う,患者およびケア提供者との間で行われる自発的なプロセス”とされています6)。より良いエンドオブライフに関する意思決定を支援し,患者さんの意向が尊重されたケアの実践を促します。重要なことは,医療者からの情報提供と患者さんの希望・価値観の表出がバランス良く行われ,双方向性のコミュニケーションとなることです(図2)7)。心不全の予後推定が難しいことも伝えながら,患者さんが情報をどう知りたいかも確認した上で対話を進めます。患者さんの価値観や目標を共有し,急変時の蘇生処置や機械的サポートに対する希望,今後の療養先について話し合います。「人工呼吸器を使用するか?」「DNARをどうするか?」「どこで最期を過ごしたいか?」の結論を出すことに...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。