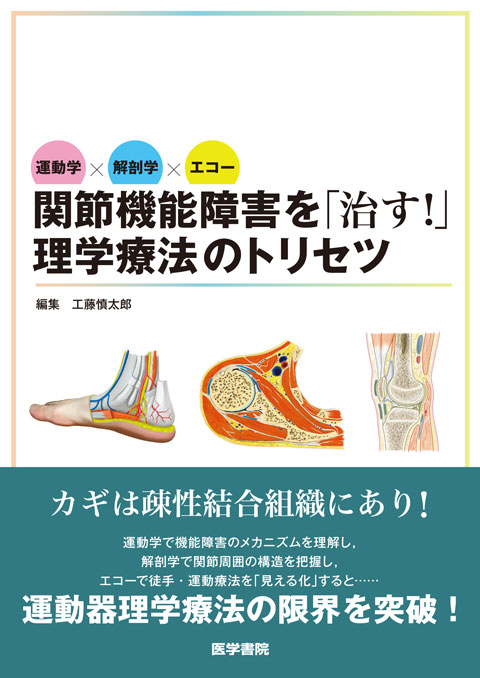MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2023.05.08 週刊医学界新聞(通常号):第3516号より
-
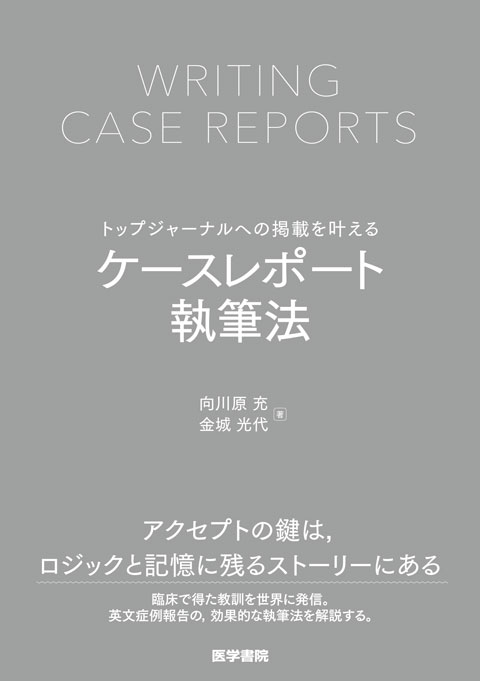
トップジャーナルへの掲載を叶える
ケースレポート執筆法- 向川原 充,金城 光代 著
-
A5・頁216
定価:3,520円(本体3,200円+税10%) 医学書院
ISBN978-4-260-05018-0
《評者》 皿谷 健 杏林大准教授・呼吸器内科学
症例報告の執筆が臨床能力をさらに高める
向川原充,金城光代両先生の執筆による本書は,タイトルの通りトップジャーナルへの掲載を叶えるケースレポート執筆法を述べた書籍である。究極的には「論文を書くこと」を通じて「臨床能力をさらに高めるための本」だと言える。向川原先生が研修を受け,金城先生は現在も診療を行う沖縄県立中部病院には,今に語り継がれる数々のクリニカル・パール(教訓)がある。その多くはcommon diseaseのuncommon presentationを一症例ずつ大切に語り継ぐ土壌があって残るのだろう。本書でも,教訓をストーリーに即して提示する意義が強調されているのは,同院のそうした風土を基に執筆されているからではないか。大学院で「英文でのCase reportの書き方――How much is enough?」と題した講義を毎年行っている評者も,本書の随所に感じられる両先生の症例報告執筆に対する信念に深い共感を持った。
そもそも臨床医が症例報告を書きたい,形に残したいと思うのはなぜか。その理由は,圧倒的な熱量を注いで診療した患者には,患者自身あるいは患者―医師間のストーリーがあり,それを残したいと思うからだ。臨床経過上の困難を教訓として残し,次にその症例に出合った時に遅滞なく解決するためでもある。ストーリーに臨場感のある症例報告は,他施設で同様の困難に直面している医師のプラクティスを変えることに必ずや貢献するだろう。
本書は,症例報告の執筆に適した状況として,①最終診断がすぐに想起できないこと,②主たる学び(教訓)の活用によって確定診断できること,③稀少すぎず,ありきたりすぎないこと――の3点を挙げている。その上で論文の執筆,掲載,症例の共有,自らの学びの深化を経て,「読者の考え方を変え,臨床の質の向上に貢献すること」を症例報告執筆の真の目的と位置付けている。
英語ができなければ英文症例報告は投稿できないかというと,必ずしもそうではない。大切なのは,ストーリーとロジックである。これは評者の大学に交換留学で短期間来日した米国のチーフレジデントと行った論文作成のやりとりでも感じた。そのチーフレジデントは,症例報告におけるdiscussionにロジックが欠如していたのだ。本書で述べられているように,時系列で得られた情報から論理的な思考(ロジック)をどう展開し,症例の診断に迫っていくのか? そのエッセンスは何なのか? を読者にわかる形で分解し提示するスキルが執筆には欠かせない。
本書で紹介するdiscussion作成のポイントは,①症例の特殊性・新規性:過去の報告との関連性,②症例から得られる仮説(病態生理や鑑別疾患),③症例から導き出せる教訓(推測できること),④Take home message/Teaching pointを各パーツで述べることである。加えて段落構成の原則であるtopic sentenceとsupporting sentenceの書き方も指南している。特に①では,最初の段落内に症例で際立つ特徴やユニークな点についてのみ簡単に述べる「症例のハイライト」や,症例の新規性・稀少性とtake home messageを要約したポイントにfocusを絞る重要性が指摘されている。本書で解説される症例報告を作成するためのロジックは,original articleの執筆にも通用する重要なエッセンスの一つである。
症例報告は,疾患・病態生理の新たな解釈や発見のヒントを与えてくれる。
《評者》 江玉 睦明 新潟医療福祉大教授・理学療法学
運動器理学療法のブレークスルーとなる一冊
本書は,新型コロナウイルス感染症により全人類の日常が大きく変化する中,その状況に動じることなく運動器理学療法の根幹である関節機能障害を「治す」ことに焦点を当てた一冊である。
本書を熟読してまず感じたのは,この書籍は「トリセツ」であり,いわゆる「マニュアル(ハウツー)」ではないということである。ちまたに「ハウツー本」が多く存在するなか,運動学×解剖学×エコーのいわばマリアージュのような組み合わせで,関節機能障害を「トリセツ」に基づいて丁寧にひもといており,執筆陣の理学療法に対する信念をも感じることができる。理学療法士のみならず,整形外科疾患の治療とリハビリテーションにかかわる全ての医療職の方々に有益な書籍であると言える。
本書は2部構成であり,第1部は「運動器の機能障害と構造破綻を理解する」というテーマである。ここでは,「トリセツ」における概要部分が...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。