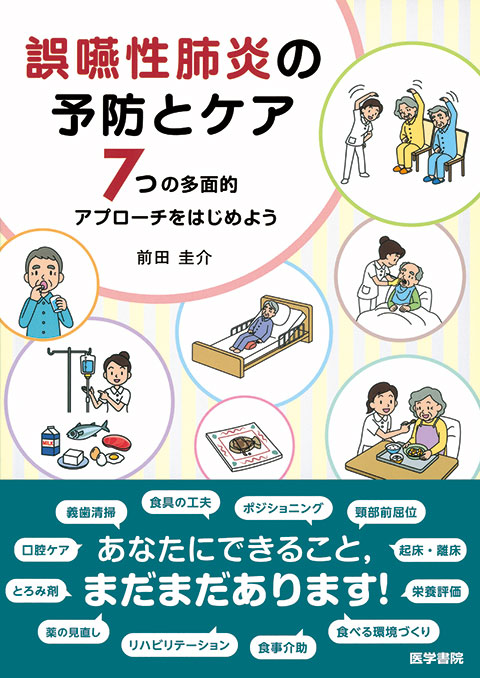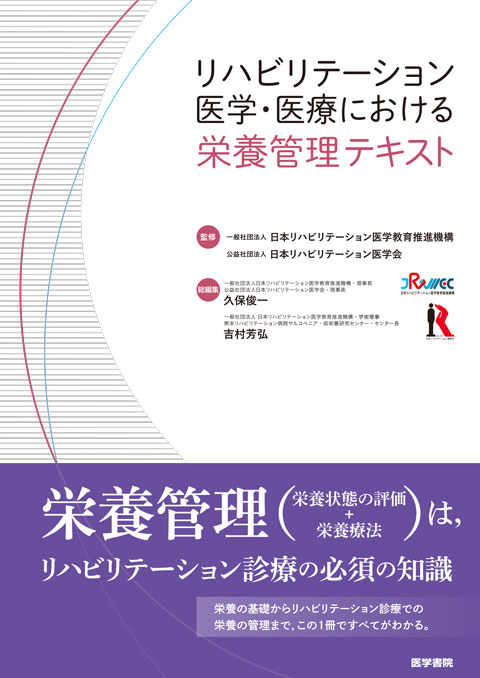多職種で支える誤嚥性肺炎のリハビリテーション
[第8回] 薬剤管理
連載 小瀬英司
2022.11.21 週刊医学界新聞(通常号):第3494号より
こんな患者さん見たことありませんか?
大腿骨近位部骨折のために入院してきた患者。入院時から臥床しており,入院前にはみられなかった食事時のムセが認められるようになった。服用薬剤を調べるとポリファーマシー状態であり,睡眠薬や抗精神病薬などを服用していた。嚥下内視鏡を行ったところ咽頭収縮力が弱く,液体の誤嚥を認め,誤嚥性肺炎と診断された。
ポリファーマシーは,現在も明確な定義は設定されておらず,研究においてもそれぞれ異なる設定をされているのが現状です。死亡率,緊急入院,転倒,認知機能,身体機能やフレイルなどの臨床アウトカムとの関連性が報告されており1),嚥下障害とも関連することが知られています2)。
薬剤の種類に明確なカットオフはありませんが,一般的な目安として5~6種類以上の薬剤の併用が挙げられます1)。一方で,患者の疾患によっては適切な処方であっても5~6種類以上の処方の併用が必要なこともあるために,単純に処方数で判断できるものではなく,潜在的に不適切な薬剤(Potentially Inappropriate Medications:PIMs)が含まれていないかの評価が必要となってきます。
厚生労働省が公表する「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」3)においてポリファーマシーは,ただ単に服用する薬剤数が多い状態を示すのではなく,それに関連した薬物有害事象のリスクの増加や,服薬アドヒアランスの低下,服薬の間違いなどの問題につながる状態であるとされています。つまり,そのような問題につながる処方を減らすことが重要であり,単に処方数を減らすことが目的とならないように注意が必要です。
本当にその薬剤は必要ですか?
◆高齢者は多疾患併存状態
複数の併存疾患に対して診療ガイドライン通りの診療を適用すると,必然的に薬剤数が増加します。各々の診療ガイドラインは基本的に疾患併存を想定せずに作成されているため,全身の生理機能が低下し,多剤併用となっている高齢者では,想定されていないような有害事象が発現することもあります。多疾患併存(multimorbidity)状態の患者には特に注意をしましょう。
◆処方カスケード
処方カスケードとは,薬剤による副作用に対して薬剤で対応することで,さらに処方が増加する現象のことを指します。例えば,高血圧に対してアンジオテンシン変換酵素阻害薬が投与されたとします。薬剤の副作用である空咳に対してリン酸...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。