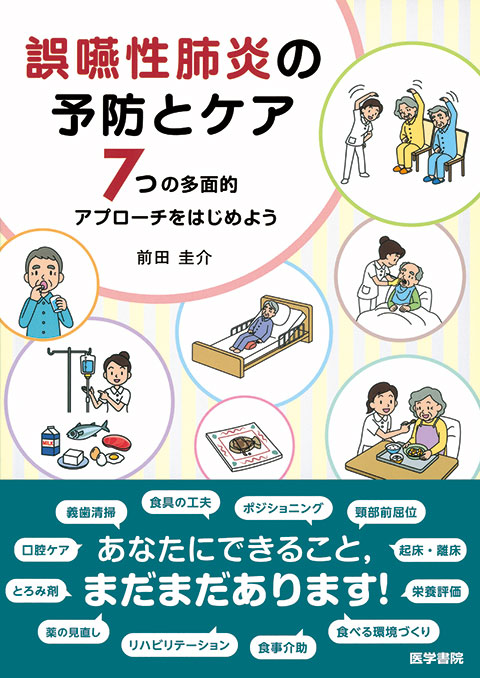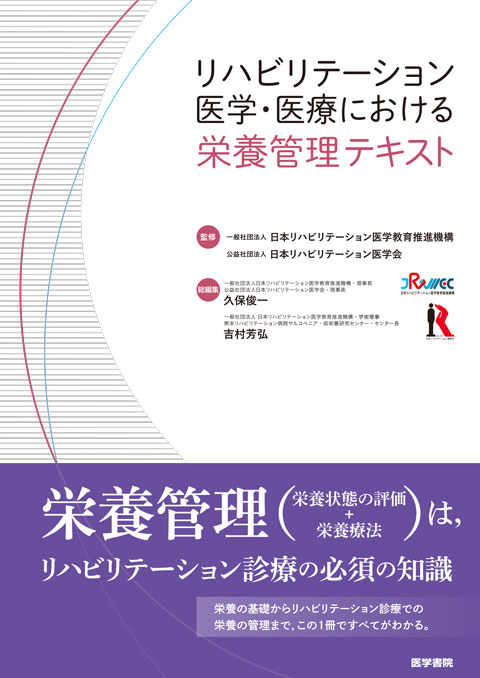多職種で支える誤嚥性肺炎のリハビリテーション
[第7回] 栄養管理
連載 白井祐佳
2022.10.24 週刊医学界新聞(通常号):第3490号より
こんな患者さん見たことありませんか?
77歳男性。食道癌術後,繰り返す誤嚥性肺炎のため緊急入院。入院後は絶食,輸液管理となり,1週間以上電解質輸液のみだった。入院時BMI 15.2 kg/m2と,もともと低体重であったが,3週間でBMI 14.3 kg/m2まで低下した。歩行困難となり活動性も低下,患者さんからも体力低下の訴えがあった。
誤嚥性肺炎は食欲不振を惹起し,低栄養状態になりやすい疾患の1つです。また,低栄養による骨格筋量の減少は嚥下障害を招くため1),低栄養と嚥下障害は密接に関連していると言えます。不適切な栄養管理は,栄養状態の低下を招き,臨床転帰に悪影響を及ぼします。治療効果を最大限発揮するには,多職種で協働し,患者の状況に合わせた多角的な栄養管理を行うことが必要です。そこで今回は,誤嚥性肺炎患者に対する栄養管理をご紹介します。
適切な栄養管理の必要性とは
誤嚥性肺炎患者の中には,誤嚥が懸念されるため一時的に絶飲食になる患者がいます。日本の65歳以上の誤嚥性肺炎で絶飲食となっている患者の栄養管理の状態を調査した研究によれば,入院7日目にエネルギー量20 kcal/kg以上の患者が5.3%,アミノ酸1.0 g/kg以上の患者が6.4%,脂肪エネルギー比率15%以上の患者が5.7%と,それぞれの目標栄養量に達していた患者は非常に少ないことが明らかになっています2)。その一方で,入院早期および絶飲食中から十分なエネルギー量とアミノ酸量を投与することは,誤嚥性肺炎患者の良好な転帰と関連することが報告されており3, 4),適切な栄養管理は誤嚥性肺炎からの回復,再発防止,予後の改善に大変重要と言えるでしょう。
GLIM criteriaを用いたアセスメント
『静脈経腸栄養ガイドライン』では,全ての患者に対して栄養スクリーニングを実施し,栄養学的リスクの高い患者に疾患や病態に応じた指標を用いて定期的に栄養アセスメントを行うことを推奨しています5)。しかしながら,誤嚥性肺炎患者に特化した栄養アセスメント指標は示されていません。
さて,臨床現場において,アルブミン値などの血清内蔵蛋白レベルを栄養アセスメント指標として活用する場面にしばしば遭遇します。一方で米国静脈経腸栄養学会によるposition paper6)では,血清内蔵蛋白レベルは栄養状態を示すものではなく炎症を特徴づけるものであり,栄養マーカーとして用いるべきではないとしています。嚥下障害による誤嚥性肺炎は急性炎症を伴う場合があり,低栄養リスクを評価するために炎症の程度を考慮することは重要です。しかし,血清内蔵蛋白レベルのみで栄養状態を評価することは誤った栄養アセスメントにつながる可能性があるため,留意が必要です。
では一体,どのような指標を栄養アセスメントに用いればよいのでしょうか。摂食嚥下障害患者を対象としたスコーピングレビューによれば,栄養スクリーニング指標であるMNA-SF,身体計測値,BIA法で測定した体組成,食形態,絶飲食期間,食事摂取量の食事評価等が,栄養アセスメント指標として抽出されました7)。これらの指標が複数含まれている栄養診断ツールとして,GLIM(Global Leadership Initiative on Malnutrition)criteria8)があります(図1,2)。同ツールは,民族または人種による違いを考慮しており,世界共通の栄養不良の診断基準として使用されています。日本の高齢肺炎患者を対象とした報告9)によれば,BMIのアジア人のカットオフ値(表)が30日院内死亡率等の独立した予後予測因子であったことから,G...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。