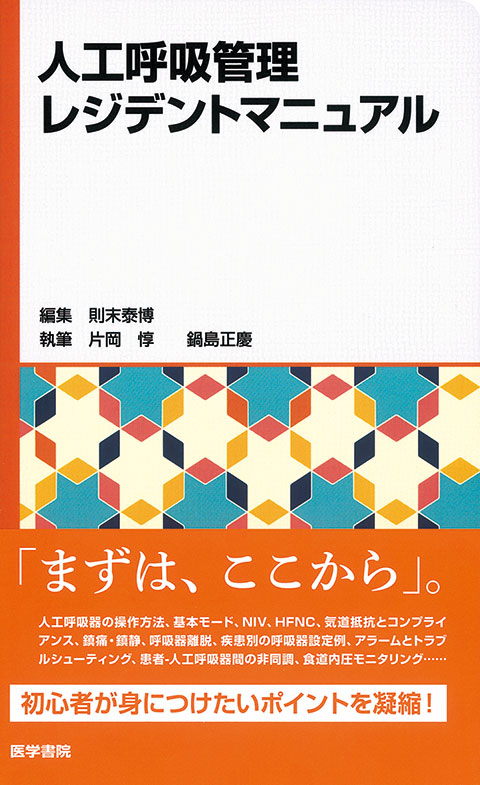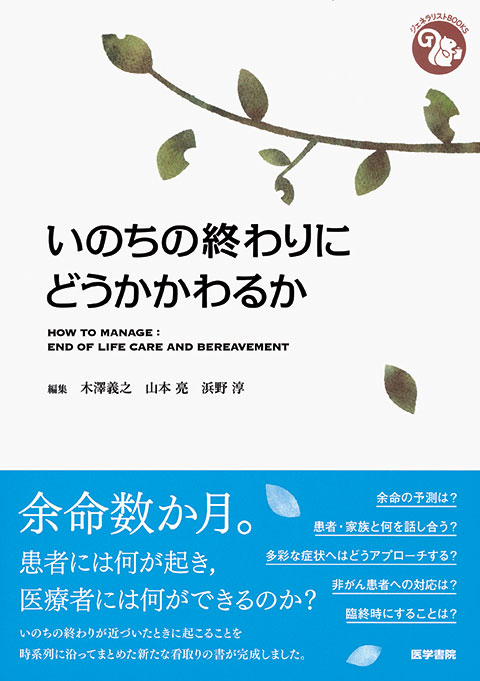救急・集中治療×緩和ケア
対談・座談会 木澤 義之(司会),伊藤 香,則末 泰博
2021.03.15 週刊医学界新聞(通常号):第3412号より

救急・集中治療の現場では,限られた時間・情報の中で治療方針を瞬時に決断し対応することが特に求められる。その際,救命を第一義とする積極的な治療だけでなく,緩和ケアを医学的にも倫理的にも検討しなければならない時もあるだろう。そしてその場面は高齢化とともに増加している。本紙では,「救急・集中治療領域こそ緩和ケアが最も求められる領域」と訴える緩和ケア医の木澤氏を司会に,米国での経験を糧に実践に励む伊藤氏,則末氏との座談会を企画。救急・集中治療領域における緩和ケアの現状と課題を議論した。
木澤 本座談会のテーマを見た読者の中には「なぜ救急・集中治療に緩和ケア?」と思われる方がいるかもしれません。これは恐らく「緩和ケアとはがんを中心とした,比較的進行が緩徐な疾患に対して提供されるもの」という考えがあるからでしょう。しかし私個人としては,救急・集中治療領域こそ緩和ケアが最も求められる領域だと考えています。今回は,そんな緩和ケアに対する固定観念を解きほぐしつつ,救急・集中治療領域における緩和ケアの実践に取り組む伊藤先生,則末先生と共に,情報発信をできればと思います。
本当に患者の望む医療を提供できているのだろうか
木澤 約20年前の話です。私はもともと緩和ケアをサブスペシャリティとする総合診療医でした。当時,北米型ERの救急総合診療部を立ち上げることとなり,救急と緩和ケアの二足のわらじを履くことになったのです。いざERでの診療が始まると,奇跡的に命を取り留める方がいる一方,懸命な治療の甲斐なく亡くなる方もたくさんいらっしゃいました。後者の場合,救命不可能と判断された時点でできる限りの苦痛の緩和を望むのが患者や家族の現実であり,患者や家族が望む最期を提供するためには緩和ケアのスキルが大いに役立つことに気が付いたのです。その後,縁あって緩和ケアの研究,実践に励む道を歩むことになりましたが,そうしたきっかけがなければ今も救急総合診療医として働いていたと思います。
お二人は米国での臨床留学時代の経験が現在の実践につながっているそうですね。帰国後に日本の救急・集中治療の現場で抱いた驚きや違和感などがあれば教えていただけますか。
伊藤 米国における緩和ケアは,疾患にかかわらず誰にでも適用されるのが原則であり,たとえ救急・集中治療の現場であっても「これ以上侵襲的なことをしてほしくない」という患者からの希望があれば,緩和ケア科に転科するのはごく自然の光景でした。しかし2016年に当センターのスタッフとして着任した際,救急科への緩和ケア科の介入がほとんどないことや,超高齢社会であるために搬送されてくる患者さんの多くが人生の最終段階に足を踏み入れていること,そしてその患者さんのほとんどが事前指示書を持ち合わせていないことに驚きを隠せませんでした。
木澤 米国と比較すると,まだまだ事前指示書を準備している方は少ないですよね。
伊藤 ええ。厚労省の調査によれば,人生の最終段階における医療について「詳しく話し合っている」と回答したのはわずか2.7%です1)。一方の米国は,あるシステマティックレビューによれば,約80万人の対象者のうち事前指示書を所持していたのは36.7%と報告2)されており,高齢になるほどその率は高まっています。
則末 帰国後に私が驚いたのは極めて強いパターナリズムです。救命できる可能性があるならば,患者の意思とは関係なく限界まで治療するのが当たり前の世界。患者がどれだけつらい思いをしていようが,その後にどんなQOLが待ち構えていようが,「命が助かるならどんなつらい治療でも我慢するのは当然ですよね」と,選択肢を与えない環境に多くの医療者が疑問すら感じていないように見えました。必ずしも患者の意思を優先できていない日本の医療現場に疑問を抱きましたね。
緩和ケアの導入≠治療の断念
木澤 伊藤先生,則末先生のように現在の救急・集中治療体制に疑問を抱く方がいる中で,いまだこの領域では緩和ケアが普及しているとは言いづらい状況です。これはなぜなのでしょうか。1つは則末先生が挙げられたパターナリズムの問題があると思います。理由を詳しく聞かせてください。
則末 複数の要因があると思いますが,最大の理由は,患者中心の医療ではなく医療者側が後で責められないことが優先され,「死なないこと」が治療成績として評価されるからでしょうか。厳しい言い方ですが,われわれ救急・集中治療医は「救命のために全力を尽くしています」と言ってしまえば,基本的に患者や家族から咎められることがなく,手の施しようがなくなれば「厳しい状態です」と単純なコミュニケーションのみで済んでしまうのです。
木澤 病院の中でも生と死が最も身近にあると言っても過言ではない救急・集中治療の現場では,ある意味パターナリズム的な考えを持っていないと医療者としての葛藤の中でサバイブできない面もあるように思います。
則末 そのような面もあるかもしれません。ですが私は教育の問題が大きいと思っています。救急・集中治療医にとって,治療のゴール設定や家族のグリーフケア等のコミュニケーションはエクストラワークと言わざるを得ません。しかし,このひと手間こそ救急・集中治療医にとって必要なスキルであり,学ぶべきことだと思うのです。
伊藤 同感です。米国ではこのスキルがとても重要視されており,臨床留学時代にフェローシップとして勤務していた施設では,Vital Talkを集中治療室用に特化したIntensive Talkの受講が必須となっていました。具体的には集中治療室で重症になった患者とのgoals of care discussionやend of life care discussionに関するフレームワークを学ぶことになります。
木澤 留学前からコミュニケーションの意義を認識していましたか。
伊藤 恥ずかしながら,当時は救命を目的とする集中治療の分野において,なぜコミュニケーション・トレーニングを受けさせられているのか疑問でした。しかし,死と隣り合わせの患者の対応を数多く経験する中でその重要性を痛感したのです。それまでは一種の職人芸と考え苦手としていたコミュニケーションでしたが,フレームワークを学べたことで臆せず取り組めるようになりました。
則末 系統立ったコミュニケーション・トレーニングは重要ですよね。
加えて緩和ケアが適用されるべき患者や,導入のタイミングに関する教育がなされていないことも課題と言えます。
伊藤 そうですね。木澤先生が指摘されていた通り,緩和ケアを比較的進行の緩徐な疾患に対して提供されるものと認識している方はいまだに少なくありません。私自身もそう考えていました。
木澤 何かターニングポイントがあったのでしょうか。
伊藤 渡米したばかりの頃,ある多発外傷の患者を担当した時のことです。なりふり構わずさまざまな治療を行い,救命できるかもしれないと微かな希望が見えた時でした。回診時に突然緩和ケア医が現れたのです。「救命できる可能性もあるのにここで緩和ケア!?」と私は驚いてしまいました。その反応を見逃さなかった指導医はすかさず「緩和ケアは誰にでも適用がある。別にそれは治療を断念することではない」と教えてくれました。
木澤 集中治療室でon goingの治療をしていても,治療の先につらい日々が待っている場合には緩和ケアが早い段階から導入されていたのですね。患者の望みをかなえるため,さらにはQOLを高めるために適時連携が取れているのは素晴らしいの一言です。
ですが現在の日本では救急・集中治療医側,緩和ケア医側双方にまだまだバリアがある印象です。緩和ケア医側で言えば,経験値の少ない急性期の現場では尻込みをしてしまう場合もあるのではと思います。こればかりは緩和ケア医側に一歩を踏み出す勇気が必要と言えますが,救急・集中治療医側からも後押しをいただけるとうれしいですね。
終末期の定義に対する誤解
伊藤 いま木澤先生が触れた緩和ケアの担い手に関する議論は必要でしょう。救急・集中治療領域で活躍する緩和ケア医の人数はごく少数です。この領域にまだ足を踏み入れていない緩和ケア医に啓発活動を継続的に行っていくことも重要だと考える一方,緩和ケア医に比べ人数の多い救急・集中治療医が緩和ケアを学んでいくことが現実的ではないでしょうか。
木澤 日常診療を行いながら緩和ケアの知識も押さえるとなれば,ややハードルが高いようにも思います。育成の手立てはどうお考えですか。
伊藤 何も緩和ケアの専門家になる必要はありません。状況に応じてコンサルテーションを行える素養を持ったprimary palliative careを提供できればよいと考えています。そのためにはまず,救急・集中治療医が提示する治療の選択肢の中に緩和ケアを追加することが求められるでしょう。特に超高齢社会に突入した近年は,明らかに人生の最終段階を迎えた方が救急車で連日搬送されてきます。搬送時に患者や家族に話を聞いてみると,必ずしも積極的な治療を望む方ばかりではないことに気が付くのです。そんな時に緩和ケアを考慮に入れた治療を提案できることが重要と言えます。
木澤 確かに救急・集中治療の現場でこそgoals of care discussionをしなければならないでしょうね。選択の余地なく「救命救急センターに運び込まれたんだから,気管挿管するに決まっている」となるのは医師の思い上がりかもしれません。
則末 同感です。しかし,その際に押さえなければならないのは「終末期」という状態に関する適切な理解です。
木澤 終末期の定義に対する誤解があると?
則末 ええ。救急・集中治療にかかわる多くの医療者にとって終末期とは,「何をやっても助からない」場合のみを指す言葉として認識されている印象です。けれども患者の置かれる状況や価値観によってその定義は変わり得るものであり,患者の視点も考慮する必要があります。いわゆる慢性期疾患の患者も最終的には「急性期」を経て亡くなるために,亡くなる過程で集中治療室にたまたま運ばれたから終末期の定義が変わるというのはおかしな話です。
木澤 なるほど。ただ先ほど話があったように,救命を第一に教育されてきた救急・集中治療医の誤解を解くことはたやすくないのでは?
則末 終末期を説明するとき,私は以下の3つの無益性を勘案して判断すべきだと伝えています。どれか1つでも当てはまれば終末期です。
①生理学的無益性
現在行われている治療が,そもそも医学的に意味がない状態
②量的無益性
救命できる可能性がたとえ10%あったとしても,その10%のために治療の負担を患者が許容できない状態
③質的無益性
救命された結果,患者が受け入れられるQOLが望めない状態
①については医師だけで決定できますが,②③は患者や家族と慎重かつ継続的に話し合って決める必要があるのです。ただし,この決断を下すためには十分な情報が不可欠であり,必要な情報がそろうまでの間,救命に全力を尽くすことは論をまちません。
個人に依存しないwithdraw/withholdの決断
伊藤 さらに付け加えるとすれば,日本の救急・集中治療が見直すべきは治療中止(withdraw)や治療の差し控え(withhold)に対する認識です。「一度開始した治療から途中で撤退する」という一見当たり前の選択肢が認識されておらず,withdrawやwithholdの選択が許されない空気が漂っていることは問題と言えます。こうした選択が許されない場合,予後が不透明な時に取り組まれるべきtime limited trial(註)が行いづらくなるのは言うまでもありません。必要に応じてwithdrawやwithholdを決断できる環境の構築は,患者・家族はもとより,患者さんが望んでいないかもしれない延命の継続に加担せざるを得ない医療者の倫理的苦悩を軽減させる術でしょう。
木澤 則末先生の施設では,withdrawやwithholdに関するマニュアルが整備されていますよね。全国的に見ても画期的な取り組みだと思われます。なぜ策定に至ったのでしょう。
則末 伊藤先生が指摘されたように,withdrawやwithholdは人命を大きく左右する決定であることから,医療者に多大な倫理的苦悩をもたらします。それゆえ決して個人の判断で実行されるべきではなく,組織全体でコンセンサスを図ったプロセスに則り決断されるべきです。当院では,院内の倫理委員会での複数回にわたるマニュアル作成のための議論を経て,いかなる延命治療であっても,多職種カンファレンス,患者または家族との話し合い,適切な緩和治療の導入等のしかるべきプロセスを踏めば,現場の判断で中止可能と明文化しました。患者を中心に考えて現場が決定したことについては病院が責任を持つという姿勢です。
伊藤 当院にも生命維持装置の中止に関するプロトコールがあります。内容に関しては米国と比較するとまだまだ課題は山積みですが,それでも個人の決定に依存しない指標は患者,医療者双方にとって有用だと実感しています。
則末先生の施設では治療方針が緩和ケア優先になった場合のマニュアルも用意されているんですよね。
則末 はい。本マニュアルの軸になるのは,緩和に役立たない治療を中止する目的で行われる抜管の方法と,その後のケアの標準化です。医療用麻薬の適切な投与や,グリーフケアを含めた家族へのかかわり方を重視しています。
木澤 なぜ家族へのかかわりが重要になるのでしょう。
則末 抜管後の患者に現れる死戦期呼吸の様子を見てご家族が驚かれてしまうことが多いからです。そのためレジデントへの教育として,「呼吸が苦しそうに見えるかもしれませんが,麻薬を使用していますのでご本人は苦しさを感じていません。安心してください」と,抜管前に家族へ伝えるよう指導しています。また,ご家族が気道のゴロゴロ音を気にされる場合は,分泌物を減らす目的でブスコパン®の投与も検討します。もし今後,当院のように緩和目的で抜管をできる施設が増えていくのであれば,このプロセスが疎かにされないことを願います。
残される家族の負担を少しでも軽減するために
伊藤 私も家族へのかかわり方は特に重要だと感じています。なぜなら,救急・集中治療の現場では患者自身がしゃべれないケースが多く,家族とのコミュニケーションが8割以上を占めるからです。どんなに手を尽くしても時に患者は亡くなることがあるために,残された家族が患者の死に対していかに納得できるか,という家族の心情も慮りながらのコミュニケーションを心掛けるべきです。
則末 家族と話す時に意識するのは,意思決定の「支援」です。患者をよく知る家族との対話を通じ,「本人ならどう選択するか」を共に考えるのです。家族に決断を無理強いすると,その後の人生において負担となりかねません。
木澤 その通りです。意思決定を下したことを大きな負担と感じていることが,私も研究に参加した「遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究3(J-HOPE3)」の結果からも明らかになりました(論文投稿中)。しかしながら刻一刻と状況が変化する現場では,多くの場合「治療方針をいま決めてください」と判断を迫ってしまうのが現実でしょう。簡単ではないと思いますが,治療方針やゴールを決定するための支援ができる救急・集中治療医の存在は大きな救いになるはずです。
則末 ええ。もちろん,可能であれは気管挿管前等の患者が話せるうちに直接確認しておくことが重要です。「お孫さんとまた遊べるように頑張りましょうね」というhope for the bestは大切なので,治療のゴールとして必ず話すようにしています。しかし,いわゆる“撤退ライン”として「残念ながら良くならない可能性もあります。もし,こういう状況であれば生きていても仕方がない,死んだほうがましだというお考えがあれば教えてください」というprepare for the worstについての情報を聞いておくことも必要です。これだけでも聞いておくと,家族による代理の意思決定の負担が減るでしょう。
*
木澤 本日はありがとうございました。ここまで議論をしてきたようにまだまだ課題の多い救急・集中治療領域における緩和ケアですが,ひょっとすると近々大きな変革が起こるのではないかと期待をしています。と言うのも,COVID-19によって医療資源に限界があることが医療者をはじめ一般の方にも認識され,図らずもgoals of care discussionの重要性を意識するきっかけになっているからです。救急・集中治療現場に緩和ケアを根付かせるためにも,一度立ち止まって真剣にこの問題に向き合う時が来ていると思います。
註:集中治療を含む治療を一定の期間行ってみて,その効果を見極める手法。
参考文献
1)厚労省.人生の最終段階における医療に関する意識調査 報告書.2018.
2)Health Aff (Millwood). 2017[PMID:28679811]
木澤 義之(きざわ・よしゆき)氏 神戸大学医学部附属病院 緩和支持治療科 特命教授
1991年筑波大医学専門学群卒。筑波メディカルセンター病院総合診療科診療科長,筑波大医学専門学群講師,同大病院緩和ケアセンター副センター長などを経て,2013年神戸大大学院医学研究科内科系講座先端緩和医療学分野特命教授に就任。17年より現職。編著に『救急・集中治療領域における緩和ケア』(医学書院)など。

伊藤 香(いとう・かおり)氏 帝京大学医学部 救急医学講座 講師
2000年慈恵医大卒。聖路加国際病院で外科専門医取得後に渡米。15年に米ミシガン州立大で米国外科専門医,16年に米デトロイト市ヘンリー・フォード病院にて米国外科集中治療専門医を取得。同年帰国し現職。監訳書に『救急×緩和ケアファーストブック』(MEDSi)。
則末 泰博(のりすえ・やすひろ)氏 東京ベイ・浦安市川医療センター 集中治療部門 部長
1996年慶大文学部心理学科卒後,東邦大医学部へ進学。2004年沖縄県立中部病院にて初期研修,06年より米ハワイ大内科レジデント,09年米セントルイス大にて呼吸器内科・集中治療科フェロー。12年に帰国し現職。編著に『人工呼吸管理レジデントマニュアル』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。