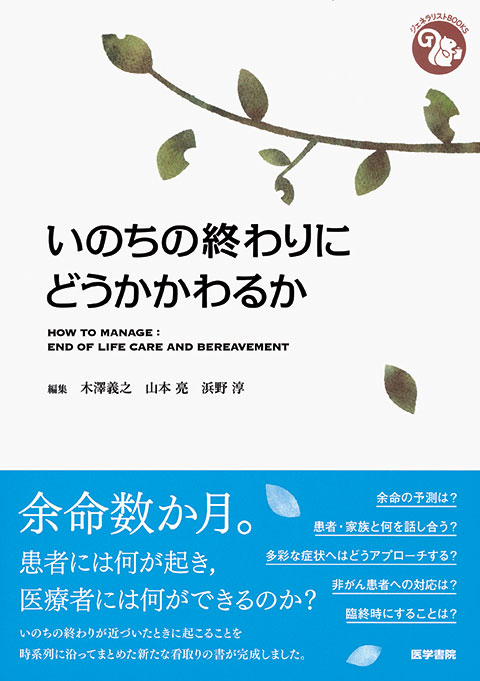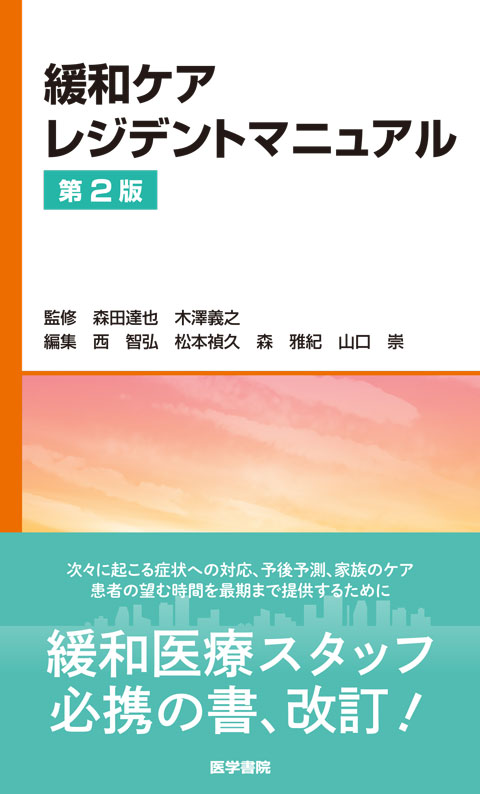いのちの終わりにどうかかわるか
「多死社会」で役立つ終末期の実践ガイド
もっと見る
総合診療医や内科医、およびそれを取り巻くメディカルスタッフに求められるエンドオブライフ患者へのかかわり方の知識とスキルをまとめた1冊。患者の同定から予後予測、患者・家族との話し合い、起こりうる症状、臨終時の対応まで、余命数か月の患者に起こること、および求められる対応を網羅。来る「多死社会」に役立てられる新たな実践的ガイドとなること間違いなし!
*「ジェネラリストBOOKS」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | ジェネラリストBOOKS |
|---|---|
| 編集 | 木澤 義之 / 山本 亮 / 浜野 淳 |
| 発行 | 2017年11月判型:A5頁:304 |
| ISBN | 978-4-260-03255-1 |
| 定価 | 4,400円 (本体4,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
一人の医師として,治癒が望めない疾患をもった患者さんとどう向き合ったらよいのか,何を話したらよいのか,そして患者さんやご家族のもつ苦悩や苦痛にどのようにアプローチしたらよいのだろうか? それができるようになりたい.
これは,私が18歳,医学部に入ってはじめての年に,聖隷三方原病院のホスピス,淀川キリスト教病院のホスピス,そして白十字診療所で訪問診療・看護を見学したことをきっかけに,将来ホスピス・緩和ケアに取り組もうと考えた際に感じた大きな課題でした.当時ホスピス・緩和ケアをしたい,と考える医学生は稀であり,相当変わり者扱いされたと思います.しかしながら,この30年余りでその状況は大きく変化してきました.わが国の緩和ケア,エンドオブライフ・ケアは急速に進歩し,特にがん医療では国の重点政策の1つとして取り上げられ,医療のなかで欠くことのできないものとなってきています.
緩和ケアは,世界保健機関(WHO)により以下のように定義されています.「緩和ケアとは,生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して,痛みやその他の身体的問題,心理社会的問題,スピリチュアルな問題を早期に発見し,的確なアセスメントと対処(治療・処置)を行うことによって,苦しみを予防し,和らげることで,QOL(quality of life:生活の質)を改善するアプローチである」1).また,エンドオブライフ・ケアはオーストラリア緩和ケア協会により以下のように定義されています.「エンドオブライフ・ケアは死が避けることができないものとなり,予想される生命予後が限られたときに行われるケアを指す.また,最後の12か月を表現するものとして使用される」2).
わが国の緩和ケア,エンドオブライフ・ケアの現状を表す1つの資料として,英国エコノミスト誌の「死の質の指標2015年度版」を取り上げたいと思います3).日本は前回の調査である2010年には世界第23位でしたが,今回の調査で第14位へと大幅にランクアップしています.これは,政府主導のがん対策が進み,基本的な緩和ケアが受けられるようになったことや,すべてのがん診療連携拠点病院に緩和ケアチームが整備されたことが大きく評価されたものだと思います.一方で,ほかのアジアの国をみてみると,日本から緩和ケアの手法を取り入れた台湾は第6位となっています.この差がどこから来ているかについてはさまざまな議論がありますが,日本ではがん以外の疾患に対する緩和ケアが整備されていないこと,病院以外での緩和ケア,特に診療所や在宅での緩和ケアが整備されていないこと,がその主な要因であるとされています.
われわれに与えられた課題は明快で,その要点は以下の3つにまとめることができます.それらは,1)疾患を問わずに緩和ケアを実践すること,つまりがん以外の疾患に対する緩和ケアを推進すること,2)患者がどこで治療・療養をしていても緩和ケアが提供されること,言い換えれば在宅や施設で緩和ケアが実践されること,3)提供する緩和ケアの質を高めること,ではないかと思います.
本書は,地域で医療の第一線に立つプライマリ・ケア医が,いのちの終わりにある患者さん・ご家族に対してどのような治療・ケア・支援を実践したらよいかについて,詳細に書かれた唯一無二のものだと自負しています.1)どのように緩和ケア,エンドオブライフ・ケアの対象者をみつけ,2)どのように評価し,3)どのような方法で余命を推定したうえで,4)治療とケアの目標を話し合ったらよいのか,そして,5)死の1週間前,6)死亡直前,7)臨終のときにどのようなケアを行ったらよいか,8)喪失と悲嘆にどう対処するか,などについてともに考えていくことができるように構成されています.この本が,プライマリ・ケア医の緩和ケア,エンドオブライフ・ケアの指針を示す海図となり,荒波に翻弄される患者さん・ご家族と舟の導き手である医療従事者の助けとなるのであれば,著者・編者一同の最大の喜びです.
2017年10月
編者を代表して 木澤義之
文献
1)World Health Organization:WHO Definition of palliative care. 2002. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/(2017年9月30日現在)
2)Palliative Care Australia:Palliative and end of life care glossary of terms. 2008.
3)The Economist Intelligence Unit:The 2015 Quality of Death Index. Ranking palliative care across the world. 2015.
一人の医師として,治癒が望めない疾患をもった患者さんとどう向き合ったらよいのか,何を話したらよいのか,そして患者さんやご家族のもつ苦悩や苦痛にどのようにアプローチしたらよいのだろうか? それができるようになりたい.
これは,私が18歳,医学部に入ってはじめての年に,聖隷三方原病院のホスピス,淀川キリスト教病院のホスピス,そして白十字診療所で訪問診療・看護を見学したことをきっかけに,将来ホスピス・緩和ケアに取り組もうと考えた際に感じた大きな課題でした.当時ホスピス・緩和ケアをしたい,と考える医学生は稀であり,相当変わり者扱いされたと思います.しかしながら,この30年余りでその状況は大きく変化してきました.わが国の緩和ケア,エンドオブライフ・ケアは急速に進歩し,特にがん医療では国の重点政策の1つとして取り上げられ,医療のなかで欠くことのできないものとなってきています.
緩和ケアは,世界保健機関(WHO)により以下のように定義されています.「緩和ケアとは,生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して,痛みやその他の身体的問題,心理社会的問題,スピリチュアルな問題を早期に発見し,的確なアセスメントと対処(治療・処置)を行うことによって,苦しみを予防し,和らげることで,QOL(quality of life:生活の質)を改善するアプローチである」1).また,エンドオブライフ・ケアはオーストラリア緩和ケア協会により以下のように定義されています.「エンドオブライフ・ケアは死が避けることができないものとなり,予想される生命予後が限られたときに行われるケアを指す.また,最後の12か月を表現するものとして使用される」2).
わが国の緩和ケア,エンドオブライフ・ケアの現状を表す1つの資料として,英国エコノミスト誌の「死の質の指標2015年度版」を取り上げたいと思います3).日本は前回の調査である2010年には世界第23位でしたが,今回の調査で第14位へと大幅にランクアップしています.これは,政府主導のがん対策が進み,基本的な緩和ケアが受けられるようになったことや,すべてのがん診療連携拠点病院に緩和ケアチームが整備されたことが大きく評価されたものだと思います.一方で,ほかのアジアの国をみてみると,日本から緩和ケアの手法を取り入れた台湾は第6位となっています.この差がどこから来ているかについてはさまざまな議論がありますが,日本ではがん以外の疾患に対する緩和ケアが整備されていないこと,病院以外での緩和ケア,特に診療所や在宅での緩和ケアが整備されていないこと,がその主な要因であるとされています.
われわれに与えられた課題は明快で,その要点は以下の3つにまとめることができます.それらは,1)疾患を問わずに緩和ケアを実践すること,つまりがん以外の疾患に対する緩和ケアを推進すること,2)患者がどこで治療・療養をしていても緩和ケアが提供されること,言い換えれば在宅や施設で緩和ケアが実践されること,3)提供する緩和ケアの質を高めること,ではないかと思います.
本書は,地域で医療の第一線に立つプライマリ・ケア医が,いのちの終わりにある患者さん・ご家族に対してどのような治療・ケア・支援を実践したらよいかについて,詳細に書かれた唯一無二のものだと自負しています.1)どのように緩和ケア,エンドオブライフ・ケアの対象者をみつけ,2)どのように評価し,3)どのような方法で余命を推定したうえで,4)治療とケアの目標を話し合ったらよいのか,そして,5)死の1週間前,6)死亡直前,7)臨終のときにどのようなケアを行ったらよいか,8)喪失と悲嘆にどう対処するか,などについてともに考えていくことができるように構成されています.この本が,プライマリ・ケア医の緩和ケア,エンドオブライフ・ケアの指針を示す海図となり,荒波に翻弄される患者さん・ご家族と舟の導き手である医療従事者の助けとなるのであれば,著者・編者一同の最大の喜びです.
2017年10月
編者を代表して 木澤義之
文献
1)World Health Organization:WHO Definition of palliative care. 2002. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/(2017年9月30日現在)
2)Palliative Care Australia:Palliative and end of life care glossary of terms. 2008.
3)The Economist Intelligence Unit:The 2015 Quality of Death Index. Ranking palliative care across the world. 2015.
目次
開く
序
第1章 ケース・ファインディング どのような患者にエンドオブライフ・ケアが必要か
第2章 評価で気をつけること
終末期の身体診察
包括的アセスメント
コーピング
予期悲嘆
第3章 予後を予測する
第4章 治療とケアのゴールを話し合う
病状認識を確かめる
意思決定能力とその判断
患者と家族の意向が異なるとき
大切にしていること/したいこと
望んでいる療養の場所
治療・ケア
家族評価とライフレビュー
第5章 死の1週間前に起こる症状とその対応
痛み
呼吸困難
せん妄
倦怠感 がん関連倦怠感を中心に
鎮静
急性増悪時の可逆性の見積もり(1)感染症
急性増悪時の可逆性の見積もり(2)電解質異常
急性増悪時の可逆性の見積もり(3)貧血
死前喘鳴
第6章 Last 48 hours
これから起こること
身体症状のアセスメントとマネジメント
今している治療の見直し
今しているケアの見直し
家族への説明
第7章 臨終時の対応
病院の場合
在宅の場合
死亡診断の作法
第8章 喪失と悲嘆
通常の悲嘆
複雑性悲嘆の見つけ方と対応
第9章 アドバンス・ケア・プランニングとベスト・インタレスト論
索引
第1章 ケース・ファインディング どのような患者にエンドオブライフ・ケアが必要か
第2章 評価で気をつけること
終末期の身体診察
包括的アセスメント
コーピング
予期悲嘆
第3章 予後を予測する
第4章 治療とケアのゴールを話し合う
病状認識を確かめる
意思決定能力とその判断
患者と家族の意向が異なるとき
大切にしていること/したいこと
望んでいる療養の場所
治療・ケア
家族評価とライフレビュー
第5章 死の1週間前に起こる症状とその対応
痛み
呼吸困難
せん妄
倦怠感 がん関連倦怠感を中心に
鎮静
急性増悪時の可逆性の見積もり(1)感染症
急性増悪時の可逆性の見積もり(2)電解質異常
急性増悪時の可逆性の見積もり(3)貧血
死前喘鳴
第6章 Last 48 hours
これから起こること
身体症状のアセスメントとマネジメント
今している治療の見直し
今しているケアの見直し
家族への説明
第7章 臨終時の対応
病院の場合
在宅の場合
死亡診断の作法
第8章 喪失と悲嘆
通常の悲嘆
複雑性悲嘆の見つけ方と対応
第9章 アドバンス・ケア・プランニングとベスト・インタレスト論
索引
書評
開く
終末期の患者・家族にかかわる医療者必読
書評者: 小澤 竹俊 (めぐみ在宅クリニック・院長)
団塊の世代が高齢化を迎え,日本の社会は超高齢少子多死時代となりました。社会保障費が高騰する中で,病状が進んだ患者さんが亡くなるまでの全てを,急性期の病院でカバーすることは困難になります。これからの時代,治療抵抗性となった患者と家族に対して医療者はどのようにかかわると良いのでしょう。従来の診断と治療というかかわり方では対応は難しいでしょう。病状を伝えるだけではなく,これからどのようなことが起こり,どのような準備をしていくと良いのか,本人・家族と一緒に考えていく必要があります。
ここ数年,注目されている課題は,「意思決定支援」です。治療の最中から,これから予想される将来について,話し合いを行い,希望する医療,希望しない医療について,患者・家族の意思を確認しておくことは,望まない救急搬送を最小限にします。かつて治療方針は,医師が最善と思われる内容を指示してきた時代がありました。しかし,医師の最善と思う内容と,患者・家族が最善と思う内容は異なることがあり,リビングウィルや事前指示(AD)のように,患者の自己決定が尊重される動きが広がってきました。ところが,施策的に事前指示を展開しても,その目的が事前指示の書類作成に陥れば,その成果は必ずしも患者のQOL向上には寄与しないことが明らかになりました。意思決定支援は,ただ自分の希望する治療内容を書類に書くことではありません。これから起こるさまざまな出来事について,きちんとした情報を元に話し合いをしていくプロセスが大切になります。
例えば,あなたがツアーコンダクターで,生まれて初めての場所に旅行に行く人の相談を受けることになりました。あなたは,移動手段や観光スポットの回る順番,宿泊所,食事などを決めなくてはいけません。そのためには,どのようなことを学ぶ必要があるでしょう? その旅行先の詳しい情報を知らないと,相談に乗ることはできません。気候から歴史,御国自慢,郷土料理まで幅広く知るのはもちろんですが,旅行に行く人の嗜好も大切な情報になります。
いのちの終わりを迎えた人の場合も同じです。これからどのような身体の変化が起きてくるのか,どのぐらいの予後が予測され,もし身体・精神的な苦痛があったとしても適切な緩和ケアが提供できること,その上で,どの場所で過ごせるのか,そして,家族への配慮などの知識は欠かせません。私たちが,いのちの終わりを迎えた患者・家族に関わる上で,必要な知識がなければ,一緒に話し合いながら,これからのことを相談することができません。
この本では,事例提示を基に,これらの必要な情報を学ぶことができます。さらに学びを深めたい人には参考になる文献もサマリー付きで紹介されています。急性期の病院にかかわらず,これからの時代は,住み慣れた地域で最後まで過ごせる社会が求められます。どこで働いていたとしても,看取りにかかわる医師には,必読の書としてお薦めします。
医療者が行うべき行動に焦点を当てた実践書
書評者: 前野 哲博 (筑波大病院教授/総合診療グループ長)
人は誰でも死から逃れることはできず,医療者は,いのちの終わりに向き合う機会は多い。ところが,医療者になるためのトレーニングでは,病気を取り除いて回復をめざす治療法については詳しく学ぶものの,エンドオブライフ・ケアについて体系的なトレーニングを受ける機会は極めて乏しい。そのため,往々にして医療者は,患者がいのちの終わりに向かう事実をタブー視したり,自らの業務範囲外と見なしたりしがちである。その上,エンドオブライフ・ケアに正面から向き合おうにも,医療者の個人的な経験や見識に任されている部分が大きいので,具体的にいつから,どのように対応すべきなのか戸惑うことも多い。
本書『いのちの終わりにどうかかわるか』は,まさにこのテーマに正面から取り組んだ本である。本書は,いのちの終わりが近づいたときの時系列に沿って構成されており,冒頭の総論に引き続いて,評価,予後予測,治療とケアのゴールの話し合いについて取り上げられている。臨死期の対応については,1週間,48時間,臨終時のそれぞれのフェーズに合わせて詳しく述べられており,さらに患者が亡くなった後の喪失と悲嘆への対応と続き,最終章では,アドバンス・ケア・プランニングとベスト・インタレスト論がまとめられている。このように,エンドオブライフ・ケアの全てのフェーズが網羅されているので,本書一冊で包括的にエンドオブライフ・ケアについて学ぶことができる構成となっている。
各章では,典型的なケースが取り上げられ,簡潔でわかりやすい解説に続いて,ケースへの具体的な対応,そしてclinical pearlの順にまとめられている。本書の特徴は,全ての章が,実際に医療者が行うべき行動に焦点を当てた実践書というコンセプトで貫かれていることである。さらに詳しく勉強したい読者に対しては,簡単な解説のついた参考文献リストがついているので,さらに掘り下げて学びを深めるガイドにもなっている。
エンドオブライフ・ケアの対象となるのは,がん患者の緩和医療のみではなく,病気の終末期になってから考え始めるものではない。医学的な症状にだけ対応すれば良いわけではなく,ケアの対象は患者のみでもない。身近なところで,包括的に,継続的に,チームで協調しながら,一人ひとりの状況や価値観を尊重しながら行うべきものであり,本書を読んで,これはまさにプライマリ・ケアの特徴として位置付けられるACCCC(Access, Comprehensiveness, Continuity, Coordination, Contextual care)に通じる概念であることをあらためて実感した。
未曾有の多死時代を迎える今,医療者としての確かなスキルを持って,いのちの終わりに正面から向き合い,最善のエンドオブライフ・ケアを提供するために,プライマリ・ケアにかかわる全ての医療者に,ぜひ一読をお勧めしたい。
これまで以上に,誰かの役に立てるという幸福感を生む1冊(雑誌『看護管理』より)
書評者: 角田 直枝 (茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター看護局長/がん看護専門看護師)
◆いのちの終わりに,こんなにもたくさんの“できること”がある
木澤義之医師が中心となって編集・執筆した本書を,医師のみならず,その他の医療者にもぜひ読んでもらいたい。
私は看護師という立場で読んだとき,医師の視点や判断を知り,その上で医師とは異なる看護の役割も再認識した。例えば,死前喘鳴への対応では,「本書には書かれていないけれど,この時期の家族に私はこうする」と思いながら読んだ。
しかし,そんなことはどうでもよい。私が伝えたいことは,読者の立場によって読み方は違っていても,いのちの終わりにこんなにもたくさんの“できること”があると気づく自己効力感の大切さだ。
◆治癒を目指さない医療も,価値ある医療
患者や利用者にいのちの終わりが近づくとき,もう何もできないと考える医療者が,今,まだ多い。日常の臨床では,「もう化学療法は無理なので,他にできることはない」とか,「心不全は治らないので,これ以上何もできない」などと説明する場面は,どこでも見られる光景であろう。確かに,治癒を目指した医療から考えたら,この説明は誤りではない。
しかし,高齢者や慢性疾患患者が増加し,医療は治癒だけを目指す時代ではなくなった。疾患と共存していく医療や,人生の最終段階の時期を穏やかに過ごすための医療を,医療者はもっと価値あるものとして捉えなければならない。
治癒を目指せなくなることを医療の敗北だと捉えるひとがいたとしても,治癒を目指さない医療だって,人生を豊かにして,尊厳を大切にする価値ある医療なのだ。
◆死=不幸という概念からの解放
ところで,私はかつて,訪問看護師として在宅でのいのちの終わりに関わり,現在の看護局長という立場では,勤務する病院で月平均60人ほどのひとの人生が終わる。また,私はがん看護専門看護師であり,看護局長であっても個別の患者に関わることもあって,こうして原稿を書いているときも,数日前に亡くなったひとの顔が浮かぶ。
医師は多くのいのちの終わりに立ち会うし,看護師はいのちの終わりの生活に寄り添う。薬剤師も栄養士も療法士も医療ソーシャルワーカーも,医療者であれば皆,いのちの終わりに触れる。
いのちの終わりは,決して終わりだけではない。そのひとや家族が穏やかで尊重される時間を持てると,死のあとに幸せを残すことができる。身近なひとの死を体験したから命の貴さを認識し,家族の思いを再確認する。弱っていくひとに寄り添うから,できないことや失うことに力を貸すことができる自分にも気づく。こうした思いは,いのちの終わりのあとも,亡くなっていったひとの存在を大切にし続ける。そして,死生観・生命観・人生観・家族観など価値観を拡大し,死=不幸という概念を解放するのだと思う。
本書は,医療者にとって,自分ができる世界の拡がりを感じさせ,これまで以上に誰かの役に立てるという幸福感を生むのではないだろうか。
(『看護管理』2018年5月号掲載)
遺族の立場を経験して(雑誌『精神看護』より)
書評者: 阿部 貴子 (立正佼成会附属佼成病院/リエゾン精神看護専門看護師/精神科認定看護師)
◆「あれでよかったのだろうか」
10年ほど前、私の父はホスピスで亡くなった。父は頑固で無口な人で、成長するにつれ父との会話はいっそう減っていた。そんな父ががんと聞いた時、私は楽観的に振る舞うことしかできなかった。治療の効果も芳しくなく、病床の父と2人きりになると何を話していいのか戸惑いを覚え、息苦しさすら感じた。それは、自分が父の死に向き合うことができない息苦しさだと思いながらも自分から話しかけることができなかった。
ホスピスに移ると、もう苦しい治療はなく、父は母と穏やかに10日間過ごした。意識もまばらになった頃、「もう、数日でしょう」という医師の説明に、私は今の状態で父が望むとしたら何ができるのだろうと考えた。私は、治療のため、しばらく入浴できていなかった父に「お父さん、お風呂入りたい?」と話しかけた。その時、確かに父は頷いたように見えた。夜になって母から「お父さん、お風呂入ったのよ。すごく気持ちよさそうにほ~って言ったのよ」と嬉しそうな声で電話があった。私はその時、それが父の体力を消耗させ寿命を短くしたとしても、父が気持ちよいと感じてくれたのであれば良かったと思えた。その翌々日、父は苦しむことなく静かに息を引き取った。
ホスピスを出た後、葬儀社の方が、もう一度家に帰りたいと願っていた故人の想いがあるでしょうと家の周りを一周してくれた。私はその時、病院にいる父ではなく家のいつもの椅子に座っている父を思い浮かべた。小さかった頃の思い出がふわっと思い出され、私は改めて父の人生はどんな人生だったのだろうと考えた。私はどうしてもっと父の人生やその終わり方について聞いておかなかったのだろう。充分に時間はあったはずなのに。私はただ「お風呂に入れてあげたい」という自分の気持ちを押し付けて父の寿命を短くしただけなのではないか、何もしなくともそばにいることが一番ではなかったかと考え始めると涙が止まらなかった。
数年前から母と姉と私は、父の亡くなった季節に旅行に行くようになった。どこに行っても、おいしいものを食べても、母は「お父さんも食べられたらよかったのにね。あれでよかったのかしら」と言う。そのたびに、姉と私は「あの時、お風呂に入れてよかったよね」と応じ、母が「そうだよね」と答える……そんなやり取りがいつもある。
◆寿命とカフェオレ
昨年の暮れに、高齢の叔父が亡くなり葬儀に行った。叔父は晩年、膀胱がんの手術後に誤嚥性肺炎を併発。胃ろうを造設し自宅療養をしていた。今回の再入院ではもう退院できないだろうと主治医に言われていたとのことだった。
葬儀の際、叔母は小さな声で、「先生はダメって言ってたけど、実はパパがカフェオレ飲みたいって言うからスプーンに一口だけ飲ませたのね。そしたら涙を流して喜んだのよ」と言った。私は不意に父のことを思い出した。叔母の行動は、直接的な原因にはならなくても医学的には禁忌な行動だとは思う。しかし私は、余命いくばくもない叔父の望みに対し、叔母がその時にできる最善を考えたのだと思った。私は思わず「よかったと思います」と答えた。「そうよね」と叔母はにっこりとほほ笑んだ。叔母もまた、私と同じように自分の行動が、叔父にとって良くなかったのではないかと後悔していたのかもしれない。誰かに「それは良かった」と言ってもらえることで自分を納得させたのではないだろうか。
遺族の気持ちというのは、悲嘆や後悔、痛みに幾度となく揺り戻され、何かひとつでも拠り所を見つけながら適応の道を辿るのだろうと思う。叔母にしても母にしてもそして私自身も、すべてが万全ではなかったという想いはありながらも、どこかで拠り所を見つけながら自分の人生に向かっていくのだろうと思う。
◆「いのちの終わり」に見通しが立ったなら
日本では、緩和ケアの対象ではない患者や家族は、最後まで治療の場から離れることも「いのちの終わり」を見極めることも難しい。日々の臨床では、もう手立てがないという状態になって初めて「いのちの終わり」について問われることになる。その時に、家族は患者の状態変化が死に至る過程だと説明されても「こんな状態になるはずがない。何か別の原因があるのではないか」と現実と向き合えないこともある。患者に残された時間が少なければ少ないほど、患者とその家族間、医療者と患者や家族間でそれぞれの想いや理解の誤差を埋め切れていないため、「こんなに急に亡くなるとは思っていなかった。何もしてあげられなかったじゃないか」という驚きと嘆き、怒りといったかかえきれない感情を医療者に向けることも少なくない。
本書の優れた点は、がん性、非がん性にかかわらず、患者や家族や医療者が「いのちの終わり」の過程で直面すると思われる治療やケア、実践について、すべてが事例を用いて構成され、それぞれの「いのちの終わり」から、患者や家族への最善のケアを見つけ出せるように具体的に記されている点である。
もちろん、事例がぴったりと当てはまるわけではないが、読み進めると確かな手ごたえがある。本書は、きっと患者や大切な人の死に向かい合う家族、医療者それぞれの立場に応じた「かかわり」を導き出すことができる本だと思う。
(『精神看護』2018年3月号掲載)
書評者: 小澤 竹俊 (めぐみ在宅クリニック・院長)
団塊の世代が高齢化を迎え,日本の社会は超高齢少子多死時代となりました。社会保障費が高騰する中で,病状が進んだ患者さんが亡くなるまでの全てを,急性期の病院でカバーすることは困難になります。これからの時代,治療抵抗性となった患者と家族に対して医療者はどのようにかかわると良いのでしょう。従来の診断と治療というかかわり方では対応は難しいでしょう。病状を伝えるだけではなく,これからどのようなことが起こり,どのような準備をしていくと良いのか,本人・家族と一緒に考えていく必要があります。
ここ数年,注目されている課題は,「意思決定支援」です。治療の最中から,これから予想される将来について,話し合いを行い,希望する医療,希望しない医療について,患者・家族の意思を確認しておくことは,望まない救急搬送を最小限にします。かつて治療方針は,医師が最善と思われる内容を指示してきた時代がありました。しかし,医師の最善と思う内容と,患者・家族が最善と思う内容は異なることがあり,リビングウィルや事前指示(AD)のように,患者の自己決定が尊重される動きが広がってきました。ところが,施策的に事前指示を展開しても,その目的が事前指示の書類作成に陥れば,その成果は必ずしも患者のQOL向上には寄与しないことが明らかになりました。意思決定支援は,ただ自分の希望する治療内容を書類に書くことではありません。これから起こるさまざまな出来事について,きちんとした情報を元に話し合いをしていくプロセスが大切になります。
例えば,あなたがツアーコンダクターで,生まれて初めての場所に旅行に行く人の相談を受けることになりました。あなたは,移動手段や観光スポットの回る順番,宿泊所,食事などを決めなくてはいけません。そのためには,どのようなことを学ぶ必要があるでしょう? その旅行先の詳しい情報を知らないと,相談に乗ることはできません。気候から歴史,御国自慢,郷土料理まで幅広く知るのはもちろんですが,旅行に行く人の嗜好も大切な情報になります。
いのちの終わりを迎えた人の場合も同じです。これからどのような身体の変化が起きてくるのか,どのぐらいの予後が予測され,もし身体・精神的な苦痛があったとしても適切な緩和ケアが提供できること,その上で,どの場所で過ごせるのか,そして,家族への配慮などの知識は欠かせません。私たちが,いのちの終わりを迎えた患者・家族に関わる上で,必要な知識がなければ,一緒に話し合いながら,これからのことを相談することができません。
この本では,事例提示を基に,これらの必要な情報を学ぶことができます。さらに学びを深めたい人には参考になる文献もサマリー付きで紹介されています。急性期の病院にかかわらず,これからの時代は,住み慣れた地域で最後まで過ごせる社会が求められます。どこで働いていたとしても,看取りにかかわる医師には,必読の書としてお薦めします。
医療者が行うべき行動に焦点を当てた実践書
書評者: 前野 哲博 (筑波大病院教授/総合診療グループ長)
人は誰でも死から逃れることはできず,医療者は,いのちの終わりに向き合う機会は多い。ところが,医療者になるためのトレーニングでは,病気を取り除いて回復をめざす治療法については詳しく学ぶものの,エンドオブライフ・ケアについて体系的なトレーニングを受ける機会は極めて乏しい。そのため,往々にして医療者は,患者がいのちの終わりに向かう事実をタブー視したり,自らの業務範囲外と見なしたりしがちである。その上,エンドオブライフ・ケアに正面から向き合おうにも,医療者の個人的な経験や見識に任されている部分が大きいので,具体的にいつから,どのように対応すべきなのか戸惑うことも多い。
本書『いのちの終わりにどうかかわるか』は,まさにこのテーマに正面から取り組んだ本である。本書は,いのちの終わりが近づいたときの時系列に沿って構成されており,冒頭の総論に引き続いて,評価,予後予測,治療とケアのゴールの話し合いについて取り上げられている。臨死期の対応については,1週間,48時間,臨終時のそれぞれのフェーズに合わせて詳しく述べられており,さらに患者が亡くなった後の喪失と悲嘆への対応と続き,最終章では,アドバンス・ケア・プランニングとベスト・インタレスト論がまとめられている。このように,エンドオブライフ・ケアの全てのフェーズが網羅されているので,本書一冊で包括的にエンドオブライフ・ケアについて学ぶことができる構成となっている。
各章では,典型的なケースが取り上げられ,簡潔でわかりやすい解説に続いて,ケースへの具体的な対応,そしてclinical pearlの順にまとめられている。本書の特徴は,全ての章が,実際に医療者が行うべき行動に焦点を当てた実践書というコンセプトで貫かれていることである。さらに詳しく勉強したい読者に対しては,簡単な解説のついた参考文献リストがついているので,さらに掘り下げて学びを深めるガイドにもなっている。
エンドオブライフ・ケアの対象となるのは,がん患者の緩和医療のみではなく,病気の終末期になってから考え始めるものではない。医学的な症状にだけ対応すれば良いわけではなく,ケアの対象は患者のみでもない。身近なところで,包括的に,継続的に,チームで協調しながら,一人ひとりの状況や価値観を尊重しながら行うべきものであり,本書を読んで,これはまさにプライマリ・ケアの特徴として位置付けられるACCCC(Access, Comprehensiveness, Continuity, Coordination, Contextual care)に通じる概念であることをあらためて実感した。
未曾有の多死時代を迎える今,医療者としての確かなスキルを持って,いのちの終わりに正面から向き合い,最善のエンドオブライフ・ケアを提供するために,プライマリ・ケアにかかわる全ての医療者に,ぜひ一読をお勧めしたい。
これまで以上に,誰かの役に立てるという幸福感を生む1冊(雑誌『看護管理』より)
書評者: 角田 直枝 (茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター看護局長/がん看護専門看護師)
◆いのちの終わりに,こんなにもたくさんの“できること”がある
木澤義之医師が中心となって編集・執筆した本書を,医師のみならず,その他の医療者にもぜひ読んでもらいたい。
私は看護師という立場で読んだとき,医師の視点や判断を知り,その上で医師とは異なる看護の役割も再認識した。例えば,死前喘鳴への対応では,「本書には書かれていないけれど,この時期の家族に私はこうする」と思いながら読んだ。
しかし,そんなことはどうでもよい。私が伝えたいことは,読者の立場によって読み方は違っていても,いのちの終わりにこんなにもたくさんの“できること”があると気づく自己効力感の大切さだ。
◆治癒を目指さない医療も,価値ある医療
患者や利用者にいのちの終わりが近づくとき,もう何もできないと考える医療者が,今,まだ多い。日常の臨床では,「もう化学療法は無理なので,他にできることはない」とか,「心不全は治らないので,これ以上何もできない」などと説明する場面は,どこでも見られる光景であろう。確かに,治癒を目指した医療から考えたら,この説明は誤りではない。
しかし,高齢者や慢性疾患患者が増加し,医療は治癒だけを目指す時代ではなくなった。疾患と共存していく医療や,人生の最終段階の時期を穏やかに過ごすための医療を,医療者はもっと価値あるものとして捉えなければならない。
治癒を目指せなくなることを医療の敗北だと捉えるひとがいたとしても,治癒を目指さない医療だって,人生を豊かにして,尊厳を大切にする価値ある医療なのだ。
◆死=不幸という概念からの解放
ところで,私はかつて,訪問看護師として在宅でのいのちの終わりに関わり,現在の看護局長という立場では,勤務する病院で月平均60人ほどのひとの人生が終わる。また,私はがん看護専門看護師であり,看護局長であっても個別の患者に関わることもあって,こうして原稿を書いているときも,数日前に亡くなったひとの顔が浮かぶ。
医師は多くのいのちの終わりに立ち会うし,看護師はいのちの終わりの生活に寄り添う。薬剤師も栄養士も療法士も医療ソーシャルワーカーも,医療者であれば皆,いのちの終わりに触れる。
いのちの終わりは,決して終わりだけではない。そのひとや家族が穏やかで尊重される時間を持てると,死のあとに幸せを残すことができる。身近なひとの死を体験したから命の貴さを認識し,家族の思いを再確認する。弱っていくひとに寄り添うから,できないことや失うことに力を貸すことができる自分にも気づく。こうした思いは,いのちの終わりのあとも,亡くなっていったひとの存在を大切にし続ける。そして,死生観・生命観・人生観・家族観など価値観を拡大し,死=不幸という概念を解放するのだと思う。
本書は,医療者にとって,自分ができる世界の拡がりを感じさせ,これまで以上に誰かの役に立てるという幸福感を生むのではないだろうか。
(『看護管理』2018年5月号掲載)
遺族の立場を経験して(雑誌『精神看護』より)
書評者: 阿部 貴子 (立正佼成会附属佼成病院/リエゾン精神看護専門看護師/精神科認定看護師)
◆「あれでよかったのだろうか」
10年ほど前、私の父はホスピスで亡くなった。父は頑固で無口な人で、成長するにつれ父との会話はいっそう減っていた。そんな父ががんと聞いた時、私は楽観的に振る舞うことしかできなかった。治療の効果も芳しくなく、病床の父と2人きりになると何を話していいのか戸惑いを覚え、息苦しさすら感じた。それは、自分が父の死に向き合うことができない息苦しさだと思いながらも自分から話しかけることができなかった。
ホスピスに移ると、もう苦しい治療はなく、父は母と穏やかに10日間過ごした。意識もまばらになった頃、「もう、数日でしょう」という医師の説明に、私は今の状態で父が望むとしたら何ができるのだろうと考えた。私は、治療のため、しばらく入浴できていなかった父に「お父さん、お風呂入りたい?」と話しかけた。その時、確かに父は頷いたように見えた。夜になって母から「お父さん、お風呂入ったのよ。すごく気持ちよさそうにほ~って言ったのよ」と嬉しそうな声で電話があった。私はその時、それが父の体力を消耗させ寿命を短くしたとしても、父が気持ちよいと感じてくれたのであれば良かったと思えた。その翌々日、父は苦しむことなく静かに息を引き取った。
ホスピスを出た後、葬儀社の方が、もう一度家に帰りたいと願っていた故人の想いがあるでしょうと家の周りを一周してくれた。私はその時、病院にいる父ではなく家のいつもの椅子に座っている父を思い浮かべた。小さかった頃の思い出がふわっと思い出され、私は改めて父の人生はどんな人生だったのだろうと考えた。私はどうしてもっと父の人生やその終わり方について聞いておかなかったのだろう。充分に時間はあったはずなのに。私はただ「お風呂に入れてあげたい」という自分の気持ちを押し付けて父の寿命を短くしただけなのではないか、何もしなくともそばにいることが一番ではなかったかと考え始めると涙が止まらなかった。
数年前から母と姉と私は、父の亡くなった季節に旅行に行くようになった。どこに行っても、おいしいものを食べても、母は「お父さんも食べられたらよかったのにね。あれでよかったのかしら」と言う。そのたびに、姉と私は「あの時、お風呂に入れてよかったよね」と応じ、母が「そうだよね」と答える……そんなやり取りがいつもある。
◆寿命とカフェオレ
昨年の暮れに、高齢の叔父が亡くなり葬儀に行った。叔父は晩年、膀胱がんの手術後に誤嚥性肺炎を併発。胃ろうを造設し自宅療養をしていた。今回の再入院ではもう退院できないだろうと主治医に言われていたとのことだった。
葬儀の際、叔母は小さな声で、「先生はダメって言ってたけど、実はパパがカフェオレ飲みたいって言うからスプーンに一口だけ飲ませたのね。そしたら涙を流して喜んだのよ」と言った。私は不意に父のことを思い出した。叔母の行動は、直接的な原因にはならなくても医学的には禁忌な行動だとは思う。しかし私は、余命いくばくもない叔父の望みに対し、叔母がその時にできる最善を考えたのだと思った。私は思わず「よかったと思います」と答えた。「そうよね」と叔母はにっこりとほほ笑んだ。叔母もまた、私と同じように自分の行動が、叔父にとって良くなかったのではないかと後悔していたのかもしれない。誰かに「それは良かった」と言ってもらえることで自分を納得させたのではないだろうか。
遺族の気持ちというのは、悲嘆や後悔、痛みに幾度となく揺り戻され、何かひとつでも拠り所を見つけながら適応の道を辿るのだろうと思う。叔母にしても母にしてもそして私自身も、すべてが万全ではなかったという想いはありながらも、どこかで拠り所を見つけながら自分の人生に向かっていくのだろうと思う。
◆「いのちの終わり」に見通しが立ったなら
日本では、緩和ケアの対象ではない患者や家族は、最後まで治療の場から離れることも「いのちの終わり」を見極めることも難しい。日々の臨床では、もう手立てがないという状態になって初めて「いのちの終わり」について問われることになる。その時に、家族は患者の状態変化が死に至る過程だと説明されても「こんな状態になるはずがない。何か別の原因があるのではないか」と現実と向き合えないこともある。患者に残された時間が少なければ少ないほど、患者とその家族間、医療者と患者や家族間でそれぞれの想いや理解の誤差を埋め切れていないため、「こんなに急に亡くなるとは思っていなかった。何もしてあげられなかったじゃないか」という驚きと嘆き、怒りといったかかえきれない感情を医療者に向けることも少なくない。
本書の優れた点は、がん性、非がん性にかかわらず、患者や家族や医療者が「いのちの終わり」の過程で直面すると思われる治療やケア、実践について、すべてが事例を用いて構成され、それぞれの「いのちの終わり」から、患者や家族への最善のケアを見つけ出せるように具体的に記されている点である。
もちろん、事例がぴったりと当てはまるわけではないが、読み進めると確かな手ごたえがある。本書は、きっと患者や大切な人の死に向かい合う家族、医療者それぞれの立場に応じた「かかわり」を導き出すことができる本だと思う。
(『精神看護』2018年3月号掲載)