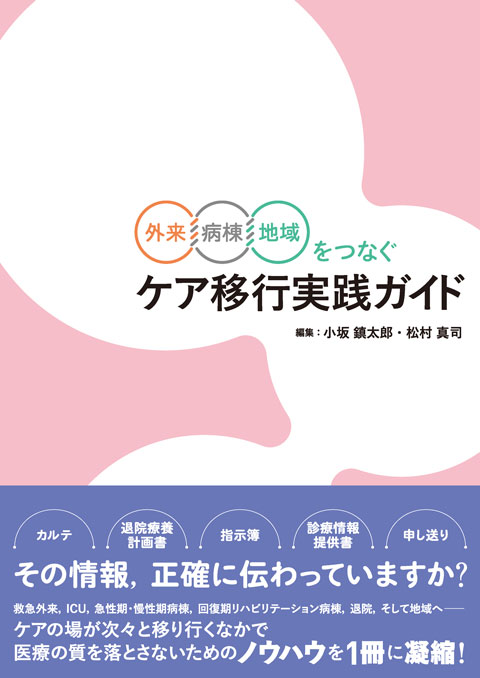良質な診療情報提供書を書くために(齊木好美)
連載
2019.07.08
スマートなケア移行で行こう!
Let's start smart Transition of Care!
医療の分業化と細分化が進み,一人の患者に複数のケア提供者,療養の場がかかわることが一般的になっています。本連載では,ケア移行(Transition of Care)を安全かつ効率的に進めるための工夫を実践的に紹介します。
[第9回]良質な診療情報提供書を書くために
今回の執筆者
齊木 好美(川崎協同病院総合診療科)
監修 小坂鎮太郎,松村真司
(前回よりつづく)
|
CASE
COPD急性増悪で入院となった80歳男性(詳細は第2回・3301号参照)。自宅退院が決まり,退院後は近所の診療所に外来フォローを依頼することとなった。 |
フォローを依頼する外来担当医へケア移行をスマートに行うためには,適切な診療情報提供書の作成が必要です。では,どのような項目を診療情報提供書に記載すべきでしょうか。
今回は病棟担当医から外来担当医へ向けたケースを想定し,診療情報提供書における必要な項目と重要性を解説します。
診療情報提供書の役割とは
診療情報提供書は,さまざまなケア移行の場面における医師同士のコミュニケーションツールとして重要な役割を果たします。活用場面には,外来担当医から専門外来や高次医療機関への紹介,外来担当医への逆紹介などがあり,いずれの状況でも紹介先にとって必要な情報は何かを考える力が必要です。
日本では,外来担当医へ患者情報を提供するために診療情報提供書が利用され,院内の診療記録としては退院時要約が用いられる場合が一般的です。つまり,診療情報提供書は,医学的記録の意義よりも情報伝達の意義が重要視されるため,多忙な外来担当医を考慮し,簡潔かつ過不足なく記載する技量とその訓練が必要です。
一方,欧米では「退院時要約=診療情報提供書」として扱われ,外来担当医へ直接送付されることが一般的です。欧米の観察研究では,退院後の初回外来受診時に診療情報提供書を入手しているケースは12~34%と低く1),入手が遅れると再入院率が高くなって,有害事象が起こりやすくなるという報告もあります2)。にもかかわらず,記載内容の教育は不十分とされ,Legaultらの研究によると,卒後1年目の研修医が記載した診療情報提供書では,35.7%に退院時の処方内容に不正確な点が認められ,15.9%に処方変更理由の未記載があったとされています3)。
読み手の視点から考えると,診療情報提供書は構造的で簡潔な内容が好まれ,診断,予後,マネジメントに関する記載が重要視されます4)。そのためにも入院中の診断名や外来で必要なマネジメントを漏れなく記載できるフォーマットが必要です。特に高齢者のケア移行時には医学的な内容だけでなく,要介護度(申請状況も含む),退院時のADL,患者および患...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2025.12.09
-
寄稿 2026.01.13
-
2026.01.13
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。