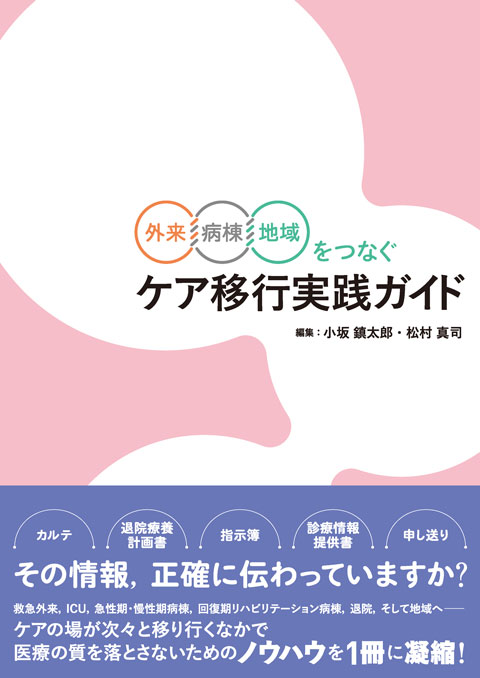効果的で根拠のある指示伝達(本橋健史)
連載
2019.02.11
スマートなケア移行で行こう!
Let's start smart Transition of Care!
医療の分業化と細分化が進み,一人の患者に複数のケア提供者,療養の場がかかわることが一般的になっています。本連載では,ケア移行(Transition of Care)を安全かつ効率的に進めるための工夫を実践的に紹介します。
[第4回]効果的で根拠のある指示伝達
今回の執筆者
本橋 健史(練馬光が丘病院総合診療科)
監修 小坂鎮太郎,松村真司
(前回よりつづく)
|
CASE
COPD急性増悪で入院となった80歳男性(詳細は第2回〔3301号〕を参照)。 |
カルテ記載(前回〔3305号〕)に続き,入院時指示を出さなければなりません。重症化の危険性やCOPDという疾患の特性を考慮した指示を出す必要があります。より良いケアにつながる指示とはどのようなものでしょうか。
指示簿の役割とは
指示簿は医師から看護師をはじめとした多職種への診療補助・処置・ケア内容の伝達手段として利用されます。指示は一般指示,処方指示,注射指示に大別され,いずれも患者ケアに大きく関与するため,根拠に基づいた上で施設ごとのルールを多職種で話し合い,内容を決めることが重要です。
医師から看護師への指示については保健師助産師看護師法第37条に規定があり,看護師が患者の状態に応じて柔軟に対応できるような「包括的指示」も可能と解釈されています1)。包括的指示とは,対応可能な患者・病態変化の範囲を明確にし,看護師が理解し得る内容であることなどの要件を満たした上で,看護師が実施すべき行為を一括して指示することです。
また,薬剤師への薬物血中濃度測定や内服・吸入コンプライアンス確認の指示,リハビリテーションスタッフへの疾患安定度を踏まえた活動度調整の指示など,職種ごとの指示内容を共有することが重要です。
スムーズなケア移行のためには,入院が決まった段階で入院時記録と指示簿を速やかに記載する必要があります。指示漏れを防ぐために,内容と手順を決めておくとよいでしょう。「ADC VAN DISMAL」という有名な覚え方2)に沿って,本症例の入院時指示の一部を示したのが図です。
|
|
| 図 「ADC VAN DISMAL」に沿った入院時指示の例(クリックで拡大) |
正しく伝えるための工夫
医師は指示内容を自由記載できるため,曖昧な表現による看護師への伝達エラーがしばしば見受けられます3)。状態変化が早い急性期では指示内容が頻繁に変わり,二重指示受けの発生による伝達エラーのリスクを伴います。指示内容は曖昧な表現を避け,変更の際は指示受け担当者に変更内容を伝えると同時に,古い指示を迅速に削除するべきです。特に病棟や診療科の移行の際に,Code Statusやアレルギーなどの情報が誤伝達しないよう,共有の掲示板や電子カルテのフロントページのようなわかりやすい場所に記載するなどの工夫が必要です。
「包括的指示」の実施に当...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。