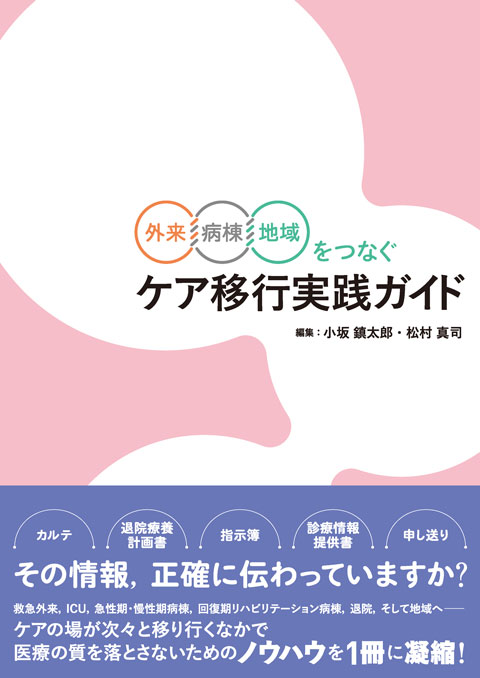症例共有と臨床教育のための症例プレゼンテーション(本田優希)
連載
2019.03.11
スマートなケア移行で行こう!
Let's start smart Transition of Care!
医療の分業化と細分化が進み,一人の患者に複数のケア提供者,療養の場がかかわることが一般的になっています。本連載では,ケア移行(Transition of Care)を安全かつ効率的に進めるための工夫を実践的に紹介します。
[第5回]症例共有と臨床教育のための症例プレゼンテーション
今回の執筆者
本田 優希(獨協医科大学病院総合診療科)
監修 小坂鎮太郎,松村真司
(前回よりつづく)
CASECOPD急性増悪で入院となった80歳男性(詳細は第2回・3301号参照)。 |
入院時のカルテ記載(第3回・3305号),指示簿の記載(第4回・3309号)を終えると,次はカンファレンスで診療科のスタッフと情報を共有することが必要です。プレゼンテーションにはどのような工夫をすべきでしょうか。
プレゼンはケア移行のキモ
症例プレゼンテーション(以下,プレゼン)は,入院担当チーム内でのカンファレンスや病棟回診,担当や勤務の引き継ぎ時の申し送り,コンサルテーションなど,日常の病棟診療におけるケア移行で頻繁に行われる,症例共有の必須技能です。医師―医師,看護師―医師間を中心に,多職種連携の技能としても重要です。
また,プレゼンは臨床教育のツールとしても重要な役割を果たしています。プレゼンターはプレゼン準備を通じて学習の機会となり,指導医はプレゼンによる研修医評価を通じて自己の指導の振り返りにもなるのです1)。
米国では,内科臨床実習(Bed Side Learning;BSL)において指導医が最も重視する能力がプレゼン能力です2)。本邦でも,2020年度から開始される臨床実習後OSCE(Post-CC OSCE)の課題にプレゼンが組み込まれ,卒前教育においても重視されています。しかしながら本邦ではその教育や評価の手法は確立されておらず,学習の機会がなかなかないのが現状です。
良いプレゼンのための「伝え方」と「内容」
プレゼンを構成する要素は,伝え方(デリバリー)と内容(コンテンツ)の2つです。
伝え方において意識するのは,速度,声調・声量,間合い,視線・表情,姿勢・身振り,時間の6つです。いかに論理的で明快な内容であっても,小声・早口で視線を合わせず話しては聞き手には伝わりません。
内容は,①一文サマリー,②病歴(Subjective data),③身体・検査所見(Objective data),④アセスメント(Assessment),⑤プラン(Plan)の5つに分類できます。
次に,本症例でのプレゼン例と,その要点を解説します。
①一文サマリー
| 【例】病院受診歴のない重喫煙者の80歳男性で,3日前から出現し徐々に増悪する発熱,咳嗽,膿性痰,呼吸困難を主訴に救急搬送されました。 |
【解説】一文サマリーとは,プレゼンの冒頭で患者ID(Identifying Data:年齢や性別といった基本情報),主訴とその持続期間,関連する既往歴などをまとめて述べる導入部分のこと。この部分はプレゼンを決定的に方向付けます。本症例では,肺炎,COPD急性増悪の診断につながるよう,COPDに関連する重喫煙歴を盛り込みます。
②病歴(S),③身体・検査所見(O)
|
【例】来院2か月前から100 m程度の歩行で息切れが出現するようになっていました。3日前から咳嗽が出現し,2日前から発熱と黄色痰を伴うようになり,今朝から呼吸困難も加わったため救急搬送されました。悪寒戦慄や夜間呼吸困難,起坐呼吸,浮腫はありませんでした。医療機関受診歴や健診受診のない方で,既往歴や常用薬は特にありません。喫煙者で,40本/日,50年間の重喫煙歴があります。
バイタルサインは,体温38.8℃,血圧140/9 |
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。