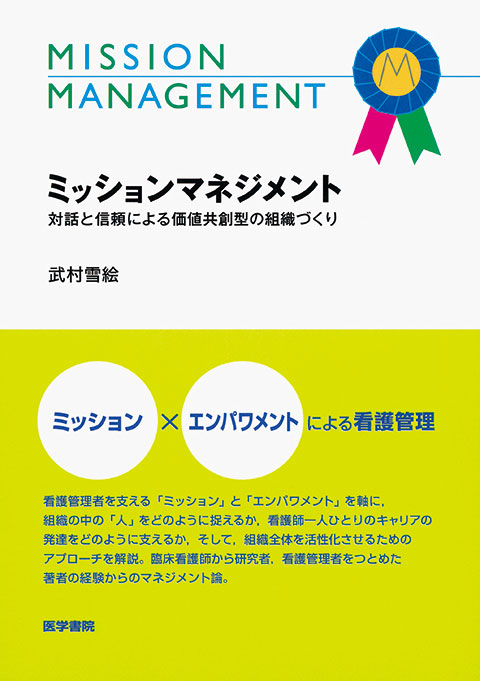組織ルーティンの学習(2)(武村雪絵)
連載
2011.07.25
看護師のキャリア発達支援
組織と個人,2つの未来をみつめて
【第4回】
組織ルーティンの学習(2)
武村雪絵(東京大学医科学研究所附属病院看護部長)
(前回よりつづく)
多くの看護師は,何らかの組織に所属して働いています。組織には日常的に繰り返される行動パターンがあり,その組織の知恵,文化,価値観として,構成員が変わっても継承されていきます。そのような組織の日常(ルーティン)は看護の質を保証する一方で,仕事に境界,限界をつくります。組織には変化が必要です。そして,変化をもたらすのは,時に組織の構成員です。本連載では,新しく組織に加わった看護師が組織の一員になる過程,組織の日常を越える過程に注目し,看護師のキャリア発達支援について考えます。
前回,新人,経験者を問わず,新しく病棟に配属された看護師は最初に,「組織ルーティンの学習」を経験すると述べた。この変化によって,看護師はその病棟で通常起こる出来事に対応する力,効率よくタスクを遂行する力を獲得できる。では,どのような要素が「組織ルーティンの学習」を促すのだろうか。
組織ルーティンの学習の促進要素
組織ルーティン,すなわち同じ局面でその病棟の大半の看護師がとる行動パターンは,その病棟で有効に機能している組織ルールが可視化されたものである。看護師は,組織ルールに従うことでうまくいったり,逆に組織ルールを守れず失敗する経験によって,組織ルールの有効性を実感し,「組織ルーティンの学習」にいっそう励むようになった。しかしその前から,自ら学習に集中する態勢を作り出していた。
◆チームの一員になりたい
新しく病棟に配属された看護師は異口同音に,「早く自分の仕事をきちんとできるようになりたい」「迷惑をかけないようになりたい」「少しは役に立つと思ってもらえるようになりたい」などと話した。チームの一員として役割を果たしたい,認められたいという思いは,組織ルーティンを学習する強い動機となっていた。逆に,チームの一員になることに魅力を感じられない場合には組織ルーティンの学習が進まず,退職に至ることさえあった。
| 経験者:ここにいたら,自分も先輩たちみたいになっちゃうんじゃないかって。なっちゃったら嫌だなって思って。 |
◆疑問と葛藤の処理
新人は,学校で学んだルールと異なっていても,現場の「生きたルール」として組織ルールを葛藤なく受け入れる傾向があった。
| 新人看護師:学生のころは,患者さんの話を親身になって聞くってことをすごく強調されたけど,人が生きる上で一番大事なのはやっぱり命だから。今優先するのは,点滴とか,検査とか,あと,リハビリ。リハビリも退院に向けて大事なんで。本当は親身になって話を聞ければいいのかなとは思うんですけど。 |
基礎教育で学んだルールが破棄されたわけではなく,新しい価値観や行動規範を学ぶことに集中し,過去に学んだルールの影響力が極端に弱まっている状態だと考えられた。また,違和感のある組織ルーティンを自分なりに理由をつけて正当化することで,そのルールに従う葛藤を解消しようとしていた。それでも解消できない葛藤は,組織ルーティンの中で解決方法を探していた。
フィールドワークでこんな場面があった。ある新人が,受け持ち患者がシーツに及ぶ便失禁をしたため,先輩看護師とその処理をしていた。お尻拭きで便を拭き取っていたが,軟便が臀部や大腿まで付着しており,1パック使い終わっても,まだきれいにならなかった。2人の看護師は「洗わ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。