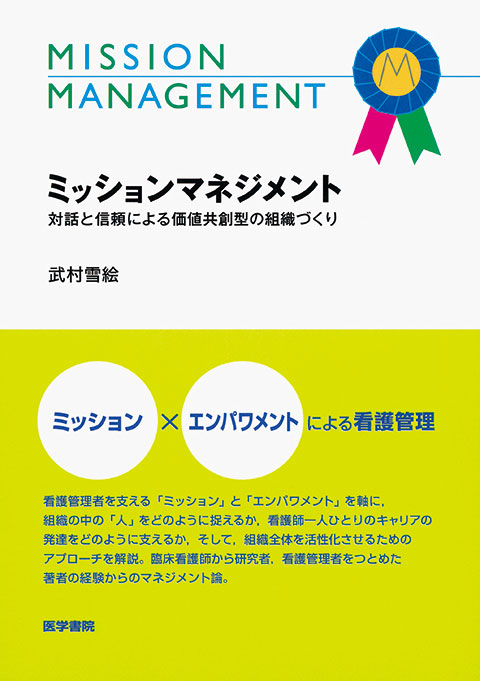組織ルーティンを超える行動化(1)(武村雪絵)
連載
2011.08.29
看護師のキャリア発達支援
組織と個人,2つの未来をみつめて
【第5回】
組織ルーティンを超える行動化(1)
武村雪絵(東京大学医科学研究所附属病院看護部長)
(前回よりつづく)
多くの看護師は,何らかの組織に所属して働いています。組織には日常的に繰り返される行動パターンがあり,その組織の知恵,文化,価値観として,構成員が変わっても継承されていきます。そのような組織の日常(ルーティン)は看護の質を保証する一方で,仕事に境界,限界をつくります。組織には変化が必要です。そして,変化をもたらすのは,時に組織の構成員です。本連載では,新しく組織に加わった看護師が組織の一員になる過程,組織の日常を越える過程に注目し,看護師のキャリア発達支援について考えます。
組織ルーティンを超える行動化
「組織ルーティンを超える行動化」は,「組織ルーティンの学習」がある程度進んだ看護師の一部にみられる変化である。組織ルーティンの範囲では,教育や前職場,あるいは自らの経験から大切だと思っている固有ルールを実行できないと感じた看護師が,組織ルーティンを超える実践を始めることを指す(図)。
| 図 「組織ルーティンを超える行動化」のイメージ ↑色アミ部分は「実践のレパートリー」,すなわち当該看護師によって実行され得るルール(存在を認識し習得できた組織ルールと,無効化されていない固有ルール)を表す。矢印は実践のレパートリーが主に拡大している方向を表す。なお,組織ルール・固有ルールとも変化するが,簡略化するため図示していない。 |
前回,「組織ルーティンの学習」は,組織ルーティンへの疑問を保留し,葛藤を処理しながら進められると述べた。組織ルーティンを超える行動化は,この疑問や葛藤が原動力になる。組織ルーティン,すなわち病棟の大半の看護師が疑問を持たずに繰り返している行動パターンに強い疑問を感じる状態,あるいは,組織ルーティンに従うために自分が大切に思う実践ができないという強い葛藤が続いた後,決意して,組織ルーティンから一歩踏み出す行動が実行される。そのため,組織ルーティンを超える行動化は,看護師自身も仕事の仕方の変化として記憶していることが多い。
組織ルーティンから大きく外れないような小さな行動から始め,結果を確認し自信を深めると,次第に明らかに組織ルーティンを超える実践が継続して行われるようになる。やがてそれが,その看護師固有の実践スタイルとなっていく。事例をいくつか紹介したい。
新人看護師の例
新人は,現場の生きたルールとして組織ルーティンを素直に受け入れる傾向があることは前回述べた。しかし,仕事に慣れたころに,保留した疑問や葛藤を再認識することがあった。
新人看護師のAさんは,尊敬している先輩看護師のことを,他の看護師なら慌しくタスクに追われる消灯前に,「今夜,寒くなりそうだから」と,自分で訴えられない患者へ毛布を持っていくなど,「見えないところ,記録に残らないところ,基本的な看護を当たり前のように行っていて,すごいなぁって思う」と話した。Aさん自身は,割り当てられたタスクを遂行するのに精一杯で,自己嫌悪に陥ることも多かったという。
| Aさん:やっぱり自分の仕事のペースを優先しがちなんです。患者さんに話しかけられても,あと何人検温が残っているとか,何時までにこれやらなきゃとか,そっちが気になって,中途半端に話を聞いたり。そんな自分が嫌だなって。 |
しかし,2年目になると,同じ場面で,時間どおりにタスクをすることを“あきらめられる”ようになり,気持ちを切り替え,患者の話に集中するといった,ささやかな変化を起こした。そして,1年半後,3年目を終...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。