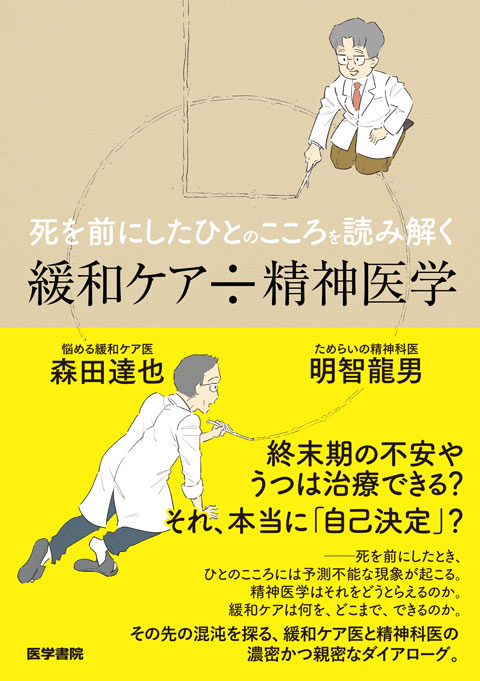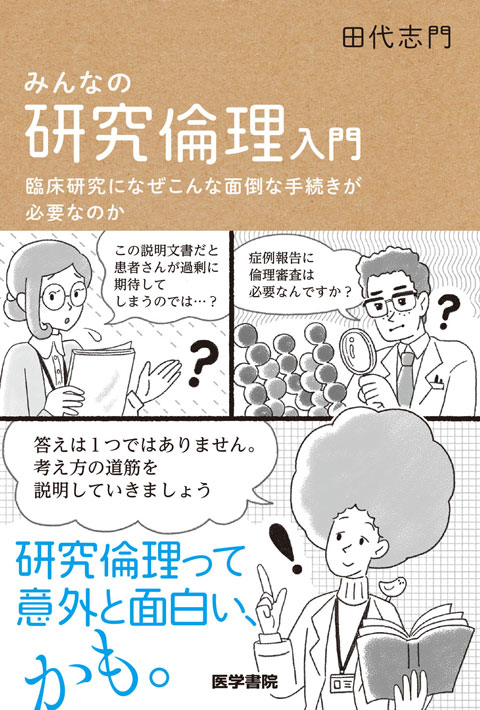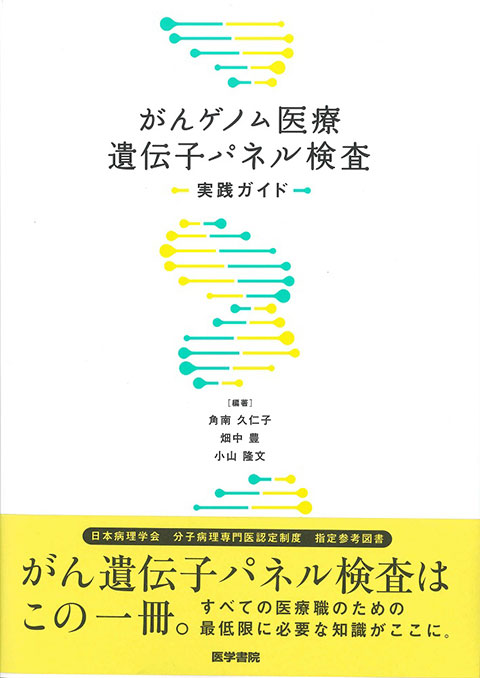- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2025年
- 医学界新聞プラス 第30回日本緩和医療学会学術大会開催
医学界新聞プラス
第30回日本緩和医療学会学術大会開催
取材記事
2025.08.05
第30回日本緩和医療学会学術大会(学術大会長=大阪歯科大学・田村恵子氏:右写真 )が7月4~5日,「緩和医療――生老病死を慈しむ」をテーマに福岡国際会議場(福岡市),他で開催された。
『医学界新聞プラス』では,治療の進歩に揺れる患者・家族の意思決定支援と,緩和ケアの新たな役割を議論したパネルディスカッション「がん治療の進歩を専門的緩和ケアはどのように受け止めるか」(座長=福井大学医学部附属病院・廣野靖夫氏)と,および医学書院が主催したスイーツセミナー「緩和ケア臨床のもやもやを考える:緩和ケア×倫理×社会学の視点から」(座長=しんじょう医院・新城拓也氏)の模様を報告する。
◆治療の進歩とともに歩む緩和ケア──がん医療の複雑化にどう向き合うか
がん治療の進歩は目覚ましく,外科治療,放射線治療,化学療法に加えて,分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬の登場,そしてゲノム医療の発展など,治療選択肢の多様化がますます進んでいる。これらの治療選択肢が発展する一方でがんによる苦痛の緩和においても支持療法や副作用の少ない薬剤の開発が進み,積極的治療の長期継続も可能なケースが増加してきた。
しかし,こうした変化により,患者や家族にとって積極的な治療を継続する選択肢は,ますます手放しがたいものになっていることも事実だ。複雑化するがん医療の中で治療と緩和ケアの関係はどうあるべきか。またその中で求められる医療者の新たな役割について,医師・看護師の視点から発表が行われた。
初めに登壇したのは富山大学附属病院にて腫瘍内科・緩和ケア内科を担当する梶浦新也氏である。がん治療医の視点からゲノム医療の意義の大きさに言及する一方で,緩和ケア医の視点からはさまざまな課題が見えてきたと語る。とりわけ氏が懸念するのは,緩和ケア導入の遅れだ。標準治療の選択肢が尽きたタイミングでゲノム医療の相談が始まることが一般的であるものの,化学療法中止の判断が遅れ,結果として緩和ケアの導入が後手に回るケースがある。また,ゲノム医療を選択したとしても,がん遺伝子パネル検査の結果を経て実際に治療にたどり着けるのは1割程度1)とされ,検査の結果を待つ間に体調が悪化し治療に至らないケースや,検査を経て「治療薬が見つかるだろう」と期待を抱き続ける患者へのケアも必要だと訴える。こうした課題に対し緩和ケアを適切に導入するには,心理的背景への配慮が不可欠だと主張。氏が提案するのは,がんゲノム外来に緩和ケアの要素を組み込む仕組みづくりだ。これは,化学療法を希望する患者が緩和ケア外来に足を運ぶことは少ないものの,がんゲノム外来であれば治療への希望を抱いて前向きに受診してくれるケースが多いためである。「前向きな受診を緩和ケアにつなげていく仕組みづくりをしていきたい」と述べ,がんゲノム外来と連動した早期からの緩和ケア導入を呼びかけた。
治療の進歩により,患者が亡くなる直前まで薬物療法を継続できるようになった今,緩和ケアへの移行や療養場所の選択は一層難しくなっている。久永貴之氏(筑波メディカルセンター病院)は,そうした状況下で緩和医療専門医の役割もまた変化していると語る。具体的には,主治医と連携しながら治療の目標を明確にしつつ,患者・家族の価値観を踏まえ適切なタイミングで緩和ケアへの移行を促す役割,そしてチーム医療の統率,職種間コミュニケーションの促進,地域資源の活用などの連携・調整を行う役割だ。進化するがん治療に対応できるよう,自身も策定に関わる緩和医療専門医の研修カリキュラムの改訂を継続的に進めていくと述べた。
最後に登壇した九州がんセンターの北川善子氏は,がん医療が高度化・専門化する中で現場に潜む葛藤について看護師の視点から発表を行った。治療の選択肢が増えたことで患者は“正解のない選択”に迷い,かつ患者・家族・医療者の目が治療効果に向いており,患者の生活・価値観は置き去りになりがちな現状に言及した。緩和ケアは治療終了後ではなく,“治療の最中”でこそ力を発揮するため,治療の過程で揺れる心や迷い,苦悩といった超全人的な側面にかかわり続けるケアが必要となる。がん患者への支援の焦点は「決定させる」ことではなく,「迷いに寄り添う」ことであり,疾患だけでなく,その人の生活・家族・人生と向き合う力が看護にはあると強調し,発表を終えた。
◆ACPの「もやもや」を見つめる
1日目に開催された医学書院主催のスイーツセミナー「緩和ケア臨床のもやもやを考える:緩和ケア×倫理×社会学の視点から」には約500人が参加し,患者・家族の意向が一致しないケースや,もう一歩患者に踏み込むべきか医療者が悩む場面に焦点が当てられ,議論が展開された。
緩和ケア医である森田達也氏(聖隷三方原病院)は,ACP(Advanced Care Planing)という言葉を用いずとも,日々のかかわりの中で患者の今の病識を自然に把握し,患者が病状に関して腑に落ちたタイミングを逃さず介入する姿勢が重要とする。「医療者側の心残りを解消するために患者の今をおろそかにしてはならない」と語り,何より患者が今話したいこと,考えていることに寄り添うケアの原点をあらためて提示した。
社会学・倫理学の専門家である田代志門氏(東北大学)は,時間を直線としてとらえ,未来から逆算して時間を無駄に使わないようにする一般的な時間感覚では,患者の今を置き去りにしてしまう危険性を指摘する。「少し先に起こることを推測できる医療者だからこそ,患者の最後の機会を大切にしたいとの思いは理解できるが,それをACPの名の下に業務として機械的に行うのは危うい」とし,死に向かう人の時間意識を想像することの重要性を訴えた。
講演後のディスカッションでは,介入のタイミングや,患者にとって“ちょうどよい”介入の在り方について,活発な意見交換がなされた。
登壇者 左から田代志門氏,森田達也氏,新城拓也氏
参考文献・URL
タグキーワード
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。