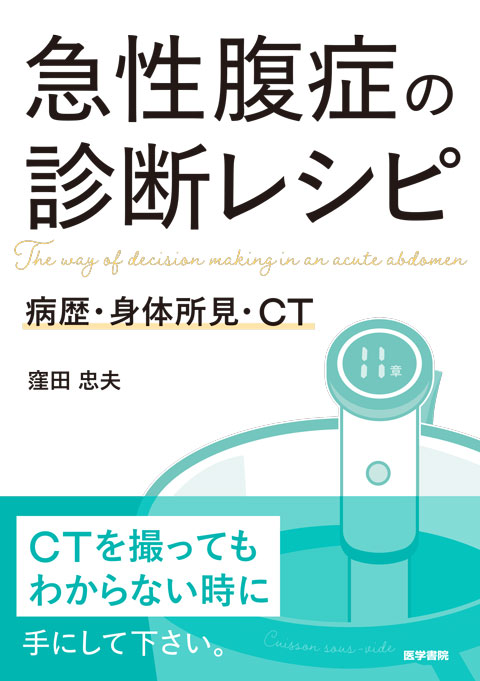- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2025年
- 医学界新聞プラス [第4回]機能性ディスペプシア 後編
医学界新聞プラス
[第4回]機能性ディスペプシア 後編
『集中講義! おなかの身体診察――フィジカル&腹診で腹部症状に立ち向かえ』より
連載 中野 弘康
2025.04.30
集中講義! おなかの身体診察
フィジカル&腹診で腹部症状に立ち向かえ
「急性腹痛の患者さんが来た! でも、CTが使えない! どうしよう…」、「慢性腹痛の患者さんか。不定愁訴の診療は苦手なんだよな…」。腹痛診療に苦手意識を持っている方は多いのではないでしょうか。でも、大丈夫、ローテクな身体診察でバッチリ対応できるんです! 急性腹痛にはフィジカル、慢性腹痛には腹診で対処しましょう。新刊『集中講義! おなかの身体診察――フィジカル&腹診で腹部症状に立ち向かえ患者さんのおなかのトラブルに立ち向かう』では、患者さんの話す“病歴”に興味をもち、“病歴”から病態を想像してフォーカスを絞った、“きりっとした身体診察”のエッセンスをご紹介します。あなたの日常診療にきっと役立つ集中講義が開講です。
「医学界新聞プラス」では、本書より「虫垂炎」と「機能性ディスペプシア」の2症例をピックアップし、ご紹介していきます。
([第3回] 機能性ディスペプシア 前編 はこちらから)
漢方方剤のアプローチ
胃内停水+心下痞硬は脾胃の機能低下が示唆される所見であり,西洋医学的には,機能性ディスペプシア(functional dyspepsia;FD)を考える病態です。めまいが主訴ですが,食欲不振と腹診の結果からは,脾胃の機能を改善させる必要があると考えました。脾虚に対する治療介入が,頭痛の改善につながるのではないかと考えたのです。
ここで,治療方剤を選択する際に,私が実践している治療法をご紹介します。漢方薬によるprobing technique(探りを入れる方法)で,松田正先生に教えていただきました。これは松田先生の著書『急性疾患にすぐ効く“特選”漢方薬』(日経メディカル)でも紹介されています1)。漢方薬を外来や救急室で使用し,その薬効の有無をもって診断の一助とする使い方で,各疾患の早期診断に役立てるというものです。
たとえば頭痛で来院した患者さんを例にとってみましょう。頭部CTを撮像してくも膜下出血がないか確認できればよいですが,実地医家の場合は画像検査へのアクセスは不良です。そのような場合,待合中に漢方薬を投与して(漢方薬で探りを入れる=probing),効果があれば漢方薬を継続することで治療が完結でき,重篤な疾患が隠れている可能性は低いと判断します。一方,効果がなければ,次の検査に進んだり,さらなる精査のために高次医療機関に紹介したりする流れです。治療的診断が可能で,かつ患者さんの苦痛をできるだけ早い段階で取り除くことが可能となるので,患者さん本位の治療が可能になると松田先生は述べています。
本症例では,probing techniqueとして,スルピリド+六君子湯を内服させて外来のベッドで寝て効果を確かめることとしました。六君子湯は脾虚でFDの治療の第一選択薬ですが,スルピリドを加えることで,六君子湯の効果を高めることができます(この治療法は松田先生とその師匠の大野修嗣先生に教わりました)。
probing technique(六君子湯+スルピリドの内服)を施行し,外来の処置室で休んでもらい,1時間後に様子を見に行くと,すやすやと気持ちよさそうに寝ていました。そして2時間後,元気になった患者さんが言った言葉です。
- “私最近生理がつらかったんです……”
- “生理前とか気圧が下がるときは決まって頭痛で出勤するのもものすごくしんどかったんです”
その後の経過
脾虚,血虚,水毒体質で,西洋医学的にはFD,片頭痛と診断し,スルピリド,六君子湯を処方し,頭痛には頓用で五苓散+呉茱萸湯を処方しました。鍼灸の親和性も良好と思われたため,鍼灸師を紹介しました。
2週間後の外来で,嘔気,めまい,頭痛は消失しました。1か月後の外来では,晴れ晴れとした表情で以下のように報告してくれました(報告してくれたことばをそのまま転記しています)。
- “頭痛がめっきり減りました!……”
- “生理前のイライラもないですし,ふわふわするめまいとか耳鳴りも最近自覚していません”
- “生活がガラッと変わって楽になりました”
症例の考察
本症例は,めまいで受診した患者さんです。西洋フィジカルでは,明確な診断名や治療方法が浮かびませんでしたが,漢方フィジカルを併用したことで,四肢の冷え,心窩部の冷え,心下痞硬,心窩部振水音などの腹診所見が得られ,脾虚,血虚,水毒と判明しました。脾虚を改善させる漢方薬+西洋薬を導入し,頓用で頭痛に対する五苓散+呉茱萸湯の併用を行ったことで,体質改善を図ることができ,めまいの改善のみならず,頭痛や胃の不調もすべて解決に至った症例でした。
その後は当帰芍薬散の定時内服に移行し,月経前症候群などに悩まされることも減り,看護師として現在も元気に仕事に励んでいます。
さらにひとこと。筆者の外来を訪れる数日前に内科医からロキソプロフェンナトリウム水和物が処方されていました。ロキソプロフェンナトリウム水和物は素晴らしい鎮痛薬ですが,その薬理作用から,体を冷やしてしまう危険性があり,そもそも冷え性の強い患者さんに投与すると病態を悪化させるリスクがあります2)。西洋医はロキソプロフェンナトリウム水和物を多用する傾向にありますが,漢方的には体を冷やす薬剤として,陰虚の患者さんには処方を控えたほうが望ましいといわれています。体の冷えを認識し,適切な漢方を処方することの大切さが伝われば幸いです。
- 文献
- 1) 松田正:急性疾患にすぐ効く“特選”漢方薬.日経メディカル,2023
- 2) 織部和宏:漢方事始め.日本医学出版,1997
集中講義! おなかの身体診察
フィジカル&腹診で腹部症状に立ち向かえ
フィジカル×漢方アプローチの二刀流でおなかのトラブルに立ち向かえ!
<内容紹介>
「急性腹痛の患者さんが来た! でも、CTが使えない! どうしよう…」、「慢性腹痛の患者さんか。不定愁訴の診療は苦手なんだよな…」。腹痛診療に苦手意識を持っている方は多いのではないでしょうか。でも、大丈夫、ローテクな身体診察でバッチリ対応できるんです! 急性腹痛にはフィジカル、慢性腹痛には腹診で対処しましょう。患者さんのおなかのトラブルに立ち向かうあなたのための集中講義が開講です。
目次はこちらから
タグキーワード
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

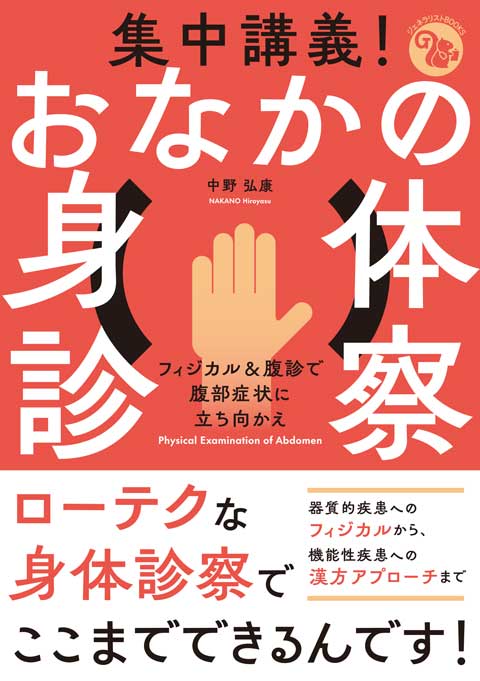
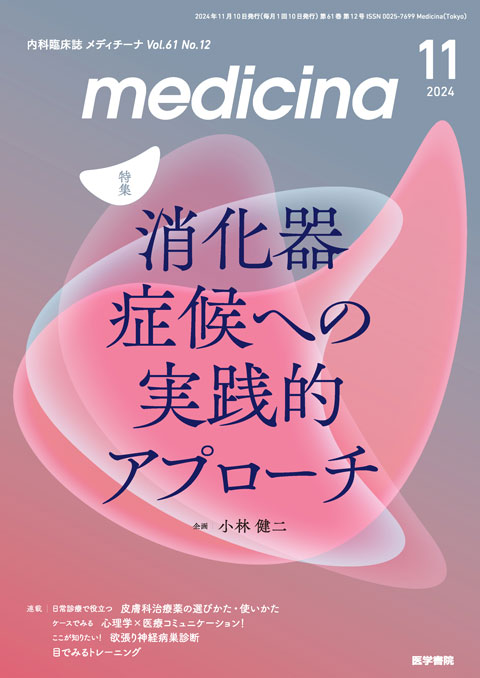
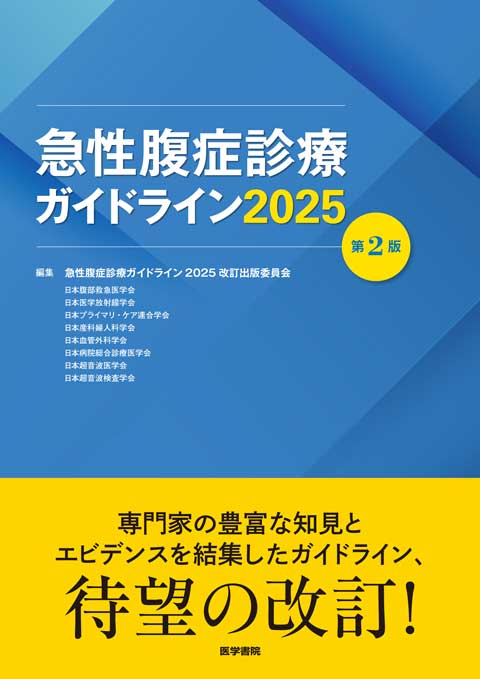
![救急超音波診療ガイド[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/1017/0063/3188/113479.jpg)