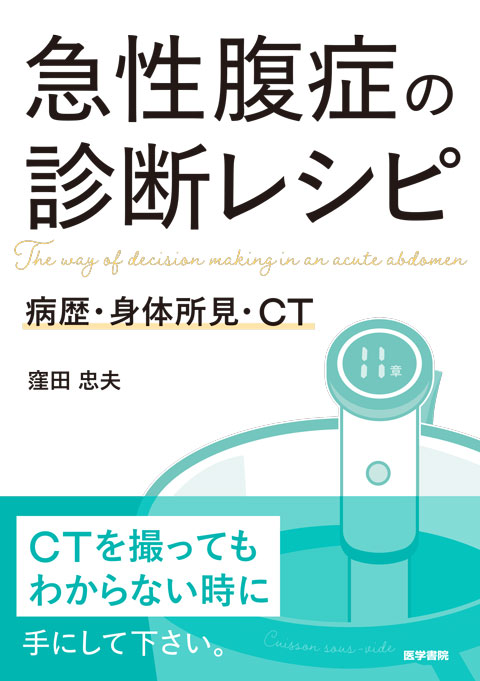集中講義! おなかの身体診察
フィジカル&腹診で腹部症状に立ち向かえ
フィジカル×漢方アプローチの二刀流でおなかのトラブルに立ち向かえ!
もっと見る
「急性腹痛の患者さんが来た! でも、CTが使えない! どうしよう…」、「慢性腹痛の患者さんか。不定愁訴の診療は苦手なんだよな…」。腹痛診療に苦手意識を持っている方は多いのではないでしょうか。でも、大丈夫、ローテクな身体診察でバッチリ対応できるんです! 急性腹痛にはフィジカル、慢性腹痛には腹診で対処しましょう。患者さんのおなかのトラブルに立ち向かうあなたのための集中講義が開講です。
| シリーズ | ジェネラリストBOOKS |
|---|---|
| 著 | 中野 弘康 |
| 発行 | 2025年03月判型:A5頁:240 |
| ISBN | 978-4-260-05786-8 |
| 定価 | 4,950円 (本体4,500円+税) |
更新情報
-
正誤表を更新しました
2025.04.07
-
正誤表を掲載しました
2025.04.01
-
【2025年3月12日開催終了】本書に関連したWebセミナーを開催しました
2025.03.13
- 序文
- 目次
- 書評
- 正誤表
序文
開く
序
おなかのトラブルを訴えて病院を受診する患者さんはとても多いです。トラブルと一口にいっても,“おなかが痛い”“おなかが腫れてきた”など,訴えはさまざまです。そんな患者さんを前に,私たちは患者さんから話を聞き,“なぜその症状が出るのだろう?”と病態生理を考えつつ,患者さんの苦しみに寄り添い,おなかを触りながらつらいところに手を当てて解決するための方法を考えます。おなかのトラブルに悩む患者さんにとって,病歴と身体診察の果たす役割がいかに大きいか……,本書を執筆しようと思ったきっかけはここにあります。
でも,みなさん,普段,どのくらい病歴と身体診察を意識して診療していますか?
医学生のころから病歴と身体診察の重要性は散々教わるはずですが,学生の間は生身の患者さんを診る機会がほとんどないので実感がわきません。医師免許を取得して現場に投入されても,目の前の所見がどんな意味をもつのかわからなければ,なんとなく惰性で病歴を聞いて診察もそこそこに画像検査(超音波検査やCT)へ……といったプラクティスを行ってしまう。これは決して珍しいことではないと思います。全国津々浦々の臨床研修病院で,悶々としている若手医師の方々は多いのではないでしょうか。
私が研修を受けた大船中央病院には,病歴や身体診察を重視する文化がありました。私が身体診察にのめりこむきっかけとなったのは須藤 博先生の存在が大きいと思います。彼は自分自身のことを古きよき時代の内科医(old fashioned Dr)と言っていました1)。古きよき時代というのは,まだ臨床現場にCTなどの診断機器が十分にない時代に患者さんを診療していた内科医のことです。今のように画像検査にeasyにアクセスできなかった時代の医師は,患者さんの悩みを何とか解決しようと五感をフルに使って診察していたことでしょう。須藤先生はベッドサイドラーニングをとても重視していました。患者さんの話をよく聞き,頭からつま先に至るまで観察を逃しませんでした。彼から教わった口伝の数々がクリニカル・パールとして私の脳裏に刻まれています。本書では,症例を通じて紙面が許す限りパールを紹介しています。ぜひみなさまの日常診療にお役立てください。
患者さんの話す“病歴”に興味をもち,“病歴”から病態を想像してフォーカスを絞った,“きりっとした身体診察”を行う。この一連の楽しさが本書を通じて伝われば嬉しく思います。
本書は,私がこれまで出会った患者さんを紹介しながら,私の思考過程と診察所見をつぶさに記録し1冊にまとめたものです。本書前半の第1章「西洋フィジカル」は,雑誌「medicina」の連載「ローテクでもここまでできる! おなかのフィジカル診断塾」(59巻5号~60巻12号)の内容をベースに大幅に加筆修正しました。また,この間,COVID-19後遺症で悩む患者さんを多数診療する機会があり,その経験から東洋医学的な考え方を日常診療に取り入れることの大切さを身に染みて感じました。第2章「漢方フィジカル」では,機能性消化管障害を中心として,おなかの症状で悩む患者さんに,日本漢方独特の診察である腹診を応用し,その有効性を示しました。本書をお読みいただけば,腹部疾患に対して西洋と東洋のハイブリッドアプローチが可能になることでしょう。ぜひ本書を有効活用していただき,おなかのトラブルで悩む患者さんを救うための一助にしていただければこれ以上の喜びはありません。
最後に謝辞を述べたいと思います。第1章「西洋フィジカル」では,須藤 博先生(大船中央病院)に動画をご提供いただきました。須藤先生の身体診察への好奇心と飽くなき探求心を尊敬しています。第2章「漢方フィジカル」では,吉永 亮先生(飯塚病院漢方診療科)に腹診の画像を提供していただきました。吉永 亮先生とご縁ができたのは,医学書院「総合診療」編集室の山内 梢氏のお陰です。また,本書の発行にあたっては,医学書籍編集部の天野貴洋氏に大変お世話になりました。この本が日の目を見ることができたのは,天野氏のお陰です。この場を借りて厚く御礼申し上げます。
最後に,日々出会う患者さんとそのご家族様とのご縁に感謝します。そして本書を手に取っていただいた読者のみなさまとの出会いにも感謝します。本書を通じて,少しでも私の臨床に対する思いが伝われば幸いです。
1)須藤博:医学古書を紐解く11(最終回)Old-Fashioned Doctorからの助言──Fred HL.『Looking Back(and Forth);Reflections of an Old-Fashioned Doctor』. medicina 60:2176-2177, 2023
2025年1月
中野弘康
目次
開く
序
総論
フィジカル&腹診術への誘い
第1章 西洋フィジカル
おなかが痛い
虫垂炎──身体診察で虫垂の位置を当てる!
家族性地中海熱──虫垂炎にみえて虫垂炎ではない病気──画像診断を鵜呑みにするな!
前皮神経絞扼症候群──画像検査で異常がみつからない腹痛
急性膵炎──おなかの“やけど”
急性胆囊炎──Murphy signだけじゃない!
腹腔動脈解離──おなかの音を聴きに行け!
脾破裂──デルマトームを意識して痛みの発生部位を把握しよう!
正中弓状靱帯圧迫症候群──身体の静かなる音に耳を傾けよう!
消化管穿孔──正常肝濁音界を習得すべし!
おなかが膨満している
尿閉──真横からおなかを見てみよう
腸閉塞──おなかの表面をじっと見てみよう!
肝囊胞──腹部膨満+αの症状に注目
腹水──病歴と視診・打診から腹水貯留をみつけよう
肝硬変──多彩な身体所見を押さえよう
腎動脈狭窄症──非消化器疾患でも常におなかの身体所見にこだわるべし
舌を見よう
巨舌──巨大な舌の背後に隠れた疾患は?
ピリピリする舌──病歴聴取+舌の診察で鑑別疾患の幅が広がる!
尿の色を見よう
黄疸──尿の色から病態を予想しよう!
便の色を見よう
消化管出血──マグロにこだわりすぎた男性
第2章 漢方フィジカル
機能性疾患は腹診でみよう
漢方フィジカル──望診,問診,腹診に挑戦してみよう
機能性ディスペプシア──血虚
月経困難症・過敏性腸症候群──血虚
過敏性腸症候群──脾虚
慢性便秘症──瘀血
慢性便秘症・精神不安──瘀血
索引
コラム
急性腹痛の患者さんでは問診と並行して必ずバイタルサインを評価しよう
飲酒量の尋ねかた
病歴聴取ではwhatよりwhyを重視しよう
女性のアルコール性肝硬変
漢方を取り入れたきっかけ──患者さんのつらい症状の背景に思いを馳せる
漢方の使いかた──general appearanceと漢方
不定愁訴に隠れた貧血に介入する
Calling,縁を大切に,一例一例を大切に
書評
開く
五感をフルに活用して診察することで,おなかの異常の本質に迫る
書評者:野々垣 浩二(大同病院院長)
医師の仕事は「Calling-天職」と著者は語る。私たち医師は,自分の仕事を「天職」と自信を持って語ることができるだろうか? 本書からは,著者の強い使命感と,「自分がやらなければならない」という強い覚悟が,ひしひしと伝わってくる。この本は,単なる診察マニュアルではなく,内科医としての著者自身の物語が込められた一冊である。
著者は,西洋医学と東洋医学を融合させて診療を,極めて丁寧に言語化している。宗教でも,医学でも,どちらが優れているかではなく,重要なのはバランスである。西洋医学と東洋医学のハイブリッドアプローチの価値を,この本を手に取れば誰しもが理解できるだろう。コロナ禍で医療者はかつてない経験をした。大切なことは,それを単なる「経験」で終わらせるのではなく,「どう行動変容につなげるか」である。著者は,COVID-19後遺症で苦しむ患者の声に耳を傾け,東洋医学を自身の診療に取り入れた。その姿勢からは,医師としての柔軟性と深い共感力が伺える。
人間の身体は,「おなか」だけが独立して機能しているのではなく,全ての臓器が関係性の中でつながっている。「心」と「身体」も切り離せない。著者は五感をフルに活用して診察することで,おなかの異常の本質に迫る。その診療の中で蓄積された暗黙知を,本書では見事に形式知化している。さらには,自身の消化管出血症例まで包み隠さず開示している。
この本は,研修医,内科医,そして消化器内科を専門にする医師にこそ手に取ってほしい一冊だ。多くの消化器内科医にとって,興味の中心は内視鏡診療である。内視鏡診療の有用性を否定はしないが,カメラを持つ前に,まずは患者に真摯に向き合い,五感をフルに活用してほしい。五感の感度を高めるには,本書から得られた身体診察の知見を,日々の診療の中で「修行」のように実践する姿勢が求められる。本書で学んだ身体診察のノウハウが,身体知として身についたとき,AIには代替できないスキルとなるだろう。なぜなら,そこには“医師としての心”が宿っているからである。
この書評を読んだだけでは不十分である。ぜひ,この本を手に取っていただき,自らの診療を見つめ直すきっかけとなることを願ってやまない。
患者さんのおなかを見て,聞いて,感じていきましょう!
書評者:横江 正道(日本赤十字社医療事業推進本部医療の質・研修部)
いまや,OSCEを経て医学部を卒業し,病歴聴取や身体診察を着実に活用して診断推論ができる研修医が増えてきています。DXやAI時代に逆行しているようにも見えますが,やはり,医師として身体診察は“基本中のキホン”です。採血してCTさえ撮影すれば診断がつく! という訳にはいかないことも多々あります。でも,身体診察って……。きっと,医学生時代には大切だと言われて,研修医時代もやるにはやったけれど,どこまで正しいのか,どこまで役に立っているのか,わからないままに今も医者やっています,という人は意外に多いのではないでしょうか。
だって,どこを触るのが正しいのか? どう触るのが正しいのか? 触ったときの感触は人によって違うなど,なんだか客観的ではないことも事実です。ましてや,ちゃんとした人(笑)に教わるかどうかは非常に重要です。その学びの違いで,身体診察の不確定要素に沼っている先生もまた,きっとたくさんいると想像します。
本書の著者である中野弘康先生は,大船中央病院のismを身につけ,腹痛に関する身体診察にまつわる心配部分を十分に汲み取って,身体診察のすごさや面白さを炸裂させています。
しかも,診察時の身体の写真と,USやCTの画像が対比された構成になっており,画像所見が身体診察ではどのような所見につながっているのかが明快に示されています。また,文字だけでは伝わりにくい,視診・聴診・打診所見がQRコードを読み取ることで,Audio & Visualとして実体験できます。一通り,本書の内容をマスターしたら,きっと,いままで自信がなかった身体診察についても,次の腹痛の患者さんにやってみようという気になるでしょう。
個人的には,第2章「漢方フィジカル」がとても新鮮で,面白く拝読しました。特に心に響いたのは,「腹診は患者と心を通わせるものであり,心地よい腹診はそのこと自体が患者を癒し,信頼関係の構築に結び付く」の一文です。患者の体に医師が触れることの意味を常に考えていれば,CTさえ撮ればという診察にはならないはずです。
ですが,ですが,ですが,身体診察は,やはり,やってみてなんぼのものです。当たるか外れるかはあるものの,やはり当てにいく身体診察の腕を磨くには,理論のみならず実践あるのみです。そして,画像診断でそれらしい所見がない腹痛こそ,身体診察のパワーが問われるときです。診断は白血球とCRPとCTではありません。身体診察は知れば知るほど楽しくなります。ぜひ,「おなかの身体診察」の一歩を本書から学び取り,患者さんのおなかを見て,聞いて,感じていきましょう!
Dual process思考(直感・分析)×Dual process思考(西洋・漢方)
書評者:寺澤 佳洋(口之津病院総合診療科)
私たちは診療の過程で,「Dual process思考」と呼ばれる2つの異なる思考様式を使い分けているとされる。一般的には,直感的思考(System 1)と分析的思考(System 2)に分類され,本書のメインテーマである腹診にも,これらの思考が活用されている。
例えば本書では,高山の圧痛点に圧痛を認めたとき,直感的には膵炎を想起する。しかし,それだけでは早期閉鎖(思考停止)につながりかねないため,分析的思考へと切り替え,さらなる身体診察が求められる。そうしたときに有用な所見として,本書ではMallet-Guy徴候などが紹介されており,急性膵炎の診断確度を高めたり,逆に下げたりする判断材料となる。また,高山の圧痛点やMallet-Guy徴候を含め,多くの身体所見については,診察時の患者の体位を含めた写真が掲載されており,理解を助けてくれる。
もう一つの「Dual process思考」は何か――。それが,本書の核ともいえる「西洋フィジカル」と「漢方フィジカル」の併存である。例えば触診の場面では,西洋フィジカルでは痛みの有無や腫瘤の有無を評価し,漢方フィジカルでは臍傍圧痛などの特徴的な圧痛所見に加えて,主に虚実の判定に用いられる腹壁の緊張度を確認することになる。一つの手技の中で得られる情報が増えることで,診療の質をさらに高めることにつながるだろう。
本書の「漢方フィジカル」の章には,東洋医学的な腹診を学ぶ上で欠かせない要点が,簡潔かつ実践的にまとめられている。豊富な写真やイラストによりイメージしやすく,初学者にも非常に親切な構成となっている。また,フィジカルの所見から導き出される漢方方剤の選択においても,直感・分析の「Dual process思考」が活かされていると感じた。
このように,本書は複層的な「Dual process思考」が織り込まれた,類を見ないユニークな臨床書といえるだろう。
最後に,著者である中野弘康先生にも触れておきたい。中野先生は肝臓専門医として,薬剤性肝障害への対応を担っていた。その過程で,漢方薬に対してネガティブな印象を抱くこともあったという。そんな中野先生が,なぜ今,漢方薬や漢方フィジカルに注目するようになったのか。そして,どのようにして学び直したのか――。本書には,こうした問いへの答えとともに,読者が無理なく学びを進められるように配慮された構成と語り口が貫かれており,そこには私が知る著者の臨床家としての優しさがにじんでいる。
多様な思考法を自然に行き来しながら展開される本書。ぜひ皆さんにも,「Dual process思考」の魅力に触れながら読んでいただきたい一冊である。
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。
タグキーワード
更新情報
-
正誤表を更新しました
2025.04.07
-
正誤表を掲載しました
2025.04.01
-
【2025年3月12日開催終了】本書に関連したWebセミナーを開催しました
2025.03.13
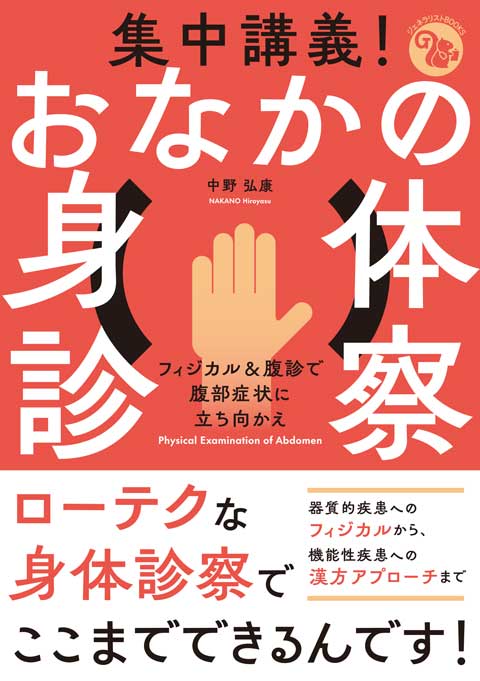
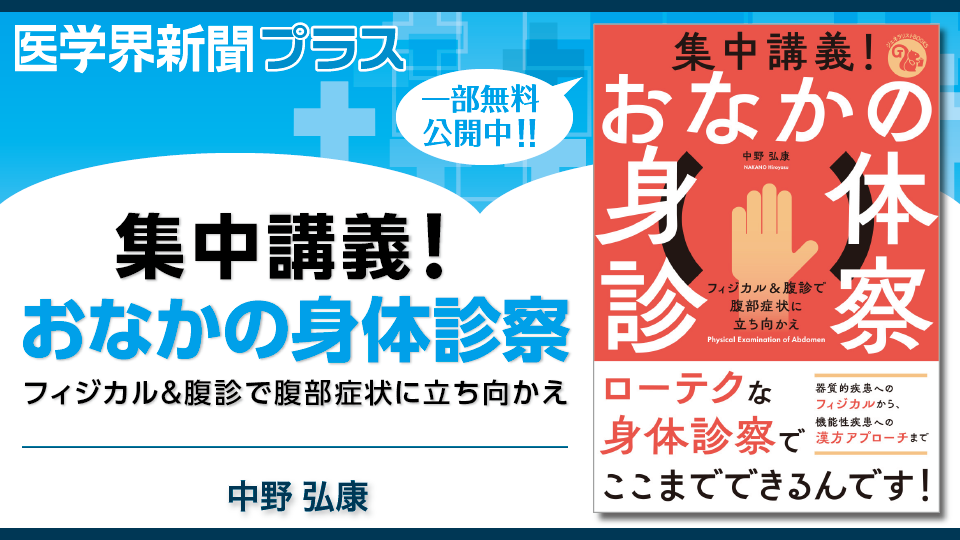
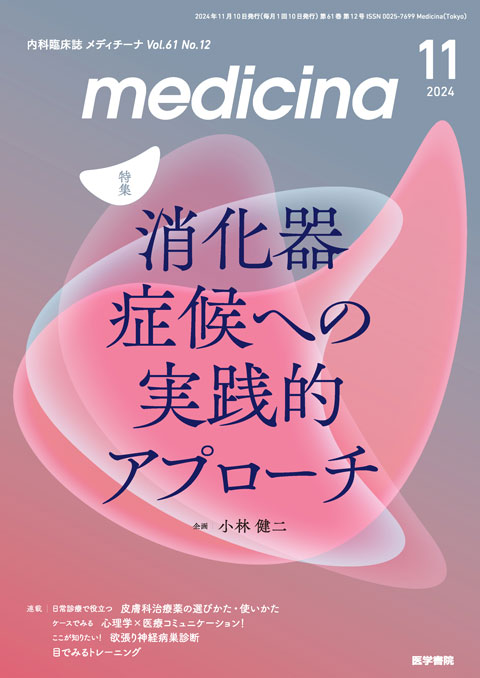
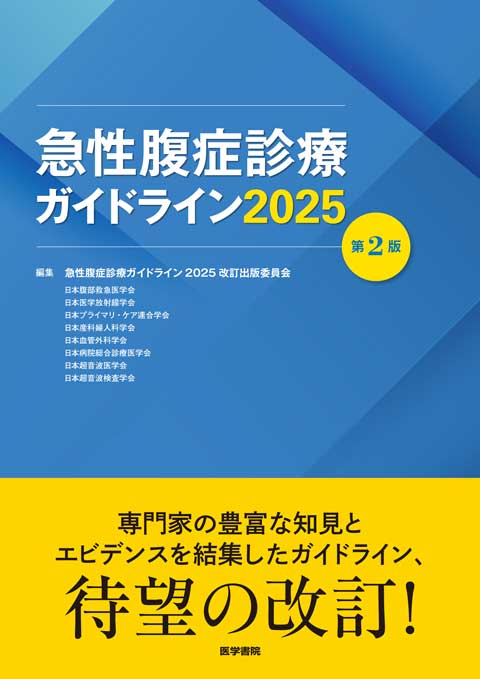
![救急超音波診療ガイド[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/1017/0063/3188/113479.jpg)