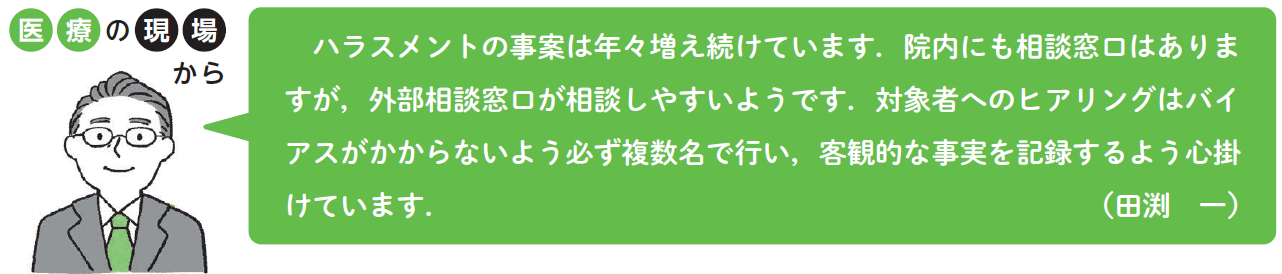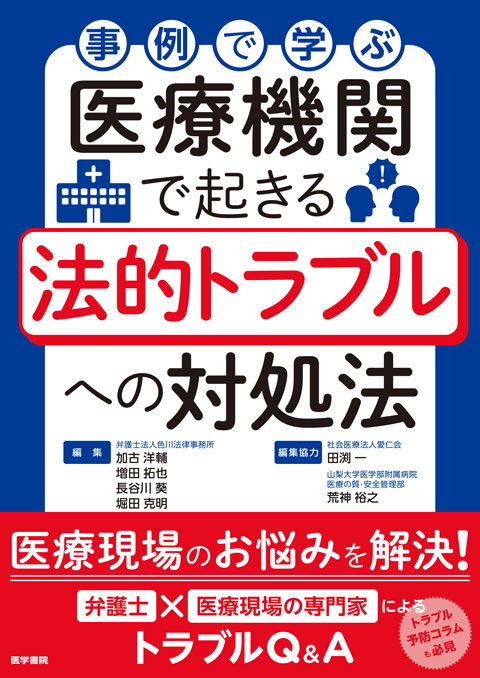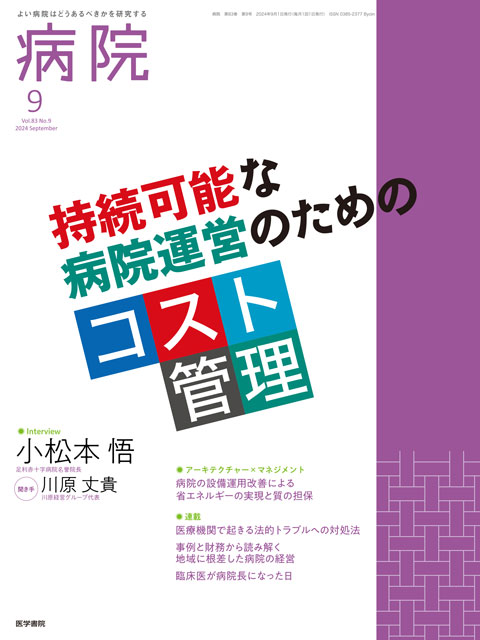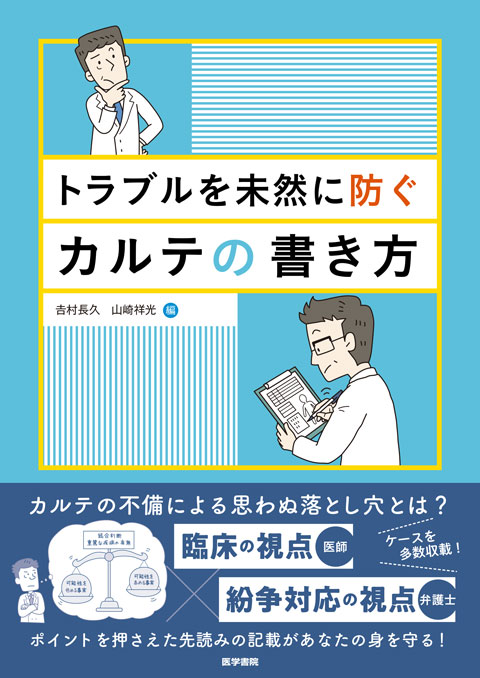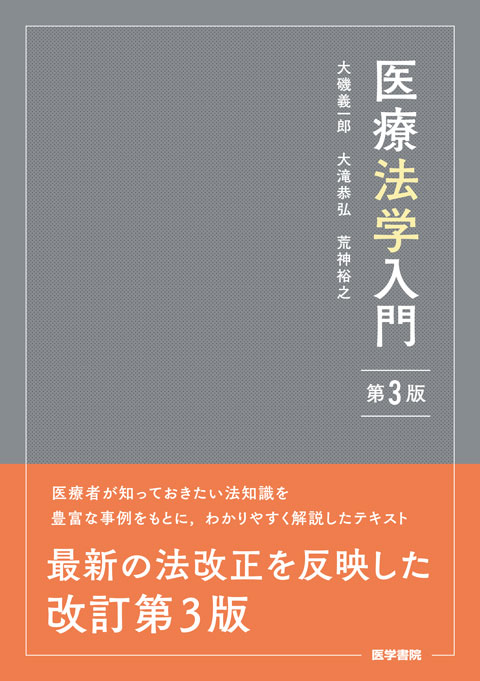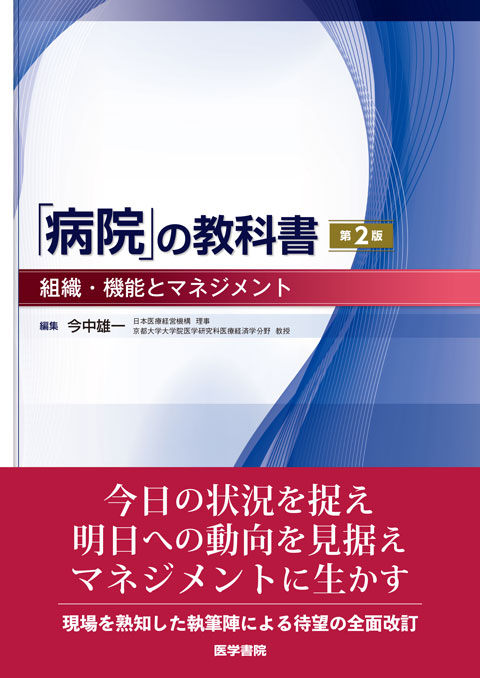- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2025年
- 医学界新聞プラス [第3回]ハラスメント対応――パワーハラスメントの例をもとに
医学界新聞プラス
[第3回]ハラスメント対応――パワーハラスメントの例をもとに
『事例で学ぶ 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法』より
連載 長谷川葵・堀田克明
2025.05.09
事例で学ぶ
医療機関で起きる法的トラブルへの対処法
病院,クリニックでは日々様々なトラブルが生じています。『事例で学ぶ 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法』は具体的な事例を紹介しつつ,トラブルへの対処や予防の方法を,Q&A形式でわかりやすく解説します。弁護士の豊富な実務経験をもとに,医療現場の専門家の視点も加わり,最新の法改正やトピックにも対応。医療事故や労務管理のみならず,SNS,サイバー攻撃,医師の働き方改革など多岐にわたるテーマを取り上げています。医療現場のお悩み解決に役立つ一冊です!
「医学界新聞プラス」では,本書より「医師・看護師への暴言・暴力への対応」をはじめ3事例をピックアップし,ご紹介していきます。
ハラスメント対応
パワーハラスメントの例をもとに
Q
当院に来て1年ほどの職員からパワハラ(パワーハラスメント)の相談がありました.どうやら部門長からたびたび皆の前で怒鳴られたり,仕事が遅いなどと大きな声で嫌味を言われたりするので,最近は職場に行くことが嫌で出勤前には憂鬱な気分になるとのことです.どのように対応すればよいでしょうか.
A
①院内にハラスメントの相談窓口があれば,相談者に対し,相談窓口に報告するよう勧めましょう.窓口がない場合には,一人で抱えこまずに事務局長や信頼できる管理職に相談するよう勧めるのがよいでしょう.
②相談を受けた医療機関は,相談者や関係者からヒアリングを行うなどして,どのような言動があったのかを確定し,それがパワハラに当たるかどうかを判断します.パワハラに当たる行為があった場合には,部門長に対する処分の検討や再発防止策としての研修の実施などを行うこととなります.
③パワハラの発生を防止・是正しない場合は,医療機関も,損害賠償責任を追及され,行政上の制裁を受けるなどの可能性があるため,適切な対応が必要です.
解説
パワハラ(パワーハラスメント)とは何でしょうか.意外と答えに窮しませんか.実は,厚労省の指針(以下,パワハラ防止指針)1で以下の3要素の要件を全て満たす場合にはパワハラであると定められていますが,法律2や指針で明確に定義されたのは最近のことです.
(1) 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって,
(2) 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,
(3) その雇用する労働者の就業環境が害されるもの
また,上記パワハラ防止指針により,以下のとおりパワハラの6類型が示されました.この6類型に当たらない限りパワハラでない,というわけではありませんが,類型ごとにパワハラに当たるか否かの事例が示されたことで,具体的な判断の指標になると思われます.
❶身体的な攻撃(暴行・傷害)
❷精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
❸人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
❹過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制,仕事の妨害)
❺過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
❻個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
冒頭の例では,部門長の行為はパワハラの6類型のうち「❷精神的な攻撃」3に当たると思われます.そして,部門長という優越的な関係にある者が,職場内で周囲に聞こえるように相談者を怒鳴ったり,仕事が遅いなどと言ったりしているので,その程度が業務上必要かつ相当な範囲を超え,かつ相談者の就業環境が害されるものに当たるのであれば,パワハラに該当します.もっとも,部門長の行為の具体的な態様や,部門長がそういった行為をした経緯を具体的に確認しなければ,業務上必要かつ相当な範囲を超えたかどうかなどの判断はできず,結局のところ,パワハラに当たるか否かはケースバイケースと言わざるを得ません.
a 法的責任やリスク
そもそも労働者間でパワハラやセクハラ(セクシュアルハラスメント),マタハラ(マタニティハラスメント)があった場合に,なぜ事業主が責任を負うのでしょうか.これは,事業主は労働者との労働契約に基づいて,労働者に対する安全配慮義務や,労働者にとって快適な就労ができるように職場環境を整えるという職場環境配慮義務を負っており,快適な就労の妨げになるようなハラスメントの発生を防止し,発生した場合には是正措置を講じなければならないためです.このような義務に反してハラスメントを放置・黙認することで,労働者がうつ病や適応障害などを発症した場合には,事業主は,労働者に対して,使用者責任や債務不履行責任に基づく損害賠償責任を負う可能性があります.
このような民事上の責任以外にも,労働者が労働局に相談し事業主が事実確認や指導を受ける可能性がありますし,パワハラ防止法により,雇用管理上の措置義務を守らなければ行政庁からの指導,勧告を受ける可能性があり,勧告に従わなかった場合は公表されるという行政上の制裁のリスクもあります.医療機関名が公表されれば,医療機関の信頼性等が大きく損なわれかねませんので,ぜひとも避けたいところです.
また,「パワハラをした」「パワハラを放置した」などのレッテルを貼られてしまうと,医療機関のイメージダウンなど大きな損失につながる可能性もあるのです.
b 雇用管理上の措置義務の内容
パワハラ防止法により定められた事業主が負う雇用管理上の措置義務を行わなかった場合には,民事上も安全配慮義務違反,職場環境配慮義務違反が認められる可能性が高いといえます.パワハラ防止指針では雇用管理上の措置義務について具体的に明記されていますが,ここでも簡単にご紹介します.
(1) 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
パワハラの内容を明確にし,パワハラを行ってはならない旨を職員に周知し,啓発することが必要になります.トップメッセージとして周知することや,就業規則にて定めることが考えられます.このほか,院内掲示板や簡単なA4用紙1枚程度のパンフレットでも構いませんので,職場内で周知することを心がけましょう.
(2) 相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備
必ず相談窓口を設置し,担当者を決めるとともに,対応フローを準備しておきましょう.相談窓口については,職員にしっかりと周知してください.パワハラ防止指針にも記載されているとおり,外部の機関に相談窓口を設けることも選択肢です.より中立性を担保したい場合や,人員などの関係で医療機関内部での対応が難しい場合であれば,弁護士事務所などの外部機関に委託してみてはいかがでしょうか.
(3) 職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
詳細はⅥ-4(154頁)で説明しますが,まずは迅速に事実関係をしっかりと調査して確認し,パワハラが認められた場合には行為者に適切な措置(懲戒処分や配置転換など)を行います.また,再発防止に向けた措置を講じます.
(4) その他併せて講ずべき措置
ハラスメントの被害者(相談者)や行為者などのプライバシーに配慮することやハラスメントの相談をしたことによって解雇などの不利益な取り扱いをしないことなどを定め,職員に周知する必要があります.
パワハラの発生を事前に防止できるように努めることは重要ですが,どうしてもパワハラと疑われる事象が発生してしまうことはあります.その場合に重要なのは,パワハラの発生が疑われた場合の事後対処,すなわち,パワハラが事実なのか否かを確認し,事実であるならば速やかに対処することです.
では,ハラスメントの相談があった場合にはどのように対応すればよいか,冒頭のQを基に検討します.
(1) ヒアリング(事情聴取)
相談窓口に相談があった場合には,まずは相談者からしっかりと事情を聞き取ります4.
ヒアリングの際には,プライバシーに配慮すること,不利益な扱いをしないことはしっかりと相談者に説明しましょう.特に相談者は警戒心を持っていることが多く,必要な事情を聞き出すことが難しい場合があります.警戒心を解くための工夫としては,以下のような姿勢を心がけるとよいでしょう.
● 相談者の話すことへの理解を伝える(相づちを打つなど)
● 相談者を責めるような口調は避ける(「なぜ~しなかったんですか?」「どうして~したんですか?」などを述べ過ぎないように)
● 相談者が話す内容を再確認しながらゆっくりと聞く
次に,相談者の話を基に,相談者以外にヒアリングすべき人を決めます.一般的には,口裏合わせなどを防止するために目撃者などの第三者からヒアリングを行い,最後にハラスメントの疑いがある行為者から事情を聞き取ります.冒頭のQであれば,相談者からのヒアリングの後,怒鳴られたという場にいた同僚・上司らから事情を聞き,最後に部門長の話を聞くことになります.
また,ヒアリングの際には時系列を意識して聞き,メモを取る際にも時系列で整理するようにしましょう.あらかじめ,質問役と記録役とは分担しておく方がスムーズです.質問役の方は,対象者の話す内容について自分で評価をせずに,あくまで対象者からの聞き取りに徹しましょう.
(2) 証拠化
ヒアリングの際には,きちんと証拠化することを心がけましょう.裁判などになった場合には,事業主の職場環境配慮義務違反か否かの判断に際して,ハラスメントに対してきちんと調査して対応していたという過程を示すことも非常に重要になりますので,その点を意識した証拠作りを意識するとよいと思います.
例えば,ヒアリングの際には録音をお勧めします.録音を始める前に,きちんと話者に録音する旨を伝えておくべきでしょう.相談者の中には録音されることに強い抵抗を示す方がいるかもしれません.このような場合でも,正確な記録を残すために必要であるということを丁寧に説明して説得しましょう.
相談者以外(行為者や第三者)の場合でも正確な記録を残すために録音するようにしましょう.裁判例によれば,基本的には,関係者に当たる上司や相談者,行為者,目撃者などには調査協力義務が認められると思われます5.したがって,調査協力義務のある職員からヒアリングを断られた場合であっても,業務命令としてヒアリングを受けるよう指示することができます.録音する旨伝えた上で録音すること自体は,基本的には必要な調査の範囲内であり問題にはならないと思われます.
また,録音以外にも聴取したメモを取るなどしましょう.あらかじめ聴取する項目を記したヒアリングシートを院内で用意しておくと便利です.
なお,担当者の話す内容も,ヒアリング対象者から特に断りなく録音される可能性を想定しておく必要があります.例えば,相談者に威圧的に話していないか,部門長に対してはパワハラと断定した口調でヒアリングしていないかなど,担当者も声の大きさや表現などの話し方,話す内容には常に気を付けるようにしましょう.
(3) ヒアリング内容が食い違った場合
関係者間でヒアリング内容が食い違うことはよくあります.冒頭のQであれば,部門長が怒鳴っていたのか単なる注意レベルの声だったのか,どのような言葉遣いをしたのかなど,立場によって受け止め方が違う可能性があります6.その場合,使用者としては誰の話を信用すればよいのでしょうか.
まず,客観的な証拠や目撃者の証言と一致しているかが重要になります.冒頭のQでは,部門長の怒鳴った声などの録音や部門長が怒鳴ったという場に居合わせた同僚の証言も重要となります.また,ヒアリング内容そのものに一貫性があるか,矛盾点がないかという点も重要になります.それを見極めるためには複数回のヒアリングを実施するのも手です.さらに,虚偽の供述をするおそれがないか,相談者と行為者の関係性などにも注視する必要があります.
(4) ハラスメントの評価
いつ,どのような発言・行為がされたのかが確定すれば,その発言・行為がハラスメントに該当するかどうか7を評価します.
冒頭のQでは,部門長が相談者に対し,どのような状況でどのような内容の発言をしたのか,そのような発言に至った経緯を認定し,部門長の言動が,業務上必要かつ相当な範囲を超えたといえるかどうかを評価します.
なお,一般にハラスメントとは考えにくい発言・行為を繰り返し問題視し訴える相談者もいるかもしれませんが,そのような場合でも同様の対応を淡々と進め,医療機関としてはハラスメントと評価しないと考えている旨を,当該相談者に説明します.
(5) ハラスメント認定後の措置
ハラスメントを認定した場合,医療機関としては,部門長に懲戒処分や配置転換を行うなどして,既に発生しているハラスメントに対して適切な措置を講じるとともに,再発しないような措置も講じる必要があります.
再発防止策としては,例えば,部門長に対して再発防止研修を行ったり,ハラスメントに関する院内研修を実施したりすることも有効です.弁護士などの専門家を講師として招くと,よりインパクトがあるかもしれません.
何より重要なことは,その場しのぎの対処をするのではなく,ハラスメントが発生した根本的な原因を探求することです.そのためには,医療機関全体に対してアンケートを実施し状況を分析することも有効です.根本的な原因を排除しない限り,ハラスメントが再発し,職業環境が害されて仕事でのミスも多くなってきます.特に,人の生命を預かる医療機関ではなお一層,「働きやすい職場づくり」が重要課題ではないでしょうか.
トラブルを予防するために
パワハラを予防するための事前措置として,トップメッセージとして周知することに加え,パワハラの発生原因や背景について,職員の理解を深めることが重要です.特に,パワハラ防止指針では,パワハラの発生の原因や背景には,職員同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題もあると考えられると指摘されています.
職員同士のコミュニケーション能力の向上を図るために,アンガーマネジメントやコミュニケーションスキルアップ等の研修を行うことや,日常的なコミュニケーションを取るよう努めたり定期的に面談やミーティングを行うことにより,風通しの良い職場環境や互いに助け合える労働者同士の信頼関係を築き,コミュニケーションの活性化を図ることも重要です.
また,労働者に過度に肉体的・精神的負荷を強いる職場環境や企業風土も,パワハラを発生させる背景になると考えられるため,適正な業務目標の設定や適正な業務体制の整備,業務の効率化による過剰な長時間労働の是正等を通じて,職場環境を改善することも,パワハラの予防につながります.
1 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚労省告示第5号).
2 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」30条の2第1項参照(通称「労働施策総合推進法」,「パワハラ防止法」).
パワハラ防止法では,セクシュアルハラスメント(セクハラ)やマタニティハラスメント(マタハラ)と並んで,パワハラに関する雇用管理上の措置義務や,パワハラを含むハラスメントに関する相談をしたことなどを理由とした事業主による不利益な取扱いの禁止などが定められました.また,これらの義務に違反した事業主(医療機関)は,厚生労働大臣による助言,指導や勧告(行政指導)を受け,場合によっては事業主名(医療機関名)が公表されるという制裁が科されます.
3 「②精神的な攻撃」の中でパワハラに該当すると考えられる例としては「他の労働者の面前における大声での威圧的な𠮟責を繰り返し行うこと」などが挙げられている一方,該当しない例として「遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ,再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をすること」などが挙げられています.
4 特にセクハラの相談の場合などは,相談者と同性の方に同席してもらうのが望ましいです.また,ヒアリングの担当者が多すぎると威圧的に思われるかもしれませんので,例えば,男女1名ずつで担当することなどが考えられます.
5 判例では,①「当該労働者が他の労働者に対する指導,監督ないし企業秩序の維持などを職責とする者であって,右調査に協力することがその職務の内容となっている場合には,右調査に協力することは労働契約上の基本的義務である労務提供義務の履行そのものであるから,右調査に協力すべき義務を負うものといわなければならない」と述べています.また,②それ以外の者についても「調査対象である違反行為の性質,内容,当該労働者の右違反行為見聞の機会と職務執行との関連性,より適切な調査方法の有無等諸般の事情から総合的に判断して,右調査に協力することが労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的であると認められない限り,右調査協力義務を負うことはない」と述べており,一定の場合には,労働者に調査協力義務が認められると考えられます(最判昭和52・12・13民集31巻7号1037頁・富士重工事件).
一般的には,①には関係者の上司である管理職等,②には相談者,行為者や目撃者がこれに当たると考えられます.
6 セクハラの場合には,パワハラと異なり,目撃者がいない密室で発生する場合も多く,その場合にはそもそも相談者が申告した事実があったか否かが問題になりやすく,相談者と行為者のヒアリング内容が真っ向から反するものになりやすくなります.
7 セクハラの場合はそもそも業務に不要なものですが,注意や指導は業務遂行上必要ですので,パワハラの評価の方が難しいといえます.
(長谷川葵・堀田克明)
事例で学ぶ
医療機関で起きる法的トラブルへの対処法
弁護士×医療現場の専門家による法的トラブルQ&A!
<内容紹介>
病院、クリニックでは日々様々なトラブルが生じている。本書は具体的な事例を紹介しつつ、トラブルへの対処や予防の方法を、Q&A形式でわかりやすく解説する。弁護士の豊富な実務経験をもとに、医療現場の専門家の視点も加わり、最新の法改正やトピックにも対応。医療事故や労務管理のみならず、SNS、サイバー攻撃、医師の働き方改革など多岐にわたるテーマを取り上げている。医療現場のお悩み解決に役立つ一冊。
目次はこちらから
タグキーワード
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。