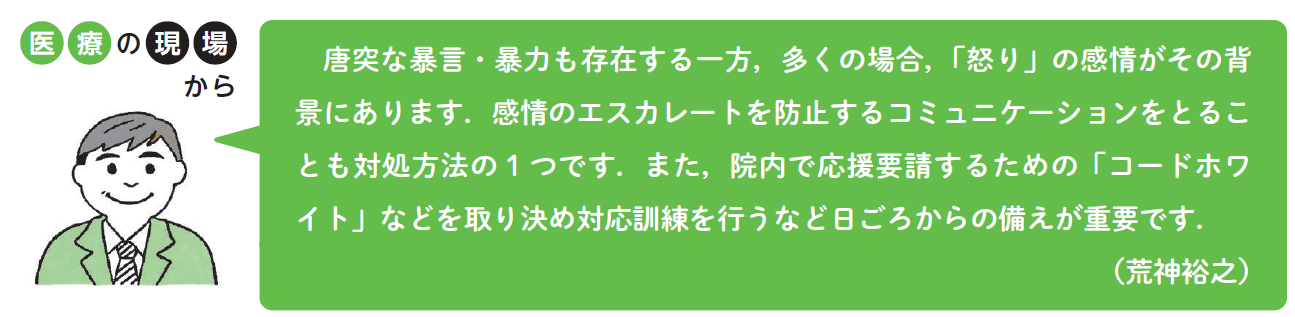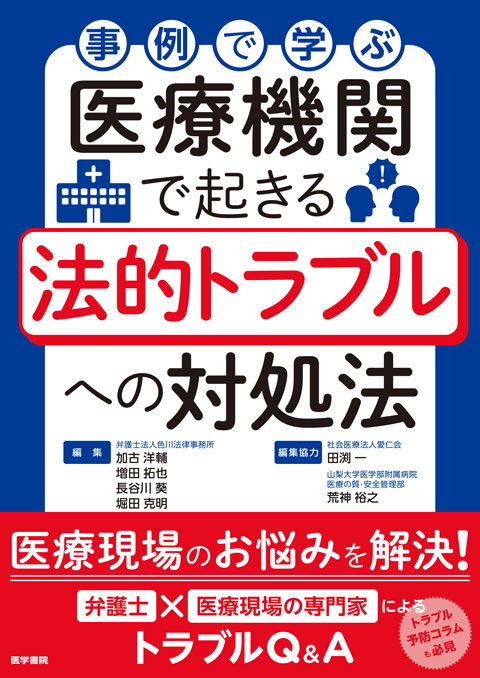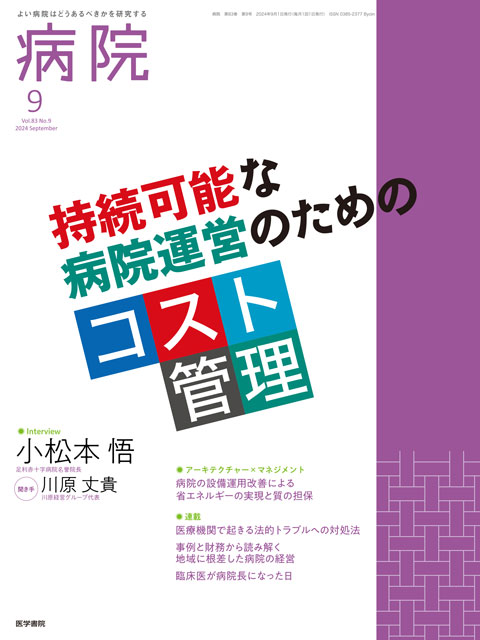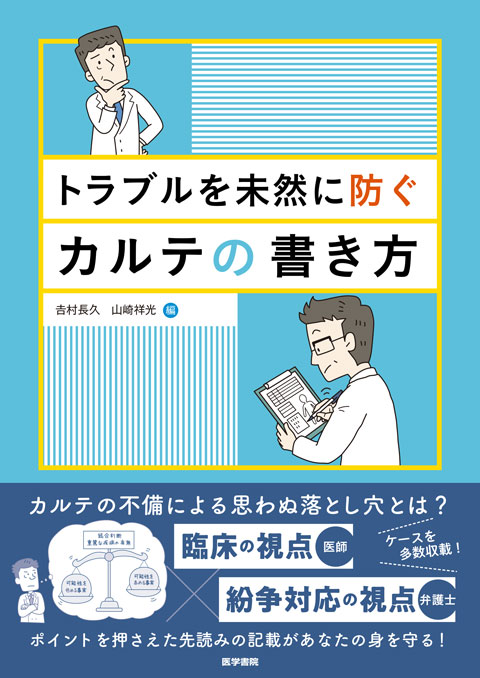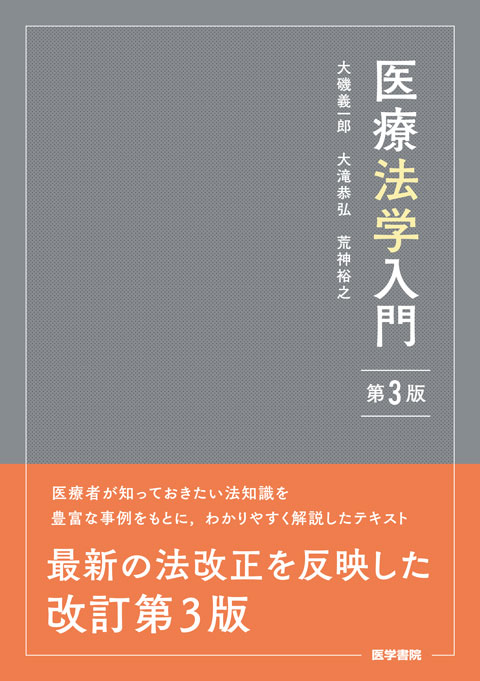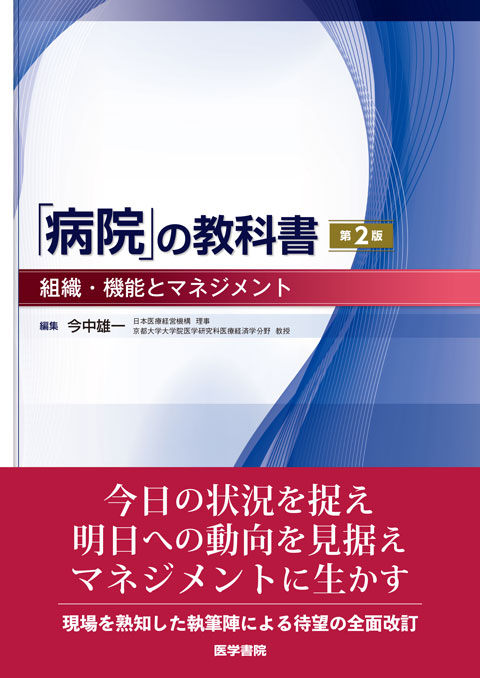- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2025年
- 医学界新聞プラス [第1回]対応困難患者への対応(2)医師・看護師への暴言・暴力への対応
医学界新聞プラス
[第1回]対応困難患者への対応(2)医師・看護師への暴言・暴力への対応
『事例で学ぶ 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法』より
連載 小林京子・高坂佳郁子
2025.04.18
事例で学ぶ
医療機関で起きる法的トラブルへの対処法
病院,クリニックでは日々様々なトラブルが生じています。『事例で学ぶ 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法』は具体的な事例を紹介しつつ,トラブルへの対処や予防の方法を,Q&A形式でわかりやすく解説します。弁護士の豊富な実務経験をもとに,医療現場の専門家の視点も加わり,最新の法改正やトピックにも対応。医療事故や労務管理のみならず,SNS,サイバー攻撃,医師の働き方改革など多岐にわたるテーマを取り上げています。医療現場のお悩み解決に役立つ一冊です!
「医学界新聞プラス」では,本書より「医師・看護師への暴言・暴力への対応」をはじめ3事例をピックアップし,ご紹介していきます。
対応困難患者への対応(2)
医師・看護師への暴言・暴力への対応
Q
アトピー性皮膚炎で,毎月,当院を受診している患者がいます.症状が改善しないのが不満 なのか,問題行動が次第にエスカレートしてきました.
①最初は,受診の際に「ちっともよくならない,ヤブ医者じゃないか」と看護師に対して詰め寄った り,医師の前でも「薬が全然効かない,医者なら病気を治せ!」などと大声で言いながら机を叩いた りする行動が見られました.
②そのうち,診察室に呼ぶ順序の先後など些細なことでも たびたび「患者対応がなっていない.訴えてやろうか」と 苦情の電話をかけてくるようになりました.その対応のた めに看護師や事務職員の業務に支障を来しています.
③前回の受診時には,晴れているのに長傘を持参し,医師 や看護師の目につくようにわざわざ診察室にも持ち込んで いたので,今後,暴力を振るわれるのではないか心配です.
どのように対処すればよいでしょうか.
A
①の段階:患者の言動の背景事情や理由を確認し,医療機関の見解を伝え,迷惑行為を行わないよう求めましょう.
②の段階(迷惑行為が継続する場合):毅然とした対応をとり,「迷惑行為が続く場合には受診をお断りすることがある」ことを口頭,書面で警告しましょう.弁護士への相談,警察への情報提供も検討しましょう.
③の段階(①や②の対応でも解消しない場合):警察への相談や通報,診療の拒否,仮処分命令の申立てを検討しましょう.
解説
患者が医療機関の職員に対して暴言を吐いたりクレームを述べたりするケースには,大きく分けて以下のような場合があります.
❷不適切な診療行為や対応があり患者の言い分にはそれなりの理由がある場合1
いずれの場合であっても,まずは患者のクレームなどの背景事情や理由を確認する必要があります.加えて,それぞれのケースにおける留意点は以下のとおりです.
医療機関としては適切に対応しており,クレームを受ける理由がないことを明確に説明するべきでしょう.冒頭のQでは,症状が改善しないことを患者が不満に思っているのだろうと医療機関側がクレームの原因を推測していますが,まずは患者の思いに真摯に耳を傾けるのがよいでしょう.意外な理由が隠されているかもしれません.
薬を塗っても直ちに症状が改善しないなど診療内容に関わることであれば,医師から丁寧に説明することで患者の理解や納得を得られることもあります.その際は患者の理解力に応じて分かりやすい説明を意識することが肝要です.
❷のケース
不適切な診療行為や対応を特定した上で,不適切であったことを認め,お詫びして今後再発防止に努めることなどを説明します2.
万一,後述するような民事裁判となった場合には,相応の理由があるクレームなどに対して医療機関が然るべき対応をとらなかったことは医療機関にとって不利益な事情となり得ますので,早い段階で謝罪と説明を行っておくべきでしょう.ただし,漠然と謝罪するのではなく,不適切と認める行為や対応を特定しておくことが必要です.
①②のいずれのケースにおいても,以上の説明に加えて,今後は暴言を吐くといった迷惑行為を行わないよう患者に対して明確に要望し,これらのやりとりについて記録を残しておきましょう〔記録の際の留意点については,3(3)参照〕.
(1) 警告
医療機関の見解を説明し,迷惑行為を行わないよう要望しても迷惑行為が継続されるような場合には,今後,同様の行為を繰り返された場合には受診を断る場合があることを警告しておく必要があります.
このような警告は,医療機関が後に患者に対して厳しい対応をとらざるを得なくなった場合に,当該対応をとる必要性や合理性があることの裏付けとなりますので,口頭で注意するだけではなく書面に記載3して患者に渡し,医療機関において写しを保管しておきましょう.後日,第三者が一読して理解できるよう,それまでに患者が行ってきた行為の概要を併せて記載しておくとよいでしょう.
迷惑行為が継続される場合には,弁護士に相談することも検討しましょう.具体的な対応方法や留意点についてアドバイスを受けたり,警告文の作成やチェックを依頼したりすることができます.事案によっては,弁護士から内容証明郵便を送付してもらうことも選択肢となります.
また,今後さらに迷惑行為がエスカレートし,警察への通報も想定されるようなケースでは,準備として,最寄りの警察署にあらかじめ情報提供し,迷惑行為が行われることがあれば速やかに駆けつけてもらうよう依頼しておくとよいでしょう.
(2)警察への通報
(1)で記載したような対応をとっても,患者の迷惑行為が収まらない場合には,警察に通報して,すぐに駆けつけてもらうことも検討しましょう.特に,以下のような場合は犯罪が成立する可能性がありますので,直ちに警察に通報しましょう4.
●長傘等を持ち込むだけでなく振り上げるなどして医療機関の職員を脅す,強要するといった行為がある場合 ⇒ 脅迫罪(同222条)や強要罪(同223条)
●長傘等を振り回して設備などを壊した場合 ⇒ 器物損壊罪(同261条)
●職員を殴った場合 ⇒ 暴行罪(同208条)や傷害罪(同204条)
●医療機関からの退去を求めたにもかかわらず居座っている場合 ⇒ 不退去罪(同130条)
また,警察OBが在籍していたり,警備員が常駐したりしている医療機関では,まずは当該スタッフが直ちに対応できるようあらかじめ情報共有し,連絡方法や駆けつけ体制を確認しておくことも重要です.
(3)診療の拒否[診療契約の終了(解除)]
迷惑行為が継続され,業務に支障が生じるような状況が発生していれば,診療契約の前提である医師との信頼関係も失われていると思われます.医療機関は,職員に対して安全配慮義務を負っていますので,その義務を履行するためにも,当該患者に対する今後の診療を断ることを選択肢として検討しましょう.
ただし,ご承知のとおり,医師は応召義務を負っていますので(医師法19条1項),診療に応じないことが正当化される事由があることが前提です.これについては,厚労省の通知5で考え方が整理されています.冒頭のQでは,患者はアトピー性皮膚炎という慢性疾患ですので,特段の事情のない限り,緊急対応が不要な場合(病状の安定している患者等)に該当し,他の医療機関での治療も可能と思われます.したがって,迷惑行為の態様や継続期間などによっては,信頼関係が喪失しているとして患者の診療を拒否したとしても応召義務に反することはないと考えられます6.応召義務は医師法上(公法上)の義務であり,民事上の義務については別途検討する必要がありますが,上記のような正当化事由がある場合には,診療契約に基づき患者を診療するべき義務の違反(債務不履行や不法行為)もないと考えられます(診療拒否の法的性質についてはⅠ-3→13頁参照).
(4)仮処分命令の申立て
仮処分命令(以下,仮処分)の申立てとは,自身に生じている著しい損害または急迫な危険を避けるために,裁判所に対して暫定的な措置をとることを求める手続です.仮処分の申立ては,法的手続の一種であり相応の手間と費用はかかりますが,医療機関と患者の二当事者間での解決が見通せない場合に,裁判所という第三者の関与を得て一定の解決が得られるという点で有用な手段です.手続が続いている間は,患者からクレーム等があったとしても「裁判手続の中で話をしましょう」と裁判外での話し合いを断ることができ,現場の負担を軽減できる点もメリットです7.
仮処分で医療機関が患者に対してどのような暫定的な措置を求めるべきかは個別の事案によって異なりますが,例えば,「侮辱的内容を交えた発言をしないこと」「職員の身体に触れるなど有形力を行使しないこと」「粗暴あるいは威圧的な言動により医療機関の診療行為などの業務を妨害しないこと」などが挙げられます.
仮処分の手続でも,裁判所が患者を呼び出して反論の機会を与えることは多く,話し合いにより,例えば,「患者は○○の行為をしないことを約束する」といった内容の和解が成立することもあります.話し合いで解決できない場合には,裁判所において医療機関側の申立てに理由があると判断すれば,仮処分決定が下されます.
毅然とした対応をとるためにも,平時から以下のような体制を構築して対応することが望ましいといえます.
(1)窓口対応者の固定
窓口対応者がまちまちですと,情報共有が不十分なことや対応にずれが生じることがあり,「Aはこう言っていた.Bが言ってることとは違うじゃないか」などとさらなるクレームなどを招く可能性がありますので,窓口対応者は固定しましょう.必要な場合には診療行為について医師から説明を行うべきですが,診療に関する説明が不要な場合には医師や看護師ら医療従事者はクレームなどへの対応はできるだけ関与せず,対処方法について一定の知識経験を有する事務職員が対応する方が望ましい場合が多いと思われます.このような体制を構築することにより,医療従事者が診療や看護に専念することができ,また医療従事者の離職防止にもつながります.
(2)複数名での対応
一貫した対応をするために窓口対応者の固定化は必要ですが,一人での対応は負担が大きく,また患者と密室で協議した場合などには,後に,「職員から○○のようなことを言われた/された」といった,事実とは異なるクレームを受けることも皆無とは言えません.診療中であれば医師や看護師が複数で対応し,診療外であれば,事務職員などが複数で対応することを原則とすべきです.
(3)記録による証拠化
最も重要なのは,客観的な証拠を残しておくことです.電話であれば録音を残しておく,廊下,受付や診察室の入口付近8に防犯カメラがあれば録画することが考えられます.診療中のやりとりについては診療録に記載する,診療外でのやり取りについては,別途の書類に記録を残しておくことが肝要です.
記録を残す際には,患者が,いつ,どこでどのようなことをしたのか(5W1H)を意識して記載するようにしてください.例えば,時間的な要素が重要な場合(長時間の電話で業務が妨害された,長時間受付に居座られて業務が妨害されたなど)には,その時間帯(電話の開始時間と終了時間,受付にいた時間)を記録します.脅迫的な発言があった場合には,具体的にどのようなことを言われたのかが重要ですので,発言内容を具体的に記録します(録音があるとベターです).不退去罪が成立し得るような場合には,医療機関の職員の誰が,どのような言葉でいつ退去を求めたのかを具体的に記録しておきます.もし職員に対する傷害行為があった場合には,医師の診断書を得ておくことも必要です.
警察への相談(情報提供),被害届の提出や仮処分などの裁判手続は,これらの証拠を踏まえて(特に重要な証拠については,これらを添えて)行うことになります.
(4)専門職の配置
前述のとおり複数の事務職員で対応するとしても,担当する事務職員の心理的,時間的な負担は大きく,また対応困難者への対応には向き不向きもあります.できれば,苦情処理を専門的に扱える人材を配置するか,または職員がクレーム対応などの研修を受けることも一案です.
1 例えば,検査に不備があり後日追加の検査が必要となった,誤りに気づいてすぐに回収したが他人の処方箋を渡してしまった,などのインシデントのケースが挙げられます.
2 金銭的な賠償が必要とされる診療行為や対応があったケースでは,通常は弁護士に対応を委任することでクレーム対策もなされますので,本項では検討の対象外とします.
3 可能であれば,書面に「私が再度……のような行為に及んだときには,診療を断られても異議はありません」という一文を入れて患者のサインを得,医療機関において原本を保管し,患者には写しを交付するという対応がベターです.しかし,このような一文が入っていることにより,患者がサインを拒否し,書面の受領を拒むことも十分予想されます.そのため大抵のケースでは,警告を記載した書面を交付し,その書面のコピーに,○月○日に職員○○が患者に交付した旨を記録に残しておく(患者のサインは求めない)ことが現実的な対応策と考えられます.
4 1や2(1)の対応を取り,何度も警告しているにもかかわらず迷惑行為が継続している事情があれば(さらに事前に警察署に情報提供を行っていれば),対応の必要性について警察の理解を得やすくなります.
5 令元・12・25厚労省医政局長通知(医政発1225・4)「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」.
6 ただし,診療拒否を巡っては患者から訴えられる可能性がありますので,具体的な迷惑行為の態様や継続期間,医療機関において1や2(1)の対応をとり患者に十分な説明と警告を行ったことなどを立証できるよう,具体的な証拠を残しておくことが重要です.
7 診療を拒否しても患者が医療機関に押しかけて迷惑行為を行うような場合や,疾患の内容などから診療拒否までは躊躇される場合で,医療機関の業務に支障が生じていると言える場合などに仮処分を申立てることが考えられます.申立てを認めるか否かは,迷惑行為の内容や継続期間,医療機関にどのような不都合が生じているか,医療機関として迷惑行為に対してどのような対応をとってきたかなどの諸事情から判断されますので,それらを裁判所が認めるに足りる客観的資料があるかどうかという観点が重要なポイントとなります.裁判所において医療機関の主張が認められる見通しが立たないケースでは,仮処分の申し立ては避けるべきでしょう.
8 診察室での診察状況を録画することはプライバシーの点で問題となり得ますので,一般的には行うべきではないと思われます.
(小林京子・高坂佳郁子)
事例で学ぶ
医療機関で起きる法的トラブルへの対処法
弁護士×医療現場の専門家による法的トラブルQ&A!
<内容紹介>
病院、クリニックでは日々様々なトラブルが生じている。本書は具体的な事例を紹介しつつ、トラブルへの対処や予防の方法を、Q&A形式でわかりやすく解説する。弁護士の豊富な実務経験をもとに、医療現場の専門家の視点も加わり、最新の法改正やトピックにも対応。医療事故や労務管理のみならず、SNS、サイバー攻撃、医師の働き方改革など多岐にわたるテーマを取り上げている。医療現場のお悩み解決に役立つ一冊。
目次はこちらから
タグキーワード
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。