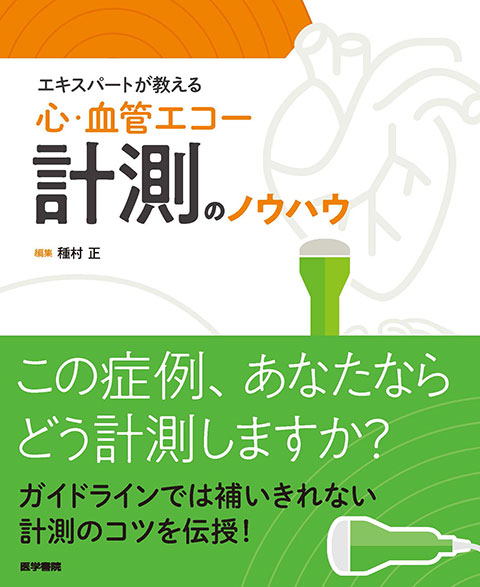診断に役立つ心エコー図検査レポートの書き方
寄稿 小谷 敦志
2025.09.09 医学界新聞:第3577号より
MRIやCT検査は身体(臓器)全体を撮影したあとで病変を診断するが,心臓超音波検査(心エコー図検査)に限らず超音波検査は,検査者が病変を映し出さなければ(病変に気が付かなければ)診断できず,レポートにも記載できない。したがって,超音波検査では検査中に得られた超音波所見を解釈しながら必要な画像を描出し,検査中に頭の中でレポートを完成させることが求められる。
心エコー図検査は,心腔サイズや血流速度など多くの計測を行う。それらの計測値と共に弁や心腔サイズについての所見をレポートに記載するのが一般的であるが,その際に検査者の総括コメントも記載することが肝要と筆者は考える。例えば,病変の経過観察を目的とした心エコー図検査の依頼では,前回検査と比較し今回がどう変化しているのかを明記する。また,心エコー図検査で重症度を評価する場合では,各計測値を照らし合わせ,考えられる重症度を記載する必要があるだろう。以上を踏まえ本稿では,実際の診断に役立つ心エコー図検査のレポート作成の要点を解説していく。
レポート作成で押さえておきたいポイント
1)長軸断面と短軸断面を含めた多断面で評価する
心エコー図検査の評価断面には,心基部から心尖部への心臓軸に対しての長軸断面と,それに直交する短軸断面という概念がある。この2段面で病変を評価することで詳細な評価が可能となる。例えば,弁の逸脱による逆流部の評価では長軸断面と短軸断面でカラードプラ法も含めて観察することで病変部の特定が可能となる。また,左室のregional asynergy(局所壁運動異常)について,胸骨左縁左室短軸断面と胸骨左縁左室長軸断面もしくは心尖部四腔・二腔・長軸断面のそれぞれにおいて多断面評価することで病変部位の診断の再現性を向上させることができる。
2)視野と時相を意識した画像を記録する
超音波検査は局所を観察することに優れており,拡大することで数mm単位の評価が可能である。その際,病変部周囲の組織や血管など空間的位置関係が理解できるよう広角視野の画像を記録しておくことが大切である。例えば,感染性心内膜炎では疣腫サイズを拡大し計測記録するが,周囲の弁や心臓組織,心腔を含めた広角視野での記録を追加することで客観的な病変部位の同定が容易となる。
また心エコー図検査における静止画の記録では,収縮期と拡張期の時相の理解が重要である。疾患や病態によっては収縮中期や拡張末期といった,細かな時相分析を行う場合もあり,それぞれの特徴的な時相を知った上で静止画の記録を行う。例えば,僧帽弁逆流(MR)の大きさをカラードプラ法で記録する場合,成因によってMRが最大に表示される時相が異なる。器質性MRであれば収縮中期が最大であるが,機能性MRでは収縮末期であることもあり,それぞれに適した時相で静止画を記録することが求められる。
3)疾患・病態別のひな形を作成しておく
心エコー図検査では,症例や病態ごとに評価する項目,注意点は大体決まっており,これはレポートに記載する所見も同様である。したがって,目にする機会が多い疾患や病態について,所見やコメントのひな形を事前に作成しておくと,すばやくレポートを完成させることができる。また,ひな形の用意があると評価するポイントが検査者間で共有できるため,計測忘れ防止にも役立つ。例えば,僧帽弁狭窄症(MS)例において「planimetry法から求めた僧帽弁口面積はA cm2,平均圧較差はB mmHgであり,中等症MSを疑う」のようなひな形では,計測値を入力するだけで一つのコメントが完成...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

小谷 敦志(こたに・あつし)氏 近畿大学奈良病院臨床検査部 技師長代行
1989年から近畿大病院中央臨床検査部に勤務。2015年より現職。18年同大大学院医学研究科心血管機能外科学博士課程修了。血管診療技師(CVT),日本心エコー図学会認定専門技師(JRDCS),日本超音波医学会認定超音波検査指導士(血管領域)などの認定資格を取得。日本超音波検査学会理事,奈良県臨床検査技師会副会長。編書に『改訂第2版 これから始める血管エコー』(メジカルビュー社),『病態・類似疾患別心エコー図検査のルーティン』(医学書院)。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2025.12.09
-
医学界新聞プラス
[第1回]心エコーレポートの見方をざっくり教えてください
『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.04.26
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第3回]冠動脈造影でLADとLCX の区別がつきません……
『医学界新聞プラス 循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.05.10
-
医学界新聞プラス
[第2回]アセトアミノフェン経口製剤(カロナールⓇ)は 空腹時に服薬することが可能か?
『医薬品情報のひきだし』より連載 2022.08.05
最新の記事
-
厳しさや大量の課題は本当に必要か?
教育現場の「当たり前」を問い直す対談・座談会 2025.12.09
-
対談・座談会 2025.12.09
-
対談・座談会 2025.12.09
-
インタビュー 2025.12.09
-
ロボット,AIとARが拓く看護・在宅ケア
安全はテクノロジーに,安心は人に寄稿 2025.12.09
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

![病態・類似疾患別心エコー図検査のルーティン[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/1817/4909/0623/115433.jpg)