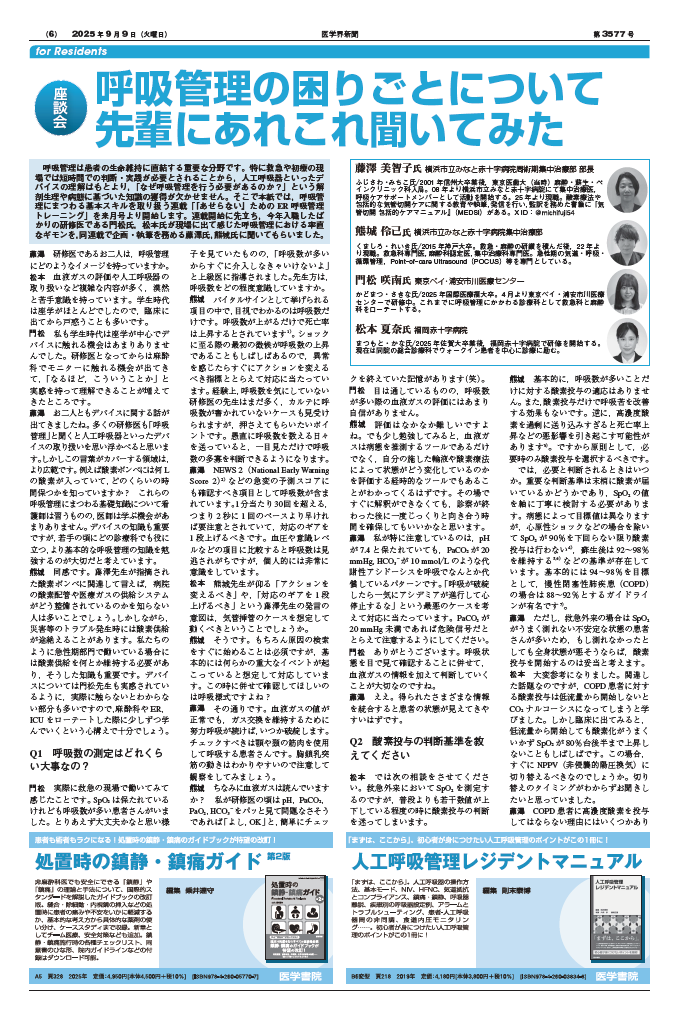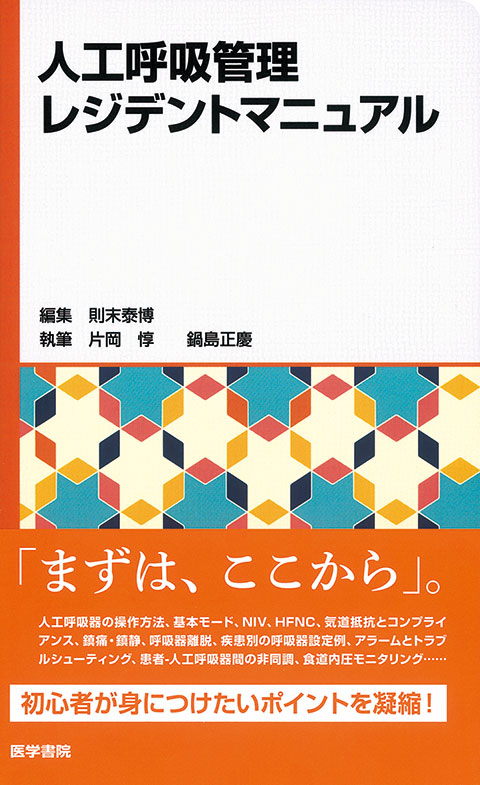呼吸管理の困りごとについて先輩にあれこれ聞いてみた
対談・座談会 藤澤 美智子,熊城 伶己,門松 咲南,松本 夏奈
2025.09.09 医学界新聞:第3577号より

呼吸管理は患者の生命維持に直結する重要な分野です。特に救急や初療の現場では短時間での判断・実践が必要とされることから,人工呼吸器といったデバイスの理解はもとより,「なぜ呼吸管理を行う必要があるのか?」という解剖生理や病態に基づいた知識の獲得が欠かせません。そこで本紙では,呼吸管理にまつわる基本スキルを取り扱う連載「『あせらない』ためのER呼吸管理トレーニング」を来月号より開始します。連載開始に先立ち,今年入職したばかりの研修医である門松氏,松本氏が現場に出て感じた呼吸管理における率直なギモンを,同連載で企画・執筆を務める藤澤氏,熊城氏に聞いてもらいました。
藤澤 研修医であるお二人は,呼吸管理にどのようなイメージを持っていますか。
松本 血液ガスの評価や人工呼吸器の取り扱いなど複雑な内容が多く,漠然と苦手意識を持っています。学生時代は座学がほとんどでしたので,臨床に出てから戸惑うことも多いです。
門松 私も学生時代は座学が中心でデバイスに触れる機会はあまりありませんでした。研修医となってからは麻酔科でモニターに触れる機会が出てきて,「なるほど,こういうことか」と実感を持って理解できることが増えてきたところです。
藤澤 お二人ともデバイスに関する話が出てきましたね。多くの研修医も「呼吸管理」と聞くと人工呼吸器といったデバイスの取り扱いを思い浮かべると思います。しかしこの言葉がカバーする領域は,より広範です。例えば酸素ボンベには何Lの酸素が入っていて,どのくらいの時間保つかを知っていますか? これらの呼吸管理にまつわる基礎知識について看護師は習うものの,医師は学ぶ機会があまりありません。デバイスの知識も重要ですが,若手の頃にどの診療科でも役に立つ,より基本的な呼吸管理の知識を勉強するのが大切だと考えています。
熊城 同感です。藤澤先生が指摘された酸素ボンベに関連して言えば,病院の酸素配管や医療ガスの供給システムがどう整備されているのかを知らない人は多いことでしょう。しかしながら,災害等のトラブル発生時には酸素供給が途絶えることがあります。私たちのように急性期部門で働いている場合には酸素供給を何とか維持する必要があり,そうした知識も重要です。デバイスについては門松先生も実感されているように,実際に触らないとわからない部分も多いですので,麻酔科やER,ICUをローテートした際に少しずつ学んでいくという心構えで十分でしょう。
Q1 呼吸数の測定はどれくらい大事なの?
門松 実際に救急の現場で働いてみて感じたことです。SpO2は保たれているけれども呼吸数が多い患者さんがいました。とりあえず大丈夫かなと思い様子を見ていたものの,「呼吸数が多いからすぐに介入しなきゃいけないよ」と上級医に指導されました。先生方は,呼吸数をどの程度意識していますか。
熊城 バイタルサインとして挙げられる項目の中で,目視でわかるのは呼吸数だけです。呼吸数が上がるだけで死亡率は上昇するとされています1)。ショックに至る際の最初の徴候が呼吸数の上昇であることもしばしばあるので,異常を感じたらすぐにアクションを変えるべき指標ととらえて対応に当たっています。経験上,呼吸数を気にしていない研修医の先生はまだ多く,カルテに呼吸数が書かれていないケースも見受けられますが,押さえてもらいたいポイントです。愚直に呼吸数を数える日々を送っていると,一目見ただけで呼吸数の多寡を判断できるようになります。
藤澤 NEWS 2(National Early Warning Score 2)2)などの急変の予測スコアにも確認すべき項目として呼吸数が含まれています。1分当たり30回を超える,つまり2秒に1回のペースより早ければ要注意とされていて,対応のギアを1段上げるべきです。血圧や意識レベルなどの項目に比較すると呼吸数は見逃されがちですが,個人的には非常に意識をしています。
松本 熊城先生が仰る「アクションを変えるべき」や,「対応のギアを1段上げるべき」という藤澤先生の発言の意図は,気管挿管のケースを想定して動くべきということでしょうか。
熊城 そうです。もちろん原因の検索をすぐに始めることは必須ですが,基本的には何らかの重大なイベントが起こっていると想定して対応しています。この時に併せて確認してほしいのは呼吸様式ですよね?
藤澤 その通りです。血液ガスの値が正常でも,ガス交換を維持するために努力呼吸が続けば,いつか破綻します。チェックすべきは顎や頸の筋肉を使用して呼吸する患者さんです。胸鎖乳突筋の動きはわかりやすいので注意して観察をしてみましょう。
熊城 ちなみに血液ガスは読んでいますか? 私が研修医の頃はpH,PaCO2,PaO2,HCO3-をパッと見て問題なさそうであれば「よし,OK」と,簡単にチェックを終えていた記憶があります(笑)。
門松 目は通しているものの,呼吸数が多い際の血液ガスの評価にはあまり自信がありません。
熊城 評価はなかなか難しいですよね。でも少し勉強してみると,血液ガスは病態を推測するツールであるだけでなく,自分の施した輸液や酸素療法によって状態がどう変化しているのかを評価する経時的なツールでもあることがわかってくるはずです。その場ですぐに解釈ができなくても,診察が終わった後に一度じっくりと向き合う時間を確保してもいいかなと思います。
藤澤 私が特に注意しているのは,pHが7.4と保たれていても,PaCO2が20 mmHg,HCO3-が10 mmol/Lのような代謝性アシドーシスを呼吸でなんとか代償しているパターンです。「呼吸が破綻したら一気にアシデミアが進行して心停止するな」という最悪のケースを考えて対応に当たっています。PaCO2が20 mmHg未満であれば危険信号だととらえて注意するようにしてください。
門松 ありがとうございます。呼吸状態を目で見て確認することに併せて,血液ガスの情報を加えて判断していくことが大切なのですね。
藤澤 ええ。得られたさまざまな情報を統合すると患者の状態が見えてきやすいはずです。
Q2 酸素投与の判断基準を教えてください
松本 では次の相談をさせてください。救急外来においてSpO2を測定するのですが,普段よりも若干数値が上下している程度の時に酸素投与の判断を迷ってしまいます。
熊城 基本的に,呼吸数が多いことだけに対する酸素投与の適応はありません。また,酸素投与だけで呼吸苦を改善する効果もないです。逆に,高濃度酸素を過剰に送り込みすぎると死亡率上昇などの悪影響を引き起こす可能性があります3)。ですから原則として,必要時のみ酸素投与を選択するべきです。
では,必要と判断されるときはいつか。重要な判断基準は末梢に酸素が届いているかどうかであり,SpO2の値を軸に丁寧に検討する必要があります。病態によって目標値は異なりますが,心原性ショックなどの場合を除いてSpO2が90%を下回らない限り酸素投与は行わない4),蘇生後は92~98%を維持する5, 6)などの基準が存在しています。基本的には94~98%を目標として,慢性閉塞性肺疾患(COPD)の場合は88~92%とするガイドラインが有名です7)。
藤澤 ただし,救急外来の場合はSpO2がうまく測れない不安定な状態の患者さんが多いため,もし測れなかったとしても全身状態が悪そうならば,酸素投与を開始するのは妥当と考えます。
松本 大変参考になりました。関連した話題なのですが,COPD患者に対する酸素投与は低流量から開始しないとCO2ナルコーシスになってしまうと学びました。しかし臨床に出てみると,低流量から開始しても酸素化がうまくいかずSpO2が80%台後半まで上昇しないこともしばしばです。この場合,すぐにNPPV(非侵襲的陽圧換気)に切り替えるべきなのでしょうか。切り替えのタイミングがわからずお聞きしたいと思っていました。
藤澤 COPD患者に高濃度酸素を投与してはならない理由にはいくつかあります。一つは,低酸素性肺血管収縮への影響です。高濃度酸素を急激に投与すると,一気に肺胞に酸素が増え,V/Qミスマッチに影響を与えてCO2が貯留しSpO2の値が上がらなくなります。もう一つは換気応答です。通常はCO2が溜まれば換気応答が刺激されますが,慢性的にCO2が溜まっているCOPD患者では,酸素の低下によって換気応答が刺激されます。そのため高濃度酸素を投与すると呼吸が抑制される可能性があります。88~92%の間での管理をめざして1~2 Lの低流量から慎重に開始し,目標値に至らないのならば酸素流量を上げつつ,ハイフローセラピーやNPPV,気管挿管を検討していきましょう。
熊城 最も避けるべきは低酸素の状態です。低酸素状態が続けば脳にダメージを負わせ,取り返しのつかない状況を引き起こします。CO2が溜まりすぎるとアシデミアによって命にかかわるケースもありますが,一時的なNIV(非侵襲的換気療法)の使用や気管挿管といった適切な換気のサポートで十分にリカバリーが効きます。低酸素状態の回避や急激に状態が悪化している患者に対しては酸素投与をためらう必要はないでしょう。
Q3 一度開始した治療を終了する場合の戦略は?
松本 一方で,酸素投与を一度開始した患者さんに対する出口戦略はどう考えればよいのでしょうか。どのように投与量を減少させ,最終的に終了するのか。感覚的に行ってしまいがちです。
熊城 面白い質問ですね。私自身,あまり言語化したことがありませんでした。基本的には酸素投与を始めたきっかけの事象が解消されているかが判断基準になります。酸素投与についてはSpO2で規定される部分が多いために,一般病棟ではSpO2の値を確認しながら1Lずつ減量し,最終的に終了の判断をすることになります。その際にチェックしておきたいのは先ほども重要ポイントとして挙げた呼吸様式です。呼吸が楽になったかどうかは,普段の様子を確認していないと判断ができません。普段の患者さんの呼吸状態をよく観察しておくことが大切です。
門松 人工呼吸器の離脱タイミングについてはどうでしょうか。再挿管のリスクも考慮し,どこまで慎重に対応すべきかを知りたいです。
藤澤 確かに,人工呼吸器の装着が長期化すると,人工呼吸器関連の肺炎や肺障害の出現,リハビリテーション開始時期の遅延が生じやすく,また早く離脱しすぎて再挿管になると死亡率が上がることが知られています8)。ベストのタイミングを見極めるのは容易ではありません。そもそもこの問題を考える時には,人工呼吸器の離脱と抜管は別の事象として検討すべきです。前者では酸素化,CO2排泄,呼吸仕事量を人工呼吸器がサポートしなくても大丈夫か,後者は気道や気道クリアランスを維持できるかが判断基準となります。人工呼吸器の離脱に関しては三学会合同ガイドラインをまずは参照してみましょう9)。このガイドラインに準じて離脱を検討している施設は多いはずです。
門松 抜管に関連した問題についても併せて伺いたいです。気管挿管中あるいは抜管後に声が出しにくい,食事がしにくいと訴える患者さんが多いように感じています。これらの原因が生理的な問題なのか,反回神経麻痺などの器質的な障害なのかが判断できず,患者さんに対してどう対応すればよいか,また声掛けをすればよいかいつも迷っています。
松本 患者さんに侵襲がある処置をした際の声かけやフォローは研修医として日々頭を悩ませる点です。無責任なことは言えないですし,どう寄り添うべきなのかを私も常に考えています。
藤澤 門松先生が挙げたように,抜管後に嗄声や嚥下障害が起こるケースは多いです。長期間の挿管やチューブ圧迫による影響など原因はさまざま考えられていますが,どう予防すればよいかはまだわかっていないのが現状です。ほとんどの患者さんで嗄声は半日ほどで症状が改善するものの,長期化する場合は耳鼻咽喉科の医師へのコンサルテーションも検討します。嚥下機能についても抜管後3時間程度で飲水テストを行い,嚥下障害があれば専門的な介入を言語聴覚士に依頼しています。このように長期的にフォローが必要な患者さんもいますので,「次第に改善していくことが多いですが,必要に応じて耳鼻咽喉科や嚥下機能の専門家に相談して対応していきますね」とお伝えするのが良いでしょう。
熊城 長期間の挿管になれば,嚥下機能はやはり低下します。解決手段は現時点でははっきりしたものはなく,予防も難しいです。けれども,これらの問題は退院後のQOLにも大きく影響します。丁寧に気管挿管をしても嚥下機能に影響を及ぼす場合もありますが,気管挿管という手技自体を回避することも念頭に置いて対応を検討する必要があるでしょう。
門松 ありがとうございます。仰るように「人工呼吸器を装着して終わり」ではないので,その後のQOLにどう影響するかを踏まえて行動することは大事だと改めて思いました。
Q4 結局ハイフローセラピーとNPPVどっちを使えばいいの?
門松 最後に質問したいのは,呼吸困難で救急搬送されてきた患者さんに対するデバイスの選択です。ハイフローセラピーかNPPVのどちらを選択すべきなのでしょうか。使い分ける基準があれば教えていただきたいです。
藤澤 判断に当たって大事なのは,それぞれのデバイスは何が得意なのか,目の前の患者さんの病態に対して何を補助したいかを念頭に置くことです。NPPVが優れているのはPEEPをしっかりかけられること,そして換気補助ができることです。例えば一回換気量が200 mLしかない患者に400 mL吸ってほしい時は十分な吸気圧をかけられるNPPVでないと対応できません。エビデンス的に特に試すべきとされるのが,心原性肺水腫とCOPDの急性増悪です10)。
一方のハイフローセラピーは,鼻からしっかりと高濃度酸素を送れるのが長所であり,死腔を洗い流してくれる効果があることから呼吸数を減少させ,患者さんを楽にします。ただし換気量を増やす効果はなく,PEEP効果も患者さんによってまちまちで基本的には期待できない点は注意しましょう。例えば「高い吸入気酸素濃度が必要だが,呼吸回数がそこまで多くなく頸で息をしていない(呼吸仕事量が大きくない)」といった方に使うことが多いです。
熊城 最近は,NIVとハイフローセラピーを比較した研究も多く発表されていて,特定の疾患群においてハイフローセラピーがNIVに劣らないとする論文11, 12)もあることからハイフローセラピーを選択するケースも出てきました。しかしながら,基本的にはCOPDと心原性肺水腫の場合はNIVを用いることが多く,そうでない場合は患者の忍容性,換気の状況を勘案してハイフローセラピーから試してみることが多いと言えます。いずれを選択するにしても大事なのは,治療の強度を上げるタイミングを見逃さないことです。ハイフローセラピーに関連した研究では,ハイフローセラピーを粘って利用し最終的に気管挿管を行った群が,すぐに気管挿管へ切り替えた群よりも死亡率が高かったとされています13)。30分~1時間観察して好転する気配がなければ強度を上げてしまいましょう。
藤澤 NPPVも同様ですね。あまり粘って使用せず,早い段階で決断することが大切です。効果がある人は5~10分ほどの短時間でも楽になります。1日単位で粘るものではありません。
門松 先日NPPVを装着したところ,たちまち呼吸が改善した患者さんを経験しました。劇的な変化を間近で見られて感動したことを覚えています。
藤澤 それは良い経験でしたね。
門松 はい。患者さんがどういう状態で,どこまで治療に耐えられるかが判断において大事ということですね。非常に納得できました。
より幅広い視点で呼吸管理にまつわる問題をとらえる
門松 本日はありがとうございました。印象的だったのは,患者さんの状態をよく見て決断を下すことが大事だということです。呼吸管理はデバイスありきではなく,患者さんありきで考えるべきものなのだと実感できました。
松本 将来どの診療科に進んだとしても呼吸管理は避けて通れない問題ですので,研修医の時期に基本を押さえておくのは非常に重要だと感じましたし,もっと勉強しないといけないなと改めて思いました。貴重な機会をありがとうございました。
熊城 呼吸管理と聞くと,人工呼吸器の設定ばかりに終始しがちですが,呼吸パターン,バイタルサイン,循環の話など,かかわる領域は非常に広範です。デバイスを触るだけでなく,生理学に基づいた観察,診療などもしっかり押さえておくと,より幅広い視点で呼吸管理にまつわる問題をとらえられるようになると思います。
その上で,患者さんにどんな医療を提供しているのかを自分で体験してみるといいですよ。例えば胸にバンドを巻いて拘束性障害のような状態を再現し,NIVをつけて換気サポートを上げていくと,少し吸っただけで胸が膨らむ感覚を得られます。ハイフローセラピーやNIVは体験しやすいと思うので,理解を深めるために先輩医師や臨床工学技士さんに手伝ってもらうのも一手でしょう。
藤澤 今日はありがとうございました。印象深かったのは松本先生からの酸素投与の出口戦略についての悩みごとです。Less is moreの視点は常に大事です。気管挿管されていることでせん妄になったり,離床が遅れたりすることもあります。今の時点で「引き算の大切さ」の意識を持たれていることに感動しました。また門松先生からの患者さんの退院後の生活を見据えた相談についても目の付けどころが素晴らしいなと思いました。どう社会復帰してもらうか,今行っている治療が患者さんにどう影響するかという視点は大切です。この先もぜひ大事にしていただきたいです。
*
藤澤 来月号より呼吸管理にまつわる基本的な知識を取り扱う連載「『あせらない』ためのER呼吸管理トレーニング」をスタートさせます。研修医の皆さんが自信を持って対応できるよう,呼吸管理のエッセンスをお届けできればと考えています。ぜひご覧ください。
(了)
参考文献・URL
1)Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2016[PMID:26940235]
2)Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2. 2017.
3)JAMA. 2016[PMID:27706466]
4)日本蘇生協議会.JRC蘇生ガイドライン2020.医学書院;2021.
5)Neurocrit Care. 2024[PMID:38040992]
6)Intensive Care Med. 2021[PMID:33765189]
7)Respir Care. 2022[PMID:34728574]
8)Crit Care Med. 2011[PMID:21765357]
9)日本集中治療医学会,他.人工呼吸器離脱に関する3学会合同プロトコル.2015.
10)日本呼吸器学会NPPVガイドライン作成委員会編.NPPV(非侵襲的陽圧換気療法)ガイドライン改訂第2版.南江堂;2015.
11)N Engl J Med. 2015[PMID:25981908]
12)Respir Care. 2017[PMID:28807988]
13)BMC Anesthesiol. 2023[PMID:37438685]

藤澤 美智子(ふじさわ・みちこ)氏 横浜市立みなと赤十字病院周術期集中治療部 部長
2001年信州大卒業後,東京医歯大(当時)麻酔・蘇生・ペインクリニック科入局。08年より横浜市立みなと赤十字病院にて集中治療医,呼吸ケアサポートチームメンバーとして活動を開始する。25年より現職。酸素療法や包括的な気管切開ケアに関する教育や執筆,発信を行い,監訳を務めた書籍に『気管切開 包括的ケアマニュアル』(MEDSi)がある。
2025年12月,気管切開ケアの品質改善を目指す団体 “TraCARE” を設立。
X ID:@michifuji54

熊城 伶己(くましろ・れいき)氏 横浜市立みなと赤十字病院集中治療部
2015年神戸大卒。救急・麻酔の研鑽を積んだ後,22年より現職。救急科専門医,麻酔科認定医,集中治療科専門医。急性期の気道・呼吸・循環管理,Point-of-care Ultrasound(POCUS)等を専門としている。
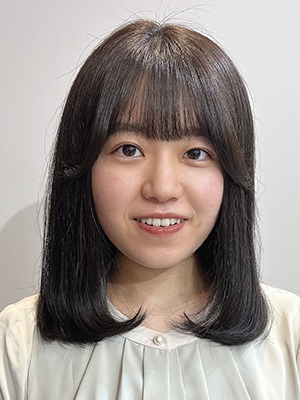
門松 咲南(かどまつ・さきな)氏 東京ベイ・浦安市川医療センター
2025年国際医療福大卒。4月より東京ベイ・浦安市川医療センターで研修中。これまでに呼吸管理にかかわる診療科として救急科と麻酔科をローテートする。

松本 夏奈(まつもと・かな)氏 福岡赤十字病院
2025年佐賀大卒業後,福岡赤十字病院で研修を開始する。現在は同院の総合診療科でウォークイン患者を中心に診療に励む。
タグキーワード
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。