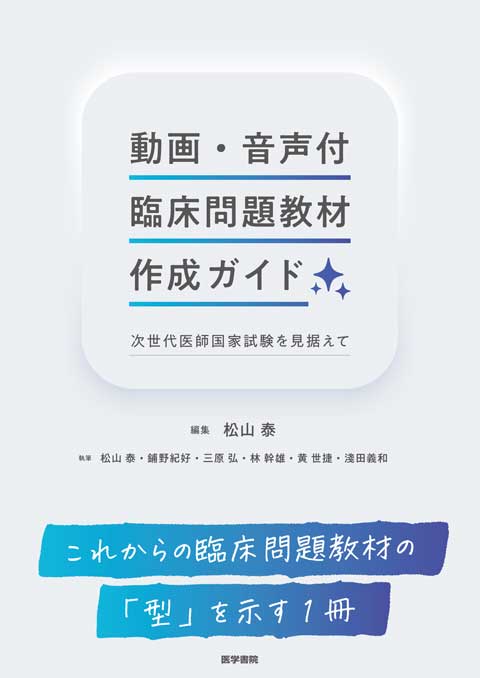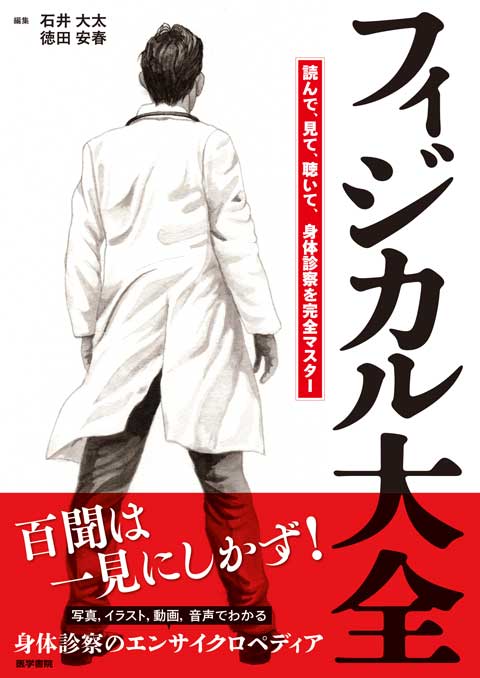動画・音声教材が変える学びのアプローチ
対談・座談会 松山 泰,鋪野 紀好,石井 大太
2025.09.09 医学界新聞:第3577号より

デジタル技術の急速な進化と普及に伴い,医療におけるICT/AIツールはより一般的で手の届きやすい存在となりました。卒前・卒後教育においても,これまで学習の根幹を担ってきたテキストや画像などの静的なツールに加え,動画・音声といったデジタルコンテンツを積極的に活用しようとする流れが進んでいます。本座談会では,デジタルコンテンツが学習者の学びにどのような変化をもたらしているのか,また,医学教育の未来を見据えて,デジタル教材を活用し,身体診察に不可欠な観察力などのスキルをいかに育むかについて議論しました。
身体所見の「正解」を知る
鋪野 松山先生の所属される自治医科大学では,2010年より医学部4年生を対象とした進級判定試験に動画・音声付きの問題を導入されていると伺いました。学生が事前に動画教材で学び,それを現場で確認し,知識の定着度を測るために試験に臨むという,自己調整型の学習サイクルを体現している印象を持ちました。導入を検討していた頃の様子を教えていただけますか。
松山 当時は臨床実習を終えた後に学生の能力や知識の定着を評価する明確な方法がなかったために,基本的な内容が身についているのか懐疑的な部分がありました。そこで,医療面接や身体診察の動画を見てもらい,得られた所見をカルテ様式の解答欄に記述する試験を採用したのです。もちろん記述式の評価は妥当性や信頼性の確保が課題になりますが,現在では一定の精度を担保した試験を実現しています。
重要なのは,学生が動画から情報を読み取り,それを言語化するプロセスを学ぶこと。これは臨床医としての第一歩と言え,そうした意識づけにこの試験が大きく寄与していると感じています。試験導入によって,「現場で異常所見を見ておかないと試験に通らない」という意識が学生に芽生え,臨床実習へ臨む姿勢が変わりました。これらの取り組みの延長線上に生まれたのが,このたび上梓した『動画・音声付臨床問題教材作成ガイド』(医学書院)です。
鋪野 臨床現場での学習は,テキスト化しにくい非言語的な情報をどう認知し,学習するかという点で,言語化された情報である教科書での学習とは大きな隔たりがありますよね。
石井 その通りだと思います。『動画・音声付臨床問題教材作成ガイド』の第1章にも,医師の五感を通じた観察による,能動的な情報認知と言語化の重要性が説かれており共感しました。臨床実習の学生を見ていても,観察する力がまだ十分に育っていない印象があります。非言語的な情報の読み取り方をどう学ばせるかという点は,私自身も試行錯誤しているところです。
松山 最近では生成AIの発展によって,文字情報をもとに即座に回答が得られる時代になりました。現行の文字情報だけで構成された試験問題や教材は,デジタル端末を診療室に持ち込める時代においては相対的に実用性が下がってきています。その一方で,臨床の現場では医師が目で見て得た情報をもとに判断を下す場面は今後もなくなることはありません。それだけに観察力や言語化能力がより重要になるはずですし,今後医師としてさらに問われる能力になるでしょう。
また,臨床で見た情報を適切に言語化できれば,指導医とのコミュニケーションも図りやすくなり,臨床推論を学ぶための入口になるのです。そうした言語化をサポートする教材として,石井先生が編まれた『フィジカル大全』(医学書院)は有用な書籍だと考えています。
石井 ありがとうございます。私自身,学生時代や研修医時代に,身体診察を学ぶ際にとても困った経験がありました。書籍や動画コンテンツはたくさんあるものの,正しい診察の方法や所見の判別,特に陽性所見や陰性所見が実際はどのようなものか,視覚や聴覚を用いて判断しなければいけない感覚的な情報を理解することは難しいです。聴診音のように動的に確認する必要があるものは,「正解」が何なのかが本当にわかりづらかったです。
鋪野 現場でその「正解」を求めても,学ぶ機会に恵まれないこともあるという課題は,多くの学習者が抱える共通の悩みかもしれませんね。
石井 私の師匠である須藤博先生(大船中央病院)は,身体所見を正しく学ぶための条件として,①その所見があること,②その場所に自分がいること,③その所見を教えてくれる人がいること,の3つを挙げています。しかし,施設によってはその「正解」を一緒に確認できる環境が整っていません。ですので,動画教材や音声教材で「正解」をまずは知る。その上で実臨床においてその所見を探しに行く。そんな学び方ができる教材が必要だと強く感じていました。そうした思いを形にしたのが『フィジカル大全』です。多くの先生方に執筆をお願いし,動画や音声をふんだんに盛り込みました。
鋪野 ご自身の学習者としての原体験が出発点にあったのですね。
石井 おっしゃる通りです。この教材が多くの学習者にとって臨床現場での所見に気づくきっかけとなればと思います。
学習者に伝わる所見を「カタチ」に残す
鋪野 私自身も患者さんの身体所見を撮影し,所見の変化の確認に加えて自己学習や教育に活用していますが,教材となる動画・音声を地道に集めていくのは本当に大変だと感じています。その点に関して工夫をされていることがあれば,ぜひ教えてください。
松山 私はハンディのビデオカメラを白衣のポケットに忍ばせ,必要な時にはすぐに録音・録画ができるようにしています。
石井 所見は一期一会ですからね。機会を逃すと,二度と出会えないこともあるため,すぐに取り出せる位置に用意しておくのは重要です。私もベッドサイドでの回診や初診の患者さんを診るときにポケットに忍ばせているものがあります。そ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

松山 泰(まつやま・やすし)氏 自治医科大学医学教育センター 教授
2001年自治医大卒。12年伊東市民病院臨床研修センター副センター長,18年岐阜大医学教育開発研究センター客員教授などを経て,22年より現職。15年蘭マーストリヒト大医学教育学修士課程修了,20年同博士課程を修了する。厚労科研事業「ICTを利用した医師国家試験の評価方法の開発と検証のための研究」において医師国家試験のCBT化に向けた動画音声付臨床問題の開発に携わる。編書に『動画・音声付臨床問題教材作成ガイド』(医学書院)。

鋪野 紀好(しきの・きよし)氏 千葉大学大学院医学研究院地域医療教育学 特任教授
2008年千葉大医学部卒。千葉市立青葉病院臨床研修医,千葉大病院総合診療科シニアレジデント, 同医員を経て22年より同大大学院医学研究院地域医療教育学特任准教授。20年には米マサチューセッツ総合病院医療者教育学修士課程を修了する。25年より現職。基本的臨床能力評価試験(GM-ITE)にて動画問題の作成に携わる。『動画・音声付臨床問題教材作成ガイド』『フィジカル大全ー読んで,見て,聴いて,身体診察を完全マスター』(いずれも医学書院)の執筆に携わる。

石井 大太(いしい・だいた)氏 聖マリアンナ医科大学総合診療内科
2019年聖マリアンナ医大卒。大船中央病院にて初期研修の後,浦添総合病院病院総合内科にて後期研修を修了。24年より現職。同大の専門教育科目である診断学シリーズで講義を担当し,動画コンテンツを活用した身体診察の教育に携わる。編書に『フィジカル大全ー読んで,見て,聴いて,身体診察を完全マスター』(医学書院)。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。