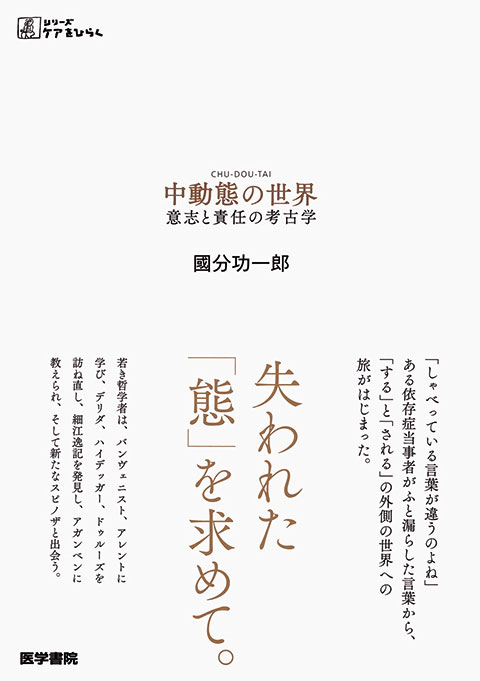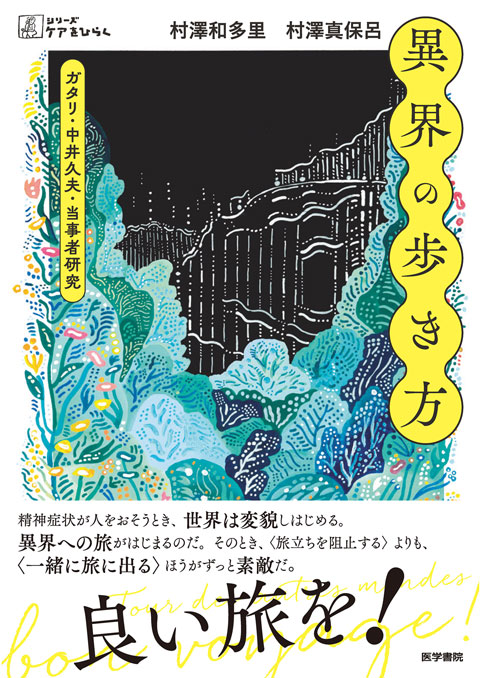精神医療の専門性
「治す」とは異なるいくつかの試み
その不思議な実践の正体は!? 治癒を目指さない精神医療の専門性について考える。
もっと見る
神社のお札(フダ)を利用して精神症状を落ち着かせる。庭にシイタケの原木を持ち込んで関係性を深める。ACT(包括型地域生活支援プログラム)で行われていた、一見、医療とは相容れないような実践たち。そこに潜む、ブリコラージュ的な専門性を、現象学を用いて炙り出す! 日本の精神医療の現状に切り込み、風穴を開ける。精神看護の第一線で活躍する著者による、他に類を見ない試みの1冊。
| 著 | 近田 真美子 |
|---|---|
| 発行 | 2024年03月判型:A5頁:176 |
| ISBN | 978-4-260-05589-5 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
薬ではなく神社のお札(フダ)を活用して、利用者の精神症状を落ち着かせる。
利用者の自宅の庭にシイタケの原木を持ち込んだり、玄関先で、たこ焼きを焼くことで利用者との関係性の構築を図る。
本書には、このように、一見、医療とは相容れないユニークな実践を展開する専門職らが登場する。彼らは、重度の精神障害者の地域生活を24時間365日地域で支えるACT(Assertive Community Treatment:包括型地域生活支援プログラム、以下ACTと略す)というプログラムに従事する看護師や精神保健福祉士、精神科医であり、国家資格を有する正真正銘の医療専門職である。
本書は、こうした“医療”と形容するには憚(はばか)られる実践のなかに、精神医療の専門性を炙り出そうと模索した記録である。炙り出すために活用したのが、ACTで働く医療専門職たちの即興的な語りと、近代哲学が生んだ現象学という道具である。
さて、議論をはじめる前に、そもそも私がどうしてこの活動にのめり込むことになったのか、というところからはじめることにする。
私が新人看護師となって初めて就職したのは、北海道の南端部に位置する浦河赤十字病院の精神科開放病棟という、慢性の統合失調症を抱えた患者が療養生活を送っている病棟であった。かつて自分が生を受けた病院へ就職するという縁に高揚しつつも、「希望者があなたしかいなかったから」というあっけない理由で精神科病棟への配属が決まったときの戸惑いは今でも鮮明に覚えている。しかし、こうした不安は、入職してすぐ吹き飛ばされることとなる。
浦河といえば、今でこそ、当事者自身が自分の病を研究という方法で探求する「当事者研究」1)で注目されているが、私が臨床で働いていたときの病棟で展開される医療は、当事者研究という側面からだけでは捉えきれない面白さや豊かさで溢れていた。
例えば、入院に至るまでの経過を苦労のプロセスと捉え、患者と一緒に振り返り共有したり、看護計画は医療専門職が解決すべき“問題”ではなく、患者の“課題”として返すべきであるという考えに立ち返り、ナースステーション内で、患者と共に看護計画を立案したり、幻聴を「幻聴さん」と名づけ、患者の身に起きている世界を共有するため、積極的に幻聴や妄想の内容を申し送りで公開し、幻聴との付き合い方について自分たちも一緒になって考えるなど、スタッフ自身が創造性を働かせながら、病棟内を自由に泳ぎ回っていた。
患者が入院してすぐ開催される入院時カンファレンスには、同じ病を抱えた地域で暮らす当事者らも同席したり、当時、病棟医であった川村敏明医師は、病院外を散歩中にたまたま出会った患者と立ち話することで回診を済ませるなど、病院の内と外を隔てる壁を感じさせない、規律の少ない柔軟なシステムで運営されている病棟であった。「病棟の規則をつくることは簡単だが、一度、つくってしまうとなくすのが難しくなる」という信念のもと、医療専門職として“すべきこと”と“してはいけないこと”を見極めるための話し合いを常に欠かさなかった。
なかには、幻聴がひどくなるなど精神症状が悪化する患者もいたが、幻聴ミーティングという場で苦労を公開する場が設けられていたこともあり、過剰な薬物投与を行ったり、隔離や拘束といった行動制限が必要なケースまで発展することは皆無であった2)。このときに味わった医療専門職としての“幸せ”な経験が、精神科看護師としての私の原点となっている。
その後、医療専門職としての技量を高めるべく浦河赤十字病院を離れた私は、患者の精神症状を薬物療法や行動制限で過剰にコントロールしようとする医療専門職の姿を目にすることで、日本の精神科医療が抱える問題を知ることになる。そして、浦河赤十字病院の精神科開放病棟で繰り広げられていた実践とは一体何だったのか、悩んだ末に、精神科看護における専門性の希薄さについて警告を鳴らし続けていた阿保順子教授の研究室に飛び込んだのである。
阿保教授は、少女のような無邪気な笑みのなかに鋭い眼光を宿しながら「看護師はなんでもやってきたし、何でもできる。だが、何者でもない」「(看護師の学修意欲の高さを揶揄しつつ)お勉強が、改革や発展に直接貢献することはない」と、マニュアルに従って行動するだけで思考しようとしない精神科看護の姿を痛烈に批判してきた。
また、精神科看護の専門性を支えてきた対人関係論やセルフケア・モデルの限界を指摘した上で、「分裂病(統合失調症)が病気であるという考えに立つこと、それが人にもたらす苦痛に沿っていくという意味において必要なのである」と述べ、中井久夫の寛解過程論(1984)をベースに看護行為の意味を導き出す精神構造モデル3)を生み出した。この精神構造モデルは、統合失調症の急性期にある患者はなぜ同じ話を反復するのか、なぜ、徘徊という行為が存在するのか、なぜ入浴を拒むのかといった「病気」についての理解を徹底的に深めていくことで、病者の行為の意味を理解し、適切な対応へと導くというものであった。
確かに、患者が病に罹患している以上、病そのものに対する理解を深めるのは、幻聴や妄想といった精神症状に悩まされている人の苦痛に沿う医療専門職として必要な営みである。加えて、この精神構造モデルという枠組みは、患者の行為の意味を徹底的に探求するという点において、精神科看護の専門性の充実をもたらす可能性を大いに秘めていた。
とはいえ、精神構造モデルという歯切れのよい枠組みも、病への解釈を強化し患者を一方的に眼差すなど、活用方法を誤ることで、かえって病者と距離をとるための道具と成り下がってしまう危険性もあるのではないか、そんな疑念が頭をよぎった。
「精神医療や看護の専門性とは、いったい何なのか……」
自分のなかで適切な答えを見つけ出せぬまま、偶然にも阿保教授の知り合いでACTというプログラムを地域で立ち上げる精神科医がいるという話を聞き、どのような実践をしているのか見てみたいと興味半分で診療所に赴いた。
そこで出会った同世代の医療専門職らの実践は、私が浦河赤十字病院の精神科開放病棟で経験した実践とは、また別の専門性の在り方を見せてくれたような気がしたのである。このとき、感じた衝撃については、補章の「ACTとは何か」でも言及するが、まずは本論で紹介する5名の実践家の語りを通して、感じていただけたらと思う。
私がはじめてACTという世界に足を踏み入れてから、すでに15年以上が経過した。その間、ACTには、さまざまな医療専門職が入れ替わり立ち代わりやってきては去っていった。研究者という形でインタビューに伴走しつつも、ときには研究する者とされる者という関係性を超えて、共に学習会やワークショップを企画したり、日本の精神医療の現状と行く末について居酒屋で愚痴を言い合い議論を交わしたこともある。ACTに来たばかりの精神保健福祉士の研修先にと浦河べてるの家を紹介したこともあれば、地域で働きたいという学生の就職相談に応じてもらったこともある。
また、彼らと共に1970年代に公的な精神科病院の廃止を成し遂げたイタリアの地域精神保健の現場をくまなく視察し4)、本場のジェノベーゼソースを絡めたパスタに舌鼓を打ち、出来立ての熱いピッツァを頰張りながら、地域における医療専門職の責任や専門性についても議論を交わすという経験もした。このときの視察で、胸に強く刻みこまれたのが、精神保健センターの廊下やオフィス内の壁など、訪れる先々で目にした精神科医バザーリア(Basaglia)の写真とこの言葉である。
「重要なのは、私たちが不可能を可能にしてみせたことです。10年、15年、あるいは20年前であれば、マニコミオを破壊することなど考えもしませんでした。もしかしたら、マニコミオは、ふたたび閉ざされてしまい、以前よりもっと固く閉ざされてしまうかもしれません。それは私にはわかりません。とにかく私たちは、これまでとは違ったやり方で狂気を抱えた人を支援できることを示したのです。この私の証言が揺らぐことはありません。しかし。ある行為を広めることができたとしても、それがそのまま勝利を意味するわけではありません。大事なことは別にあります。つまり、不可能だと思われていたことも可能になるということを、今では人々が知っているということが大事なのです」5)
Franco Basaglia リオデジャネイロ 1979年6月28日
浦河赤十字病院の精神科開放病棟での経験を出発点として日本の精神医療の現状に直面し驚愕するなか、ACTと出会い、その魅力に巻き込まれてはや十数年が経過した。世界にも類を見ないほど精神科病院への長期入院を余儀なくされている患者が多く、地域生活中心へと転換しきれていない日本において、ACTというやり方で重度の精神障害者の地域生活を支えている人々が存在している現実を、どのように示し伝えていくことができるだろうか。ACTで働く医療専門職の活動に伴走し、ACT実践の目撃者である自分にできることは何であろうか。悶々としつつも、終始一貫していたのは、私が精神科看護ならびに精神医療における専門性について、こだわり続けてきたという点であろう。
さて、本書の構成と概要は以下のとおりである。
本書は、ACTで働く医療専門職の実践の成り立ちを、現象学という道具を用いて可視化する営みを通して、精神医療における専門性を探求したものである。
序章では、入院医療中心から地域生活中心へと転換しきれていない日本の精神医療の現状について、患者と医療専門職の非対称性をはらむ関係性という観点から整理した。
続く第1章から第5章では、ACTで働く医療専門職5名(看護師3名、精神保健福祉士1名、精神科医1名)の個々の実践の成り立ちを示した。お札やシイタケの原木を用いるといったユニークな実践を、従来のように、感性や個性という表現で片づけて手の届かない場所へ放り出すのではなく、彼らが事象をどのように意味づけていたのか、経験の内側から眼差すことを試みた。
第6章では、そこまでの議論を踏まえながら、ACT実践から見えてきた精神医療の専門性について言及した。
本書は、閉塞感ただよう日本の精神医療に希望という名の未来を見出したい、そんな切なる願いを込めて書かれた。本書を通じて、専門職1人1人が精神医療の専門性を問い直し、医療が、再び人々の人生を支える堅固でしなやかな杖として息を吹き返し、そこに、支援する人、される人、お互いにとっての幸福となる道筋を見出せれば、幸いである。
目次
開く
はじめに
序章 日本の精神医療の現状
1.政策の推移
2.病院と地域という場における支援観の相違
3.精神科病院という空間における患者と医療専門職の非対称性
4.多様な価値観が内包された地域という空間
5.地域という場における専門性とは何か
第1章 支配から信頼へ──精神症状をその人の本質として捉える
1.固有の語りから専門性を炙り出す
2.患者の見え方の違い──精神科病院と自宅
3.生活を支配する支援への疑問
4.「その人が考える」ことを目指す
5.利用者の主体化を図る基盤としての安心と信頼
6.地域では見れないという感覚の消失
7.精神症状を人間らしさの本質として捉える
第2章 薬より、お札やったんや!──専門職としてではなく、人として関係性をつくる
1.さまざまな実験を行う実践
2.「この世界」への応答
3.人としてあたりまえの感覚
4.「孤独」から「一緒」に
5.ウルトラ問題児から普通の姉さんへ
6.精神医学以外の方法による接近
第3章 「治す」ではなく「暮らす」を目指して──精神疾患を病ではなく、その人の苦悩の一形態と捉える
1.実践は暴力的な意味を帯びていた
2.症状ではなく、困りごととして取り上げる
3.関係性の反転をはらむ「ごめんなさいとありがとう」
4.「薬が必要」から「薬が自然」へ
5.精神疾患をどう位置づけるかで実践は劇的に変化する
第4章 意味のある支援──主体化を目指し、利用者に責任を返しながら伴走する
1.表面的には捉えにくい事象への関心
2.ホールディングを保証する
3.手当ができる距離まで近づく
4.背後にあるものを読み取る
5.意味のある支援を展開する
6.利用者に責任を返しながら主体化を目指す
第5章 医療から社会生活へのシフトチェンジ──保護的な支援から、いつか到来する「自己実現」に向けた支援へ
1.利用者のリカバリーに関する問題
2.ACTの限界を起点として
3.振り回されるという意図を込めた関係づくり
4.支援の限界点──良質な抱え込みから悪質な抱え込みへ
5.利用者の新たな顔を見出す──人と場の拡大
6.医療から生活支援へ
7.支援者中心から本人中心の支援への視点の転換
8.自分本位から自己実現に向けて
9.保護的な支援からの脱却
第6章 精神医療の専門性をつくり変える
1.維持・管理から離れて発揮される専門性
2.支援の出発点としてのホールディングと苦楽を共にするという経験
3.地域生活の維持という状態からリカバリーへの転換
4.専門性の方向を見定める
補章 ACTとは何か
1.ACT-Kとの出会い
2.ACTの概要
注一覧
初出一覧
引用文献
あとがき
索引
書評
開く
精神医療の専門性を新たに問い直す画期的な書
書評者:榊原 哲也(東京女子大学現代教養学部人文学科哲学専攻・教授)
本書は,「精神症状」に着目し,「薬物療法」等によって症状を管理して治療を行う,日本の精神科病院において支配的な「医学モデル」に根差した精神医療に対して,それとは異なる試みを参照することで,「精神医療の専門性」をあらためて問い直そうとしたきわめて意欲的な試みである。
著者は,浦川赤十字病院の精神科開放病棟で精神科看護師としてのキャリアを始めたが,別の現場で患者の精神症状を薬物療法や行動制限で過剰にコントロールしようとする医療専門職の姿を目の当たりにして,現代日本の精神科医療が抱える問題に直面し,阿保順子教授(北海道医療大学,当時)の研究室に跳び込んだ。そして阿保教授の紹介で,重度の精神障害者の地域生活を24時間365日地域で支えるACT(包括型地域生活支援プログラム)に出会って衝撃を受け,一気に魅了された。本書の副題にある〈「治す」とは異なるいくつかの試み〉とは,まさにこのACTの実践の試みである。
本書では,序章で日本の精神医療の現状が示されたあと,第1章から第5章にかけて,京都のACTで働く看護師,精神科医,精神保健福祉士,計5名へのインタビューの現象学的分析から,彼らそれぞれの実践の成り立ちが鮮やかに明らかにされ,これらを受けて,第6章で精神医療の専門性が問い直される。限られた紙幅では,5名の方々のユニークかつ魅力的な実践の成り立ちを,具体例とともに詳しく紹介することは叶わないが,以下,評者なりの仕方で簡潔にまとめてみたい。
■利用者との間に「信頼」が生まれ,利用者の主体化と自己実現がめざされる
精神症状だけに目を向け,積極的に薬物療法を行使する医学モデルでは,症状観察や薬物管理が重視され,精神症状の増悪に対しては入院による行動制限という措置がとられがちである。ところが,ACTでは,精神疾患による「症状」の「治療」ではなく,地域で生活していくうえでの「困りごと」に着目し,その地域で暮らしていけることをめざす(第3章・高木医師)。それゆえ,医療者側の意思で利用者の生活をコントロールするような支援ではなく,その人が「素になって」一人で考えて自分で答えを出せるよう,利用者を信頼して「待つ」ことが重要になる(第1章・安里看護師)。
重度の統合失調症の利用者は,妄想や幻覚・幻聴といった孤独な病の世界にいて,現実世界との間でたびたび摩擦を起こすが,ACTのスタッフは,それでも利用者の好きなこと,関心事に注目して,例えば保護室の壁に神社のお札を貼るなど,能動的にアプローチ(「実験」)し,利用者の孤独な世界に風穴を開け,コミュニケーションを図ろうとする。こうした実践を支えているのは,あなたが「心配」だから,という利用者に対する医療者の気がかり,利用者の「安心」をめざそうとする医療者の「関心」である。また,こうした実践を通じて利用者と苦楽を共にすることにより,利用者との間に「信頼」も生まれるのである(第2章・大迫看護師)。
それだけでなく,医療者の「関心」は,利用者の生活環境やそこにある道具(例えば「黒電話」)にも向けられる。道具から利用者の関心や生活状況が見えてきて,具体的な支援につながるのだ。めざされるのは,利用者に伴走しつつも,利用者自身が自分で考え課題に向き合い「自分で責任をとって」いけるような「利用者の主体化」だ。精神症状を有する利用者を医の論理によって保護的に扱うのではなく,利用者に責任を返しつつ主体化を促すことがめざされるのである(第4章・福山看護師)。ACTにおいて最終的にめざされるのは,支援を「医療」から「生活支援」へとシフトさせることである。家族や近隣住民といった「周りの心配事」に着目すると,「医療」的な措置がとられ,それが「医療の責任」として正当化されやすい。医療専門職者で構成されるACTもその傾向は免れない。しかし大切なのは,家族や近隣住民や支援者の「心配事」から,利用者本人の10年先を見据えながら本人中心の「生活支援」を行い,利用者本人の「自己実現」をめざすことである。まさに「本人が社会生活をしていく」というゴールがめざされるのである(第5章・金井精神保健福祉士)。
■スタッフの主体化が利用者の主体化を後押しする
第6章では,以上5つの章の考察が改めてまとめられたうえで,「精神医療の専門性」が問い直される。ここで注意しなければならないのは,「医学モデル」「医の論理」を著者が否定するわけではないという点である。「地域生活支援において必要な精神医療の専門性」とは,「医療者中心ではなく利用者中心の支援であることを踏まえたうえで,医学モデルとそれ以外の価値を同等に扱い,状況に応じて活用できる力」なのだと著者は述べる。大切なのは,「利用者の主体性を回復するという,まさに利用者の主体化へのプロセスを支える支援」であるが,そのためには「スタッフの主体化」も必要である。医療専門職自身が医学モデルを踏まえつつもそれを相対化して遠近法的に眼差すことによって,専門職として主体化することで,利用者の主体化も実現するのである。
現象学という哲学を専門とし,ベナーの現象学的看護論に関心を寄せる評者にとっては,利用者の関心に注目する医療者の関心が利用者に伝わることで信頼関係が築かれていく大迫看護師の実践が,ベナーの看護論を想起させ,利用者に責任を返しつつ利用者の主体化をめざす福山看護師の実践が,自分で自分を気遣えるよう気遣いを相手に返す他者への気遣いを説くハイデガーの思想とリンクするなど,触発される部分が数多くあったが,詳細を述べる余裕は残念ながらない。しかしいずれにせよ,本書が,精神医療,精神看護に関心をもつ者だけでなく,現象学という哲学を研究する者にとっても必読の好著であることは間違いない。
(「看護研究」 Vol.57 No.3 掲載)
精神医療の専門性を問い直す
書評者:小瀬古 伸幸(訪問看護ステーションみのり)
書評を見る閉じる
読後の感想は「衝撃」の一言に尽きる。何が衝撃かと言うと、これまで私たち精神科医療に携わる者が重視してきた経験の持つ意味が、現象学という手法を用いて見事に言葉にされ、本書のなかに散りばめられているのである。
本書はACT(Assertive Community Treatment)に従事する支援者の実践を事象への意味づけという段階から可視化した、著者の博士論文がもとになっている。ACTでは重度の精神障がい者の地域生活を24時間、365日支えるという性質から、その専門性は高く、他の在宅ケアでの活用は難しいと考えられがちである。しかし、本書を読めば、その思い込みは一蹴され、むしろ共通項が多く、私たちが上手く言葉にできなかった「治す」とは異なる試みの本質的な意味が理解できる。
例えば、p.132に「安里氏の実践は、利用者と苦楽を共にし、彼らの素の姿が見えてくるという見え方の変化が地域生活支援を可能にすることを示していた」と記されている。私たち精神科訪問看護の実践においても、苦労を苦労のまま受け入れ、その苦労を共有しながら試行錯誤していくプロセスを重視している。そして、その苦労を乗り越えた先には、笑顔や喜びも分かち合えるものだと考えている。この関係性には「寄り添う」という体験の共有が内包されており、それがケアとして意味を持つものだと思っている。
しかし、私の実践において、それだけでは説明のつかない側面もあった。それは「なぜ、支援者はその大変さにくじけず、寄り添えるのか」ということである。その問いに対するひとつの答えが、近田氏の記した「彼らの素の姿が見えてくるという見え方の変化が地域生活支援を可能にする」という言葉にあった。つまり、その試行錯誤に追い詰められたときにこそ、本来のその人らしい姿や望む人生の方向性が浮かび上がり、その時間を共にすることによって、医療の枠を超えた素の姿を受け入れる自然な現象が起こっていたのではないかと考える。
このように在宅支援者として私たちが行っている実践には、専門書には記載されていないが、その人の本質的な理解を促す関わりが含まれている。これは、直線的に考えれば専門的知識の文脈にはあまり適合せず、医療とは異なる見え方になるかもしれない。ところが、近田氏の述べる「専門性の主体化」という観点から考えると、それは医療と異なるものではなく、むしろ混ざり合うものであるという意味が理解できる。最後に私が最も印象に残った近田氏の言葉を紹介したい。
「問題は専門性の方向なのだ」
この言葉を聞くと、また「専門性とは何か?」という、目的地の見えない旅が始まるかもしれない。しかし、精神科医療の専門性とは、そういうものであり、そういうものであることを忘れてはいけないと思う。
(「訪問看護と介護」 Vol.29 No.3 掲載)
地域のすべての支援者への贈り物として
書評者:高木 俊介(精神科医(ACT-K)/京都・一乗寺ブリュワリー代表)
書評を見る閉じる
僕らがACT(包括型地域生活支援プログラム)を京都で始めて、ちょうど20年になる。ただただこの国の閉塞した精神医療、福祉に風穴を開けたくて、ひた走ってきた。10年も過ぎた頃、その熱意だけの実践に行き詰まりが見え、組織に綻びが生じはじめたことに気づき、持続のための模索をはじめ、今、ようやく僕らのACT-Kは第二のスタートラインに立ったところだ。
そんなとき、僕らの実践にはじまりから注目し続けてくれていた近田真美子さんから、素敵な贈り物が届いた。彼女は、僕らの「ユニークな実践」を単に個人の力量という特殊一回性のものとして片付けてしまうのではなく、スタッフ個々人への膨大なインタビューを現象学的に分析して「彼らが事象をどのように意味づけていたのか、経験の内側から眼差」してくれた。精神医療の専門性がその眼差しによって問い直され、「再び人々の人生を支える杖」として甦るのだ。
僕が自分で書いたり話したりしているのは、社会に精神医療改革を求めるアジテーションであり、自分自身の日常の実践を詳しく語ることはあまりしない。なぜなら、自分の行いを本人が公に語るとき、特に対人支援の実践では無意識の美化や偏りが避けられず、ほんとうに大切なところは自身の主張から外れたところにあるからだ。
そして、あらゆる新しい実践は、高らかな理念を掲げていても、足元の現実の中からしか立ち上がらない。この現実という泥の中に首までつかったまま、実際に成し遂げられることは、小さい。語れば語るほど、奢りと陳腐化が生まれ、組織は硬直する。だが、語られない実践はこの現実の旧弊な土壌に埋もれる。行い継がれることなく、消える。精神医療はそうやって、あらゆる抵抗と試みを呑み込んで停滞してきた。
近田さんの本書は、僕らだけでは埋もれるままにしておくしかなかった僕らの試みを、僕らの知らないどこか遠くにまで運ぶ。「『治す』とは異なるいくつかの試み」という不思議な種を、多くの場所で芽吹かせてほしい。僕ら自身もまた、彼女の眼差しの中に自分たちの知らなかった自分たちを知り、新しい歩みをはじめる。
ありがとう、こんちゃん。
(「精神看護」 Vol.27 No.3 掲載)
寿司職人と美容師と精神医療の専門性
書評者:磯野 真穂(医療人類学者)
書評を見る閉じる
本書を読みながら,寿司職人や美容師が,自分の専門性についてこんなふうに悩むことがあるだろうか,と考えた。理由は,著者自らが当事者として,精神看護学と精神医療の専門性に悩み,遂には博士論文まで書いてしまっているからである。加えてあとがきでは,審査員の斎藤環氏に「あなたが言いたかった精神医療・看護の専門性とは何か」と問われ,しどろもどろになりながら答えたというエピソードまで吐露される。何が著者をここまで悩ませたのか。
本書は,重度の精神障害者の生活を,地域で支えるACT(Assertive Community Treatment)に携わる医療従事者への聞き取りに基づいている。そこで逆照射されるのは,精神医療や精神看護の現場においてしばしば見られる専門性の発露のされ方が,むしろ異様であるということだ。
その専門性とは,例えばこんなことである。指示から外れる患者のさまざまな行動を,「症状」とか「逸脱行動」といった形で医療の言葉に置き換えて理解し,その解釈のもとに,患者の行動変容を促す技術を動員する。「退院させる」というように,医療者が主体で患者が客体であることを前提とした会話が普通になされる。専門知識,技術,権限を用い,患者を自分たちの価値観に染め上げることが当然とされる。
これらは一見ありふれたことのように思える。病院とは多かれ少なかれそういう場所だ。しかし,寿司職人や美容師がこんなふうに自らの専門性を発揮したら,つまり,自分は専門家なのだという自負のもと,あれをしなさい,これをしてはならない,私の考えの方が正しい,などと言い出したら,かれらの店はすぐに閑古鳥が鳴くだろう。かれらの専門性は,素人を思い通りに動かすためにあるわけではない。それは,客の人生を楽しくするために発揮されてこそ光り輝く。
それを踏まえると,ACTに従事する人々の患者との関わりこそが,あるべき専門性の発露ではと思えてくる。魔物退散を願って火を焚く患者に,火を起こす際の油の調合を尋ねるとか,植物好きの患者の家に,シイタケの原木をそっと置いてみるとかいった関わりは,精神医療の専門性とは何の関係もないように見える。しかしこれらはすべて,かれらが持つ専門性と患者の暮らしの接点を探るための試みであり,その根底には,患者と患者を取り巻く人たちの暮らしに,自分の専門性をどのように活かせるか,という問いがある。これを専門性と呼ばずして何と呼ぼう。
15年以上前,あるシンポジウムの質疑応答で,お昼の時間に間に合わないと怒鳴り散らす参加者に遭遇した。「むしろあなたのせいでお昼が遅れる」と遠巻きに眺めていただけであったが,ACTの専門家であれば,私には思いもよらない関わり方をし,かれらの専門性は,人間に対する私の見方すらも変えてくれたのではないか。そんな読後感すら抱かせる,温かい希望に満ちた1冊であった。
ただ最後に苦言も呈したい。本書では,協力者の語りとその分析に,下線,太字,色文字,複数の種類の括弧が多用され,逐語録は付されていないにもかかわらず,「(逐語録,p.~)」といった但し書きが何度も登場する。語りに忠実であろうとする姿勢には敬意を表したい。しかしこれらの特殊表記に注意を奪われ続ける結果,本書の肝である語りに集中できない。現象学的研究の方法に則るとのことだが,このような形で読者の主体性を奪う作文は,現象学の本質とも,本書の意図とも相容れないのでないか。一考を促したい。