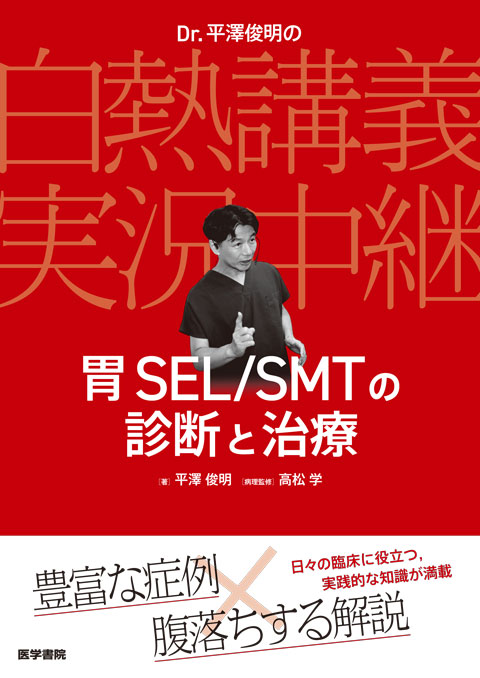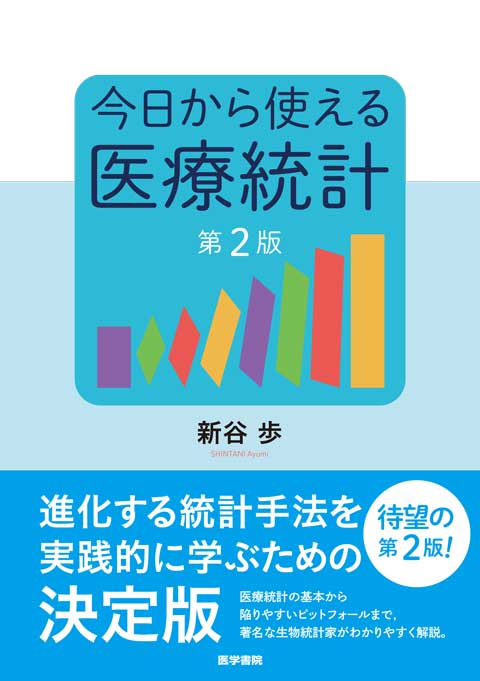MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2025.03.11 医学界新聞:第3571号より
《評者》
阿部 展次
杏林大教授・消化器・一般外科学
同大病院上部消化管外科診療科長
良書との出合いはいつでも素晴らしいものだと実感できる,そんな一冊
一通り目を通し,さて,書評を書こうかと思ってリビングで本書を広げていると,医学部4年生の息子がやってきて本書を手に取り,しばし目を通した直後に「何これ。めっちゃわかりやすいじゃん。講義でこの領域聴いたけど,何が何だかわからなかった。知識が整理できるなあ。ちょっとしばらく借ります」と言って自室に持っていってしまった。書評を書こうかとせっかく重い腰を上げたのに出鼻を挫かれた感があったが,すぐさま,このエピソードは使える,と思い直した。この愚息の放った一言は本書の本質を突いたものであった。
胃の内視鏡治療・外科治療に携わる私の仕事の多くは胃癌に関するものであるが,胃の粘膜下病変(subepithelial lesion:SEL)の診療に当たることも少なくない。胃SELには多彩な病変が含まれており,鑑別診断が時として難しく,治療方針も病変によって大きく異なる場合が少なくない。頻度が低いことからも,体系的に学べる成書は極めて少なく,消化器内科関連雑誌の特集号が散発的に発刊されるだけである。そのような中,満を持して本書が刊行された。本書では,長年にわたり胃SELの診療に携わってきた著者の平澤俊明氏が持つ豊富な経験を通じ,SELの分類や頻度,(質的・鑑別)診断の実際,各々の病態,病理像,重要なリサーチ結果,治療法などが,満載される美しい画像とともに網羅・整理・解説されている。
平澤氏は本書を作成するにあたり,受験生のときに巡り合った「予備校講師の実況中継」というシリーズ参考書からヒントを得たという。実況中継とはどういったものなのか? 文書で実況中継が可能なのか? といった思いで読み進めた。そしてすぐにわかった。とにかくわかりやすい。レイアウトにも工夫が凝らされ,視覚的に理解がどんどん進む。混乱あるいは理解が十分でなく頭の中で?が浮かんでいると,本書ではすかさず「Point!」「さらに掘り下げ!」「まとめ」「Note」「コラム」などが差し込まれ,読者が抱くであろう(素朴な)疑問点に対して鮮やかに知識が補填され,まさに「腹落ちする」方向で読者を満足させていく。これが本書の真髄となる「実況中継」ということであり,あたかも読者が手を挙げて質問するであろう内容の回答が用意されているのである。見事な構成と言わざるを得ない。自身が3回も経験したアニサキス症とアニサキスの生態に関する記述もここまで掘り下げて記述されたものはなく,執念すら感じて実に微笑ましい。楽しく読める,これも本書の大きな特徴であろう。
評者は胃SELに関しては日常臨床に携わるだけでなく,医学部3年生の講義も担当している。本書を読んで,ああ,このように講義すればいいよな,と再考させられた。このように,本書は年代・職位にかかわらず,SEL診療に関与する全ての消化器内科医,消化器外科医に大いに役立つものとなろう。全ての読者が「腹落ち」し,満足すること間違いなし,必読の書として自信を持ってお薦めする。また,医学生や研修医などの初学者が手に取れるよう,医学部図書館や医局単位での所蔵も望まれる。良書との出合いはいつでも素晴らしいものだと実感できる,そんな一冊である。
《評者》 神田 善伸 自治医大教授 / 同大さいたま医療センター教授・血液学
医療統計に立ちはだかる壁が崩れ,視野が広がる一冊
医療統計解説書のベストセラー,『今日から使える医療統計』の待望の第2版が刊行された。本書は皆さんご存じ,大阪公立大学大学院医療統計学の新谷歩先生の著書である。
新谷先生は米国ヴァンダービルト大学から帰国されて以来,日本の生物統計学の脆弱な基盤を改善するために教育的活動に熱心に取り組まれている。多くの医師が感じる医療統計の高い壁。本書を読むことでその壁が徐々に崩れ落ち,視野が広がっていく。そんな一冊である。
10年ぶりの改訂となった第2版では,リスク比やオッズ比,回帰分析のメカニズム,欠損値の補完,繰り返し計測データの解析,ベイズ法などの実践的な項目が追加された。偶然か否かを示す値に過ぎないP値は,効果の大きさを表すことはできない。やはり,重要なのはリスク比,オッズ比などのエフェクトサイズを理解し,活用することである。また,後方視的研究において必然的に生じる欠損値をどのように考えるか,補完しない場合/補完する場合の問題点がわかりやすく解説されている。ベイズ法は臨床医の日ごろの感覚に,より近いと感じられるかもしれない。
巻末には新谷先生のYouTubeチャンネルの教育動画のQRコードが掲載されている。なんとその数は122本である。これだけでも新谷先生の医療統計教育にかける情熱が伝わってくる。かたや私は血液内科医であり,代表著書は同じ医学書院から刊行の『血液病レジデントマニュアル 第4版』である(宣伝)。医療統計の専門家ではない私がなぜ本書の書評を執筆させていただいているのか。それは,私が個人的趣味で開発し,無料公開している統計ソフト「EZR」を新谷先生も教育現場で積極的に活用してくださっており,私自身もEZRのバージョンアップ作業においてしばしば新谷先生に相談させていただいているつながりからだろう。
新谷先生が「EZR」に関連する書籍を出版された際には,私のEZR書の売り上げが落ちるのではないかと心配したが,逆にEZRの知名度を高めてくださることで拙著の売り上げも上昇した。おかげさまでEZRの開発を紹介した論文の被引用回数は1万2000回を超えている。
新谷先生にはこれからも,医師を正しい医療統計解析へと導いてくださる架け橋としてご活躍を続けられることを期待している。
《評者》 伴 正海 おうちの診療所目黒院院長 / 医師
多職種による質の高い看取りの実現のために
◆アセスメントからケアプランまでを階層的に導く
『インターライ方式 看取りケアのためのアセスメントとケアプラン』は,20か国の研究者(フェロー)で構成されるインターライ(本部は米国)が開発した国際標準のアセスメントツールのうちの1つである。このたび池上直己氏らにより翻訳され,このたび医学書院から出版された。
インターライ方式の特徴は,アセスメント担当者...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。