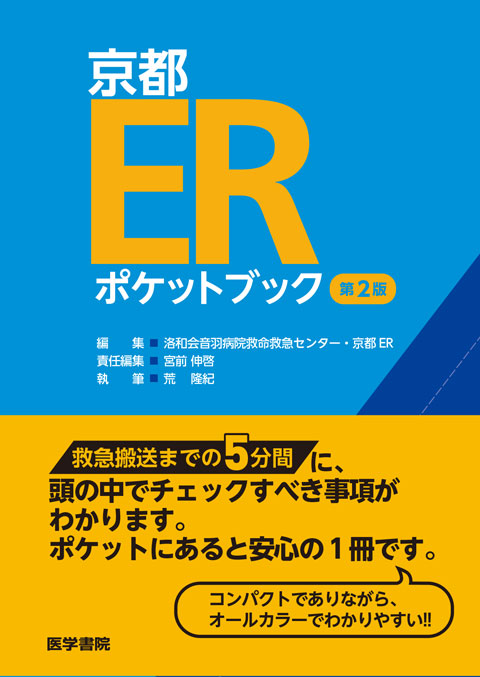ピットフォールにハマらないER診療の勘どころ
[第23回] 胸骨圧迫の中断時間を最小限に!CPRリターンズ
連載 徳竹雅之
2024.04.09 医学界新聞:第3560号より
おかげさまで,本連載が始まってからあと少しで2年が経過しようとしています。これまで心肺蘇生(cardiopulmonary resuscitation:CPR)に関連する話題を2回取り上げましたが,その間にもガイドラインは次々と更新されました1, 2)。
今回は,変わらぬ重要ポイント,陥りやすいピットフォール,そして今後スタンダードになり得る内容を総まとめします。ぴっかぴかの研修医1年目から心停止に直面する可能性のある全医療従事者にとって,必読の内容です!
CPRは「質の高い胸骨圧迫」にはじまる
CPRにおいて最も重要なのは「質の高い胸骨圧迫」です。心停止を認識し,胸骨圧迫を開始するのには勇気が要りますが,心配は無用! 心停止していない患者にCPRを行うことに伴うリスクは心停止患者にCPRを行わない場合よりもはるかに低いという原則を覚えておきましょう3)。十分な脈拍が触知できない場合,無反応で呼吸がないか,異常な呼吸(死戦期呼吸)を呈する場合には心停止と判断して直ちに胸骨圧迫を始めます。
さて,CPRにおける胸骨圧迫の重要ポイントを確認しましょう。
● 胸骨中央に圧迫者の体重がかかるようにする。
● 1回の圧迫で5~6 cmの深さまで圧迫する。
● 圧迫と圧迫の間には胸部を完全に元に戻す。
● 1分間の胸骨圧迫回数は100~120回を目標にする。
● 患者の下に硬い板を置く。
● 胸骨圧迫を中断する頻度と時間を最小限にする。
「胸骨圧迫の中断時間を最小限にする」ことは実際には難しいものの,救命を行う上では極めて重要性が高い項目です。これまでのCPRは,救命率を高めるために胸骨圧迫の中断時間を最小限にすることに焦点を当ててきました。現場での工夫を確認しましょう。
◆胸骨圧迫中断時間を最小限にする工夫①:パルスチェックをしない
CPRを行う際,2分ごとのサイクルでリズムチェックをすることが一般的です。これは除細動を行うべきかどうかを判断するため,すなわち除細動が可能な波形(shockable rhythm)の存在を確認するために不可欠です。
しかし,この段階においてルーチンでパルスチェック(頸動脈を触知できるかどうか判断する行為)を行う必要はありません。皆さんも「本当に脈拍を感じているのだろうか?」と迷った経験があるかもしれませんが,そうした迷いに時間を費やすことは無益どころか有害です。実際,パルスチェックの正確性は約80%,脈拍の有無を判断するのに約20秒かかるとする研究結果もあります。さらに,心停止状態であるにもかかわらず「脈拍あり」と誤診したケースが14%も報告されており4),これは致命的な転帰につながる可能性があります。パルスチェックをルーチンに行うことから卒業しましょう!
◆胸骨圧迫中断時間を最小限にする工夫②:パルスチェックに超音波を使う
2分ごとのリズムチェックでshockable rhythm以外の波形が検出された場合,パルスチェックが必要になります。しかし前述の通り,パルスチェックは正確性に欠ける上,胸骨圧迫の中断時間を延長する原因ともなり得ます。この問題を解決するために超音波を用いたパルスチェックを試してみましょう! 従来の方法と比較して時間を半分に短縮できるだけでなく,操作も簡単です。プローブを頸動脈に当てておくだけです。
頸動脈が圧迫されてつぶれる場合はROSC(return of spontaneous circulation)には至っていないと判断できます。逆に,頸動脈がつぶれないか拍動がある場合はROSCと判断できます。この方法は胸骨圧迫中に...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。