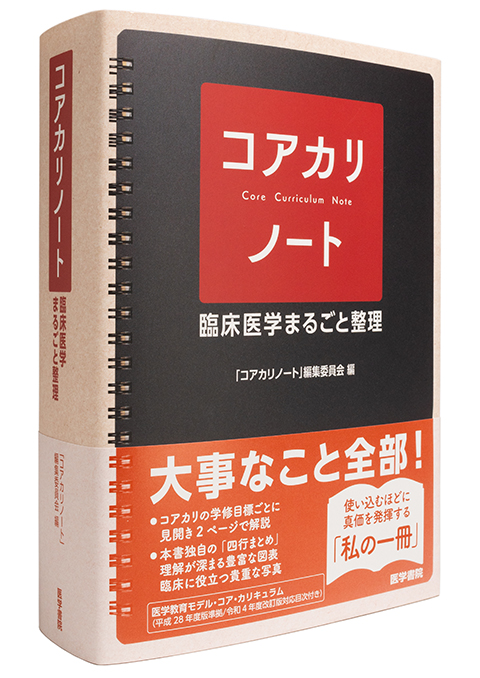試験・評価を学習者の味方に!!
対談・座談会 松山泰,錦織宏,伊藤彰一,斎藤有吾
2024.04.09 医学界新聞:第3560号より

「医学教育モデル・コア・カリキュラム」(以下,コアカリ)令和4年度改訂版では,「学修評価」についての節が独立して設けられ,医師として求められる資質・能力を適切に評価するための考え方,評価方法等,幅広い内容が扱われている。
本紙では自治医科大学で医学教育研究に従事する松山氏を司会に,コアカリ令和4年度改訂版の「学修評価」の節を取りまとめた伊藤氏,「医学教育モデル・コア・カリキュラム等の次期改訂に向けた調査・研究 医学チーム」で副座長を務めた錦織氏,教育学の専門家である斎藤氏を迎えた座談会を企画。今後の医学教育における学習者評価の在り方を考えた。
松山 本日はお集まりいただきありがとうございます。コアカリ令和4年度改訂版では学修評価という節が新しく設けられました。医学教育における学習者評価の重要性が認識されつつある今,コアカリ作成に携わったメンバーも交えて議論ができることを非常にうれしく思っています。
斎藤 コアカリ令和4年度改訂版を拝読しましたが,医学教育において何をどのような基準で評価しなければいけないのかとの視点が明文化され,教育現場の判断に役立つ情報がわかりやすくまとめられていると感じました。
伊藤 ありがとうございます。私が学修評価の節の取りまとめを担当しました。コアカリの読者は医学教育を専門にされていない方も多いため,評価ツールなどの各論よりも,総論的な理解を深めてもらうことをめざしました。 例えば,基本的な医学教育における評価の概念として紹介したのが“Millerのピラミッド”(MEMO)です。医学教育で実践的な能力の評価をするに当たっては,模擬的な環境も含めた場で自らの能力を行動で示す力であるShows how,実際の診療現場において実践する能力であるDoesに対する評価が主体となります。
MEMO Millerのピラミッド
1990年に提唱された医学教育評価に関する概念図であり,下層から順にKnows,Knows how,Shows how,Doesの4層から成るピラミッドで示される1)。最も基盤にあるKnowsは専門職としての能力を発揮するために必要な知識,Knows howは収集した情報を分析・解釈して診療に応用する能力,Shows howは模擬的な環境も含めた場で自らの能力を行動で示す能力,Doesは診療の現場で実践する能力を示す。KnowsやKnows howは筆記試験,Shows howはOSCE,DoesはWBAで評価されることが多い。診察などの実践的な能力の評価においてはShows howやDoesの能力評価を意識する必要がある。
松山 コアカリでは資質・能力の評価についての基礎も説明されていましたね。医師として求められる資質・能力は複数の多面的な能力から成るものであり,その能力は知識や技能,価値観,態度などの要素を含む観察・評価可能な能力(コンピテンシー)から構成されます。1つの評価方法で学習者のコンピテンシーを完璧に評価することは不可能です。筆記試験,OSCE等の実技試験,診療現場での観察評価(WBA:workplace-based assessment),ポートフォリオ等で多面的に,妥当性を考慮しながら評価される必要があります。
錦織 学習者評価は各大学の特色などさまざまな影響を受けるものであり,決まりきった正解はありません。そのためコアカリの中では,資質・能力の評価について考えてもらいたい問いをいくつか読者に投げかけています。各教育機関で問いの答えは考えていただきたいと思っています。今後,これらの問いからコアカリがどう発展していくのか,今から非常に楽しみです。
学習者にとって評価は敵なのか
松山 学習者評価の議論に際して,まずは日本の医療教育における「評価」のイメージを考えたいです。私は,医学に限らず日本の教育全般で「評価=試験」という先入観があるのではないかと感じています。集団で一斉に行い,その成否が学習者のその後の人生を左右する,医師国家試験のような試験が評価のトップに位置付けられている印象を抱きます。先生方のイメージはいかがでしょうか。
伊藤 全く同意見です。試験は試験でも授業内で行う小テストのような軽いものではなく,入学試験,卒業試験のような格式ばったものがイメージされているように思います。
斎藤 合否判定や選抜の場面でのみ評価が意識されている,という印象でしょうか。確かに,学習過程で行われ,学習者が目標を達成するために不足している点を気づかせ,改善を促すための「形成的評価」より,学習過程の終了時期に行われ,学習者が目標に達しているか否かの判定に用いられる「総括的評価」が圧倒的に重視されている雰囲気はあります。
錦織 国試はまさに医師になる人を選抜する総括的評価の場ですよね。
伊藤 そうした文脈での試験は「傾向と対策」といった言葉とセットで語られます。立ち向かって越えるべき,相対するものであって,自分の味方になるものではないと考える方が多いと思います。
錦織 試験を課す先生はロールプレイングゲームの敵キャラクターのようなイメージですよね。だから楽々倒せるような問題を出してくれる先生が良い先生と思われていたり(笑)。
斎藤 良いたとえですね。医学教育現場では,1つでも単位を落としたら留年する可能性があったり,国試と同じ形式で持ち込み禁止のペーパー試験を行ったり,インパクトの大きい国試のための厳しい対策が日ごろから強く意識されているように見受けられます。「敵を倒すために頑張れ」と1年生のころから常に学習者に発破がかけられている印象です。
松山 私が懸念しているのは,国試という厳格な総括的評価とその対策のための学習が,臨床能力が高い医学生を育て,評価するという本来の目的からかけ離れたものになってはいないかという点です。ペーパーテストに強い学生を作り選抜するという,敵を倒す点のみに注力した学習過程になっては本末転倒ではないでしょうか。
評価は敵ではなく,学習者の成長を支援する「味方」です。「評価を味方に」という視点で,以降の議論を進めていければと思います。
形成的・総括的評価を兼ねるWorkplace-based assessment
斎藤 教育評価論における教育評価や学習評価の目的は,学習者を序列化したり選別したりすることではなく,学習者の資質・能力の発達を保証することと,教育活動を改善していくことです。評価によって学習者に自分の現在の状況を把握してもらい,成長に向けた道しるべを示して改善につなげてもらうわけです。
伊藤 指導・教育の中でのフィードバックに代表される形成的評価の視点ですね。総括的評価が目標を達成できたか否かを評価するのに対し,形成的評価は目標の達成に向けて支援する役割を果たします。まさに学習者の「味方」と言える評価だと思います。
松山 形成的評価としての側面も期待されている医学教育における学習者評価の概念に,Workplace-based assessmentがあります。WBAの一種であるmini-CEX(註1...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
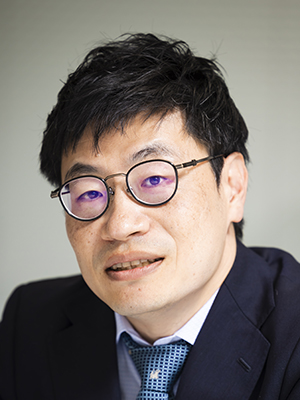
松山 泰(まつやま・やすし)氏 自治医科大学 医学教育センター 教授
2001年自治医大卒。15年蘭マーストリヒト大医学教育学修士課程修了,20年同博士課程修了。博士課程では学修評価の世界的権威であるCees van der Vleuten教授に師事。12年伊東市民病院臨床研修センター副センター長,18年岐阜大医学教育開発研究センター客員教授などを経て,22年より現職。日本医学教育学会認定専門家制度コースワークの実施責任者。同学会学習者評価部会メンバー。

伊藤 彰一(いとう・しょういち)氏 千葉大学大学院医学研究院 医学教育学 教授
1998年千葉大医学部卒。2003年同大大学院博士課程修了。02年成田赤十字病院,04千葉大助教,09年同大講師などを経て,19年より現職。千葉大において卒前・卒後の医学教育以外にも他職種の研修にも携わり,高等教育センターの副センター長として全学のアセスメントポリシーの作成を行っている。医学教育モデル・コア・カリキュラム令和4年度改訂版において「学修評価」の執筆の取りまとめを担当した。

錦織 宏(にしごり・ひろし)氏 名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学教育センター 教授
1998年名大医学部卒。2008年英ダンディー大医学教育学修士課程,20年蘭マーストリヒト大医療者教育学博士課程を修了。07年東大医学教育国際研究センター,12年京大医学教育推進センターを経て,19年より現職。医学教育モデル・コア・カリキュラム等の次期改訂に向けた調査・研究医学チーム副座長。日本医学教育学会理事長補佐。

斎藤 有吾(さいとう・ゆうご)氏 新潟大学教育基盤機構 准教授
2011年京大教育学部卒。18年同大大学院博士課程修了。博士(教育学)。17年同大高等教育研究開発推進センター,18年藍野大医療保健学部理学療法学科助教,19年新潟大経営戦略本部教育戦略統括室准教授などを経て,22年より現職。専門は教育学,特に高等教育における教育評価論と教育測定論。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。