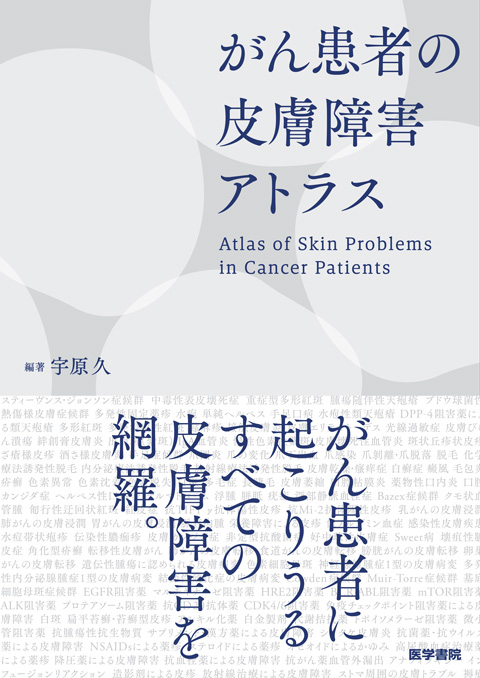多様化するがん患者の皮膚障害
宇原 久氏に聞く
インタビュー 宇原久
2024.02.19 週刊医学界新聞(通常号):第3554より

分子標的薬,免疫チェックポイント阻害薬の登場により,がん薬物療法は大きく進歩した一方で,薬剤の作用機序の違いから,患者に見られる皮膚障害は複雑化している。さらに担がん状態では薬剤と関連しないさまざまな皮膚障害も発症する。がん患者に皮膚障害が見られた際,医療者はどのように見極め行動すべきか。『がん患者の皮膚障害アトラス』(医学書院)を上梓した宇原氏に,がん患者に現れる皮膚障害への対応を聞いた。
――2014年の抗PD-1抗体ニボルマブの登場を機に,がん薬物療法は加速度的に進歩しています。ニボルマブの治験段階から携わり,皮膚腫瘍を専門とされてきた宇原先生はこの進歩をどう見ていますか。
宇原 私が医師になった1986年からニボルマブが登場するまでのおよそ30年間,皮膚腫瘍に対して保険収載されている薬剤は種類も治療効果も限られていました。特に悪性黒色腫は薬物療法が効きにくく,転移すると3年生存率が数%以下でしたので,ニボルマブが承認された時は,長いトンネルを抜けた感じがしました。
個別の対応が必要になったがん薬物療法による皮膚障害
――皮膚腫瘍に限らず,がん薬物療法は殺細胞性抗がん薬に加えて,低分子分子標的薬,免疫チェックポイント阻害薬が重要な役割を占めるようになりました。皮膚科の観点から変化はありましたか。
宇原 薬剤性皮膚障害への対応が複雑化しています。殺細胞性抗がん薬にアレルギー性の皮膚障害が出た場合は,中止せざるを得ないことが少なくなかったのですが,低分子分子標的薬の登場以降は,薬剤ごとに皮膚障害の特性を理解し,なるべく治療を続けられるような個別の対応が必須となってきました。例えばEGFR阻害薬に伴うざ瘡様皮疹など,薬剤の主作用による皮膚障害が出現するようになりました。一般に顔面の皮疹にステロイド外用剤を長期に使用することは避けるべきですが,ざ瘡様皮疹では治療継続のため積極的に使用するようになりました。アレルギー性の薬疹は投与を繰り返すと重症化しますが,低分子分子標的薬の中には再投与しても皮疹が再発しない薬剤があります。
加えて,低分子分子標的薬では二次感染にも注意が必要です。ざ瘡様皮疹を含め,膿疱があれば細菌培養は必須です。内服中のミノサイクリンに耐性ブドウ球菌が検出できる症例が少なくありません。また,EGFR阻害薬による爪囲炎を含めた皮膚障害には外的な刺激が影響します。洗髪,洗顔,靴の選び方と履き方の指導が必須であり,予防を含めた総合的な対応ががん治療継続のために重要になってきました。
――免疫チェックポイント阻害薬による皮膚障害にはどのような特徴がありますか。
宇原 免疫チェックポイント阻害薬の免疫関連副作用(irAE)は,発現時期,発現臓器,重症度を含めた経過が予測できず,重症筋無力症や心筋炎に代表されるように,従来のタイプと対応が異なる場合も少なくないです。皮膚障害はirAEの中で最も高頻度に認められますが,重篤なものは少なく,多くはかゆみに対するステロイドの外用や少量の内服でコントロール可能です。まれですが,乾癬,扁平苔癬,自己免疫性水疱症など多彩な皮膚疾患が出現するものの,通常の...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

宇原 久氏(うはら・ひさし)氏 札幌医科大学医学部皮膚科学講座 教授
1986年北大医学部を卒業後,信州大病院で研修し,88年より国立がんセンター研究所(当時)病理部と皮膚科で皮膚腫瘍の研修を行う。90年より諏訪赤十字病院。信州大病院を経て,2017年より現職。『がん患者の皮膚障害アトラス』(医学書院)など編著多数。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。