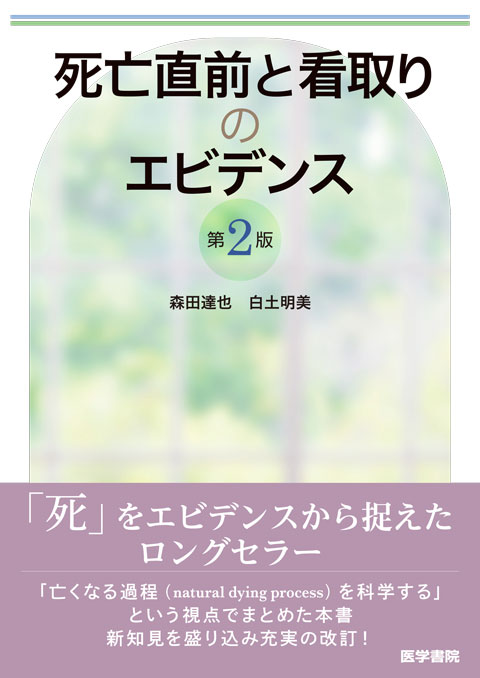MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2024.01.22 週刊医学界新聞(看護号):第3550号より
《評者》 林 ゑり子 横市大大学院看護学
臨床とエビデンスがマッチした,看護実践に役立つ良書
このたび本書の第2版が出版されることを発行前に知り,どのような内容になるのかと待ち遠しく,書籍が届いた後は,やはり初版と同じように,すぐに下線や丸印,付箋ばかりになりました。私が付箋を貼ったり下線を引いたりする部分は,①これまでの自身の臨床経験の中で患者や家族に役立ちそうだが半信半疑で実践しているケアについて,最新の研究結果を納得できるよう紹介している部分です。「こんな研究がなされているんだ,テーマに新規性があり,しかも最新データが載っている」という感じで,臨床実践と研究結果がマッチしているところが面白いです。そして,②引用文献に加えられた森田達也先生のコメントです。短い文章で研究内容を紹介していることも勉強になるのですが,時折「〇〇が話題になった古典です」「△△を明確にした~~っぽい」などのカジュアルなコメントに親近感があり,気に入っています。さらに③各章の見出しの部分(エビデンスの要所,臨床でのボトムライン,今後追加されるエビデンス)は多くの臨床現場での状況を映し出しており,私たちの病院の実践の目標値にもなり,安心します。
第2版では,初版で紹介されている内容も共有されています。例えば,最期のお別れの場面に間に合うか・間に合わないかと,遺族の抑うつとの関連についての研究が紹介されています。看護師として,私は最期の旅立ちに間に合うようにご家族の身体的な疲労を考慮して,あまり早く連絡をし過ぎず,息を引き取る瞬間に間に合うタイミングを見計らって連絡することを心掛けていますが,連絡が間に合わずに先に旅立たれることがあります。間に合わなかった家族に対して,看護師としての判断への自責の念が大きく,責任を感じることが多いのですが,本書には間に合うことが重要なのではなく,お別れが言えているかどうかが,家族の抑うつや悲嘆に影響することが示されています。私たち看護師は,この研究結果にどれだけ救われていることでしょうか。この10年で看護師のグリーフケアの重要性が言われていますが,看護師は最善のケアをしたつもりでも,患者のケアに後悔したり,振り返ったりするたびに「もっと違う方法があったのではないか」と考えることがあります。その意味でも,本書は看護師のグリーフケアに役立つ書籍だと思います。
本書著者の森田先生より今回の書評執筆のお話を頂いた際には,「林さんのこの領域に関する思いみたいなものも記載してほしい」とのご依頼でしたが,看護師としての私は,緩和ケアは「ケアリングや愛」なのではないかと思うときがあります。このような...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。