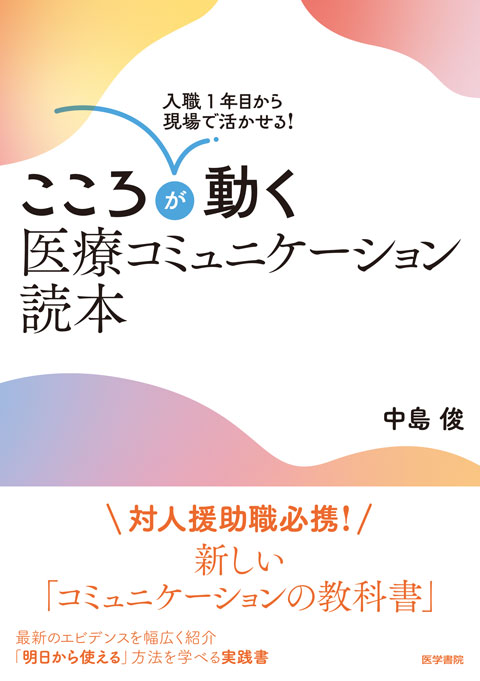MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2023.09.11 週刊医学界新聞(レジデント号):第3532号より
《評者》 柴原 純二 杏林大教授・病理学
通読可能な分量に神経病理のエッセンスを凝縮
病理医が慢性的に不足するわが国にあって,多くの病理医はgeneral pathologistとして諸臓器に向き合うことを余儀なくされているが,新規知見が加速度的に蓄積される現代において,各領域の知識を十全に備えることは年々難しくなってきている。特に神経病理は,その複雑な解剖,多彩な組織構築や構成細胞,独特の染色法の数々からして,多くの病理医が苦手とするところであるが,もとより疾患が多様である上に,概念の変遷があり,新規病型の提唱や疾患の細分化が進んでいることが,習得をより困難なものとしている。また,神経病理の特徴の一つは,病理解剖でなければ経験できない疾患が多いことであるが,新型コロナウイルスの流行により解剖の機会の減少に拍車がかかり,経験を積むことが一層困難となりつつあることも,神経病理を学ぶ上での大きな障壁となっている。
この度改訂された『神経病理インデックス』は,こうした難点を孕む神経病理の学習や診断の実践において大きな手助けとなってくれる1冊であり,定評のあった旧版から実用性がさらに増した印象である。表紙イラストも魅力的な本書をひとたび開けば,美麗な肉眼・組織写真の数々,理解を促進する豊富なイラスト,正常組織や種々の疾患についての簡潔明瞭な解説に夢中となってしまうであろう。私見では現状で最も優れた神経病理の教科書と言っても過言ではなく,母国語でこのような良書に触れられることに幸せを感じずにはいられない。通読可能な分量でありながら,エッセンスは漏れなく盛り込まれているため,病理学や脳神経内科学を研修中の医師や医学生を含む初学者にまずはお薦めしたい。また,経験豊富ながら神経病理は敬遠しがちな一般の病理医にとっても,神経病理の最新を網羅的に知ることができる本書は一読の価値がある。「インデックス」の名が示す通り,辞書的な活用ももちろん可能である。
著者の新井信隆先生は神経病理分野で数々の業績を残してきた一流の研究者であるとともに,「東京都医学研・脳神経病理データベース」の構築に従事するなど,わが国の神経病理学の教育に多方面から貢献してこられた先生である。現在は自ら設立された唯一無二の神経病理専門の株式会社「神経病理 Kiasma & Consulting」を運営され,文字通り全国を飛び回って神経病理学のコンサルト活動を展開されている。当施設でも病理解剖症例を中心に新井先生にご指導を仰いでおり,深い教養を持ちつつ,ユーモアを兼ね備えた先生のお人柄に魅了されている。本書においても詩的な表現がちりばめられ,ページ右下にはさりげなく海馬発生のパラパラ漫画が配されているなど遊び心が反映されており,新井先生ならではの1冊に仕上がっている。大幅な発展を遂げた本書の次の改訂版を今から期待しつつ,これから数年間は本書を堪能しながら神経病理に向き合っていきたい。
《評者》 竹林 崇 大阪公立大教授・作業療法学
コミュニケーションに迷うならば手に取ってほしい1冊
医療において,コミュニケーションは基盤となる知識および技術である。どれだけ確実性の高い医療技術があったとしても,それを施術してその後のサポートを行う医療従事者に対する納得と信頼を得られなければ,対象者はそれらの技術は選ばないかもしれない。また仮に選んだとしても,医療従事者に対する不信は,対象者の心身の予後を悪化させる可能性もある。これらの観点から,医療者がコミュニケーションを学ぶことは,エビデンスや知識・技術を学ぶことと同様,非常に重要なものであると考えている。
しかしながら,医療者におけるコミュニケーションについては,養成校などでも特化した授業が少なく,また経験的に実施してきた先人も多いため,エビデンスを基盤としたコミュニケーション技術に対する教育はいまだに確立されていない。一方,情報化の時代がさらに加速する昨今,医療事故やミスに関する報道が一気に加熱することで医療に対する対象者の不信感が過去に比べて膨らんだという社会的背景もあり,コミュニケーションや接遇に対する必要性がより一層重視されている。
そういった背景の中,医療者に対して「コミュニケーションは何なのか」「今自分が取っているコミュニケーションの問題点はどこにあるのか」「そしてそれらを改善するためには何をすべきなのか」を過去の豊富な研究を基盤にわかりやすく丁寧に解説しているのが,『入職1年目から現場で活かせる! こころが動く医療コミュニケーション読本』である。
本書の素晴らしいところは,先行研究で調査されたエビデンスを基盤に読者の現在のコミュニケーションを振り返らせて,それらを認めてさらに改善するための方法が論理的に示されている点である。さらに学術用語だけでは理解が困難なニュアンスについては,いくつものシチュエーションと会話というCaseを通して,具体的にどういった発言がどのような問題を孕み,改善の余地があるかなどをわかりやすく解説している点も,理解を促す役割を果たしている。
卒前・卒後のコミュニケーションを見直す際に,これほ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。