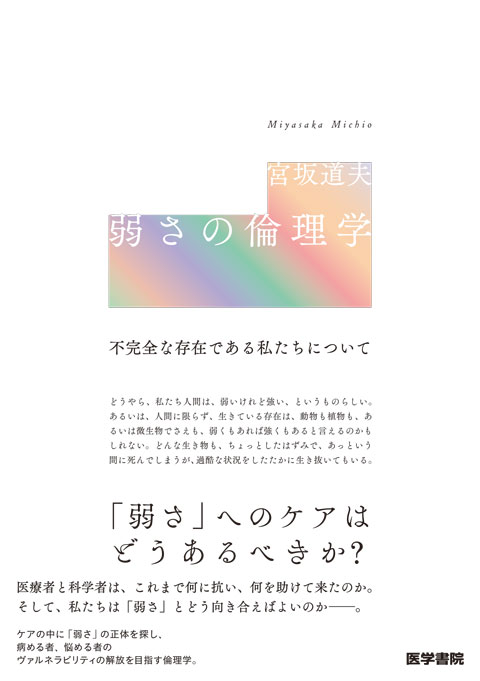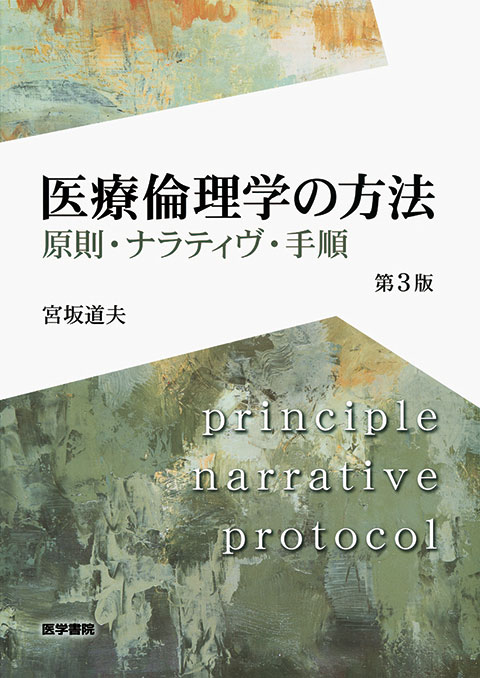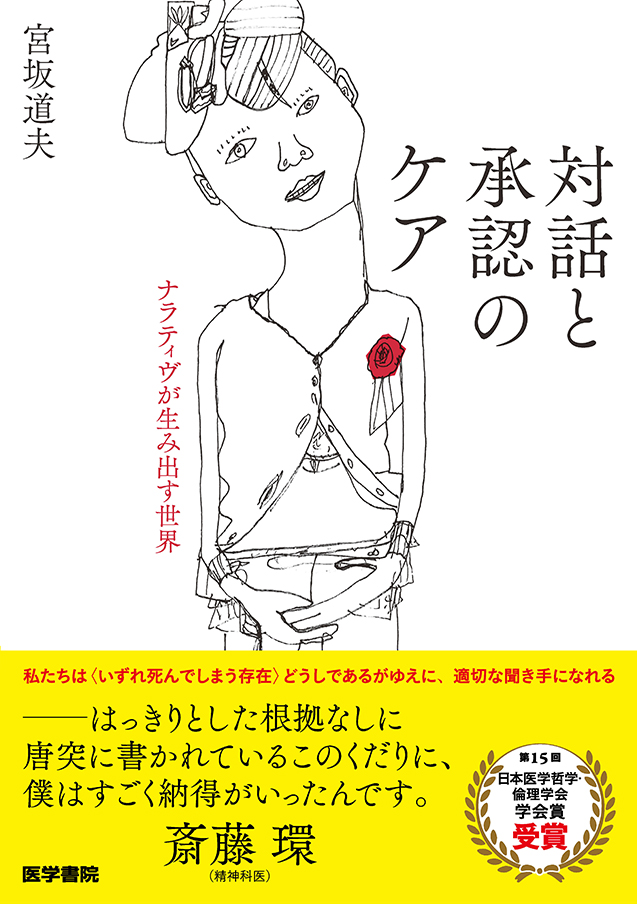新潟発のELSI――「弱さ」へのまなざし
寄稿 宮坂道夫
2023.09.04 週刊医学界新聞(通常号):第3531号より
ELSI〔Ethical,Legal and Social Implications(またはIssues)〕とは,科学技術の開発に伴って生じる「倫理的,法的,社会的な課題」を意味し,遺伝子編集やAIの開発によって近年注目が集まっている。新潟大学では2023年2月に日本で3番目となるELSIセンターを立ち上げた。本稿では,構想段階からかかわってきた筆者がELSIの歴史と新潟大学ELSIセンターの研究構想について述べる。
ヒトゲノム計画に端を発するELSIの歴史
ELSIの概念は,1980年代末に米国で始まったヒトゲノム計画の中で示された。人間の全ゲノム情報を解読しようというこの壮大な計画に対しては,さまざまな疾病の治療法の開発などにつながるとして大きな期待が寄せられる一方で,数多くの倫理的,法的,社会的問題を引き起こすのではないかという懸念も当初から指摘されていた。そのため,米国の国立予防衛生研究所とエネルギー省が合同でELSIを検討するための作業部会を立ち上げたのだった。作業部会は,ヒトゲノムの解読が個人や社会に及ぼす倫理的,法的,社会的影響を詳細に予測・評価し,一般市民の議論を喚起し,ヒトゲノム情報が個人や社会に利益をもたらすように活用されるための政策を考案することを目的に,学際的な調査研究に取り組むことを自分たちのミッションとして定義し,1990年1月に最初の報告書を発表した1)。
◆欧州発のRRI
米国発のELSIに対して,最近になって欧州から提案されているのがRRI(Responsible Research and Innovation),すなわち「責任ある研究・イノベーション」という概念である。ELSIが,科学技術の開発がもたらす課題に後から対処しようとするのに対し,RRIはめざすべき社会像や価値をまず提示して,研究開発をそれに合致したものとなるように推進していく考え方とされる2)。最近では,RRIの考え方がELSIにも採り入れられるようになり,科学技術の開発を人文・社会科学領域の知見を活用しながら「めざすべき社会像や価値」の視点で分析し,早い段階で規制または方向づけを行い,必要であれば研究開発を一時停止する「モラトリアム」の期間を設けることもしばしば議論されるようになっている。最近の例では,ゲノム編集3)の倫理的問題やAI4)の社会的な影響への懸念などをめぐる専門家たちの提言が,その顕著な例と言えるだろう。
◆医学の発展とELSI
医学の領域では,こうした議論は新しいものではない。1960年代には臓器移植が,1970年代には体外受精などの生殖医療技術が大きな社会的論争を巻き起こし,その規制の在り方が検討されていた。研究開発や臨床応用を一時停止するモラトリアムについても,遺伝子組み替え技術や心臓移植などの前例がある。遺伝子組み替え技術を討議した1975年のアシロマ会議では,安全な技術開発が確立されるまで,いくつかのタイプの研究を実施すべきでないという提案が行われた。心臓移植では,1967年に南アフリカで世界の第一例が行われ,翌1968年は「移植の年」と呼ばれるほどに多くの移植が各国で行われたが,1969~70年にかけては,移植件数が大きく減った。これは,規制の強化によるものではなく,現場の医師たちが自らの判断で移植の実施を一時停止した「臨床的モラトリアム(clinical moratorium)」と呼ばれている5)。
新潟大学ELSIセンターが注目する「弱さ」の可能性
わが国では政府の科学技術政策の方針である科学技術基本計画に,2006年の第3期計画からELSIへの取り組みが明記されたこともあり,大学でもELSIに対する具体的な取り組みが模索されるようになった。2020年に阪大が国内初のELSIセンターである社会技術共創研究センターを設置し,中大(2021年),新潟大(2023年)がこれに続いた。これらのELSIセンターは,基本的な活動方針を共有しつつ各大学の特色を反映して,おのおのにユニークな個性を持っている。阪大はメルカリやNECのような民間企業と...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
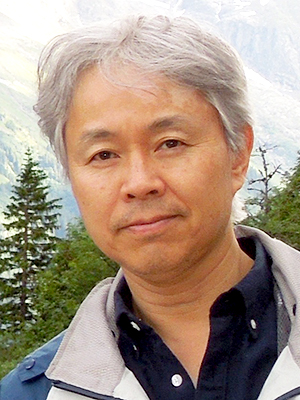
宮坂 道夫(みやさか・みちお)氏 新潟大学大学院医学部保健学研究科 教授
早大教育学部理学科卒業,阪大大学院医学研究科修士課程修了,東大大学院医学系研究科博士課程単位取得。博士(医学)。専門は生命倫理,医療倫理,ナラティヴ・アプローチなど。2011年より現職。著書に『医療倫理学の方法――原則・ナラティヴ・手順』『対話と承認のケア――ナラティヴが生み出す世界』『弱さの倫理学――不完全な存在である私たちについて』(いずれも医学書院)など。
いま話題の記事
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。