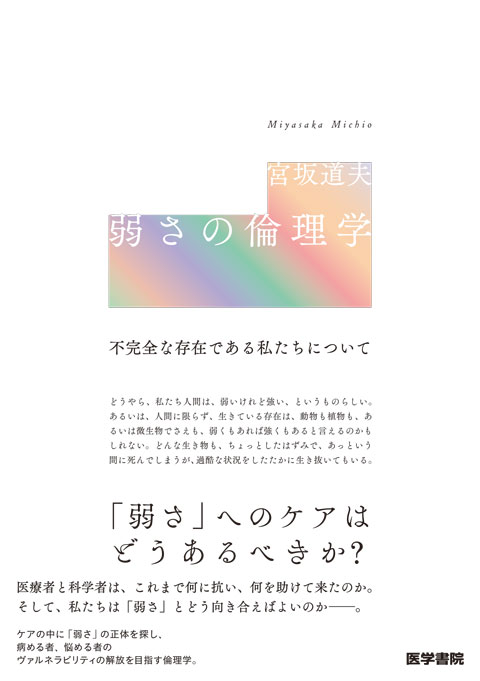弱さの倫理学
不完全な存在である私たちについて
弱さへのケアはどうあるべきか。ヴァルネラビリティの開放を目指す倫理学。
もっと見る
「弱さ」へのケアはどうあるべきか? 医療者と科学者はこれまで何に抗い、何を助けて来たのか。そして私たちは、「弱さ」とどう向き合えばよいのか。ケアの中に「弱さ」の正体を探し、病める者、悩める者のヴァルネラビリティの解放を目指す倫理学。
| 著 | 宮坂 道夫 |
|---|---|
| 発行 | 2023年02月判型:A5頁:248 |
| ISBN | 978-4-260-05114-9 |
| 定価 | 2,420円 (本体2,200円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
倫理とは何か。
それはしばしば、「ものごとのよしあし」だとされてきた。
「ものごとのよしあし」を考えるのは人間であり、人間が「ものごとのよしあし」について考えて初めて、倫理というものが立ち現れる。
倫理は、重力のように、地球のすみずみにまで行き渡り、そこにいるすべての者に作用するものではない。倫理とは、人間だけに働く力であり、他の動物や、植物や岩石には働かない。それどころか、人間にとっても、四六時中つねに働くものでもないだろう。人間は不完全な存在であり、私たちが「ものごとのよしあし」を考える瞬間は、そう頻繁にはやってこない。
では、それはいつ、どんなときか。
この本ではそれを、弱い存在を前にしたときだろう、と考える。
つまり、ここでは倫理を、弱い存在を前にした人間が、自らの振る舞いについて考えるものだと、考えてみるのである。
弱い人を前にしている自分がいる。
自分も大して強くはないが、いま目の前にいる人に比べれば、少しは余力がある。
そこで考える。
もしかすると、その人の助けになることを、してあげられるかもしれない。
いやその逆で、その人の持っているものを奪ったり、弱みにつけ込んで利用して、儲けたりすることが、できるかもしれない。
そんなときに、自分はどう振る舞うべきなのかと問う声が、自分の心の中から聞こえてくる。
その問いかけが倫理ではないのか。
逆の状況もあり得る。
自分の方が弱いという状況である。
例えば、深い穴の中に落ちてしまって、這い上がることができない状況だとする。
高いところにある開口部を見上げながら、誰かが通りかかるのを待っている。
だいぶ長い時間待って、ようやくこちらを覗き込んだ人の顔が見えた。
無表情に、こちらを見ている。
私は「助けてください」と、声を出す。
しかし、相手はじっと黙っている。
私は次に何を言うべきか。
「お願いです」と乞うべきか、あるいは、「どうして何も言わないんですか」と、不満の気持ちを伝えるか。
私の心の中には、「こういう状況では、助けてくれるのが当然ではないのか」という声がこみ上げてくる。
この「当然ではないのか」という問いかけもまた、倫理ではないのか。
この声は、私自身にではなく、穴の上にいるその人に向けられたものである。その人は、地の底に落ちた私という弱い存在を前にしているではないか。私はその人に、どうか自らの振る舞いを、よく考えてみてほしいと願っている。
これもまた、倫理ではないのか。
私自身が弱い存在で、それを自分で見つめている、という状況もある。
私はひどく憂鬱な気分を抱えていて、誰にもこの気持ちを打ち明けられない。職場でも家庭でも、自分が疎(うと)まれているように感じている。この憂鬱を抱えたまま、何日も何年も生きていかなければならないのか。
立体駐車場に車をとめて、ふらふらと端の方まで歩いて行く。見下ろすと、ここは4階か5階らしい。飛び降りれば、まず死ぬだろう。
そのとき私は、すっかり弱くなった私というものを、見ているような気持ちになる。
隣のビルから眺めているかのように、自分を見ている。
自分自身に向ける声が、心の中から聞こえてくる。
「死ぬのはダメだろう」とか、「いや、もう終わりにしてしまえ」とか。
これらの声は、私という弱い存在を前にして、私自身が自らの振る舞いを考えさせようとする問いかけだろう。
これもやはり、倫理ではないのか。
このように、倫理というものを、弱い存在を前にした人間が、自らの振る舞いについて考えるものだと仮定してみると、これまでバラバラに論じられてきた倫理の問題を、同じ視界の中で考えられるのではないかと思えてくる。医療の倫理も、科学技術の倫理も、あるいは他の生物や、地球環境の倫理でさえも。
つまり、倫理についての探求としての「倫理学」を、弱さというものを基点にして組み立てることができるのではないかと、思えてくるのである。
本書はそのような試みである。
*
倫理学は歴史の古い学問であり、「弱さ」について論じた人もそれなりにいる。
例えば、フリードリッヒ・ニーチェという人がそうだった。ただし、彼は、弱さを価値あるものとして捉えたのではなく、蔑(さげす)んだのだった。
反対に、弱さこそが人間の倫理を成り立たせているものであり、弱さに価値を見いだすべきだと主張した人たちもいた。例えば、アルスデア・マッキンタイアという人は、人間とはお互いに依存し合う弱い存在であり、そこから離れて倫理を構想することはできないと主張した。
また、「弱い存在」について考えることで、私たちの視野を広げ、社会を変革しようとしてきた人たちがいる。世の中には、私たちがその存在に気づけていないほどに、きわめて弱い者がいる。そのような者を置き去りにし、存在していることすら忘れてしまう。それはきわめて非倫理的なことだと訴えてきたのは、女性、障害者、性的マイノリティ、人種的マイノリティ、あるいは人間以外のさまざまな生物の権利を守ろうとしてきた人たちである。
倫理学が、そのような「弱さ」あるいは「弱い存在」の一切を視野に入れ、私たちがどう振る舞うべきかを考えるものであるならば、それはスケールの大きな総合的学問になるだろう。今日の倫理学は、「文系」の小さな領域の様相を呈していると言えなくもないが、「弱さの倫理学」を考える際には、人文社会科学から自然科学を横断していく必要があると筆者は考えている。
本書は、そのような学際的な「弱さの倫理学」を作っていくために始めた、少し大胆な、新しい試みである。
第1章で、まず人間の弱さについて考える。
第2章と第3章では、人間が自分たちの弱さに対し、科学技術によって対抗してきた様子を振り返る。そのような対抗の結果として生じたのが、今日のさまざまな倫理的問題だというのが、ここでの見立てである。
第4章から第6章では、こうした問題意識を踏まえて、「弱さの倫理学」というべきものを考えていく。
本書は、6枚の絵で構成された展覧会のような設(しつら)えになっている。
6枚の絵で描けることは限られている。ただ言えることは、6枚の絵を貫く共通のテーマは、弱い存在を前にした人間が、自らの振る舞いについて考えるものとして、倫理を考えるということである。
目次
開く
はじめに
第1章 私たちの弱さについて
1 生き物としての私たちの弱さ
2 心の弱さ
3 他者との関わりの中での弱さ
4 技術による弱さへの対抗
第2章 医療技術による弱さへの対抗
1 科学技術による弱さへの対抗
2 臓器移植の物語──乾燥した南アフリカの病院で
3 体外受精の物語──殺風景な工業地帯の病院で
第3章 テクノロジーによる弱さへの対抗
1 技術倫理と環境倫理
2 燃えやすい車の物語──フォードが作った駁毛の馬
3 御せない技術の物語──原子力技術のニヒリズム
4 他の生き物たち
第4章 「理系」の倫理学
1 倫理の法則性を求めて
2 重い歴史
3 「理系」の倫理学をひらく
第5章 「対話」の倫理学
1 話し合って決める
2 対話のテーブルの情景
3 対話のテーブルに着くことができない、きわめて弱い存在
第6章 弱さを抱きしめて
1 古典的な倫理理論の課題
2 弱い側から見た景色
3 弱さを抱きしめて
文献・註
索引
あとがき
書評
開く
弱さの可能性を実感する
書評者:向谷地生良(浦河べてるの家)
●「新しい力が湧き出てくる源は弱さにある」
「21世紀」を目前にした1999年に、注目すべき一冊の書物が世に送り出された。それは『21世紀へのキーワード 「弱さ」 インターネット哲学アゴラ』(金子郁容・中村雄二郎 岩波書店)という本であった。
そのなかで、著者の金子・中村両氏が明らかにしたのが、社会が高度情報ネットワーク化することによって、「強いものが弱いものを保護するというやり方の行き詰まり」と、「逆に新しい力が湧き出てくる源は弱さにある」という“予言”であった。そこに必要とされるのが、「ネガティブとネガティブが合わさってポジティブになる」経験であり、そこに「弱さの強さ」の根拠と「弱さの思想」の基盤を見出そうとする視点である。
この本は、精神障害などを経験した若者たちと起業を目指して立ち上げた「浦河べてるの家」(1984)の活動理念「弱さを絆に」「弱さの情報公開」が、私たちの経験を越えて、時代を考える大切なキーワードである可能性を指し示してくれた気がする。
以来、数多くの“弱さ”本が、各方面の領域から世に生み出されてきたが、このたび著された『弱さの倫理学』も、「ケアの倫理」を、「弱さ」をキーワードに掘り下げ、“自分ごと”にする手助けをしてくれる一冊である。
●倫理をめぐるゆらぎの最前線で
著者は「倫理」を、「弱い存在を前にした人間が、自らの振る舞いについて考えるもの」と仮定した上で、生命論、テクノロジー、自然科学、思想哲学の領域で倫理がどのように扱われてきたかを紹介しているが、これを読むと、時代の中で、常に「倫理」とは何か、何が大切なのかを巡る葛藤とジレンマとともに、社会の進歩があったことがわかる。この歩みに一貫しているのが「問題解決」や「リスクの軽減」と「倫理」との間に生じる相克である。特に医療・保健・福祉の現場に立つ専門家は、倫理をめぐる揺らぎの最前線に立たされていると言える。
それに対して、著者は新たな「倫理」の方向性を提示する。それは、伝統的な「弱さを克服する」ことに貢献する倫理から、「弱さを抱きしめる」ことに向けた倫理への転換であり、「弱さ」そのものに可能性と意味を見い出そうとする立場である。もしかしたら、それは現場に立つ私たち一人ひとりに託された、大切な当事者研究のテーマなのかもしれない。
(「精神看護」 Vol.26 No.4 掲載)
自分の「弱さ」を抱きしめられるか──新たな「いのち」の倫理学の構築を目指して
書評者:足立智孝(亀田医療大学看護学部教授)
書評を見る閉じる
●「弱さ」という視点から生命倫理を問い直す
私たちは,科学技術の開発・発展による多大な恩恵を受けて生活している一方で,科学技術の開発は,さまざまな社会的課題も生み出してきた。そのうちの生命に係る課題に対し,学際的にアプローチする学問分野がバイオエシックス(生命倫理)である。バイオエシックスが扱う「いのち」の問題は幅広いため,科学技術が適用される領域や検討課題などに区分して,「医療倫理」「技術倫理」「環境倫理」などと細分化して論じられることが多い。
本書は,倫理学の議論において中心的に取り上げられることの少なかった「弱さ」という概念を鍵に,別々に論じられてきた「○○倫理」を総合的に捉え直し,新しい「いのち」の倫理学の構築を目指した壮大な試みの書である。
●倫理原則によって拓かれた対話と弱い存在への配慮
本書では「弱さ」をどう扱っているのか。まず倫理というものを,「弱い存在を前にした人間が,自らの振る舞いについて考えるもの」(p.4)と規定する。その上で,第1章では,人間の弱さを,個体としての身体と心,さらに他者との関係から考察し,科学技術をその弱さへの対抗手段と捉える。
第2,3章では,医療,工学(技術),環境の各分野における科学技術の応用例が紹介され,第4章では,医療,工学,環境の各分野の倫理を同じ地平で論じる試みとして,医療倫理で用いられる4原則の他分野への拡大適用が模索される。特に自律性原則は,科学技術の適用を受ける側の弱い立場の者に対して,適用の可否に関する対話への参加を拓く原則として論じられる。
第5章は,各分野の倫理における対話に関する考察で,弱い存在が目の前にいるか否かの違いにより,同列での議論が難しい点や,全分野に共通する最大の課題として,対話の席にさえ着けない「きわめて弱い存在」に対する配慮の必要性を指摘する。
●専門職としての責任を自覚しながら,真の「強さ」に向けて
この配慮の必要性に気づくために,最終章である第6章ではオーストラリアの哲学者ロバート・グッディンの脆弱性(依存性)モデルを参照し,専門的な技術を持つ職業に就いた人は,その人の扱う技術に依存する全ての存在(弱い存在)の利益を保護する責任が生じると提案する。さらに拡大適用すると,技術を持つ人には,対話の席に着けない人間以外の生物も含む「きわめて弱い存在」に対しても相応の責任が生じると論じている。
本来「弱い」存在である人間は,よりよい生活を求めて科学技術という手段によって「強さ」を獲得してきた。しかし著者は,今後の科学技術の開発は「弱さの克服」と「弱さの抱きしめ」の2つの方向性があると述べる。私たちは「弱さの克服」による「強さ」と,「弱さの抱きしめ」による「強さ」の両方を見つめなければ,科学技術の発展による真の「強さ」を手に入れることにはならないのだろう。
本書には,医療を含む科学技術の開発との向き合い方についての新たな倫理的な考え方が示されている。
(「看護管理」 Vol.33 No.7 掲載)
人間の弱さは文系・理系の区別を飛び越える──新しい倫理学の大胆な提案の書
書評者:池田 喬(明治大学文学部教授)
書評を見る閉じる
弱い人間を前にした人間が自らの振る舞いについて考えるもの──これが本書の提案する「弱さの倫理学」である。弱さに寄り添う,という最近よくある話かと思うなかれ。この提案の中身は驚くべきことに「理系」の倫理学であり,文学部の一部に置かれている「倫理学」を学際的に作り直す大胆な試みなのである。
人間は弱い。体も心も脆い。しかし,人間はこうした弱さに技術で対抗してきた。衣服を作り出して身体を保護し,病気や死に対抗する薬や医術を編み出した。技術を科学と結びつけて飛躍的に発展させた。だが,この高度科学技術が数々の倫理的問題を生じさせている。
例えば,医学は臓器移植や体外受精を可能にしたが,それによって人体の資源化などの問題を生じさせた。科学技術は自動車を生み出して圧倒的な速さでの移動を可能にした代わりに,人間の死のリスクを高めた。原子力技術は人間による世界破壊を現実的にさえしている。そして,このような科学技術による被害を被るのは,当の人間だけではなく,地球全体である。現代の倫理は人間に対する責任で尽きるものではありえない。
本書が目の覚めるような仕方で指摘するのは,これらの問題が実際に生じているのは医学,工学,生態学などの理系の領域においてだということである。人間は弱いし,他の生物だって自然だって弱い。しかし,技術はより強くなるものと弱い存在になるものの違いを生む。技術の服をまとった医療従事者と病気に苦しむ裸の人間の間に。エンジニアと例えば公害に苦しむことになりうる人々の間に。人間と他の生物や環境の間に。「理系」の倫理学とは,技術によって強くなった人間たちが,相対的に弱くなったものを前にして,自分のやっていることは本当によいのかを問うものであり,この意味で「弱さの倫理学」なのである。
本書で指摘されるように,大学において倫理学は「文系の中の文系」である文学部の中の小さな領域に過ぎない。その文系の倫理学者の中には,医療倫理,技術倫理,環境倫理に従事する者もいる。しかし,そのやり方は,功利主義や義務論といった近代の学説を現代の個別の問題に適用する「応用倫理学」の形をとってきた。現場から言えば,上から目線の倫理であり,倫理的な問題が生じている現実のリアリティからずれている。本書の弱さの倫理学は,倫理学が人文科学から自然科学を横断していく必要があること,いやもっとポジティブに,倫理学こそが分断された学問のつなぎ目になりうること──これを示す試みだ。
その試みに力を与えているのは,私の見るところ,歴史的でナラティブ的な手法である。例えば,本書で,臓器移植や原子力技術の倫理的問題は,整理された論点の提示によってではなく,歴史上の医師や技術者自身が実際に葛藤した様子の緊迫した記述によって提示される。読者はこれらの記述によって理系の倫理学の生き生きとした現場に立ち会える。少なくとも,典型的な文学部の哲学教師でありながら,「応用倫理学」には著者同様の不満を表明してきた私はそう感じた。上空飛翔的だった倫理学が生(なま)の現実に着地しつつある,という実感とともに。
(「看護研究」 Vol.56 No.2 掲載)
弱さは絶望ではなく希望である
書評者:山内 志朗(慶大文学部名誉教授)
書評を見る閉じる
著者は倫理を次のように宣言する。倫理とは,「弱い存在を前にした人間が,自らの振る舞いについて考えるもの」であると。
倫理学は正義とは何か,善とは何か,幸せとは何か,そういったことを考える学問だと考えられている。ただ,そういった問題設定は強い者目線での思考に染まりがちだ。強さは戦いを招き寄せる。だからこそ,世界的な宗教は,キリスト教も仏教も徹底的に弱者の地平から人間の救済を考えてきた。本質的に人間は弱く不完全であり,不完全なまま生き続けるものであるという事態を前にして,私たちは絶望に陥らず希望を語ることが求められている。
著者は,前著『対話と承認のケア』(医学書院,2020年)の中で,ケアというものが,対話において弱さが顕現することの過程と,弱さを承認し,その弱さに配慮し,世話していくことを語った。この弱さのお世話こそ,ケアの本質である。この流れは本書でも継承されており,弱さを巡る本質論として結実している。
自律,責任,理性といった,強い者のため倫理学が,倫理学の主流を占めてきた。その流れに対して,著者は静かでありながら断固としてあらがう。著者の姿は一貫している。
弱さとは,生きている存在だけが持つ強さの代償,脆さは高機能の代償であり,死や有限性は高度な統合性を獲得したことの代償であるという。代償ということ,これこそ本書の基調を成すものであり,弱さを正しく位置付け評価するための重要な基本命題になっている。弱さとは取り除かれるべき存在の側面であるのではなく,存在することの必然的条件であり,それを喪失すること自体が人間であることをやめることなのである。
古い倫理学に代わって,20世紀の倫理学は,徳倫理学もケアの倫理も,不完全性や非存在をまなざしの中心に据えている。
死をできる限り遅くすることが医学の基本課題であるとすると,倫理学は不死を理想状態とするものではない。死を忘却して,死なないことではなく,必ず死ぬという人間の避けがたい弱さを中心に据える視座こそ,弱さの倫理学のテーゼである。
人間は死の前には弱い存在だ。それは呪いではなく,祝福であり,そうでなければならない。
他者とのかかわりの中でも,人間は弱い存在であり,他者との絆に巻き込まれ,それを取り込む存在である以上,弱さを甘受し,内化することができなければ,共同存在ではいられない。弱さとは人間であることの本質的条件なのである。 強さを求め荒れ狂う世界の現状の中で,本書の放つ声は小さいようだが遠くまで響くものだと思う。私の心もまた共鳴した。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。