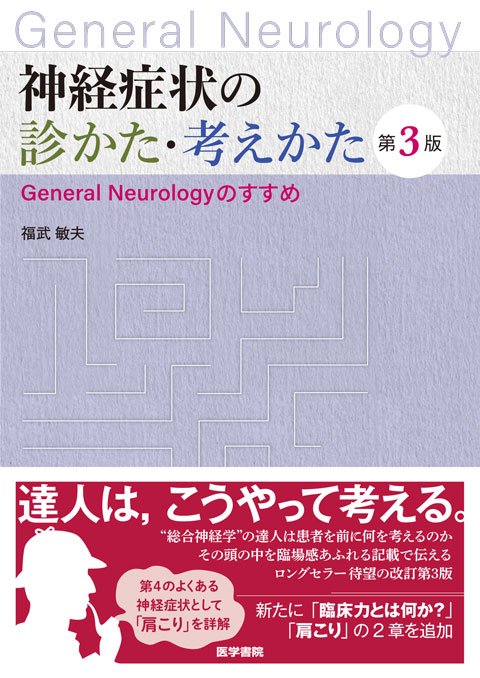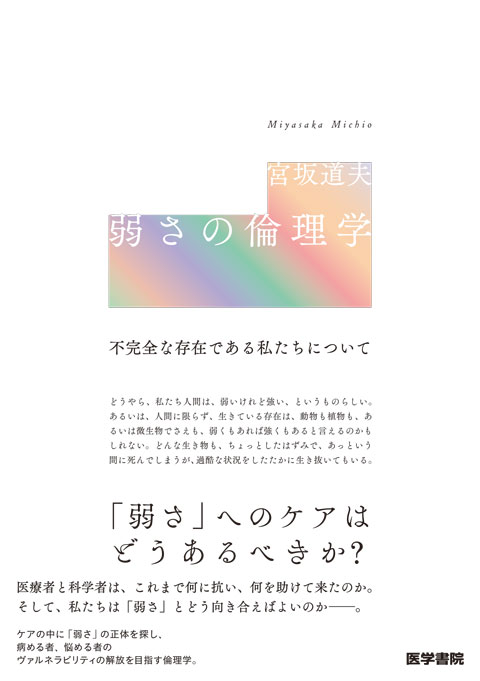MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2023.06.19 週刊医学界新聞(通常号):第3522号より
《評者》 下畑 享良 岐阜大大学院教授・脳神経内科学
繰り返し読み続けたい,エキスパートの診かた・考えかた
著者の福武敏夫先生は脳神経内科領域のオーソリティとして,誰もが認める存在である。私は先生と本書の大ファンで,本書は初版から繰り返し読み続けている。病歴聴取と神経診察の実例を通して,一貫したエキスパートの診かた・考えかたを学ばせていただいた。まさに第2版の帯に書かれていた「傍らに上級医がいる」ような感覚になるテキストである。関心のある項目から読み始めても良いが,本書を持ち歩き,私のように繰り返し読むことをお勧めしたい。きっと先生方の血肉になると思う。
第I編では日常的によく遭遇する症状(頭痛,めまい,しびれ,パーキンソン病,震え,物忘れ,脊髄症状など)が,第II編では緊急処置が必要な病態(けいれん,意識障害,急性球麻痺,急性四肢麻痺,脳梗塞)が,そして第III編では神経診察の手技上のポイントと考えかたに加え,画像診断におけるピットフォールが,いずれも具体的な実例を基に解説されている。私は「どうしたらこれほど具体的で豊富な事例を記載できるのですか?」と尋ねたことがあるが,福武先生は「一日の終わりに診療した患者のことを思い出し,ノートにつけて勉強している」と答えられ,合点がいくと同時に先生の不断の努力に改めて尊敬の念を抱いた。
今回の第3版では多くの記載の追加がなされたが,特に第Ⅰ編に多彩な全身症状のもととなる「肩こり」が追加されたことと,序章として「臨床力とは何か?」が加わったことは注目に値する。実は後者の「臨床力とは何か?」は自分がずっと考えてきた問いであり,ぜひ福武先生に伺ってみたいと考え,自身が編集委員を務める『Brain and Nerve』誌において原稿依頼をした経緯があった。先生は「例えば,ホスピタルツアーをここで終わりにするとか,医療・医学のレベルアップのために教科書を一行でも書き換えるとか(中略)そういう気概を『臨床力』と呼びたい」と答えられた。そして第3版の目的を,後進の脳神経内科医の「情熱と気概を喚起」することとお書きになっている。私たちが「気概」を得るためにどうしたら良いか? 知識は不可欠だが,それだけでは不十分であり,好奇心(患者への人間としての興味)が大切で,さらに観察力,幅広い注意力,型にはめない推理力・思考力が必要だと述べておられる。つまりガイドラインや診断基準に安易に当てはめるだけではダメということである。それらはある意味で過去のものであり,それらをマスターすることイコール臨床力ではないということだ。全ゲノム解析や多彩な自己抗体の測定により,治療可能な疾患を見いだせる時代においてこそ,患者を正しく理解するための症候学の重要性が増していることを認識する必要がある。「症候学は古い学問ではない。日々最も新たにならなければならない分野であり,『最新』の研究こそ症候学のversion upに寄与しなければならないし,寄与しない研究は意味がない」という先生の言葉は肝に銘じる必要がある。神経学を学ぶ者にとって必携の書として本書をご推薦したい。
《評者》 山内 志朗 慶大文学部名誉教授
弱さは絶望ではなく希望である
著者は倫理を次のように宣言する。倫理とは,「弱い存在を前にした人間が,自らの振る舞いについて考えるもの」であると。
倫理学は正義とは何か,善とは何か,幸せとは何か,そういったことを考える学問だと考えられている。ただ,そういった問題設定は強い者目線での思考に染まりがちだ。強さは戦いを招き寄せる。だからこそ,世界的な宗教は,キリスト教も仏教も徹底的に弱者の地平から人間の救済を考えてきた。本質的に人間は弱く不完全であり,不完全なまま生き続けるものであるという事態を前にして,私たちは絶望に陥らず希望を語ることが求められている。
著者は,前著『対話と承認のケア』(医学書院,2020年)の中で,ケアというものが,対話において弱さが顕現することの過程と,弱さを承認し,その弱さに配慮し,世話していくことを語った。この弱さのお世話こそ,ケアの本質である。この流れは本書でも継承されており,弱さを巡る本質論として結実している。
自律,責任,理性といった,強い者のための倫理学が,倫理学の主流を占めてきた。その流れに対して,著者は静かでありながら断固としてあらがう。著者の姿は一貫している。
弱さとは,生きている存在だけが持つ強さの代償,脆さは高機能の代償であり,死や有限性は高度な統合性を獲得したことの代償であるという。代償ということ,これこそ本書の基調を成すものであり,弱さを正しく位置付け評価するための重要な基本命題になっている。弱さとは取り除かれるべき存在の側面であるのではなく,存在することの必然的条件であり,それを喪失すること自体が人間であることをやめることなのである。
古い倫理学に代わって,20世紀の倫理学は,徳倫理学もケアの倫理も,不完全性や非存在をまなざしの中心に据えている。
死をできる限り遅くすることが医学の基本課題であるとすると,倫理学は不死を理想状態とするものではない。死を忘却して,死なないことではなく,必ず死ぬという人間の避けがたい弱さを中心に据える視座こそ,弱...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。