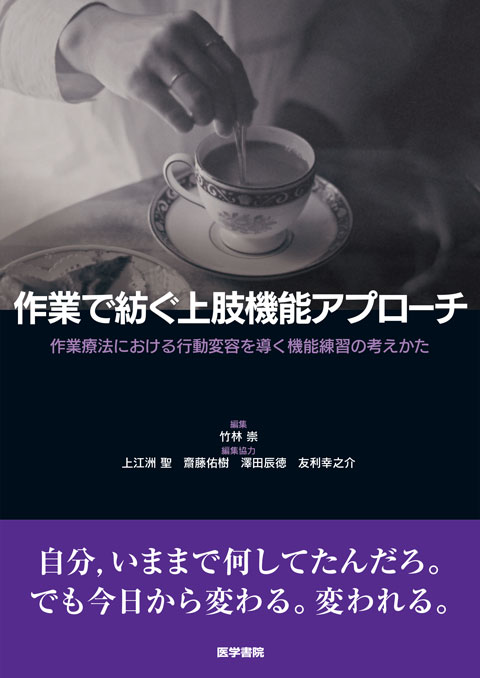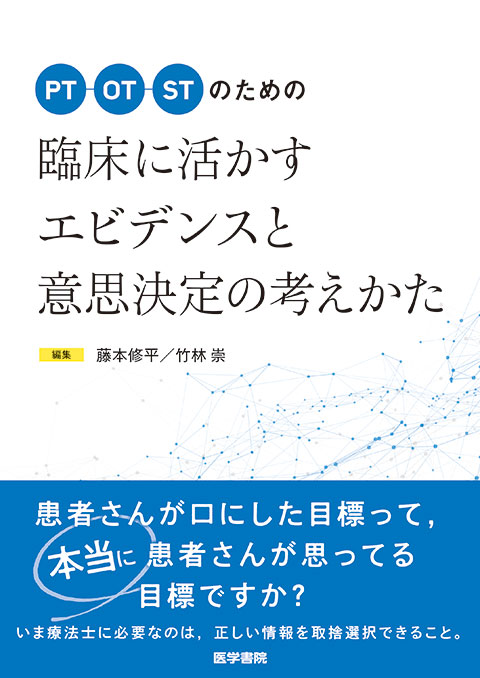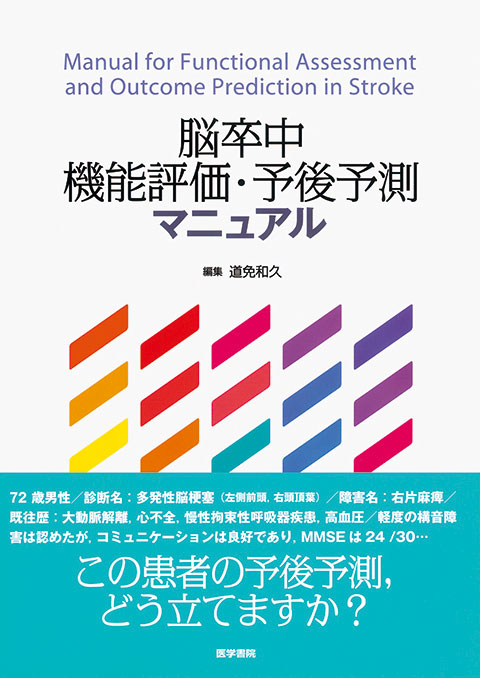予後予測の実践で磨き上げるリハビリテーションの思考力
対談・座談会 竹林崇,庵本直矢,平山幸一郎
2023.06.19 週刊医学界新聞(通常号):第3522号より

経験の浅い療法士にとって対象者の予後を正確に予測することは容易ではない。予後について先輩に意見を求めるも,アドバイスが主観や経験則に依拠しがちで眼前の対象者に適用できない場合もある。そこで参考となるのが機能障害の経過を調査した予後予測研究だ。
このたび発行された『PT・OT・STのための臨床5年目までに知っておきたい予後予測の考えかた』(医学書院)では,数多く存在する予後予測研究を自身の臨床に結び付けるための工夫が紹介されている。今回,編者である竹林崇氏を司会に,臨床現場で予後予測を実践しながら若手の指導も行う庵本直矢氏,平山幸一郎氏を迎えた座談会が開かれた。若手療法士が予後予測を行う際の考え方を学びたい。
竹林 適切なリハビリテーションプログラムを組むには対象者がどのような経過をたどるかを予測する必要があるものの,予後予測に自信のある若手療法士は多くないのが実情です。このたび,予後予測に必要な知識や実際の方法などを解説した『PT・OT・STのための臨床5年目までに知っておきたい予後予測の考えかた』が発行されました。庵本先生,平山先生は本書の執筆や査読にも携わり,臨床現場において予後予測を日々実践されています。本日は,若手療法士が予後予測を行う際のヒントを探っていきたいと思います。
予後予測は対象者の未来にたどりつくための地図
竹林 そもそも現場の若手療法士は予後予測に対してどのようなイメージを持っているのでしょうか。若手の指導も行われているお2人の印象を聞かせてください。
平山 後輩を指導する中で感じるのは,エビデンスに基づいた予後予測が難しいものと考えられがちということです。自らの少ない経験や身近な先輩・上司の経験則のみで予後予測を考えてしまう若手が多いことは,療法士全体の課題となっていると思います。
庵本 同感です。養成課程に予後予測を学ぶ機会が少ないのが一因でしょう。臨床現場では,これまで経験則に基づくリハビリテーションが代々受け継がれてきているのが現状です。
竹林 養成課程で予後予測を学ぶ機会が少ないのは,私が学生であったおよそ20年前からそうでした。そうした現状に一石を投じたのが『脳卒中機能評価・予後予測マニュアル』(医学書院)であり,同書の登場によってリハビリテーション業界では予後予測を基に対象者のアウトカムを計測する重要性が意識され始めました。一方で,発行から10年が経過し療法士の人数も増えたものの,そうした考えがまだ十分には広がりきっていないのでしょう。
予後予測が難しいととらえられてしまう理由は何だと思いますか。
庵本 交絡因子の多さではないでしょうか。先行研究と眼前の対象者を比較した時に,交絡因子が全て一致することは非常に少ないため,どのように解釈すれば良いかに悩み,挫折する若手は少なくないはずです。
平山 加えて,環境や療法士側の要因も挙げられます。施設によっては,予後予測をしたくても参考にできるデータがそもそも存在しない場合もあるでしょうし,論文を読み慣れていない若手療法士が多いことも考えられます。
竹林 たしかに英語論文をすらすらと読んで討論できる若手はそこまで多くないと思います。また,論文検索ができたとしても次の壁にぶつかる人がいます。それは先行研究をどこまで参照すべきかという問題です。先行研究で「~となる可能性がある」のような表現を見つけた時,どう考えるべきなのでしょう。
庵本 先行研究はあくまで特定の予後をたどる確率を算出したデータに過ぎないと考えることです。研究結果は絶対ではありません。たとえ予後不良である可能性が高いと判断されたとしても「自身の介入によって研究結果をどう上回るか」について考えることが重要だと思います。
平山 おっしゃるとおりです。ただ,そうした柔軟な発想を持つことは難しいですよね。
竹林 ええ。ですので,先行研究は対象者の未来にたどり着くための地図だと考えるとよいでしょう。対象者がたどる経過(道筋)は多岐にわたりますが,アウトカムを継続的に計測し,予後予測を繰り返し行うことで無数にあった道筋を徐々に絞っていくイメージを持つと良いと思います。
振り返りの言語化と多角的な評価で経験値をためる
竹林 予後予測を考えるに当たり,参考となる論文を2本紹介します。1本目はPrabhakaranら1)の論文(PMID:17687024)です。これは脳卒中後の上肢麻痺を呈した対象者において麻痺手の機能予後が予測できるかを検証した研究で,3~6か月後の最大回復FMA(Fugl-Meyer Assessment)上肢項目の値を予測する式〔0.7×(66-発症時のFMA上肢項目の値)+0.4〕を立てたものです。初期の障害の重さにかかわらず回復がほとんどみられない対象者を除いて,最大回復FMA上肢項目の点数は89%の確率で同予測式に適合したとしています。
2本目はWintersら2)の論文(PMID:25505223)です。これは1本目で紹介したPrabhakaranらの予測式の妥当性や外れ値の要因を検証した研究で,対象者211例におけるFMA上肢項目の値を同予測式に当てはめた結果,146例(69%)に対して適合したと報告しています。また,同予測式に適合しなかった残りの対象者 65例を検証したところ,「72時間以内に手指の伸展が出現しない」といった複数の要因が判明し,これらの要因を除いた症例では新たな予測式〔1.99+0.78×FMA上肢項目の値(R=0.97,R2=0.94)〕が成り立つとしています。
これらの結果からもわかるように,いかに予後予測の確度が高い研究結果だとしても,それが眼前の対象者に適合しない可能性...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

竹林 崇(たけばやし・たかし)氏 大阪公立大学 医学部リハビリテーション学科 作業療法学専攻 教授
2003年川崎医療福祉大医療技術学部卒。同年より兵庫医大病院リハビリテーション部に勤務。18年兵庫医大大学院修了。博士(医学)。22年より現職。『作業で紡ぐ上肢機能アプローチ』『PT・OT・STのための臨床5年目までに知っておきたい予後予測の考えかた』(いずれも医学書院)など編著書多数。

庵本 直矢(あんもと・なおや)氏 名古屋市総合リハビリテーションセンター 作業療法科
2013年名大医学部保健学科作業療法学専攻を卒業後,名古屋市総合リハビリテーションセンターに入職。脳画像解析による対象者の機能予後予測に関する研究を行う。『作業で紡ぐ上肢機能アプローチ』『臨床5年目までに知っておきたい予後予測の考えかた』(いずれも医学書院)を分担執筆。

平山 幸一郎(ひらやま・こういちろう)氏 岸和田リハビリテーション病院 リハビリテーション部 主任
2017年鹿児島大医学部保健学科作業療法学専攻を卒業後,岸和田リハビリテーション病院に入職。23年大阪公立大大学院修了。修士(保健学)。『作業で紡ぐ上肢機能アプローチ』(医学書院)を分担執筆。査読協力者として『PT・OT・STのための臨床5年目までに知っておきたい予後予測の考えかた』(医学書院)の制作に携わる。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。