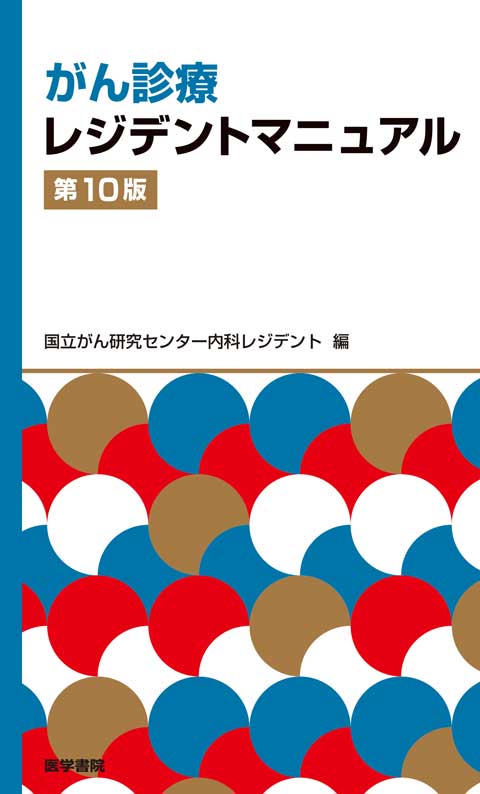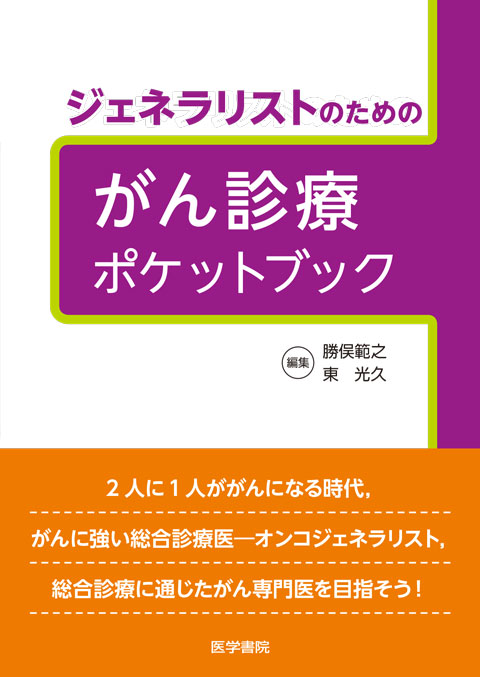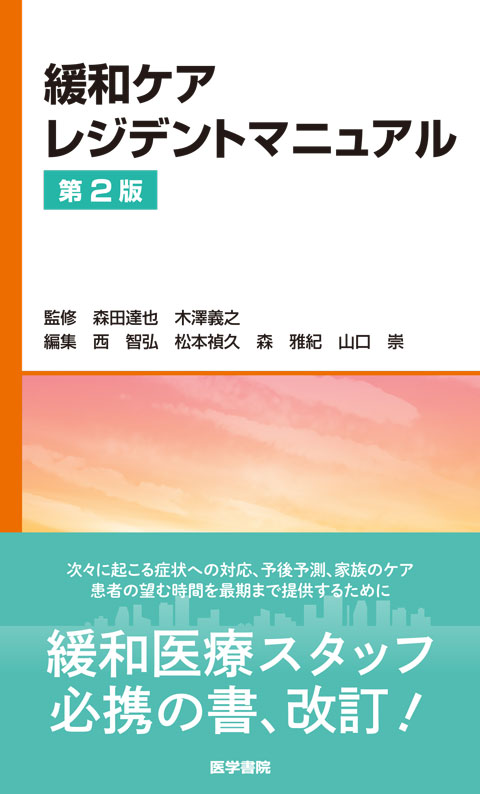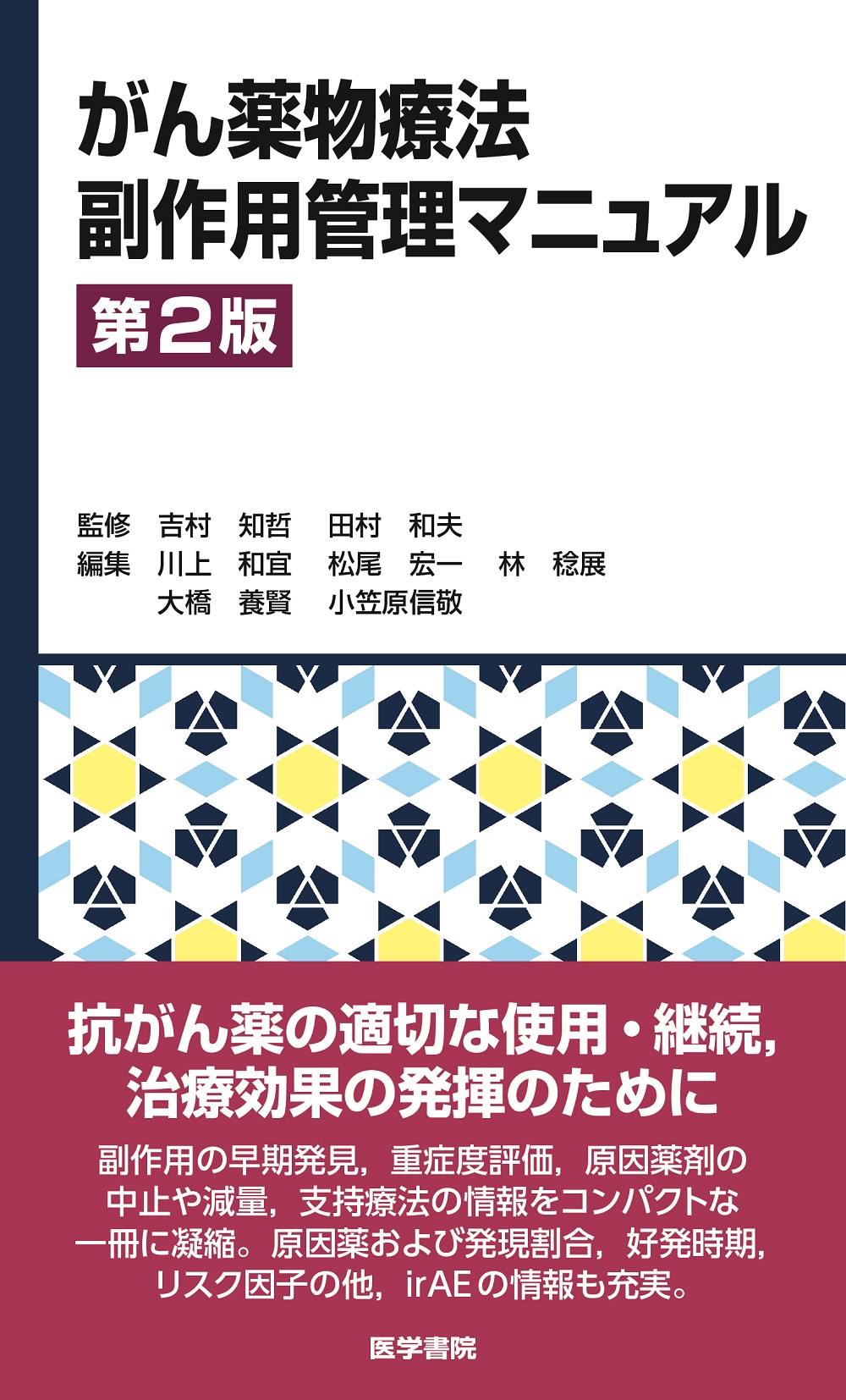がん診療25年の歩みと次の見取り図
対談・座談会 勝俣範之,山本昇,後藤悌
2022.11.21 週刊医学界新聞(通常号):第3494号より

勝俣範之氏らが初版の編集に携わった『がん診療レジデントマニュアル』(医学書院)発行から25年を経て,この度第9版が上梓された。四半世紀の間には分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった画期的な治療薬の登場など,がん診療の在り方自体が大きく変容した。本紙では勝俣氏を司会に,同じく本書の編集にかかわる山本昇氏,後藤悌氏の3氏による座談会を企画。近年の歩みを振り返るとともに,高齢化に伴い重要性を増し続けるがん診療は今後どう変わっていくのか,その展望を語った。
エビデンスに基づく腫瘍内科レジデントのための本,誕生!
勝俣 気心の知れた3人ですが改めて,今日は集まっていただきありがとうございます。私が企画に携わった『がん診療レジデントマニュアル』(医学書院)が,初版発行から四半世紀の節目を迎えました。山本先生が第2版から,後藤先生が第7版から現在まで編集に携わってくれています。
後藤 初版はどういう経緯で発行に至ったのですか?
勝俣 きっかけとなったのは,それまでエビデンスに基づいた信頼できるがんの教科書がなかったことです。1990年代後半の当時は,EBMという言葉が米国で生まれたばかりの黎明期でした。その中で私は,「自分が臨床で使用できる本が欲しい」と考えました。また当時,がんは外科が診ていたため需要が懸念されたものの,私は「腫瘍内科」と「エビデンスベースト」にこだわった教科書にしたかった。実は,本書にはプロトタイプがあったのですよ。
山本 そうなのですか。
勝俣 ええ。国立がんセンター中央病院で,私の前にチーフレジデントを務めた小山博史先生(東大)が院内の研修用に作った「がんセンターレジデントマニュアル」です。小山先生もさまざまな出版社に相談したものの,発行を断られたそうです。その経緯を知っていたので,私から当時の上司だった渡辺亨先生(浜松オンコロジーセンター)に相談し,総長の故・阿部薫先生から医学書院に企画を持ち込んでもらいました。
後藤 レジデントから話を上げたのですか。すごいですね。
山本 当時レジデントだった私も,抗がん薬の血管外漏出に関する項目を執筆担当したのを覚えています。
勝俣 「レジデントによる,レジデントのためのマニュアル」がコンセプトですからね。レジデントが執筆を担当する方針は今も踏襲してくれているのですよね。
山本 はい。ただ,専門的知識を要する内容は,該当領域の医師に確認を依頼しています。また,レジデントが配属されていない領域もあって,担当に悩むこともありますね。一方で,例えば肺がんや胃がん,乳がんなど症例数の多い領域は,自ら「書きたい」と言ってくれるレジデントもいます。
後藤 執筆に前向きに取り組んでくれる若手が多いのは,伝統がなし得る業でしょう。締め切りなどもきちんと守ってくれます。もちろん,われわれがプレッシャーをかけているのもあるでしょうけど(笑)。
勝俣 誇りを持ってくれているのは素晴らしいことですね。昔の編集委員会はすったもんだしたものです。中でも第4版の編集時に,中島光先生(米セントルーカス大病院/テンプル大)と山本先生が喧嘩を始めたのは印象深いですね。でも,それほど真剣に取り組んでいたということですよね。
山本 喧嘩というほどではなかったですけど(笑)。米国帰りの中島先生が米国の標準治療を推奨されるのに対し,抗がん薬の用法・用量の違いなど,日本の現状から完全に離脱できない当時の私がいました。ただ,今から考えると非常に刺激を受けました。また,版を重ねて緩みかけていたエビデンスベーストの方針を,中島先生が再確立してくれたのですよね。
勝俣 その後,私は第5版を最後に編集から離れてしまいました。この度発行した第9版からは後藤先生が編集の中心を担っていると聞きます。何かと苦労されるかと思いますが,この本を引き続きよろしくお願いしますね。
後藤 はい。学びがいがあり面白い領域ですので,若手には本書をきっかけにして,ぜひがん診療に興味を持ってほしいですね。
がん薬物療法の2大変革
勝俣 さて本日は,本書にちなんでこの四半世紀におけるがん診療の歩みを振り返り,今後の展望までお話しできればと思います。おふたりは,がん診療の変化をどうとらえていますか。
山本 長期生存できる患者さんが増えました。私が当院に赴任した1995年当時,肺がん患者さんの予後は1年だと指導されました。現在は気づけば5年の付き合いという患者さんも多くいらっしゃいます。
後藤 もちろん患者さんごとの幅がありますね。5年以上治療を続けている患者さんもいれば,予後の悪い患者さんもやはりいらっしゃいます。また,以前は当初の見込みと疾患の進行が概ね一致していましたが,経過中に病状がダイナミックに変わることが増えました。2年以上,まるで病気など抱えていないかのように元気に過ごした後に,急激に悪化する患者さんがいるのです。
勝俣 特にお二人の専門である肺がん患者さんの予後は劇的に変わりましたよね。それはひとえに治療が進歩したためでしょう。どんな治療が生まれたか,改めて教えてください。
山本 まず挙げるべきは,やはり分子標的薬(MEMO①)です。今ではより優れた薬が上市されていますが,肺がん領域で画期的だったのは,何と言っても2002年に非小細胞肺がんに対して実用化されたゲフィチニブ(イレッサ®)です。患者さんの長期予後が見込めるようになり,10年近く継続してイレッサ®を使用している患者さんもいます。
勝俣 現場では衝撃的でしたよね。
分子標的薬の次の進歩が,免疫チェックポイント阻害薬(MEMO②)の実用化です。どのような印象でしたか。
後藤 腫瘍内科医になって初めて,「治るかも」と期待を持ちました。中でも肺がんにはよく奏効しますね。肺がんでは,2015年12月にニボルマブ(オプジーボ®)が,切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対して初めて承認されました。それからまだ7年ほどですが,ニボルマブ投与後に寛解し,その間全く無治療の患者さんもいます。再発が起こり得るがんについて,何年経過すれば「治った」のかはわかりませんが,近い状態と言えるでしょう。
勝俣 素晴らしいですね。がんと共存できる時代になったと言って良いでしょう。この四半世紀のがん診療において,90年代後半から2000年代初頭の分子標的薬の実用化が第一の変革で,10年代の免疫チェックポイント阻害薬の実用化が第二の変革ですね。
山本 それから,以前と比べると緩和ケア科か...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

勝俣 範之(かつまた・のりゆき)氏 日本医科大学武蔵小杉病院 腫瘍内科 教授
1988年富山医薬大(現・富山大)卒。茅ヶ崎徳洲会総合病院(当時)での研修を経て,92年国立がんセンター中央病院内科,2003年同院薬物療法部薬物療法室医長。04年米ハーバード大公衆衛生大学院留学。10年国立がん研究センター中央病院乳腺科・腫瘍内科外来医長。11年より現職。『がん診療レジデントマニュアル』(医学書院)を企画し,第5版まで編集を務める。近著に『ジェネラリストのためのがん診療ポケットブック』(医学書院)。

山本 昇(やまもと・のぼる)氏 国立がん研究センター中央病院 副院長/先端医療科 科長
1991年広島大卒。95年国立がんセンター中央病院内科にて研修後,同院呼吸器内科,医員を経て,2013年より先端医療科科長。19年より臨床研究支援部門長,副院長(研究担当)を兼務。第2版から『がん診療レジデントマニュアル』の編集に参画する。呼吸器内科を専門とし,新規抗がん薬の早期開発に携わる。

後藤 悌(ごとう・やすし)氏 国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 外来医長
2003年東大卒。同大病院,三井記念病院,国立がんセンター中央病院などで経験を積んだ後,11年より東大病院呼吸器内科助教。14年国立がん研究センター中央病院呼吸器内科医員,16年より現職。『がん診療レジデントマニュアル』第7版から編集に参画。この度発行した第9版では,編集の中心的役割を担った。診療の傍ら,呼吸器腫瘍に関する新薬の開発・実用化に尽力する。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。